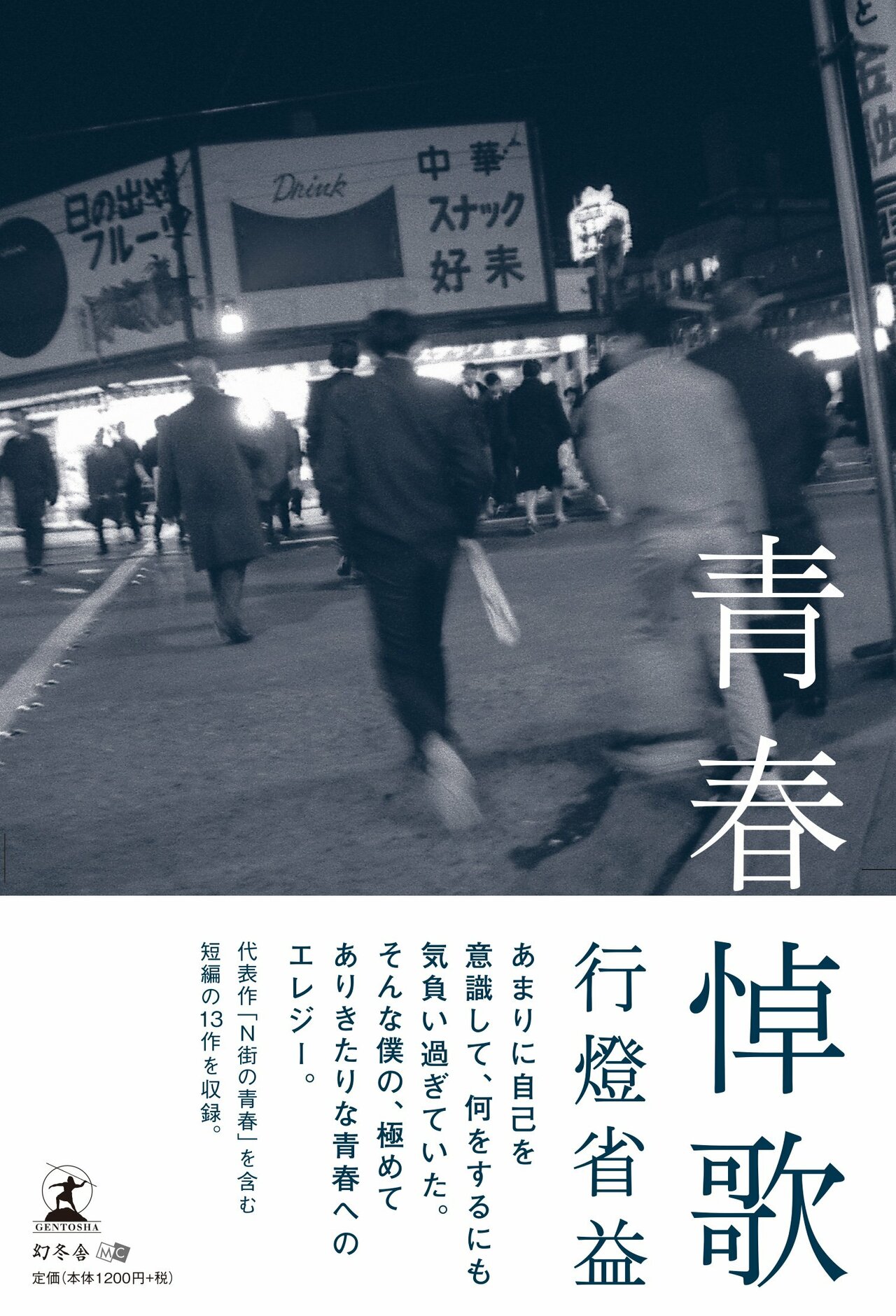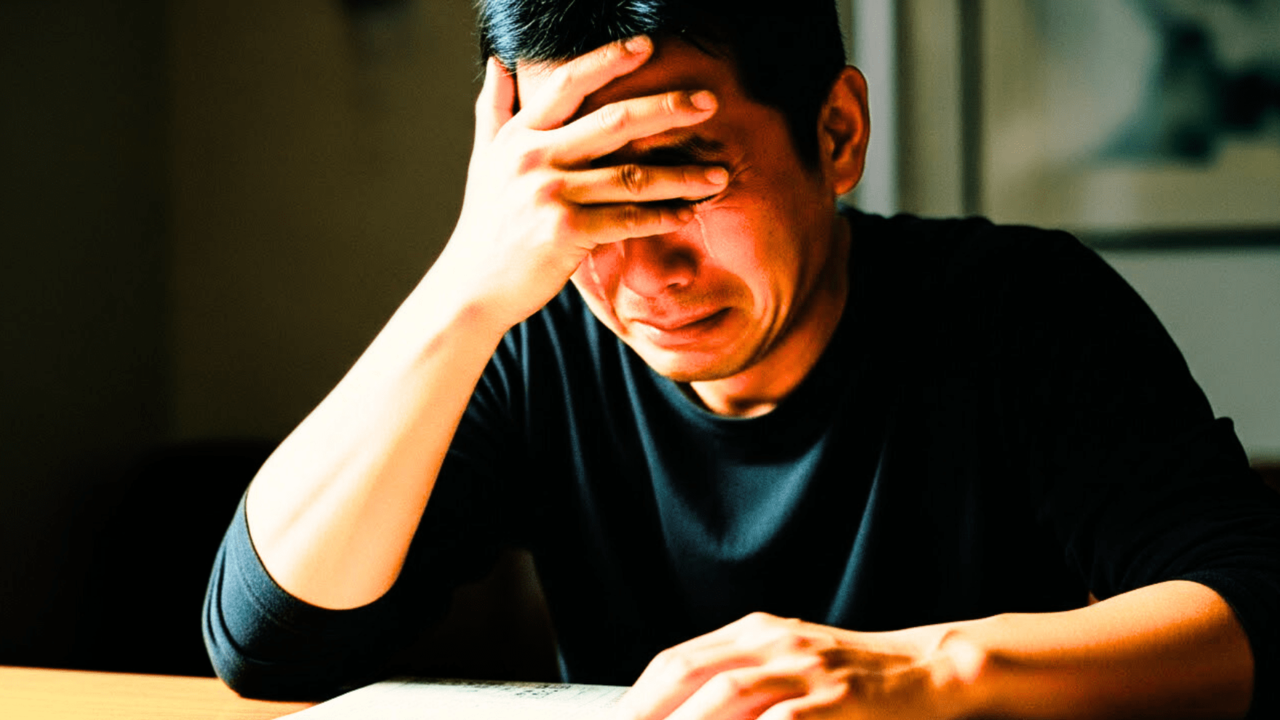けれど、少なくともその時までは、彼にも自らの取るべき具体的な行動は、まだ、はっきりとは見えてはいなかったはずである。ところが、それから暫くしたある時を境にして、高校時代あれほど僕より冷静で慎重に思えた彼が、その大学に勢力を持つ某セクトの強いオルグに遭うと、積極的に、いやひとが変わった様に、革命を標榜する彼らの政治運動へと傾斜していくのであった。
中途半端ではあったけれど、一連の学生運動に影響を受けて、その流れの中に飛び込んでいったのは、むしろこの僕の方が先であった。けれど、それはマルクスを理解していた訳でもなく、毛沢東に心酔していたせいでも無かった。それよりも僕のそれは、世の中のあらゆる不条理的な存在に対する、単純な拒否反応であったと言っていい。
だから僕の目には、彼らセクトの過激な政治行動は、とても現実的なものには思えなかった。まして、過激さだけを競うかの様に思えた彼らの政治スローガンには、どうしても馴染めなかったのである。
今思うと、傍観者的で稚拙ではあったけれど、それでも自分なりに喘いでいた、そうした思想的葛藤の中で、元々は全共闘運動の理念に賛同しただけで、ある意味何の確信も無く曖昧な理解だけで、ただ何となくこの運動の流れに参加した身からすれば、以前のNを思うたびに段々と複雑な心境になるのであった。
Nのこの変化は、女性の死がきっかけになったとは言え、当初僕は、彼の行動は純粋に政治的動機からであると理解していた。すなわち積極的な政治行動が伴わなければ、穏健で合法的な解放運動と行動とだけでは、自ら抱える深刻な差別問題は、もはや簡単には解決出来ぬと考える様になったからであると。