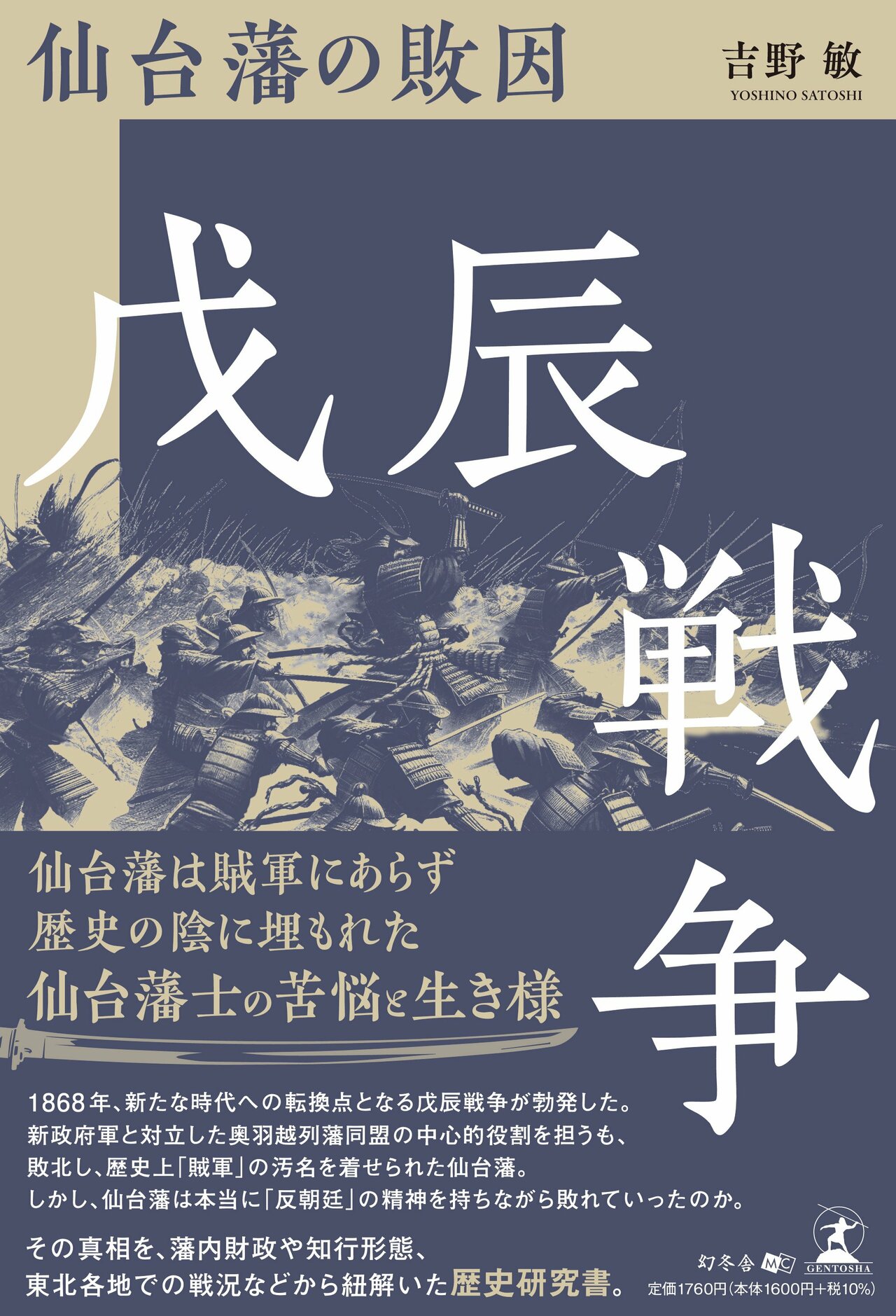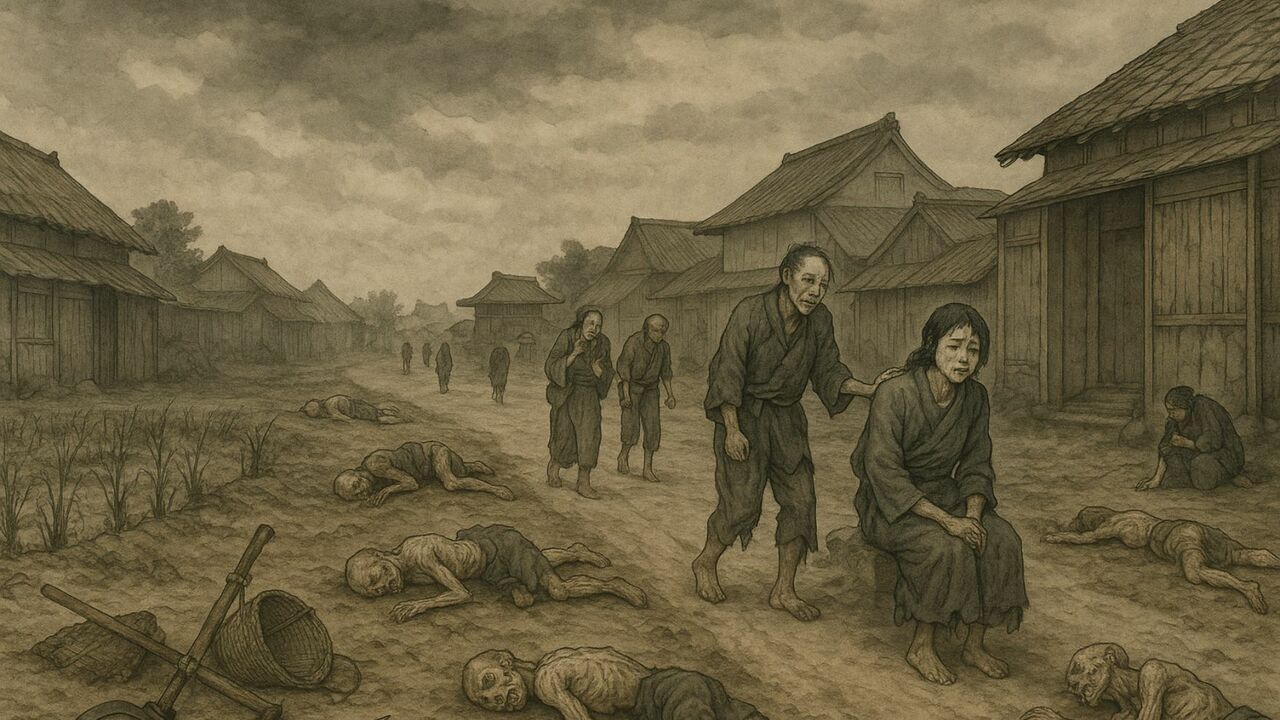禄の支給形態は、地方支給、蔵米支給、切米支給、扶持方支給とあった。
この中で元文三年(一七三八)に行われた調査の「家譜」に基づいて知行高に対する比率を求めると、
一万石以上八名 二八・八パーセント
五千石以上六名 六・八パーセント
三千石以上五名 三・三パーセント
一千石以上四十八名 一一・八パーセント
一千石以上六十七名の比率にして約六パーセントの知行の家臣が総知行高の五〇・七パーセントを占めているのに対し、三百石以下で家臣数の八四・六パーセントの者の総知行高は三三・三パーセント。
平均百八十二石の小禄者は「手作り」の生活を含んでいた。特殊拝領形態は、北上、迫、江合、鳴瀬の河川流域の葛西、大崎地方抑えや湿地・野谷地の新田開発の促進をねらったもの。
また、町場は、城下町の形成を図り経済の流通・交通網の成立を図ったもの。
要害、所を拝領している一門、一家などの家格の門閥層には所替えがなかったので領主的・大名的性格を有し小幕藩体制になっていた。
これが藩内の連帯を欠く一因にもなっていた。
【イチオシ記事】彼と一緒にお風呂に入って、そしていつもよりも早く寝室へ。それはそれは、いつもとはまた違う愛し方をしてくれて…