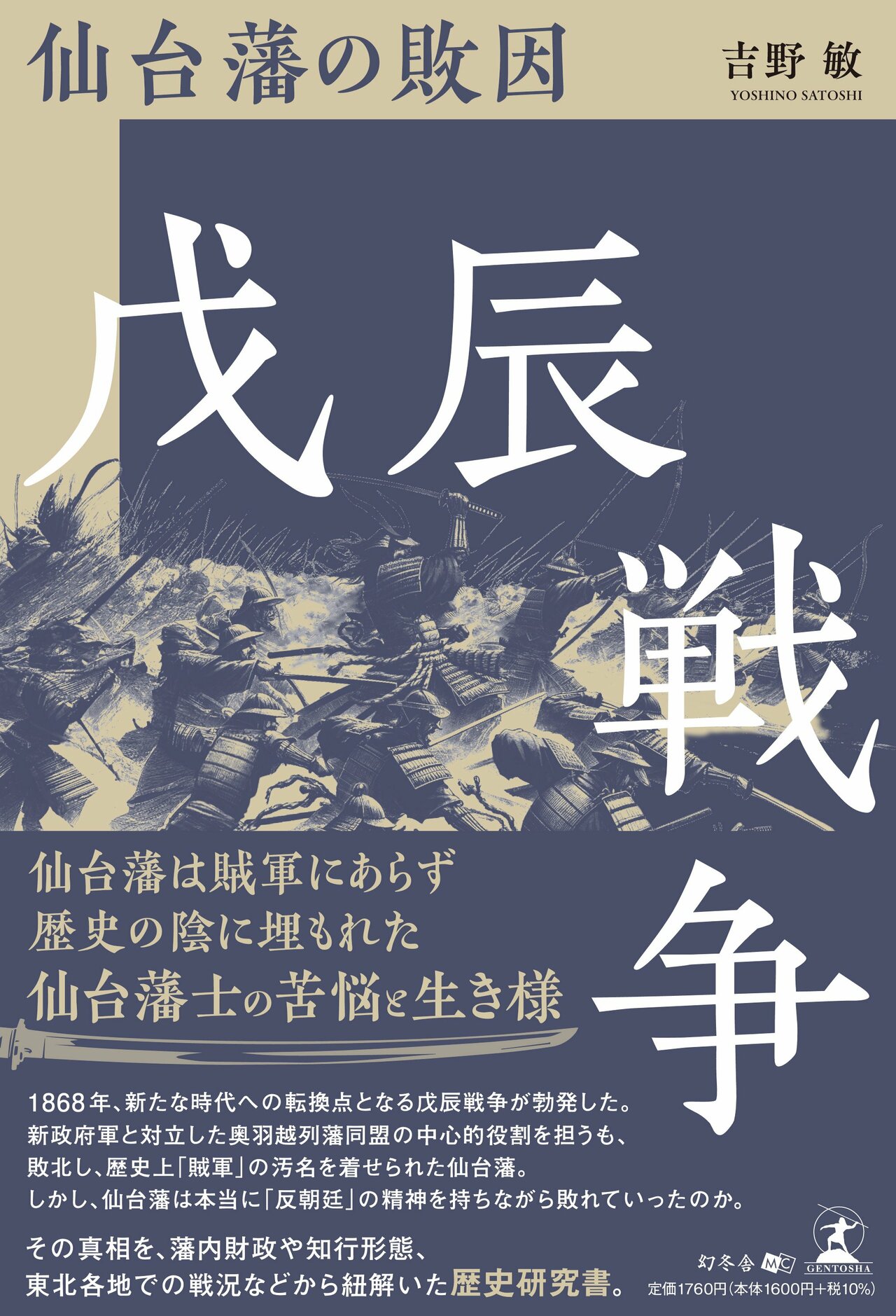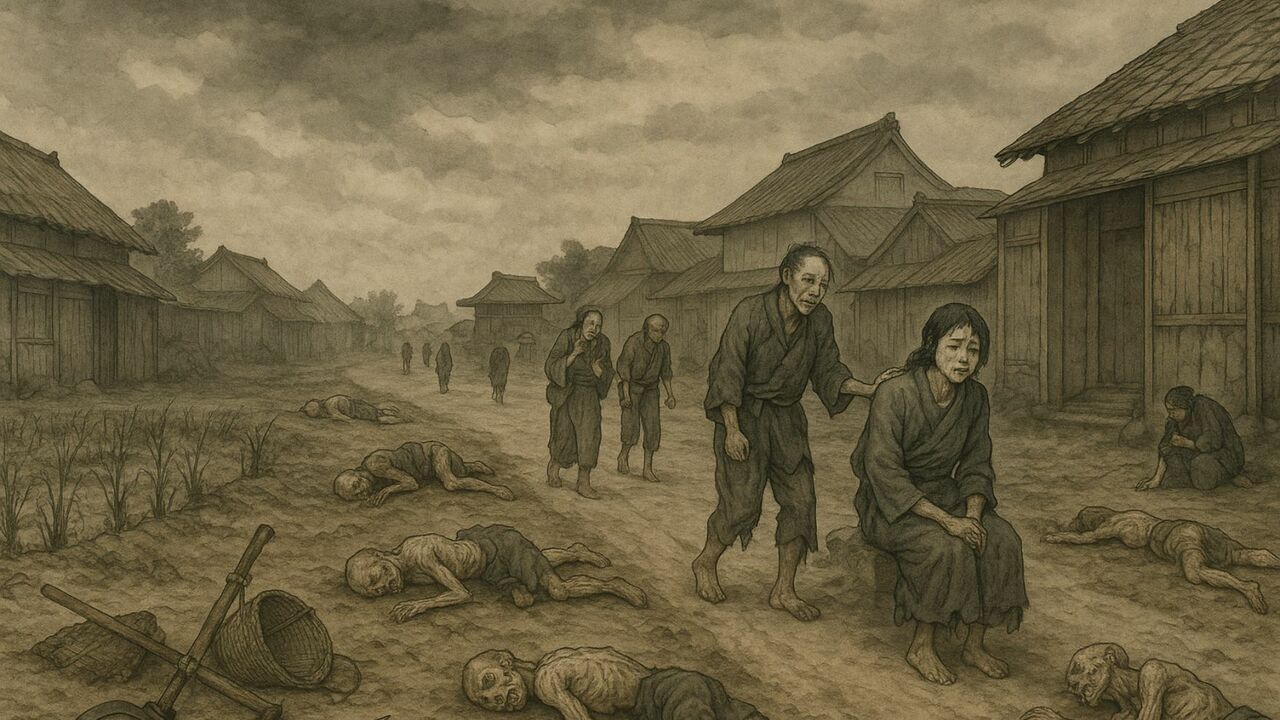三 仙台藩の知行形態
仙台藩の家臣の知行形態は、重層的で複雑であった。そのため中世的要素が残存していると評されている。
家臣の人数は、組士・足軽などを含め一万人前後、それに家格として一門、一家、一族、宿老、着座、太刀上、召出、平士があり、一門十一家、一家十七家、準一家八家、一族二十二家と門閥家格が占めている。
一門(十一人)は、かつて伊達氏と対等の大名であったが、のちに服属した氏やそれに準じた、或いは重臣であった家柄。
一家(十七人)は、晴宗の頃からの姻戚関係や譜代の主従関係を持つ者。
準一家(八人)は、かつては大名、多くは政宗の代に召し抱えられた者。
一族(二十二人)は、多くは伊達家の世臣或いは政宗の早い頃に仕えた者。
宿老、着座、太刀上、召出のうち宿老は、奉行職に任じられる家柄の四家、着座は、政宗の近習或いは低い身分から重用された者、家格によらず政宗の親近と手腕によって取り立てられた。
さらに知行形態が、城拝領、要害拝領、所拝領、在所拝領という特殊拝領形態と普通拝領形態という在郷に分類される。
城は、町場、山林、居屋敷、侍足軽屋敷を含むもの。要害は、町場、山林、居屋敷、侍足軽屋敷を含むものであって実質には城と同じであるが、城は、幕府が指定したものとされており、白石城のみである。
幕府の指定は一国一城が原則。要害は藩が指定したものであった。所は町場、山林、居屋敷、侍足軽屋敷を含み藩が指定したもの。
在所は、山林、居屋敷、侍足軽屋敷を含み藩が指定したもの。
在郷は、知行地で自前の居屋敷や家中、足軽屋敷を取り立てたもの、また知行地に家中、足軽屋敷がないもの。