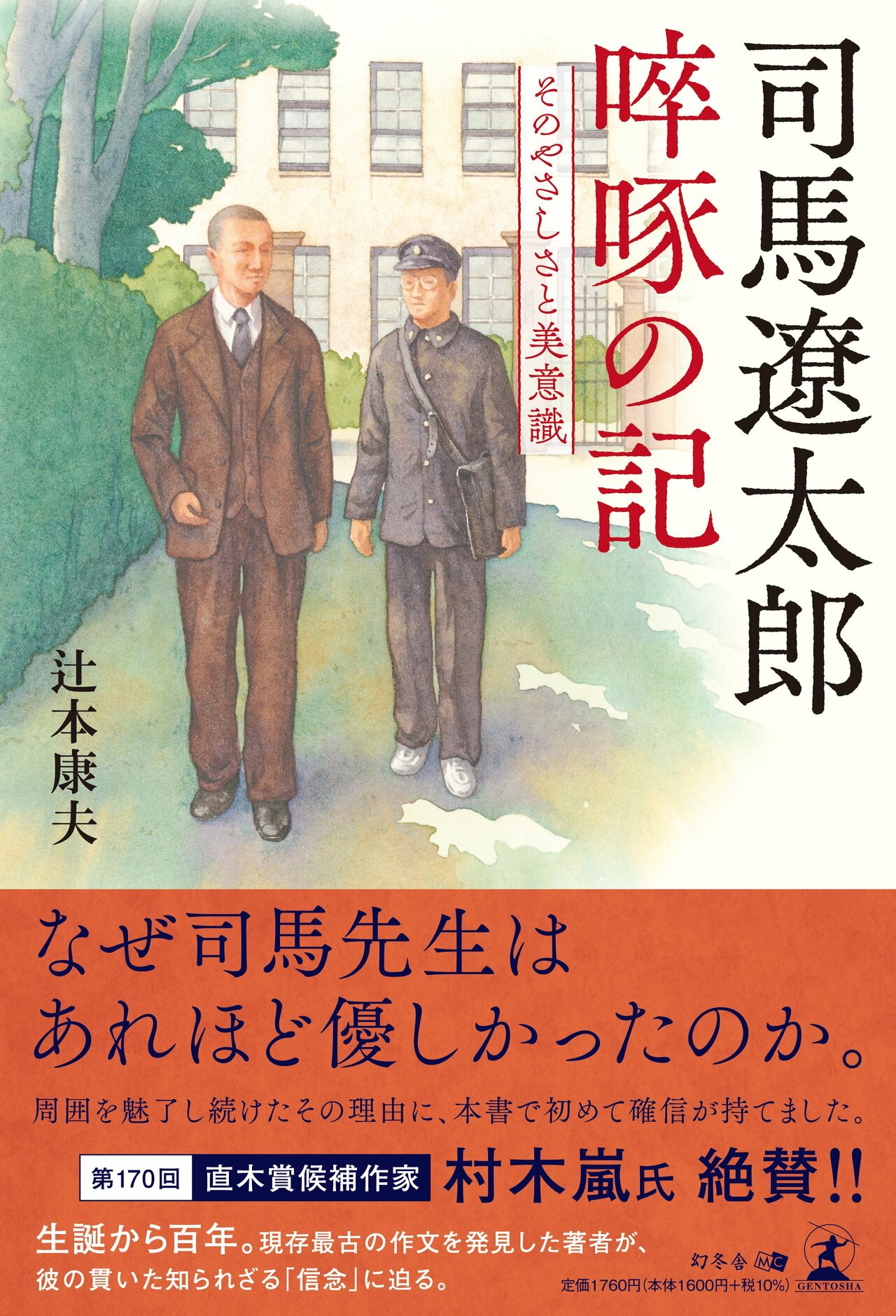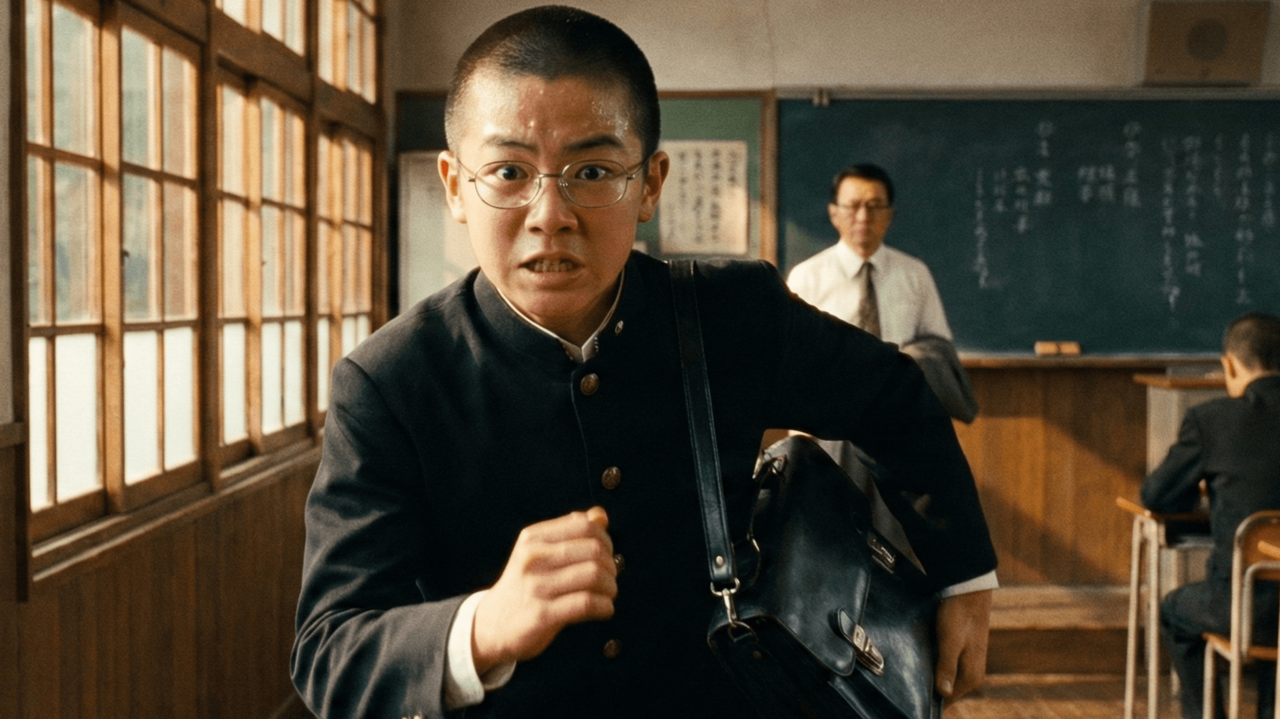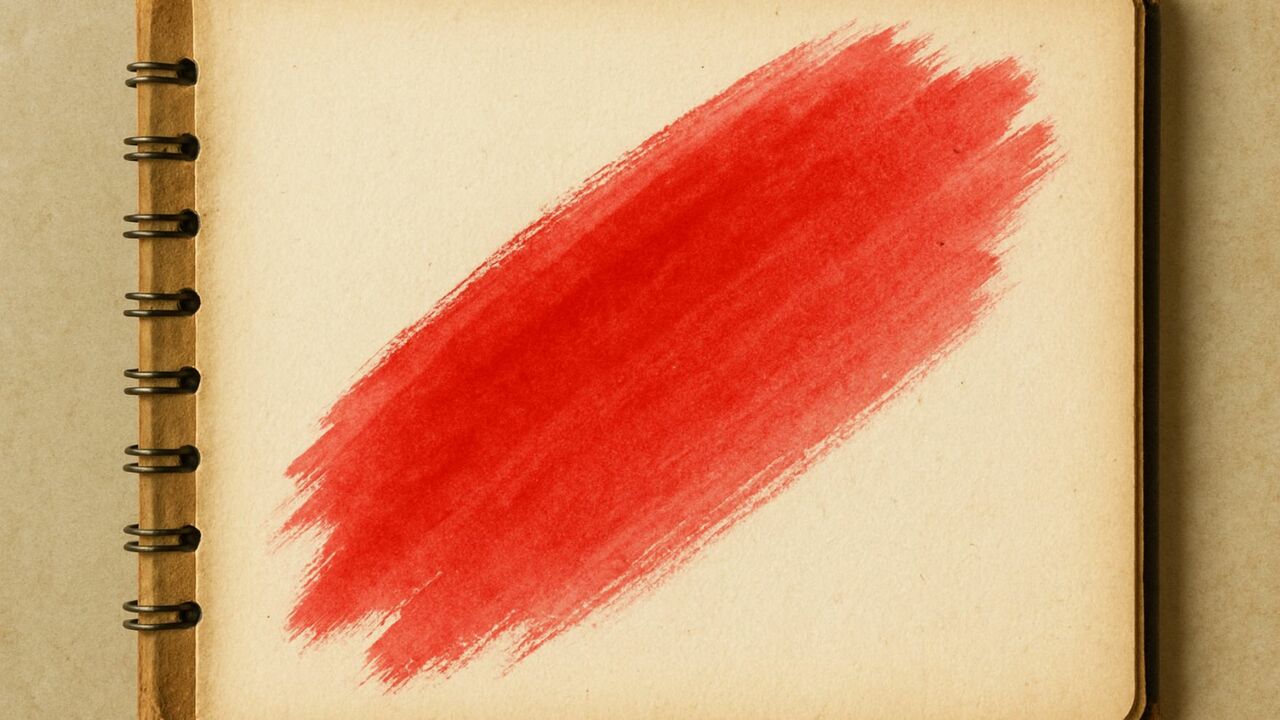これらの言葉はまるで中学一年の時に書いた作文「物干臺に立つて」を書いた意図を、作家になった司馬さんが解説文で書いているかのように思えます。もしかすると、司馬さんが俯瞰的な視点の面白さや自分の絵画的に捉える特質を最初に発見したのは、この「物干臺に立つて」を書いた時だったのかもしれません。もしそうであれば、この短い作文は司馬さんの文学を考える上でさらに特別な意味を持つことになりそうです。
幻の作文
司馬さんは講演会で、作文の授業があったのは二年生の時だったと話をしているのですが、それが二年のいつだったのかは話していません。もしそれが前年のように、秋に実施されていたのであれば、二年の二学期末の第33号に掲載された可能性があるのですが、残念なことに、第33号は非常時局特輯号ということで作文の掲載はなかったようです。
また、次の三学期末の第34号は卒業記念号ですから、もとより作文の掲載はありません。つまり、この年は作文の掲載の可能性がある校友会雑誌は一学期の終業式に配布された第32号しかないことになります。
しかし、一学期は年度初めで、行事が多い学期ですから、作文の授業があったかどうか、何ともいえない、微妙な時期でもあります。
さらに残念なことは肝心の第32号が学園に存在しないことです。おそらく他の号と同じく、戦後の混乱で失われてしまったのでしょう。どなたか、戦前の上宮中学校の校友会雑誌『上宮』の第32号をお持ちの方がおられましたら、(もちろん、それ以外の号でも構いません)是非上宮学園か私までご一報いただければと思います。
可能性は低いと言わざるを得ませんが、もし第32号が見つかれば、司馬さんの中学時代の第二の傑作が見つかる可能性もあります。何しろ、芦名先生が激賞した作文なのですから。
1『私の小説作法』『司馬遼太郎全集』32文藝春秋 一九七四年
【イチオシ記事】彼と一緒にお風呂に入って、そしていつもよりも早く寝室へ。それはそれは、いつもとはまた違う愛し方をしてくれて…