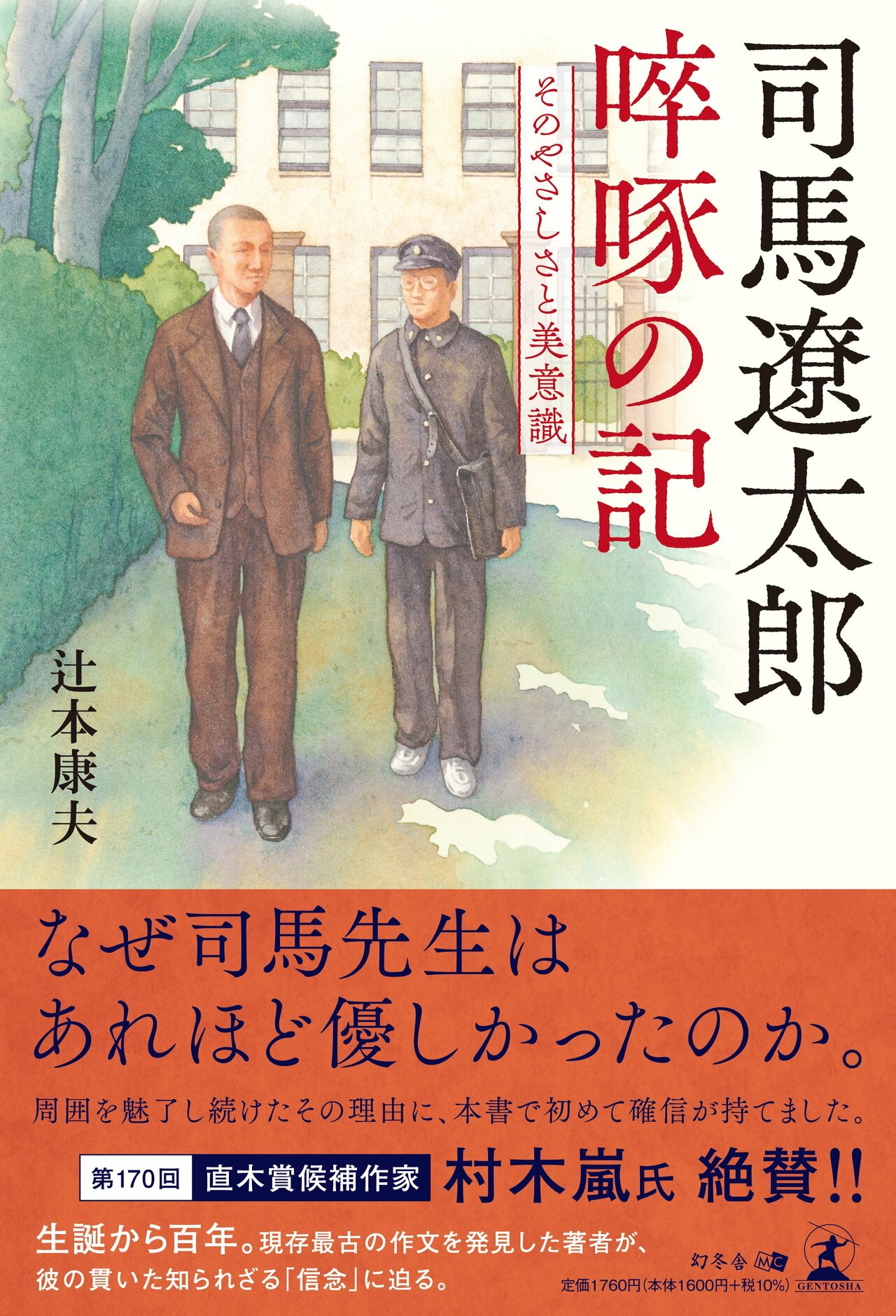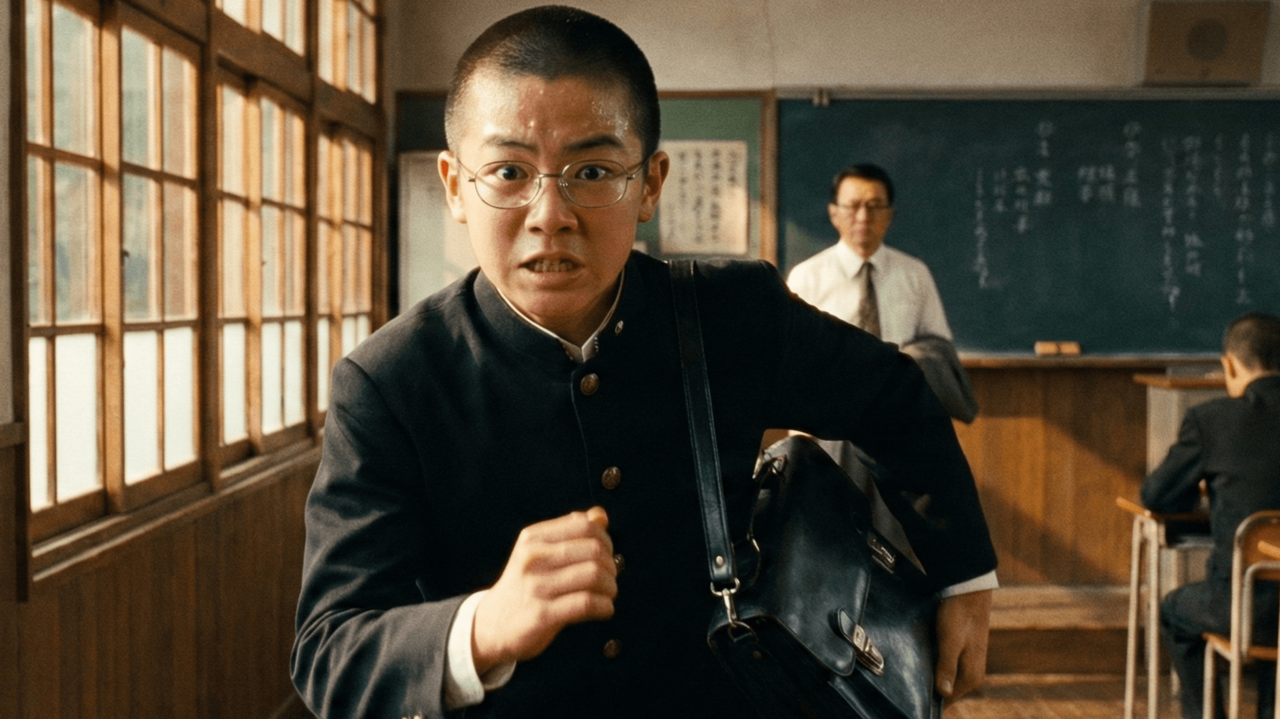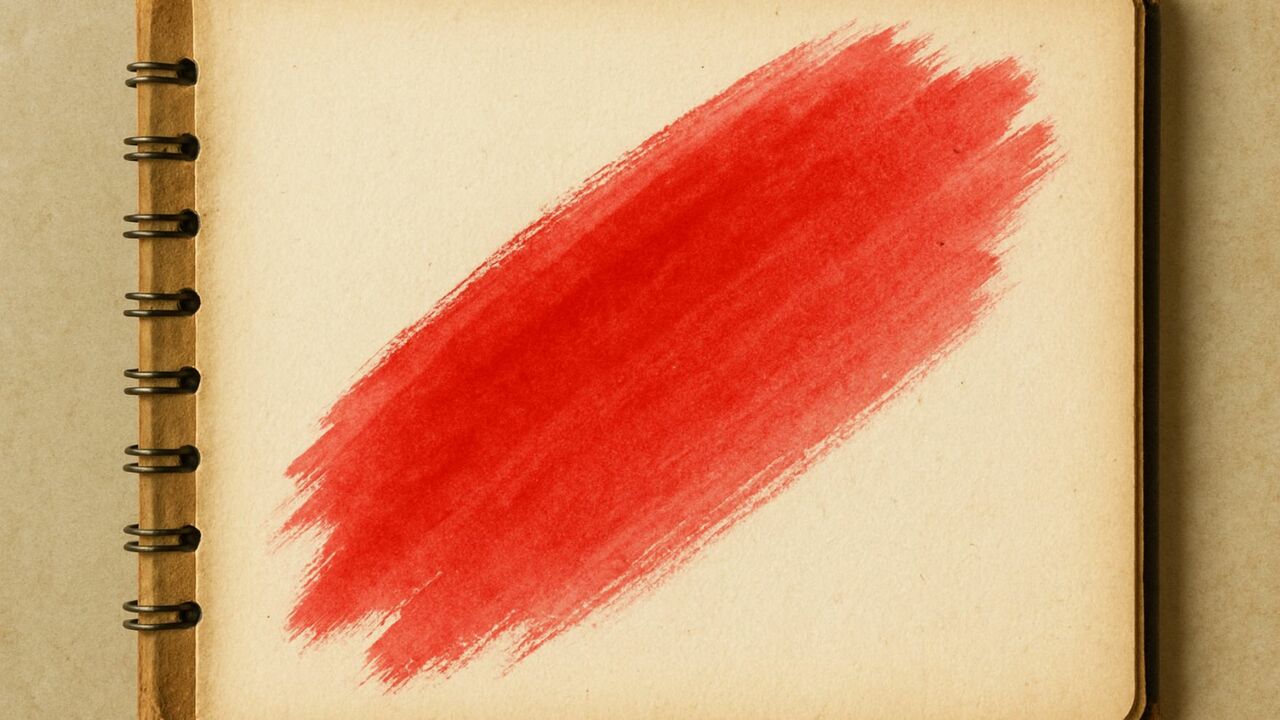最後に、司馬さんの作文につけられた短評についてふれたいと思います。昭和十一年度の旧制上宮中学校は五学年で二十五学級ありましたが、全部で二十六の作文が選ばれて、校友会雑誌の文苑欄に掲載されました。そして、一年二組の代表として司馬さんの作文が選ばれたのです。
司馬さんの作文につけられた短評を書いた先生の名前はありませんが、書いたのは、一年の国漢の授業を担当していた芦名先生で間違いないと思われます。なぜなら、一年生の全クラスの国漢の授業を芦名先生が一人で担当していたと考えられますし、作文の授業も芦名先生が担当していたからです。
そういった意味で、集まった作文の中からクラスの代表を選んだり、短評を書いたりするには、芦名先生が適任でした。また、校友会雑誌の編集をしていた文芸部の顧問も芦名先生が担当することが多かったこともつけ加えたいと思います。
短評の「素早い観察の中にも無邪気な空想が乗せてある」は作文が難波周辺の風景をスケッチ風に描写していることを指しているのだと思います。芦名先生の読解力の鋭さがよくわかる短評だと思います。
『私の小説作法』1で司馬さんは、「ビルから、下をながめている。平素、住みなれた町でもまるでちがった地理風景にみえ、そのなかを小さな車が、小さな人が通ってゆく。そんな視点の物理的高さを、私はこのんでいる。つまり、一人の人間をみるとき、私は階段をのぼって行って屋上へ出、その上からあらためてのぞきこんでその人を見る。おなじ水平面上でその人を見るより、別なおもしろさがある」と書いています(全集第32巻)。