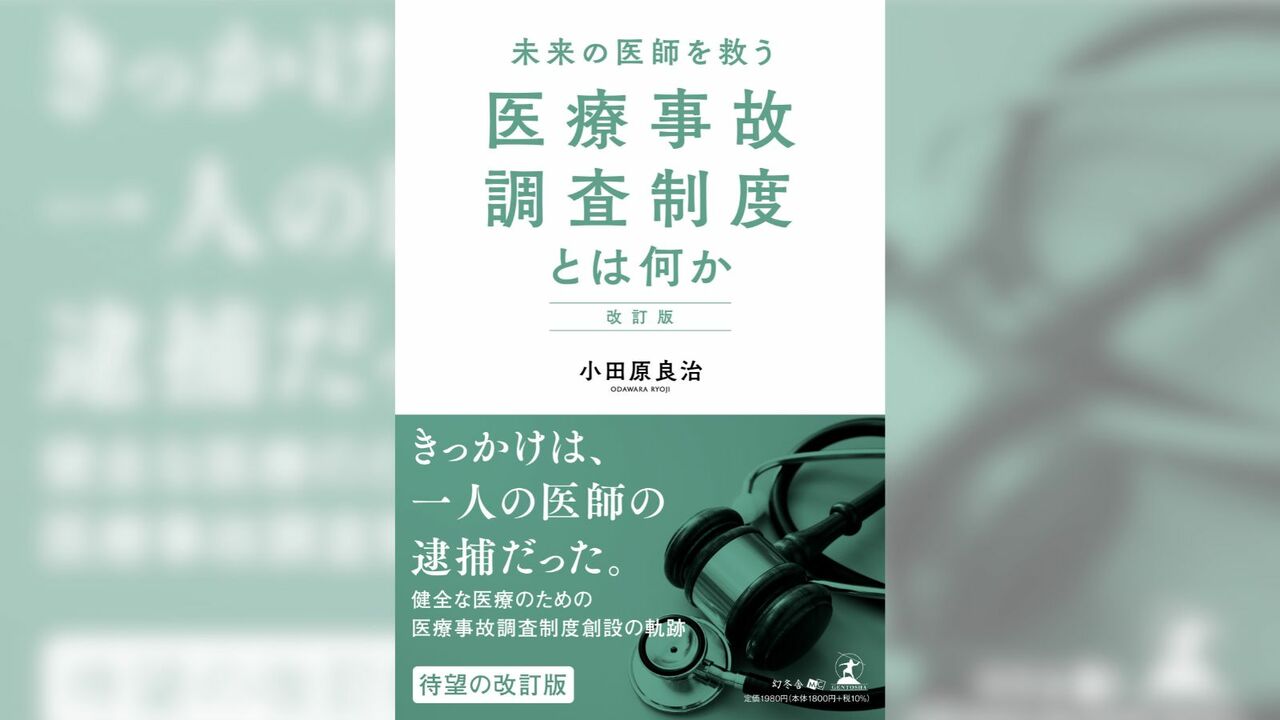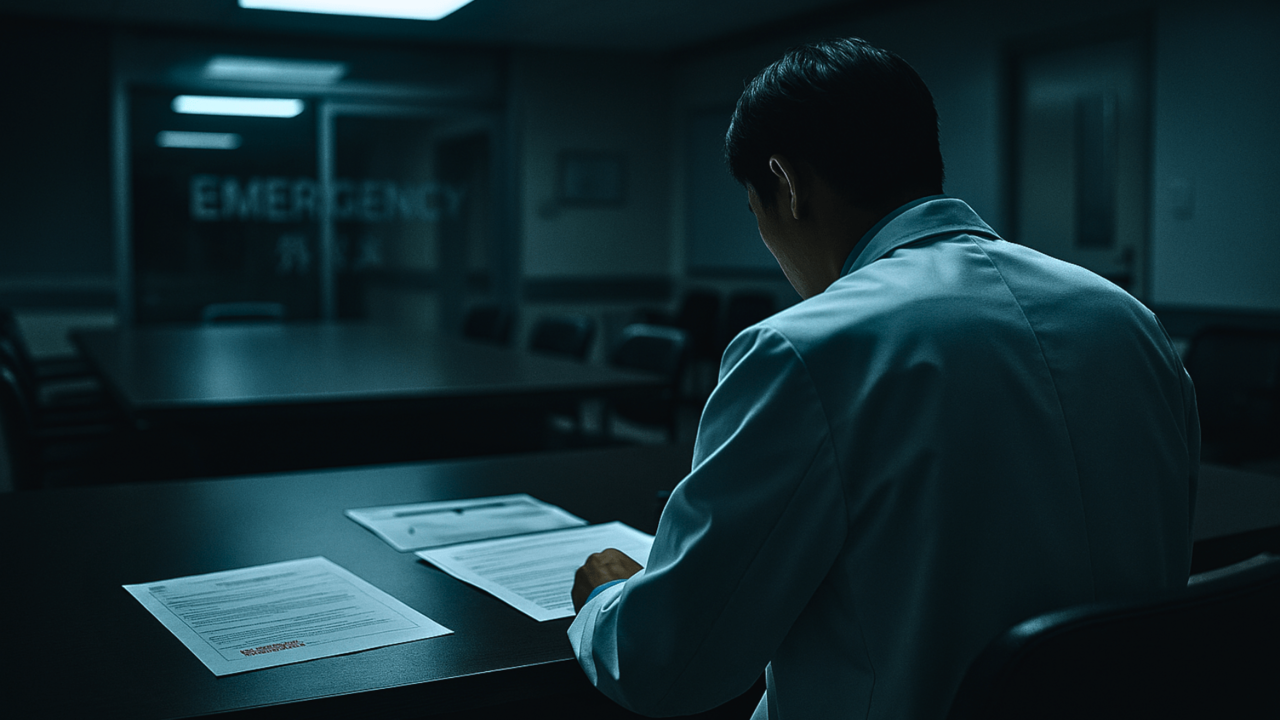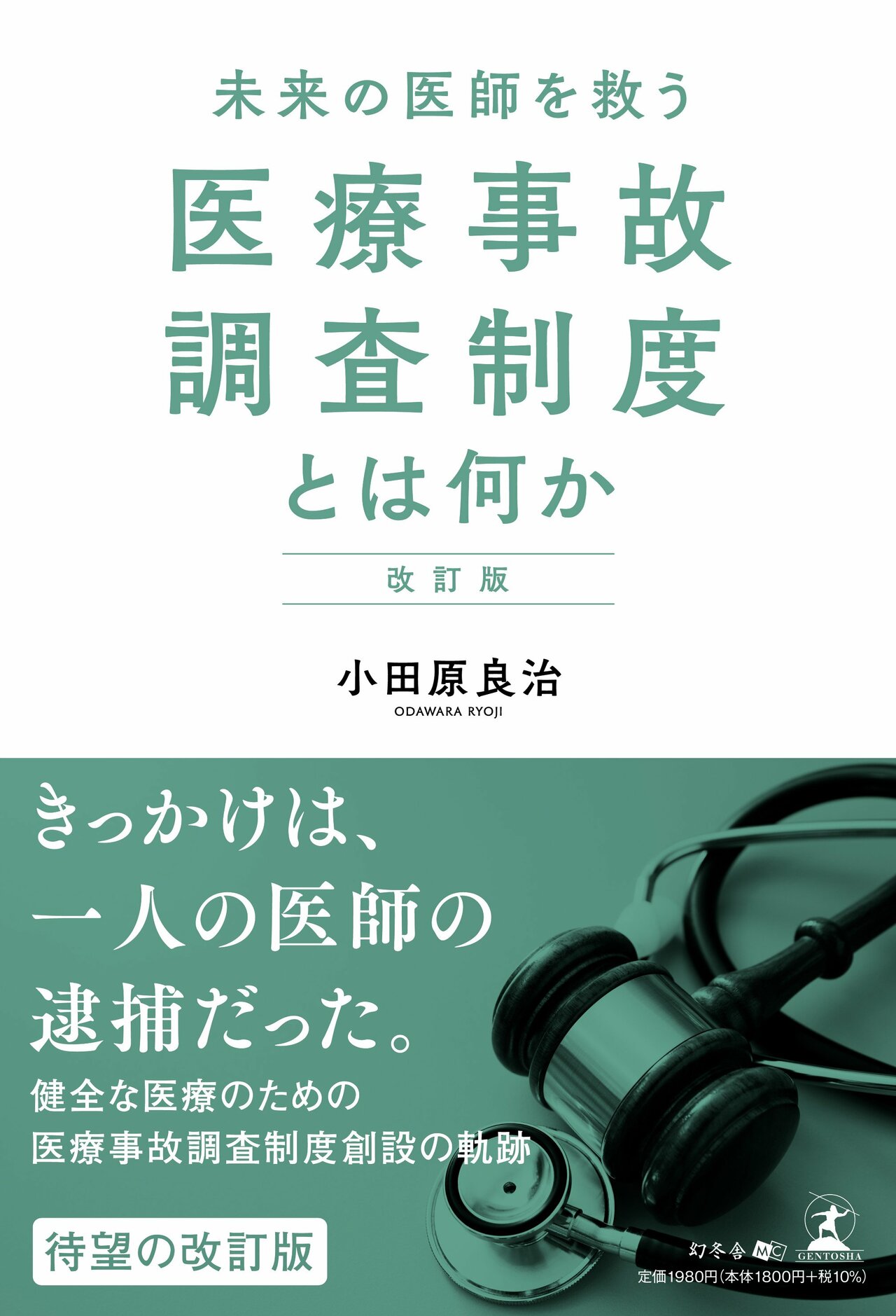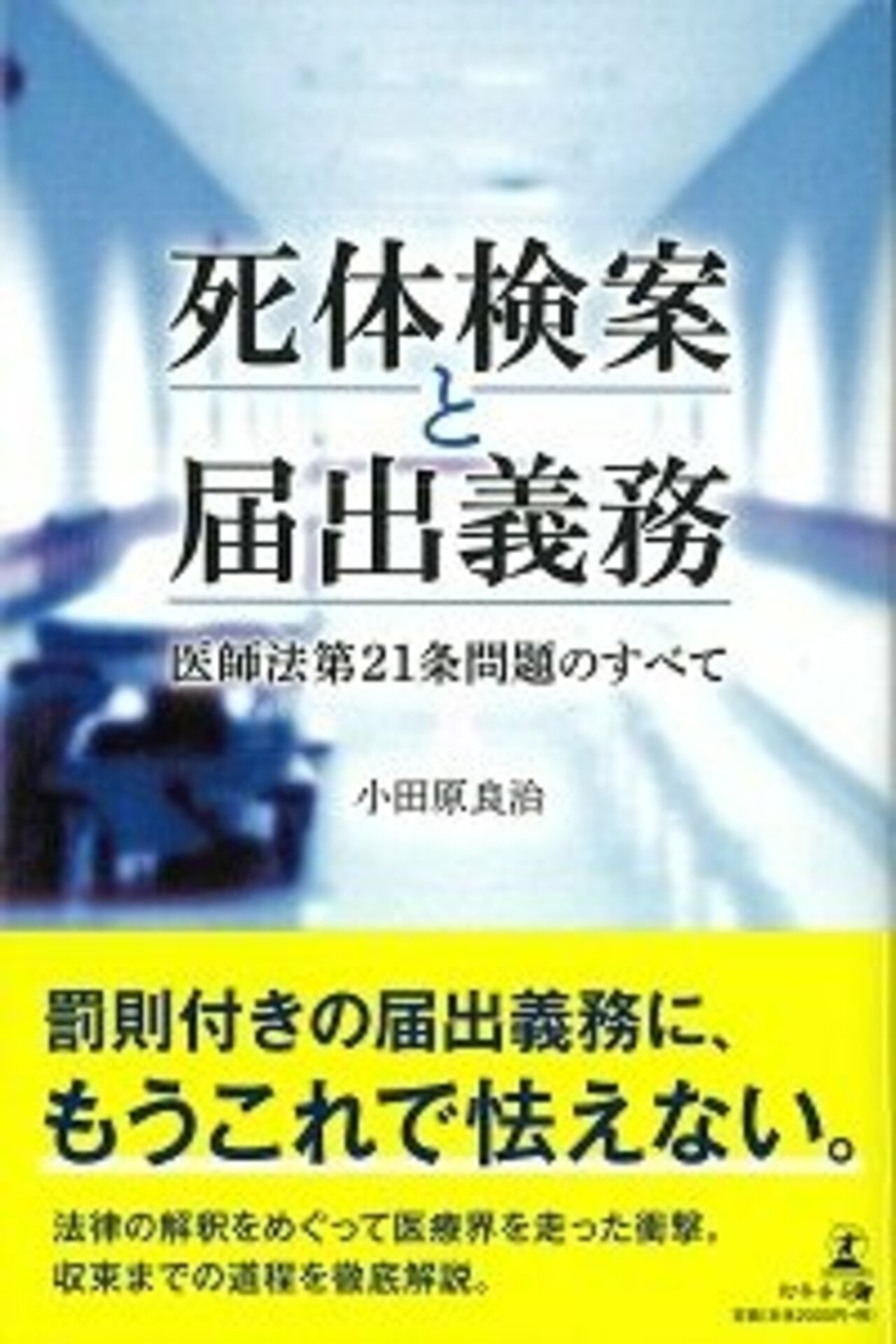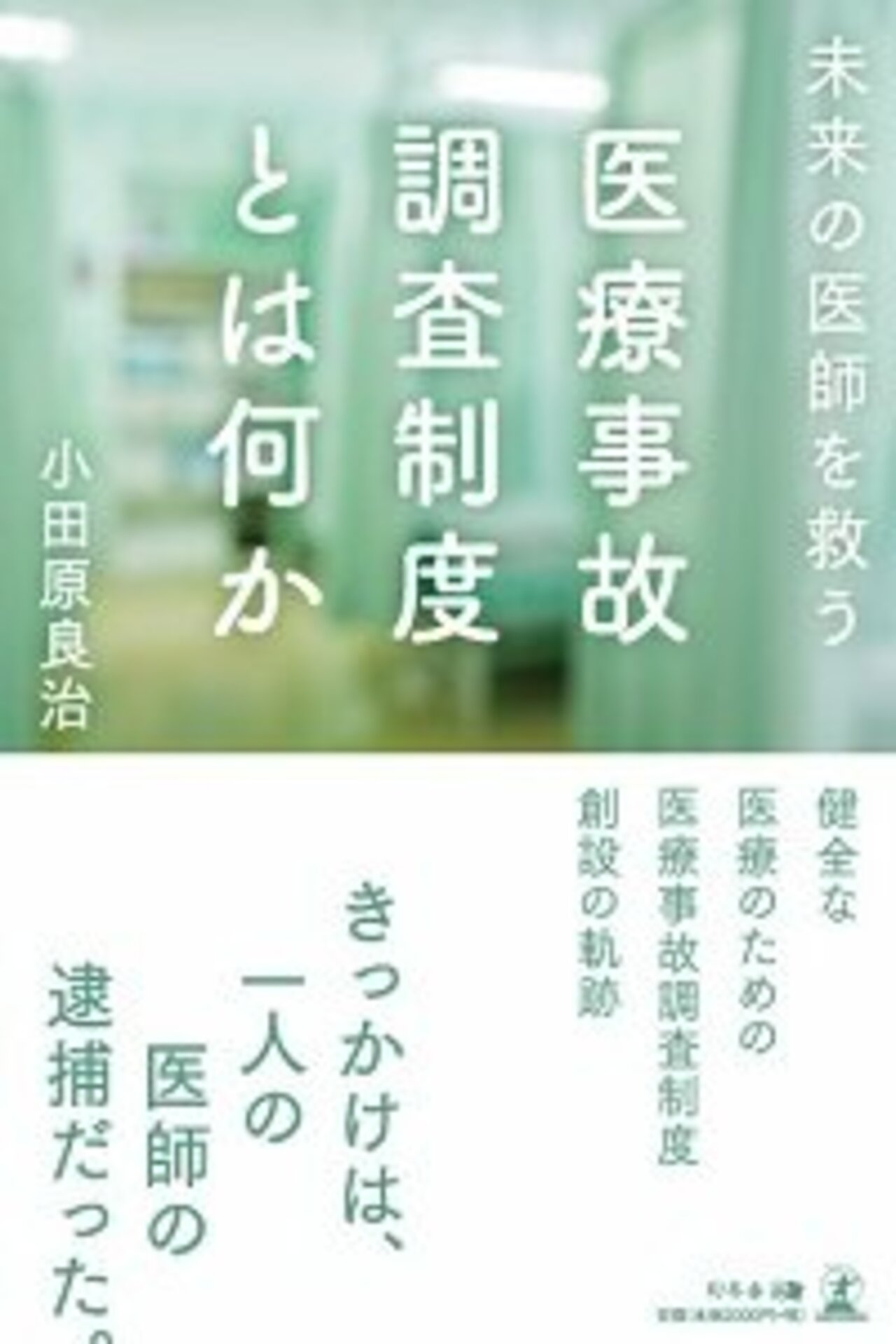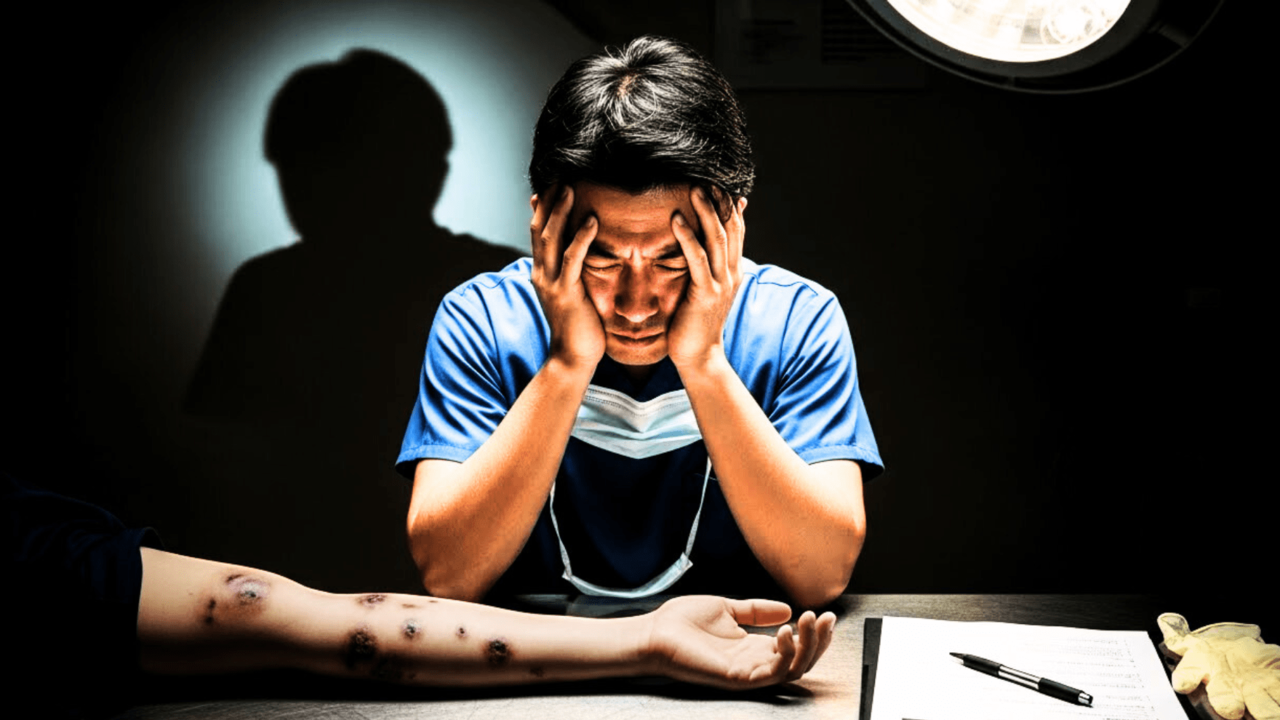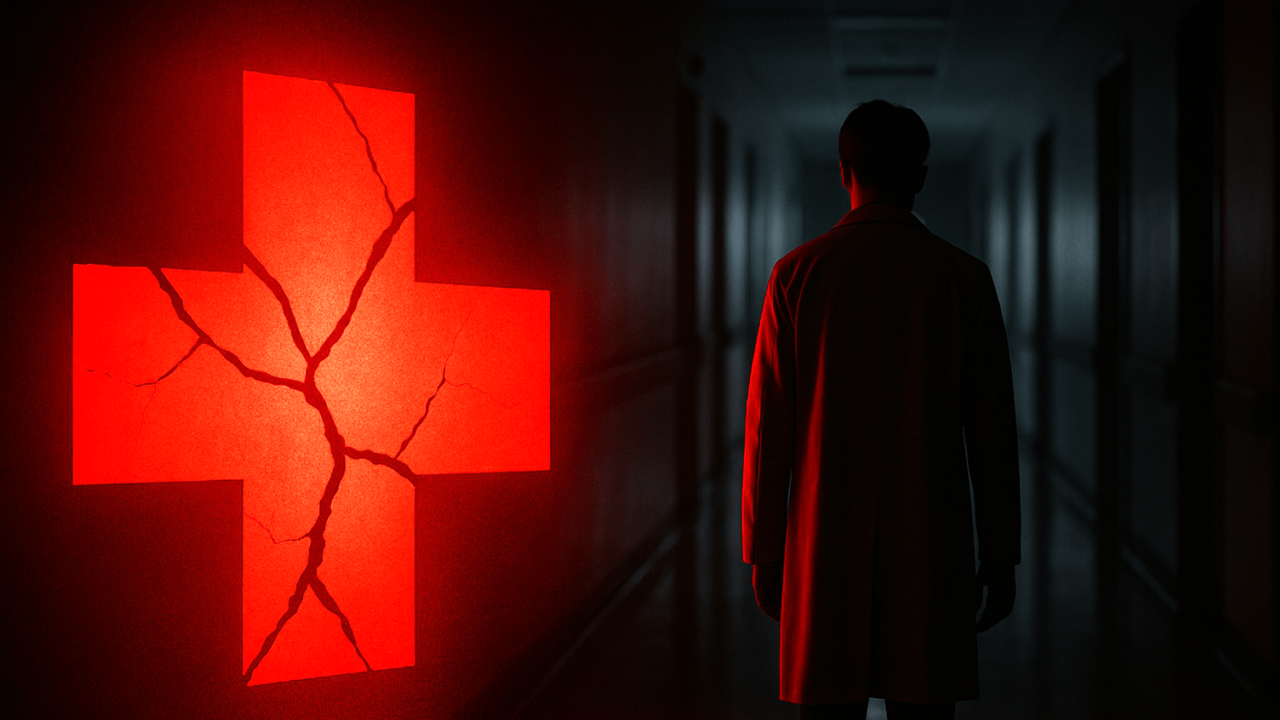【前回の記事を読む】なぜ医師は逮捕されるのか? 医師法21条の誤解が招いた逮捕リスクと医療崩壊
第1章 医師法第21条(異状死体等の届出義務)について
―医師法第21条は、異状死の届出義務ではない―
(5)東京都立広尾病院事件最高裁判決
人の一生の経過の中の、あるいは病気の経過の中の終局が「死(死亡)」である。この「死(死亡)」を証明するものが死亡診断書である。一方、その場に存在する「死体」を見分して、すでに死亡した「死体」であることを証明するものが死体検案書である。
死体を見分するに際しては、その死体が犯罪等との関わりがある可能性もあるので、「死体」に異状を認めた場合には警察に協力するように定められたものが医師法第21条の規定である。したがって、医師法第21条には「異常」ではなく、状態を現す「異状」の文字が使われている。この死亡診断書と死体検案書の関係、検案の意義、異状とは何かが争われたのが東京都立広尾病院事件裁判である。医師法第21条についての要の判例なので詳述したい。
この事件は、都立病院で、看護師がヘパリン加生理食塩水と消毒液を間違えて注入し、患者が死亡した事件である。この死亡した患者の右腕の点滴部分には、静脈に沿って、赤い色素沈着が認められた。同病院の院長が医師法第21条違反で起訴された。同院長は、1審、2審ともに有罪となり、上告したものである。
上告審の争点は(1)生前に患者であった者について死後見分することは、「検案」に当たるか否か、ということと、(2)仮に、生前に患者であった者に対して行う死後の見分が「検案」に当たるとしても、業務上過失致死等の刑事責任を負うおそれのある者に警察への届出義務を課すことは、憲法第38条1項の自己負罪拒否特権に違反するのではないか、ということであった。
(1)について、法医学用語辞典等では、「『検案』とは、医師が死者の外表検査により死因や死因の種類を判定する業務」とされていたが、この死者に、診療中の患者であった者が含まれるか否かが問題となった。当時は、「死体検案書」と「死亡診断書」の使い分けに関して、「死体検案書」は、原則として、診療中の患者以外の者が死亡した場合に作成されるものとされていたのである。