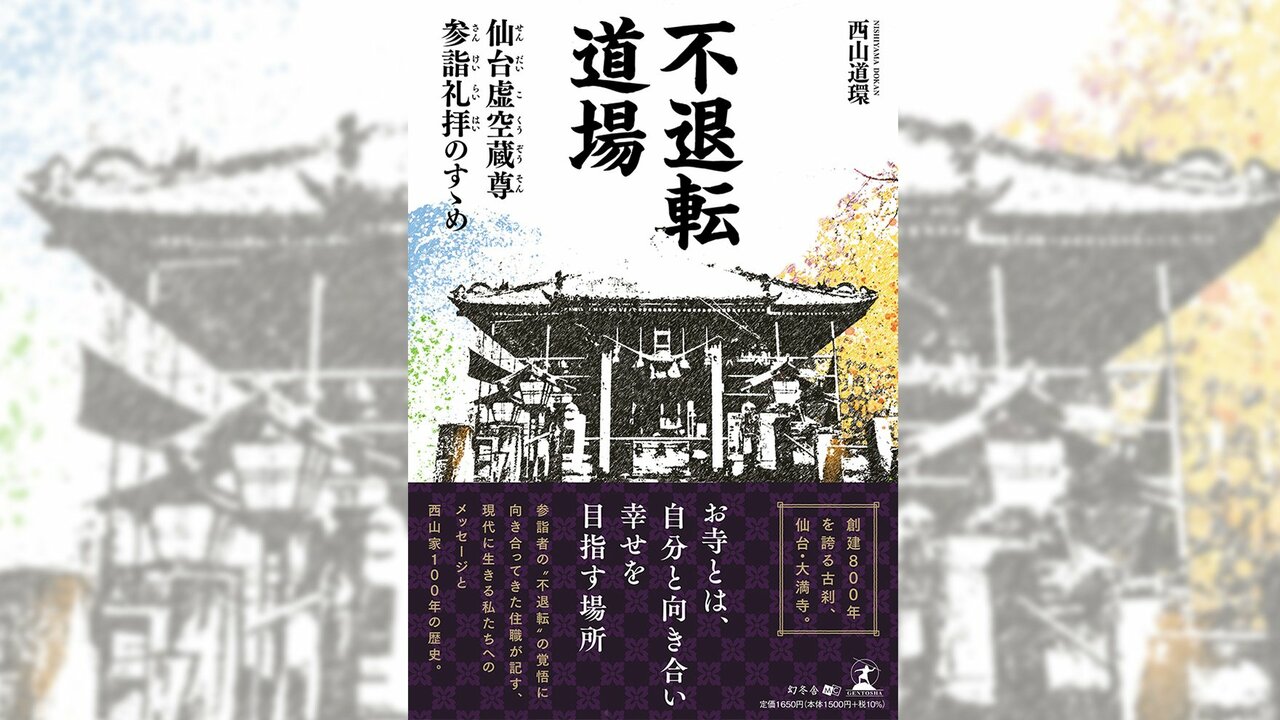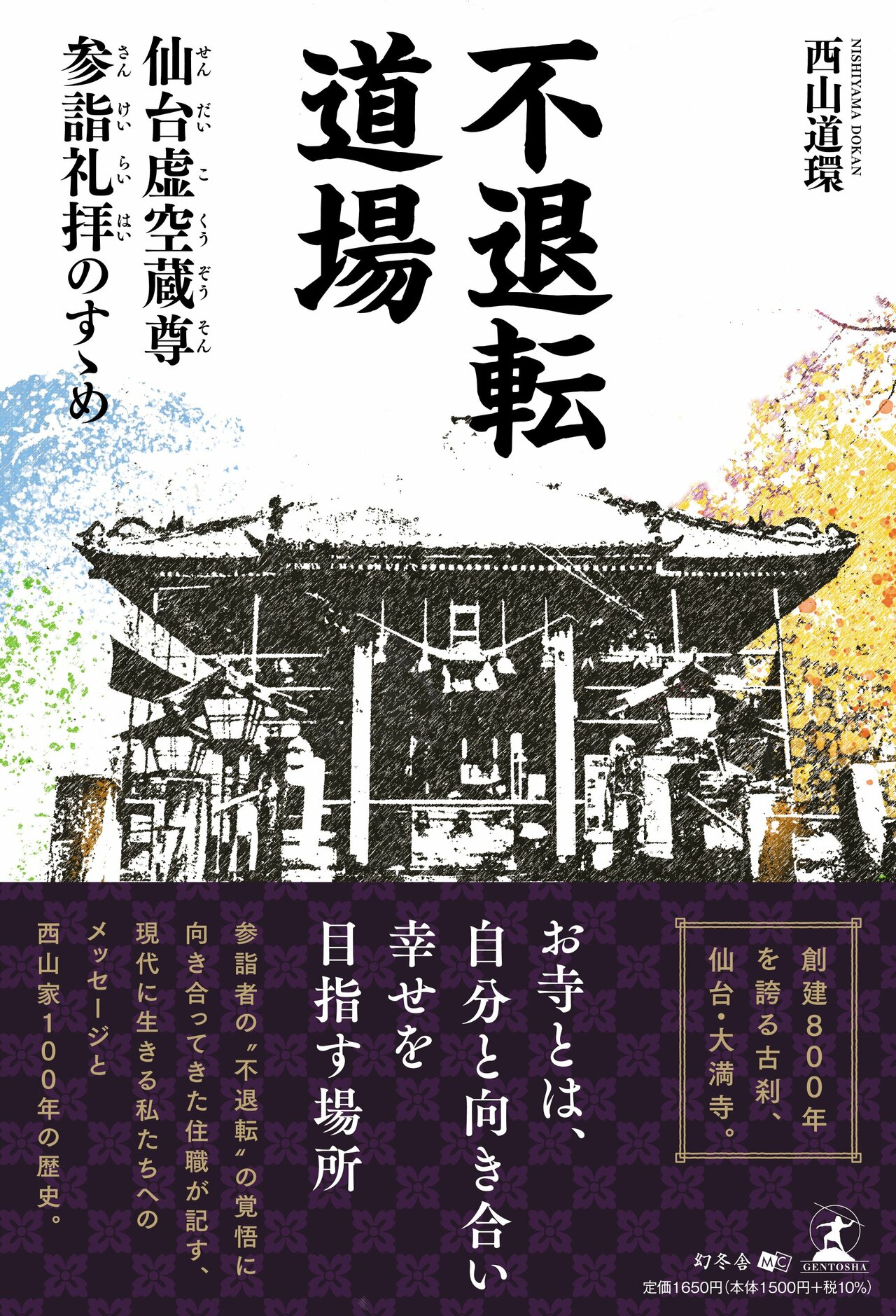【前回の記事を読む】少子高齢化に、お墓に対する意識の変化…お寺の役割は機能不全状態?
寺院にとっての宝とは
しかし米寿を迎えた令和五年、福島さんは急逝され仏の世界へ旅立たれました。亡くなられた日もお寺にお越しになられ、元気なご様子で談笑して寺カフェで一緒に食事をしてくださったばかりだったので、次の日に訃報をいただいた際には信じられませんでした。
大切な方が亡くなってから気付くことがございます。福島さんが大満寺にとってどれだけ大きな存在だったかを旅立ってから感じました。福島さんを失った大満寺はこれから護持できるのだろうか、そんなことさえ頭に浮かびました。
大きな喪失感に襲われ、寺院サポーターの鑑、大満寺の応援団長としての存在がどれだけ住職にとって心強かったのか、福島さんのような方がおられたことで八百六十年以上大満寺は護持されてきたのだなと改めて感じたのでした。
福島さんはお寺にとっての宝であったと思うとともに厳しい冬の時代を迎えたお寺にとって福島さんのように菩提寺を拠り所としてくださる方を今後どう教化すれば良いのだろうかと先行きに大きな不安を感じました。
では、福島さんが菩提寺の住職である私に期待したこととは一体何だったのでしょうか? 福島家の御先祖さまが眠る菩提寺である大満寺を次世代に繋いで欲しいということ、自らの人生を終えて仏の世界へ旅立つ際には正しくお涅槃に導いて欲しいということ、福島家の安寧、家門繫栄、子孫長久を祈願して欲しいということ、いろいろあったでしょう。
旅立たれてから、いま思うことは福島さんは仏・法・僧の三宝の大切さを言葉でなく生き方として理解されていたのだと思うのです。福島さんの生き方には住職と檀信徒としてお釈迦さまの御教えの下に一方通行ではなく、尽くし尽くされお互いがリスペクトし合う関係がありました。
檀家、檀信徒の由来にもなっていることですが、私たちが普段使う旦那さまという言葉は「檀那」(ダーナ)というサンスクリット語で相手に尽くすという意味から来ております。