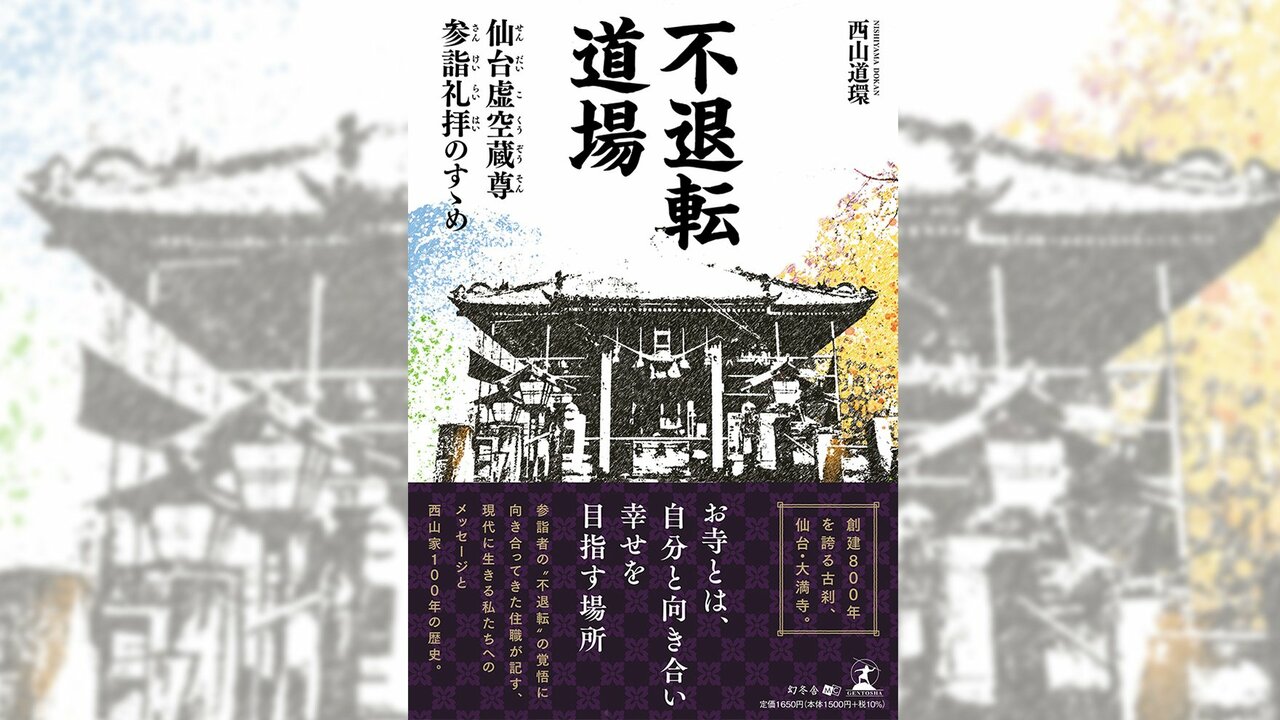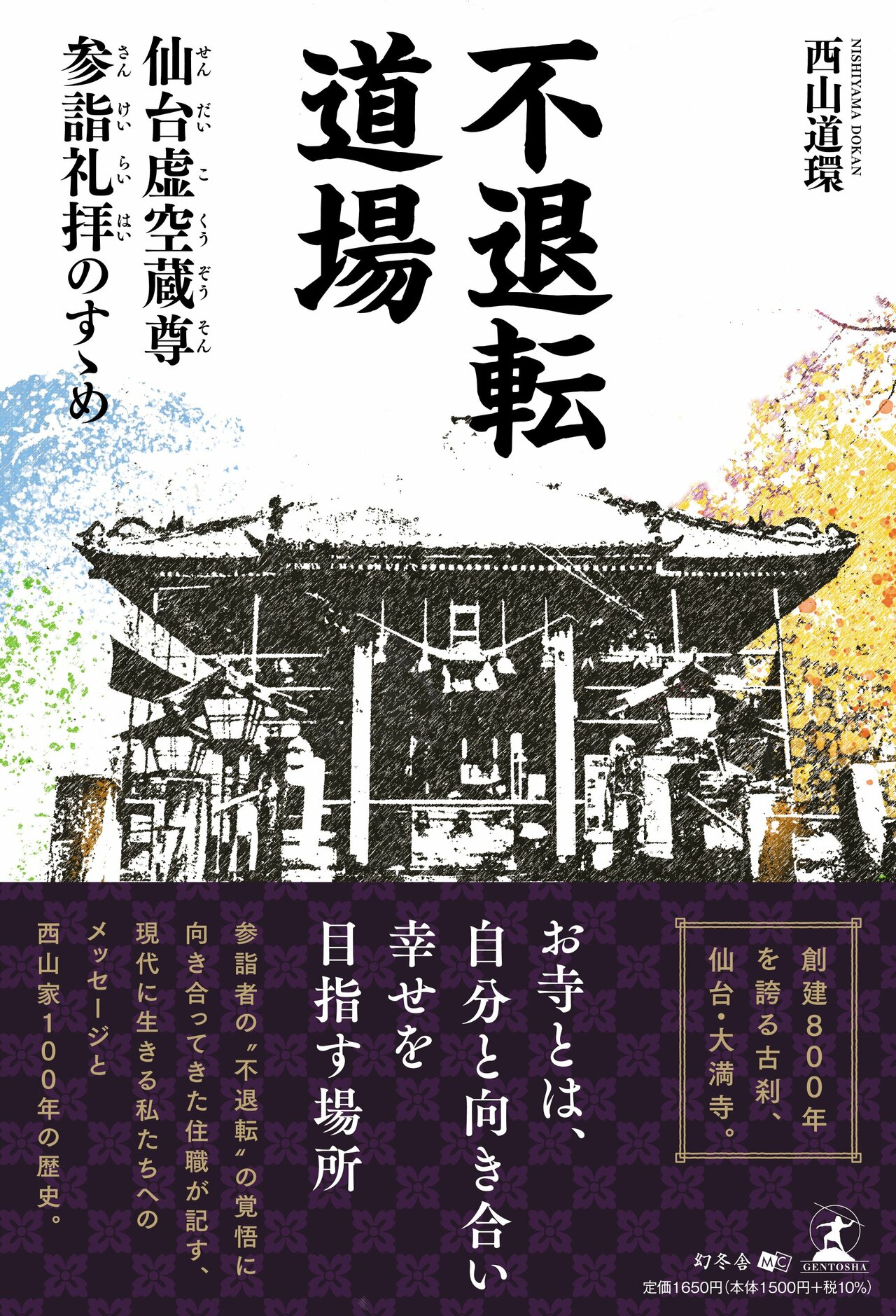【前回の記事を読む】【人は亡くなるとどうなる?】十三仏の導きと法名に込められた"還る"という祈りの意味
寺院にとっての宝とは
古代、聖徳太子も「篤く三宝を敬いなさい」と十七条の憲法の中であらわされておられますように、寺院にとって最も大切なことは仏・法・僧の三宝であります。
お釈迦さま(仏)とそのお釈迦さまの教え(法)、その教えを守ってきてくださった方々と一切に関わる人たち(僧)、これら仏法僧が一体となり、拠り所としている場所が寺院であり、仏、法、僧を三つの宝で「三宝」と申します。ですからこの三つの宝がない場所は寺院とはいえない訳でございます。
御存知のように現代日本では少子高齢化が急速に進んでおります。当山、虚空蔵山大満寺がある太白区向山は仙台市の中でも特に少子高齢化が進んでいる地域です。私が通っていた小学校では四十年前と比べて生徒数が四分の一まで減少しております。
今後も人口減少が続くとみられており、あらゆる場所、様々な場面で弊害が出ると思いますが、当然寺院にとっても人がいないということは先祖代々のお墓を護る方がいなくなることであり深刻な問題であります。檀信徒の減少とともに、それに拍車をかけるのが日本人の意識の変化であります。
先祖代々の御先祖さまが眠られる菩提寺として仏事を執り行い心の安らぎを得る場として、数百年の昔から地域社会のコミュニティとして活用されてきた寺院ですが、菩提寺に対する意識の低下によりお寺が持っていた役割が機能不全に陥りかけております。
家族についての考え方やお墓に対する意識の変化などから墓じまい、樹木葬、散骨、永代供養等のキーワードが先行する供養の多様化による檀信徒の減少が進んでいます。
戦国時代の覇者、織田信長公が最も愛した側室「吉乃(きつの)」の生家・生駒家の菩提寺である愛知県江南市の昌久寺(きゅうしょうじ)が廃寺になったことをネットニュースで知りました。
お寺の老朽化が進み、維持管理するのは財政面からも困難などとの判断から廃寺が決まったようです。このように全国的に見ても近頃では廃寺やお寺の吸収合併などもゆるやかに始まっております。寺院を取り巻く環境がこのような現状であるから今後、世襲で継がれることも多かった住職の後継者不足も顕在化してくるでしょう。仏・法・僧の三宝が保てない危機に瀕するなかお寺を次世代に残せるのだろうか?
そんなことが胸中にある寺院関係者も多いかと思います。