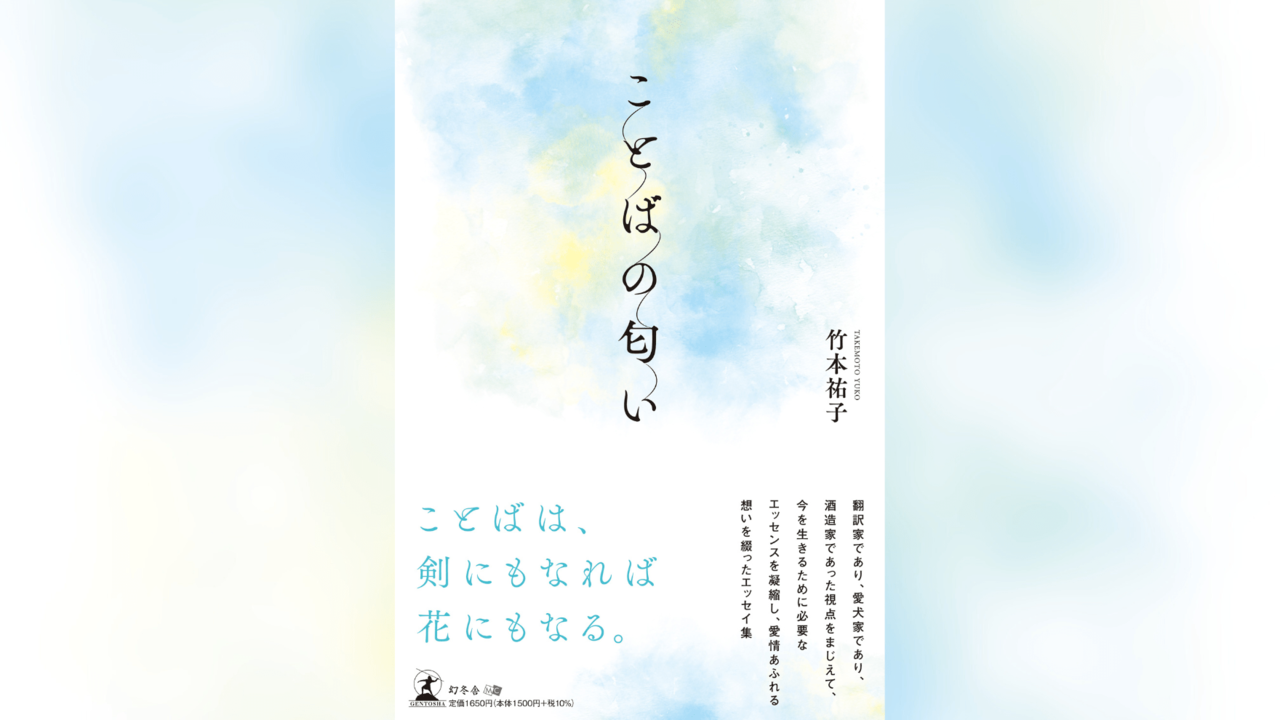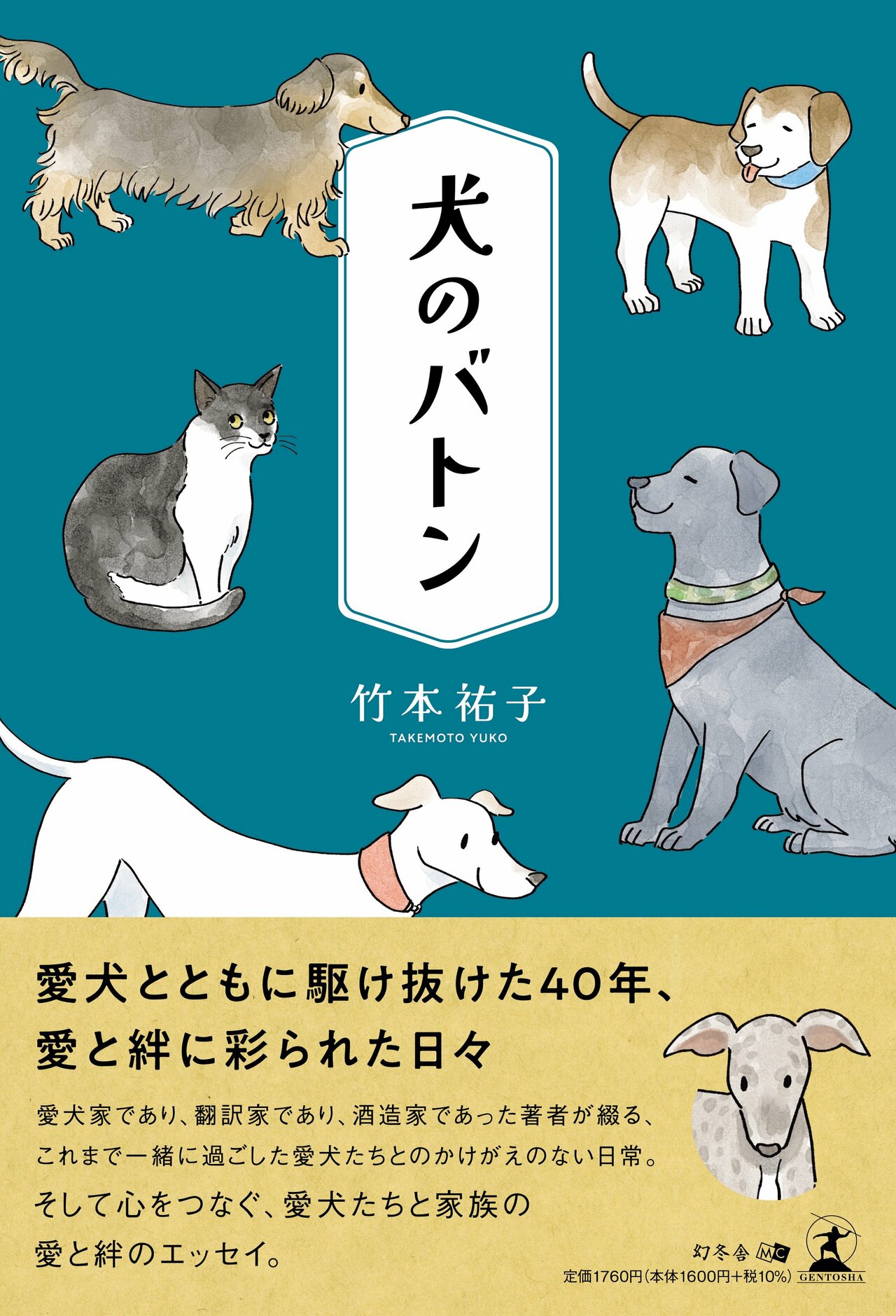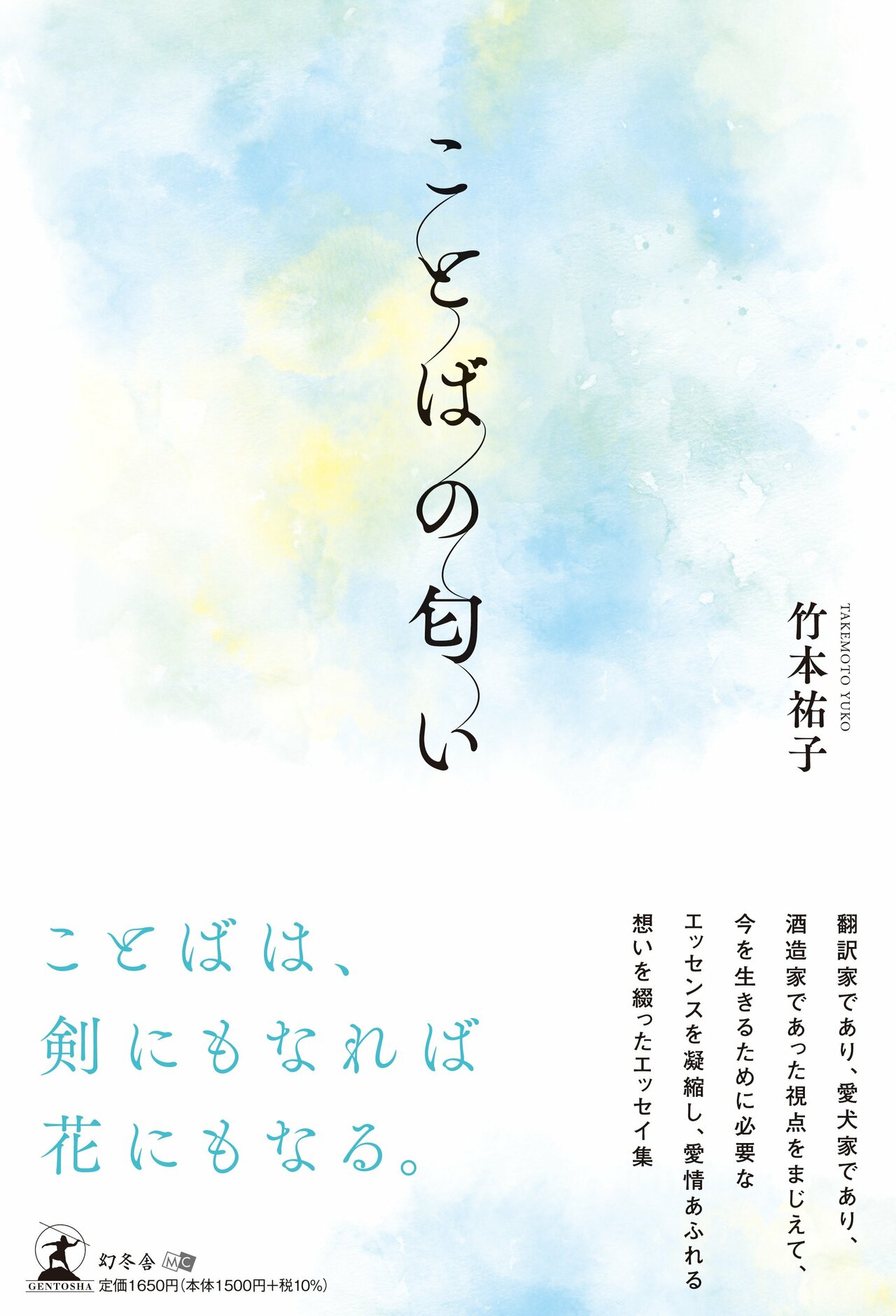【前回記事を読む】ミョウガを食べると物忘れがひどくなるってホント?
第二章 洋の東西
鏡の国
鏡と鏡を相対させると、そこには不思議な世界が展開する。
影絵の森美術館では、作品の左右に鏡を配してあった。覗き込むと、タイムトンネルのように幾重にも永遠に連なる影絵の世界があった。ひょっとしたら見る者もその中へ踏み込んでいけそうな錯覚を覚える。
松本市美術館の展覧会でも、お馴染みの水玉の前衛芸術作品にまざって、暗い部屋にぼうっと浮かび上がる縄梯子のような作品があった。床と天井に貼られた鏡が、縄梯子を上は天国へ、下は地獄へと繋げている。下を覗けば、奈落の底へと落ちていく犍陀多(かんだた)が見え、上には豆の樹を元気に登っていくジャックが見えるようだ。
たかが鏡二枚あるだけなのに、光の反射作用とかき立てられる想像力で、そこには別世界、異空間が広がる。
そんな鏡の国でありったけ不思議な体験をしたのはアリス。ルイス・キャロルの一八九六年の作品である。兎のあとを追いかけて迷い込んだ「不思議の国」ではトランプの女王と出会うが、続編ともいうべき「鏡の国」では、登場人物がチェスの駒であり、アリス自身もゲームの一員として物語が進んでいく。
斬新奇抜なストーリー展開と実験的文体、ファンタジーの要素盛りだくさんの物語は、百年以上も前に書かれた作品とは思えない。造形であれ、文章であれ、異才の作品に触れると、何やら不思議な気分にさせられる。
(二〇〇五・九)