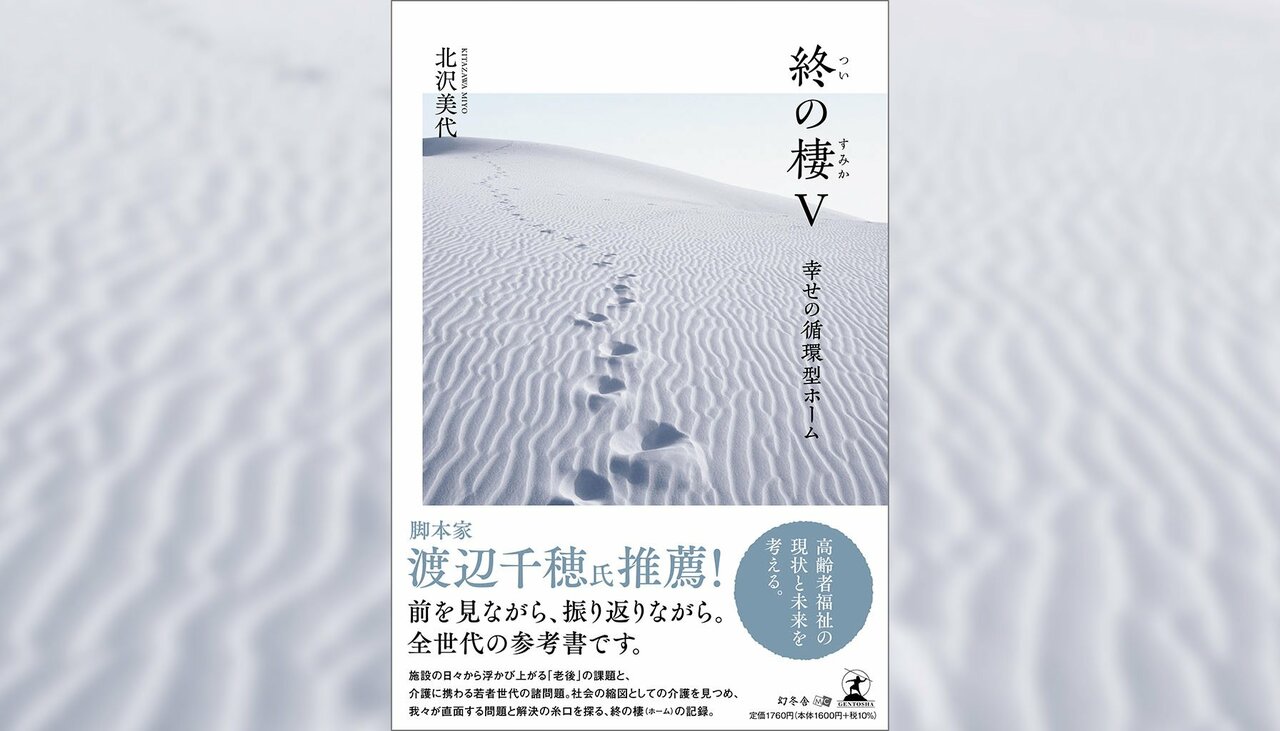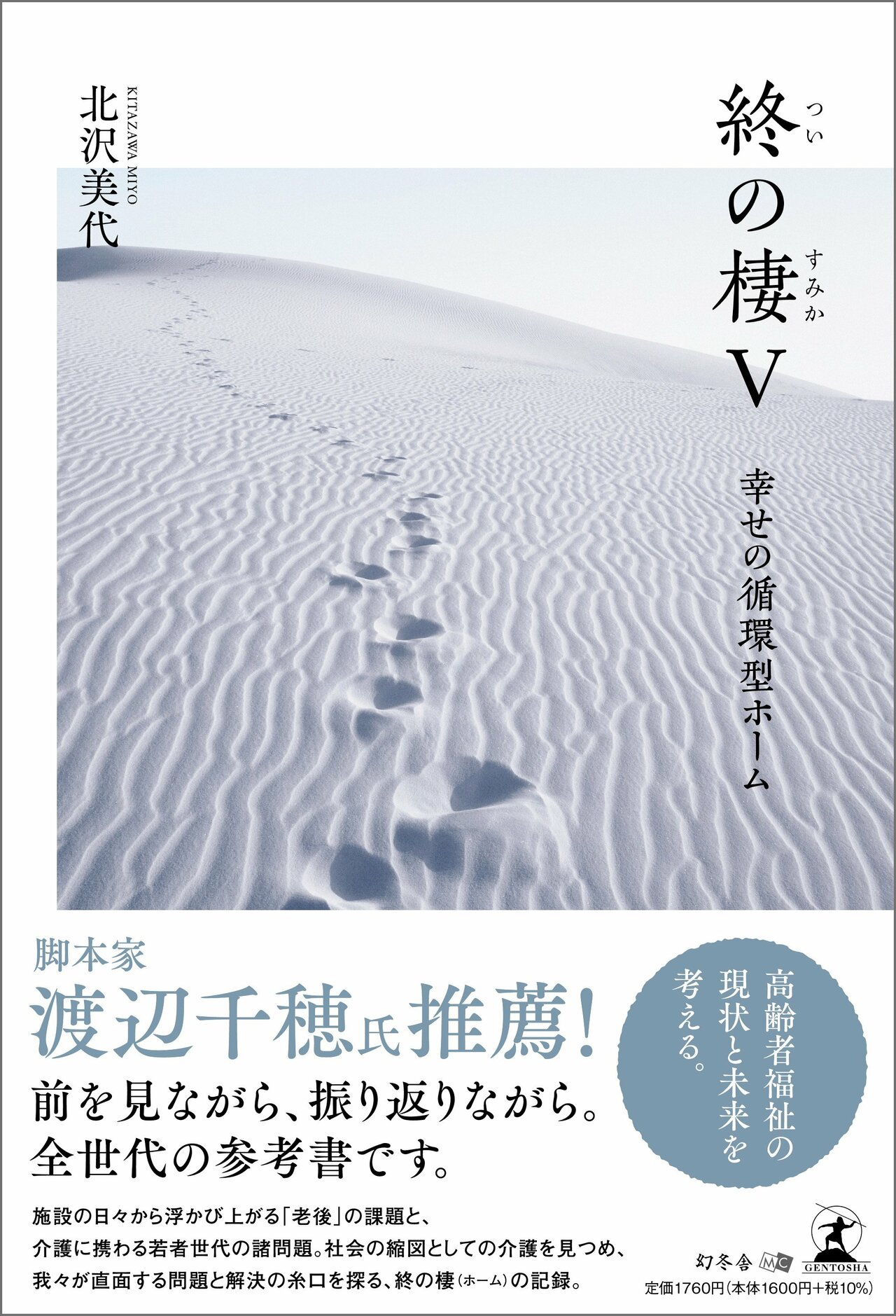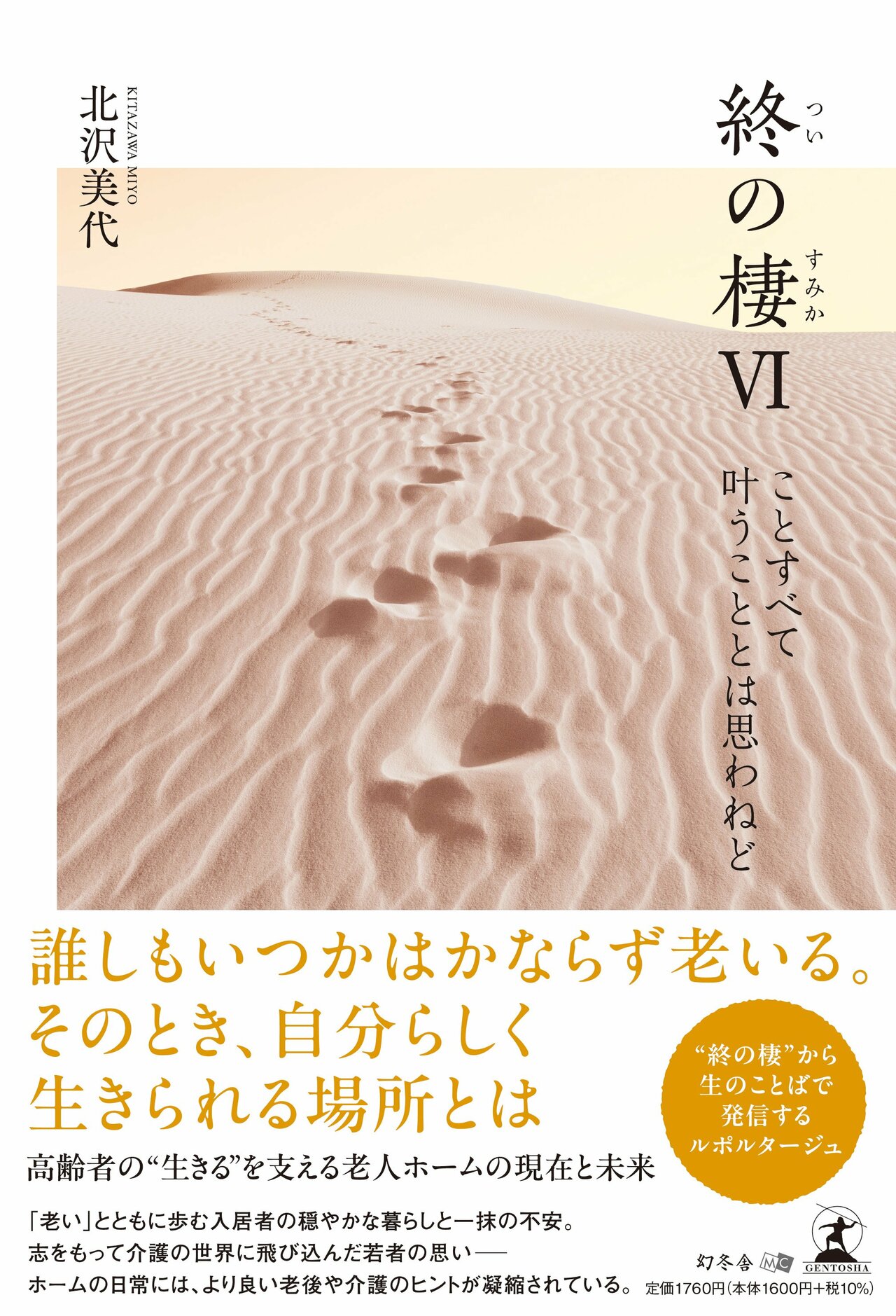【前回の記事を読む】母親は娘に下の世話をさせるのを嫌がっていた。すると娘は「お母さん、今日から私がお母さんよ」と呼びかけ、母は…
第二章 これが老いなのか、誰もが迎える不確かな世界
「自分」であって「自分」でない
何のこと?と読者は思われるかもしれない。私が老後を家で暮らしていたら遭遇しなかったかもしれないこともある。しかし老人ホームでこの「自分」であって「自分」でないは決して珍しいことではない。
イタリアさんも入居当初、食事が終わると「お代はいくら?」と尋ねていた。
ショートステイで入ってきた人で食後に「お代は? どうしたらいいの。私、お金を持っていないんだけど」と不安そうに尋ねた人は一人や二人ではない。
誰しも、「タダ食い」「無賃飲食」など「自分」ではないのだから、不安になって尋ねるのは当然である。
入居当初、水戸さんは娘さんが水戸さんのほしいものを届けに来ていた。その時水戸さんはいつも不満そうな顔をした。
「ママのお金から出したのだから心配いらないわ」と必ず言われるのだが、水戸さんにしてみれば自分の手元の財布から代金を払うと思っているので私にもその娘さんの言ったことに納得がいかず、その不満をぶつけていた。自分が握った財布から出さない支払いは「自分」のものであって、「自分」のものではないからだ。
お金に関してだけではない。私の隣り席のコウリャンばあちゃん、入居当初、ごはんが運ばれてくると「こんなに食べれないから半分にして」とスタッフに言っていた。
しかしスタッフは決まって「ご家族から、お母さんにはしっかり食べてほしいと言われています。召し上がれなかったら残して下さってけっこうです」と言ってそのまま去っていく。
コウリャンばあちゃんは「もう百歳に近いのにこんなにたくさん食べれないわ」と愚痴る。そして「残すなんて、もったいない」とつぶやく。
我々の世代は配給の時代である。家庭でも同じ状況だった。兄、私、妹の三人に母が分けてくれた食事の分量は多分兄が一番多く、次いで私、そして妹の順だったと思う。しかしそれに文句は言わなかった。それしかないということを子ども心に知っていたからだ。
私にもこんな思い出がある。祖母がいつもごはんを一口残す。私にしてみれば一口にも満たない量なのだ。しかもそれを次の食事の時のために戸棚にしまう。
さすがに私は次の食事までとっておくことはしないが、最後のあと一口が食べられないことがままあるのだ。
食べられなければ平気で捨てるのは「自分」ではないのでコウリャンばあちゃんは愚痴るのだ。しかし彼女はおかずはすべて食べる。完食である。野菜は残さず食べるが、肉、ソーセージ、玉子料理はたいていその三分の一を残す私よりずっと優秀だ。
それで私はスタッフに言った。「娘さんがいらしたら私からちゃんとお話ししますからごはんを当人の食べれる量にしてあげて下さい」
こうして初めてコウリャンばあちゃんのごはんの量が減らされた。ようやく「自分」を取り戻したのである。それも隣りに私という強い支援者がいて実現した「自分」なのだ。