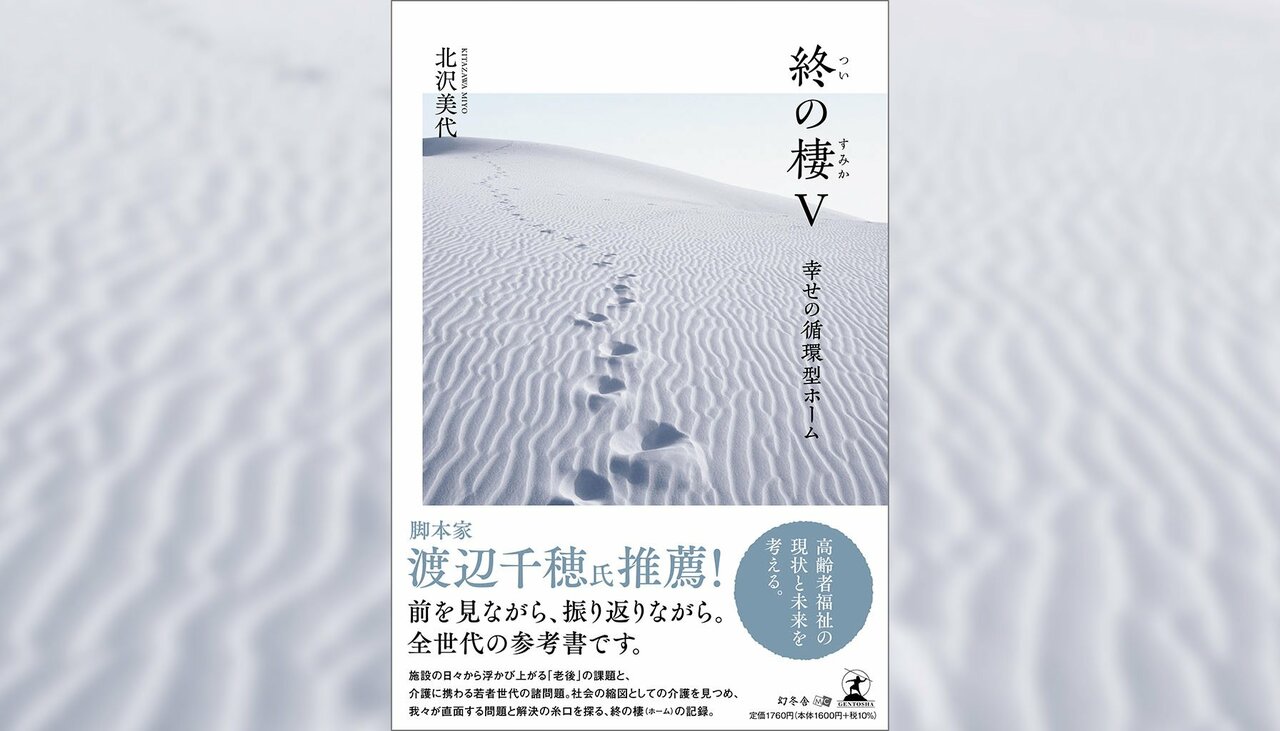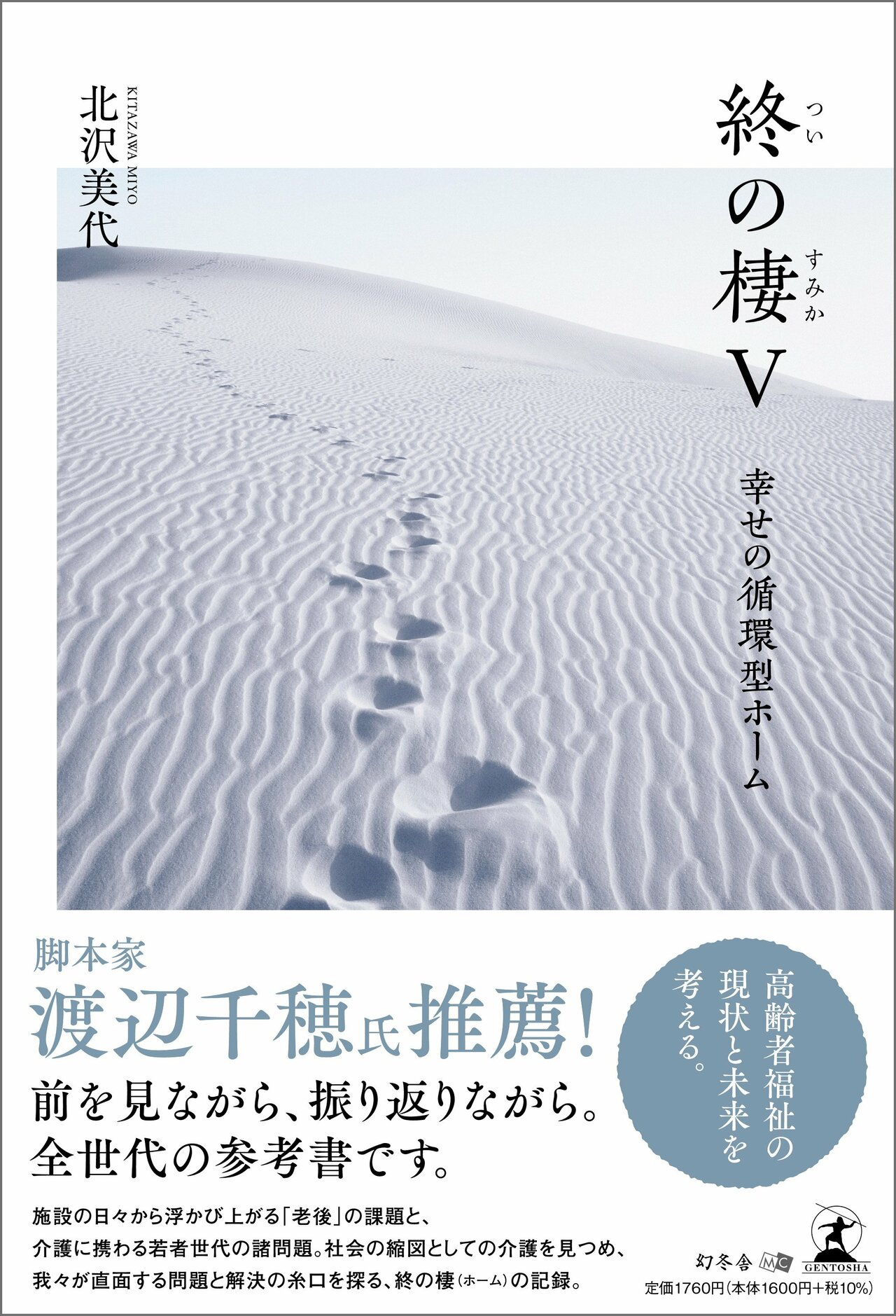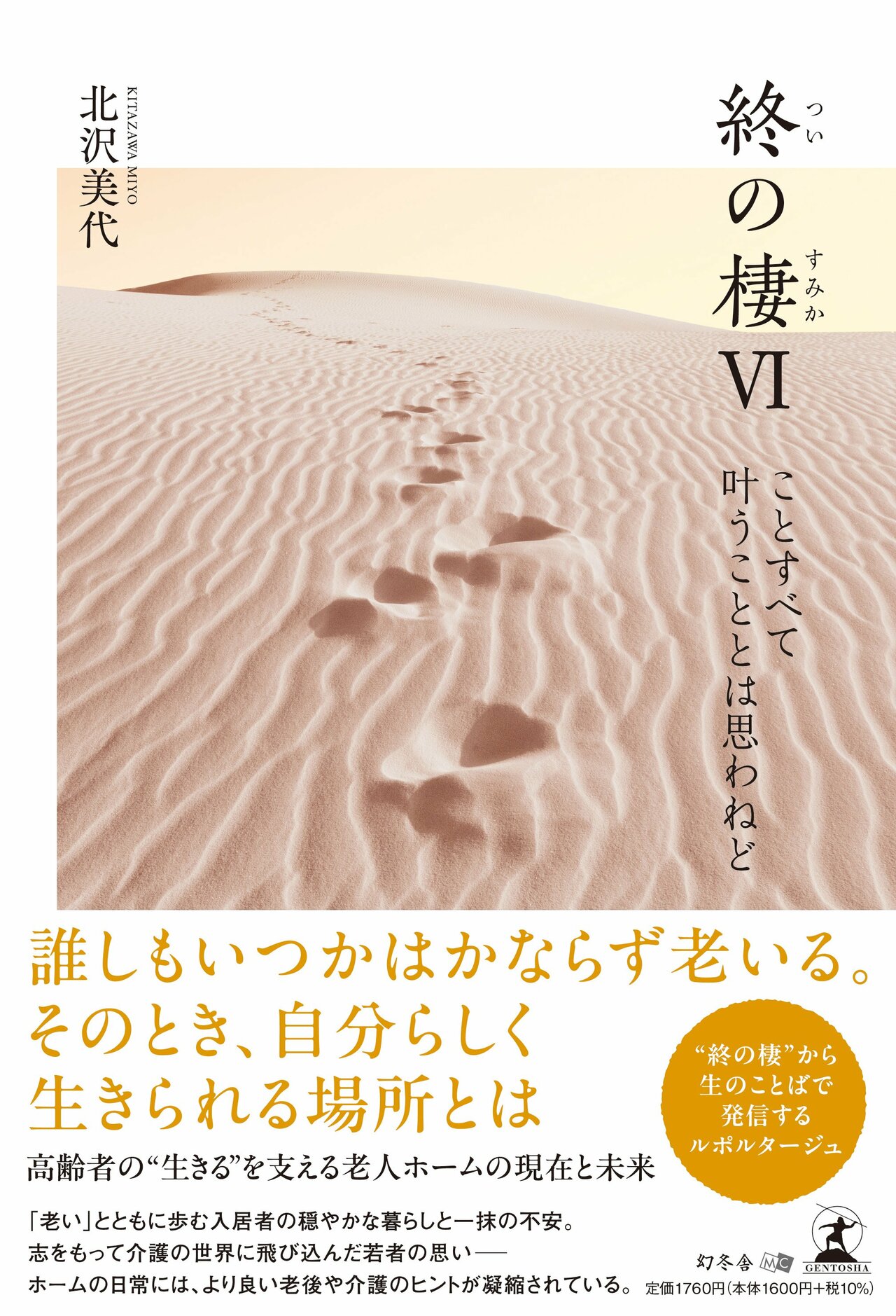【前回の記事を読む】結核を患い、ひとりで暮らしていた祖母。亡くなった時に見つかった手垢のついたノートをひろげると、そこには…
第二章 これが老いなのか、誰もが迎える不確かな世界
とりあえず
私はまだナースコールを押したことがない。『終の棲』シリーズを書き始めた時、「介護」「老人ホーム」は看取りを以て完結すると考えていた。しかし冷静に考えてみればそんなことはあり得ないことだ。
ちょうど祖母の最後の頁の文字が流れて読み取れなかったのと同じだ。何を書き残したかったのかな、という無念さが私の胸の内に淀んでいる。それで私はこの「とりあえず」を思い付いたのだ。
「とりあえず」は途次の表現だから最終点に至らなくても今の私が書き残すことができる。こんな適切な表現はないと自ら満足しているのだ。
ナースコールも押せない、つまり他人のスタッフに下の世話をしてもらわざるを得ないということである。今までまともに向き合えなかったのはその屈辱感である。自身を忌々しく思う自分に耐えられなかったからだ。
しかし今の私ならばなんとか書き終わらせられる。屈辱的で忌々しいのが「老い」ならばそのまま書くしかない。それには「とりあえず」書くしかない。それが今の正直な気持ちである。
人は生まれてきた時、自らは何もすることができない。しかしその赤ん坊は日々、月々「できる」が増えていく。
「老い」は「できない」が日々、月々増えていく。長い人類の歴史の中で誰もこれを繰り返してきた。これを循環というのだろうか。
この時、私は昔母親を介護していた女性の「お母さん、今日から私がお母さんよ」と いう呼びかけを思い出していた。
母親は娘にも下の世話をさせるのをイヤがっていた。ある時その娘さんが「お母さん、今日から私がお母さんよ」と呼びかけた。その日から少しずつ少しずつ抵抗感をなくしていったという。