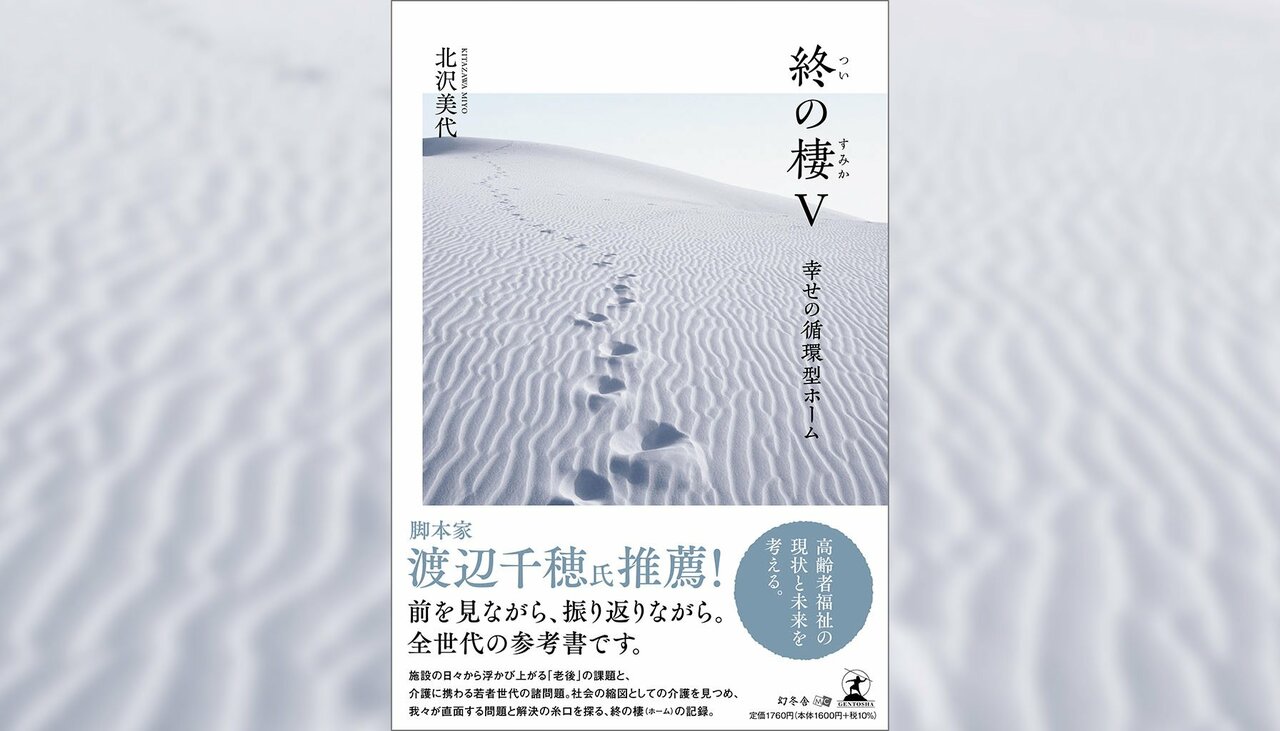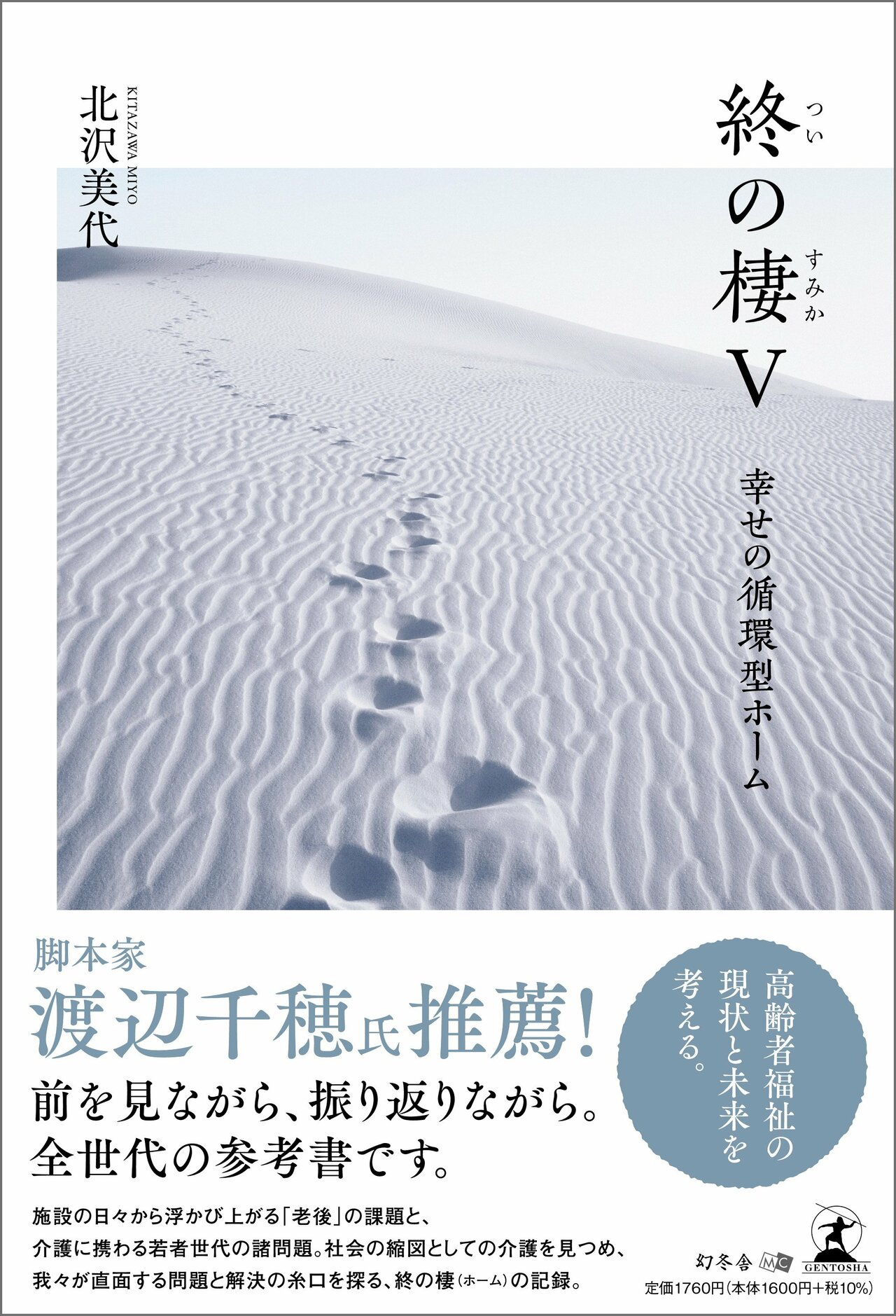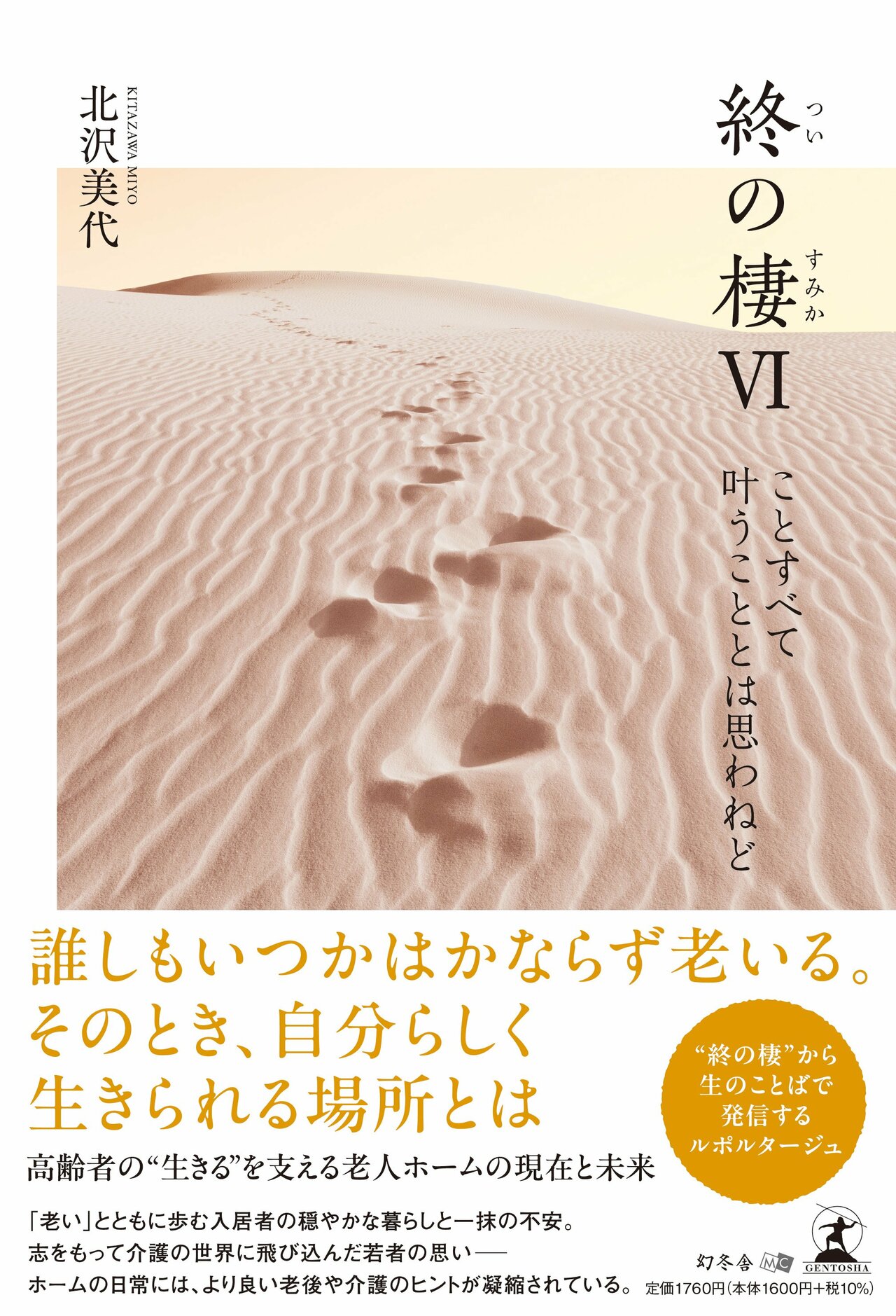【前回の記事を読む】私は「浦島太郎」を体験した。――認知症セミナーのために調布へ。「なじみ」の街のはずが、駅に降り立つと…
第二章 これが老いなのか、誰もが迎える不確かな世界
有能なガイドがいてくれてのこと
ホームの中でもスマホを使っている人たちはいる。しかし聞いてみると使っているのは電話を「受ける」「掛ける」「メール」の三つのようだ。しかし私はそのスマホさえ持たない。長年買い換えてきたのはアナログの携帯電話である。
しかし最近雑音が入って聞きとりにくくなったので、意を決してスマホに変えることにした。スタッフから「シルバー向けのものもあるそうですよ」と聞いていたのでその種のものにしようと思っていた。
その買い換えには姪が同行してくれた。彼女の同行がなかったら、買い換えも決意することができず、まさに外界との接触を失うという悲愴な思いでその日を待った。 彼女が携帯ショップの受付の予約をとっておいてくれたので長く待たされる時間ロスなしだったのは体力のない私にはなによりだった。
彼女が予約の時間を考えてタクシーで迎えに来てくれた。タクシーの予約も、その支払いも、途中のコーヒータイムの支払いも彼女のスマホ一つで済ます。行く先の住所を言うと「そこを右に曲がって、踏み切りを渡ったらすぐを左へ」などいちいち指示しなくても運転手はカーナビを見て目的地まで連れていってくれる。
姪とはすべての手続きを終えて、携帯ショップで別れたが私はホームの玄関口でタクシー代を払うために財布や小銭入れを出す煩わしさもなかった。
携帯電話をスマホに買い換えるための手続きは受付のお兄さんと姪がすべてそのやりとりをしてくれた。私はまるで外国で有能な通訳の隣りに座っている思いだった。
時々姪が私にたずねても私は首をタテに振ったり、ヨコに振ったり「そうねえ」と考えて「それにしてちょうだい」とこたえるだけ。たまに「それ、どういうこと?」と聞くと彼女が説明してくれる。この通訳がいなかったら携帯電話からスマホに買い換えることすらできない。
しかしこの一連の手続きを終えてホームにたどり着いた時、私はかなりのショックを受けていた。その間の二時間はまるで「浦島太郎」だったからである。私の世界とは全く切り離された別世界で過ごした感じだったのだ。それはちょうど夢遊病者の心境にも似ていた。ニューヨークの街中を有能なガイドに従ってついて歩く、ただついて歩く私だった。
毎日二紙の新聞を読み、セミナーにも参加してきたという自負心が粉々に砕かれて、終の棲のベッドに倒れこんでいた。