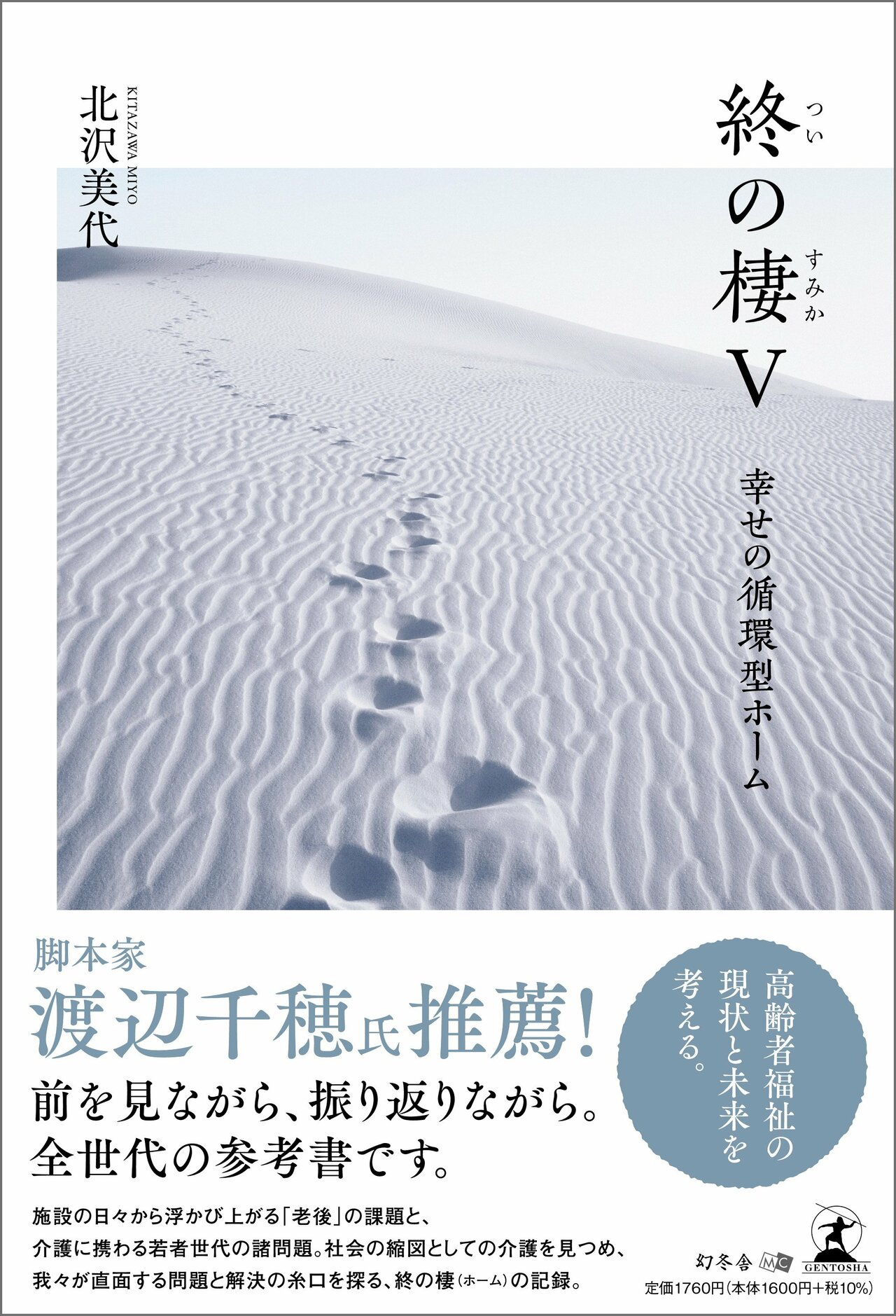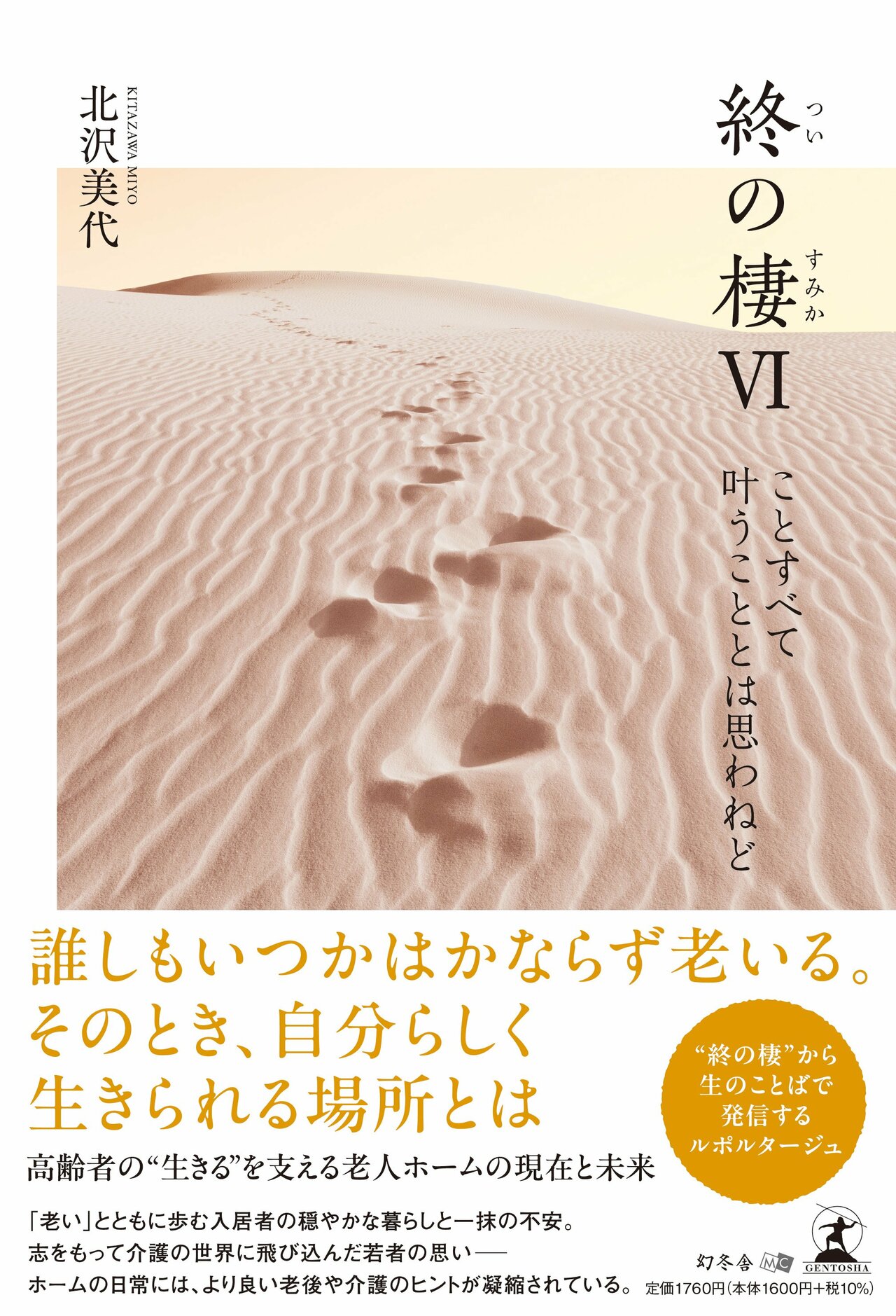ホーム小話3 ごほうび
イタリアさんが腕や脚をしきりにさすっている。見ると寒がりのイタリアさんがこの日は薄手のブラウス姿だ。イタリアさんの寒がりはスタッフたちはみんな知っているので大きなウールの膝掛けを持ってきているのだがこの日は車椅子の背にかけたままであった。
それで私はそれを肩から背にかけてあげた。すると「利口、利口、エライ、エライ」と私の気遣いをほめてくれ「あとで何か買ってあげるわね」
彼女はいつもごほうびを約束してくれ、私としては楽しみにしたいところだが、忘却とは忘れ去ることなり、忘却を忘れ得ずして忘却を誓う心の哀しさよ。ごほうびを約束された私の方はいつもこの名文句を思い浮かべて引き下がるしかない。
とりあえず
私はこの章を書く時、最後を迎えた祖母のことを思い出していた。祖母は老人性肺結核を患い、一番奥の部屋でひとり暮らしをしていた。
私が祖母を訪ねると、ものの十分もしない内に「若いもんがいる所じゃない」と言って追い帰された。往診に来た医師には「治るものならお願いもしましょうが、今度ばかりは助かるとは思いませんので、どうかお引き取り下さい」と診察を断ったという。それ以前に祖母は献体の手続きをとっていた。
その祖母が亡くなった時、一冊の手垢のついたノートが見つかった。祖母はそのノートに日々の思いを綴っていた。
小さな庭に自ら植えた草花と雑種犬のジロをかわいがっていたことが知れた。さみしさを人に頼らず草花と雑種犬に自らを慰めていたのだろう。
祖母は濃い黄色の花は品がないから好きではないと記していて、祖母のその心を知ってからは私も濃い黄色い花は好きになれないでいる。
最後の二頁は文字が流れて読み取ることができなかった。干からびたみみずがかすかなくねりを見せているように力なく流れていた。
【イチオシ記事】一通のショートメール…45年前の初恋の人からだった。彼は私にとって初めての「男」で、そして、37年前に私を捨てた人だ
【注目記事】あの臭いは人間の腐った臭いで、自分は何日も死体の隣に寝ていた。隣家の換気口から異臭がし、管理会社に連絡すると...