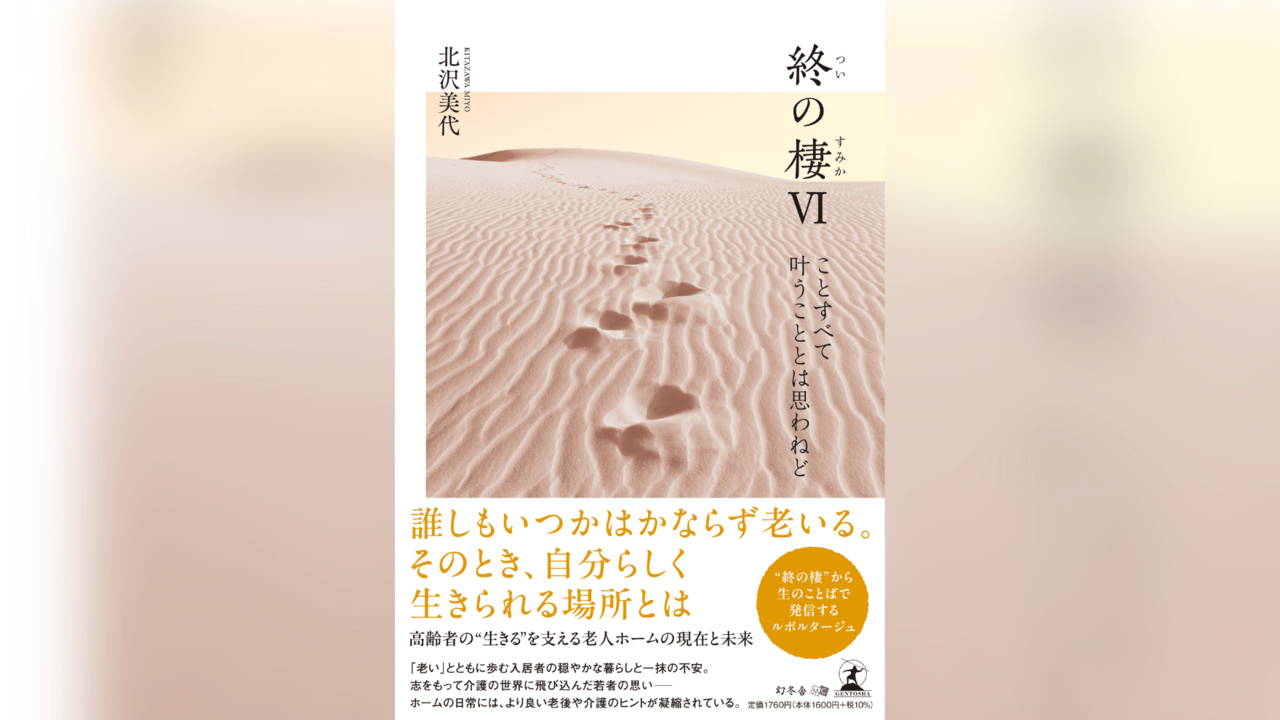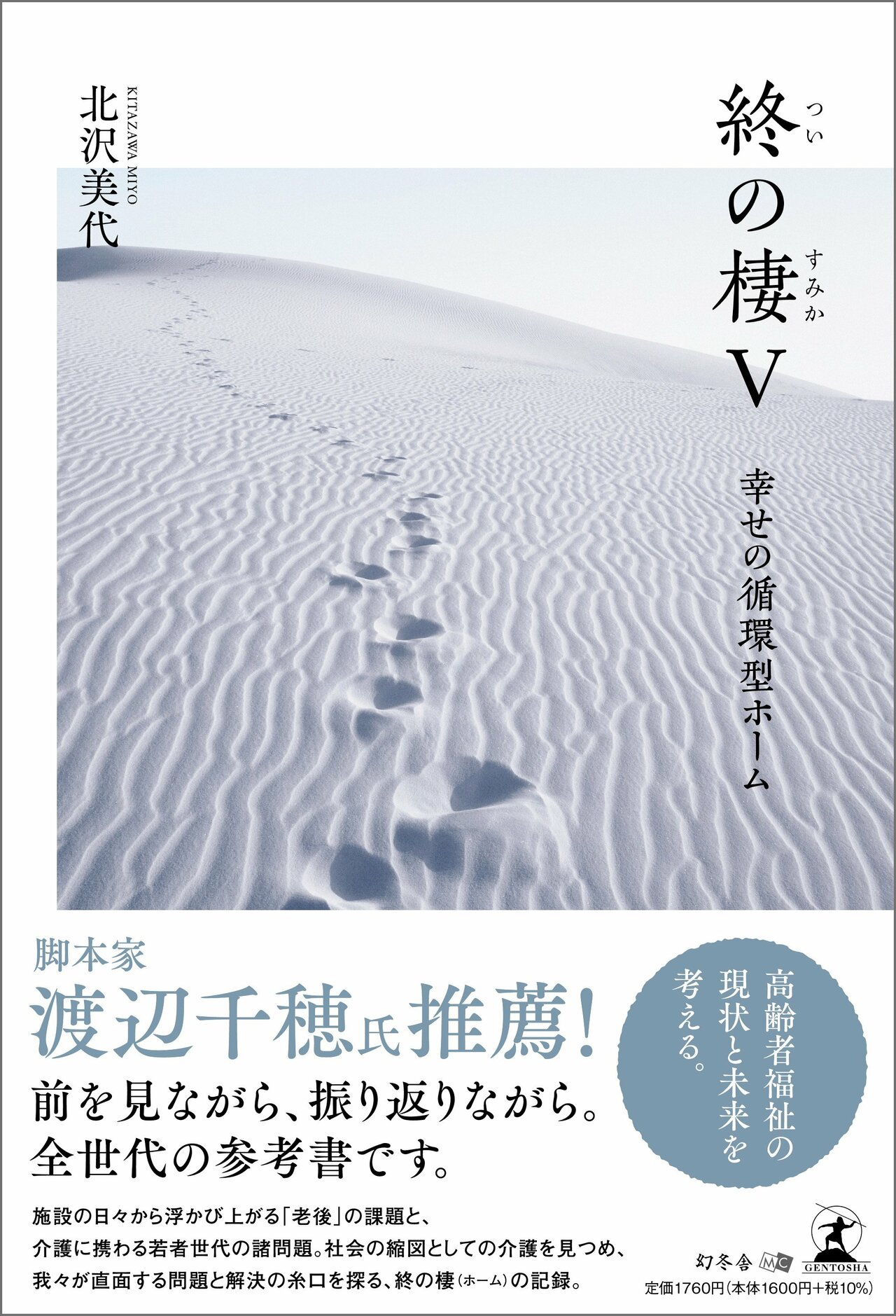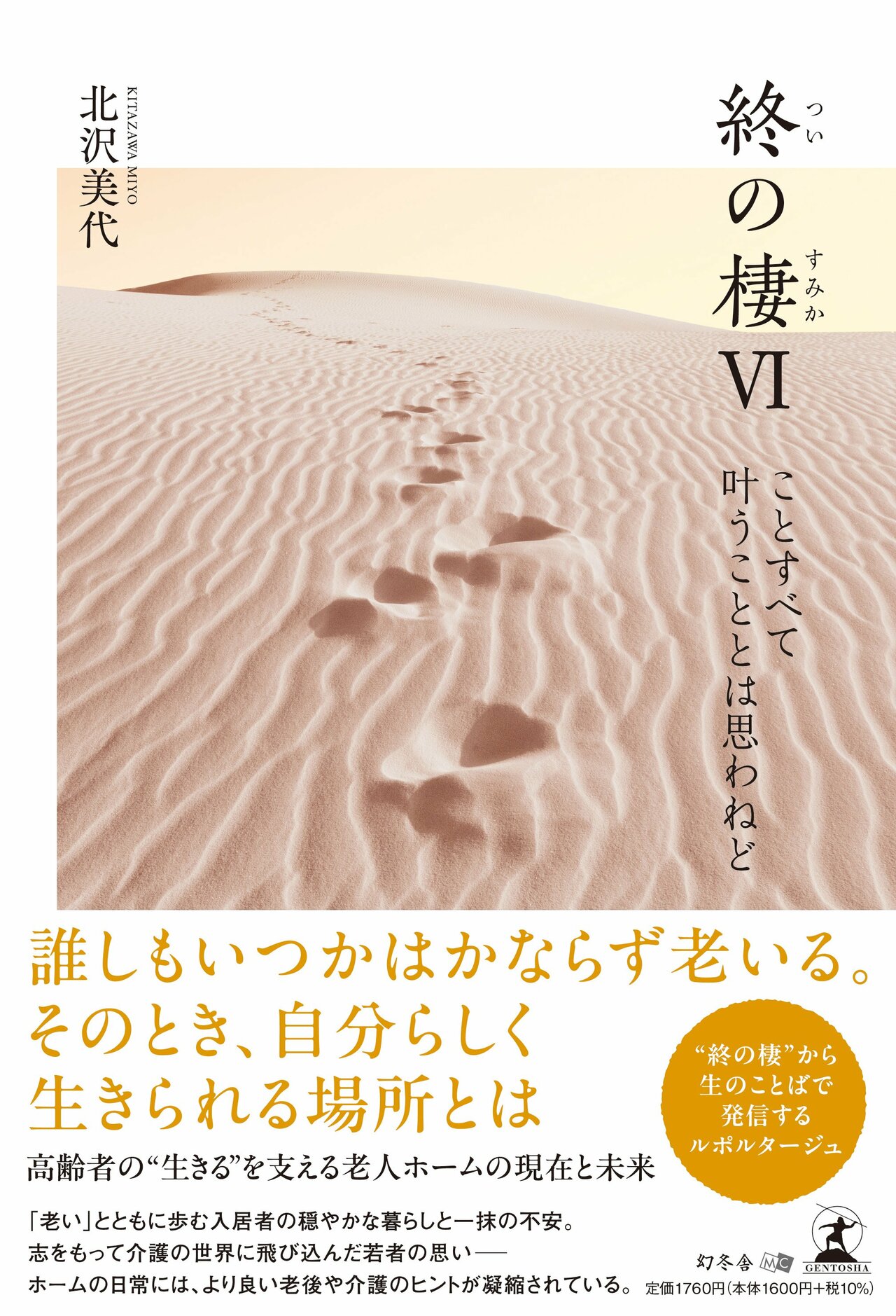【前回の記事を読む】"このこと"に気づいてから、介護を受ける「負い目」が少しだけ軽減した――老人ホームで暮らす彼女が気づいたこととは
第一章 介護は人生の循環
大学生の就活に変化
就活事情の変化を知ってしばらくした時だ。こんな記事が載っていた。
「親と祖父母、子を真ん中に」と題した記事である。執筆者は大阪教育大学教授・小崎恭弘氏。
曰く、子どもの成長において様々な年齢や多様な人との関わりは大切。三世代世帯減少、国が出している世帯の動向を見ると昭和61年(1986)には15.3%あった三世代世帯は令和5年(2023)には3.8%にまで下がっている。祖父母は良いサポーター、アドバイスをしてほしい。
なぜ私がこの記事を取り上げたかというと私の知る限り、このホームのスタッフたちが介護を仕事に選んだ理由に「祖父母にかわいがられた」を挙げる人が多かったからである。それでこのデータは私をネガティヴな気持ちにさせた。
「老いと共に歩む」。これは翔君が介護に向かい合う姿勢である。彼は祖父母にかわいがられて育ち、彼自身も祖父母が好きだったという。ホームの中で年寄りを介護する彼の言動はまさに孫がおばあちゃんに寄り添う姿だった。
このホームに夜勤専門スタッフがいる。彼女は「両親以上に祖父母が好きだった」と言う。それが介護への動機だったようだ。親御さんは「お前のような小さな体で介護の仕事は無理だ、体を壊してしまう」と心配したそうだが、それもうなずけるような華奢で小さい体格をしている。
しかしその動きは活発で、しかも明るい。夜勤明けで退社する彼女を私はことさら労いの思いを込めて「ご苦労さまでした」と送り出す。
そして「ありがとうと言ってくれてありがとう」の篠原さん。介護を「笑ってなんぼ」だとも言った。彼女については「終の棲Ⅱ」で書いたが、姑や母方の祖母を介護する母親とつながりの中で「常に高齢者と関わってきて、それがあたりまえのこと、しかも高齢者は心の落ち着く存在だった」と言った。
理学療法士の菊池さん。彼女は家の事情で聴覚障害の祖父母に育てられ、結婚後も頻繁に祖父母のいる仙台に通っていた。温泉に連れていきその時を楽しんでいたようだ。
音のない世界がどういうものか、テレビの音を消して観たということも聞いた。彼女の「ジッちゃん、バッちゃん」を聞くと私までがその中に引き込まれる錯覚をもった。
そしてもう一人、なんともおっとりとした風貌で体の大きなスタッフがいる。私はすぐに「大きな坊や」とニックネームをつけたくらいだ。彼は四国の過疎の村で育ったという。
小学校は一年生から六年生、総勢で二十五名というのだから私には想像もつかない寒村だったのだろう。若者は卒業と同時に村を出てしまうので村は年寄りばかり、つまり年寄りに囲まれて育ったという。ともかく明るく、おっとりしている。彼を見るだけで心が落ち着くのだから私はこの老人ホームでは貴重な存在だと思っている。