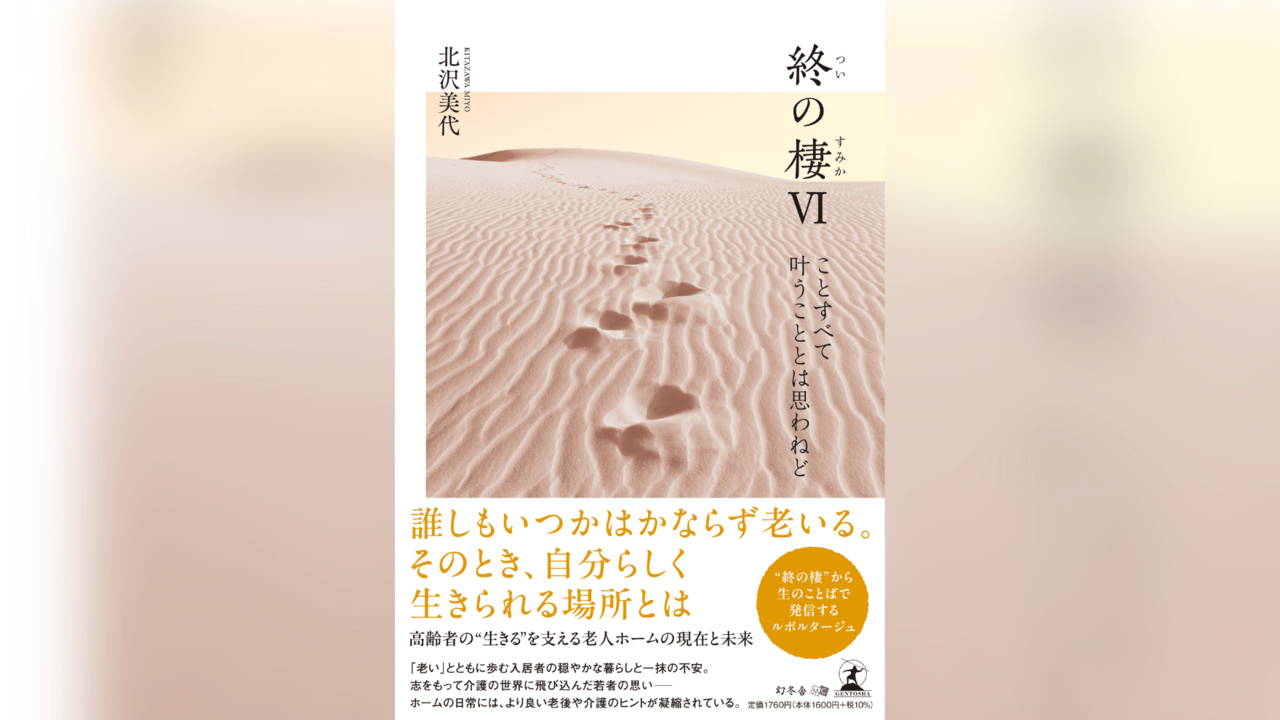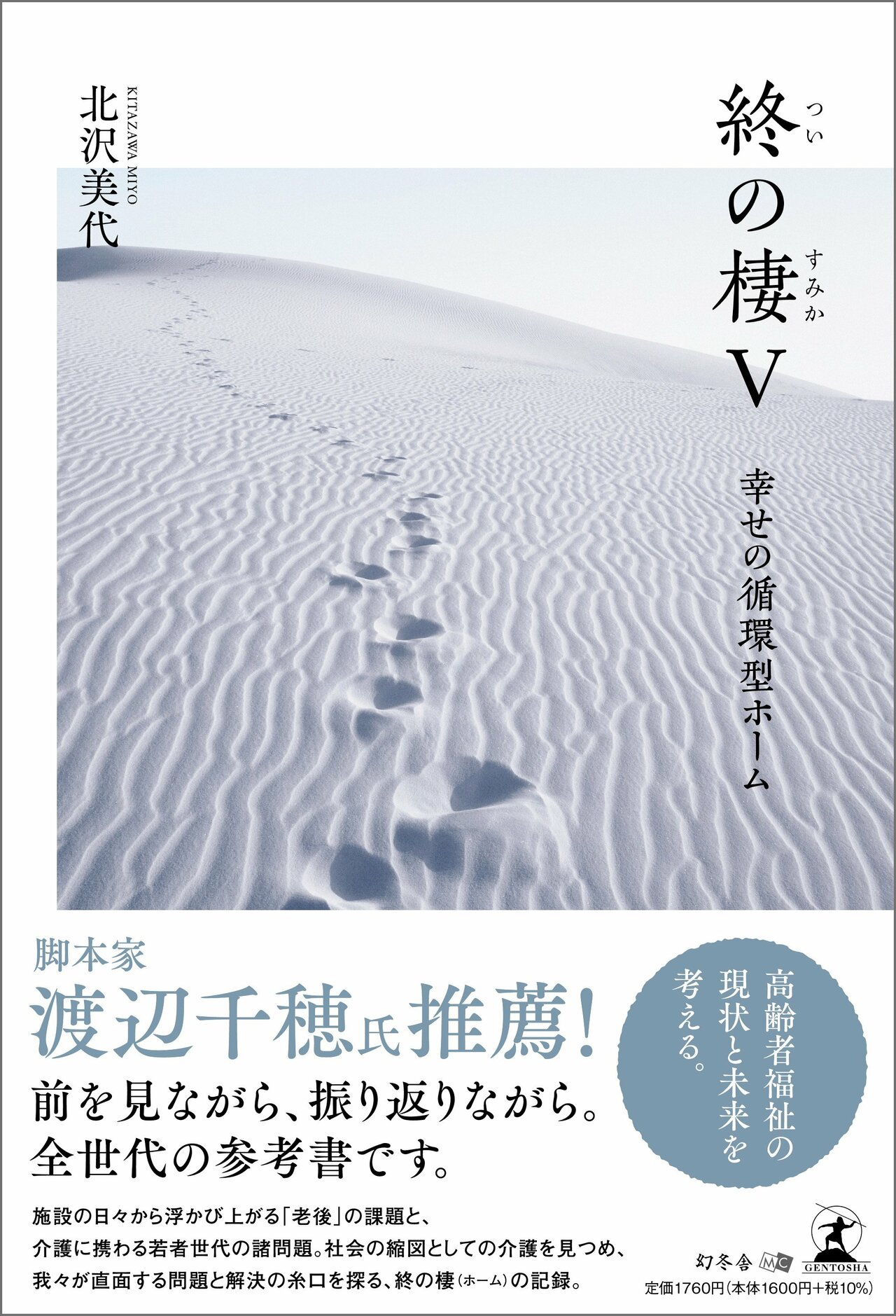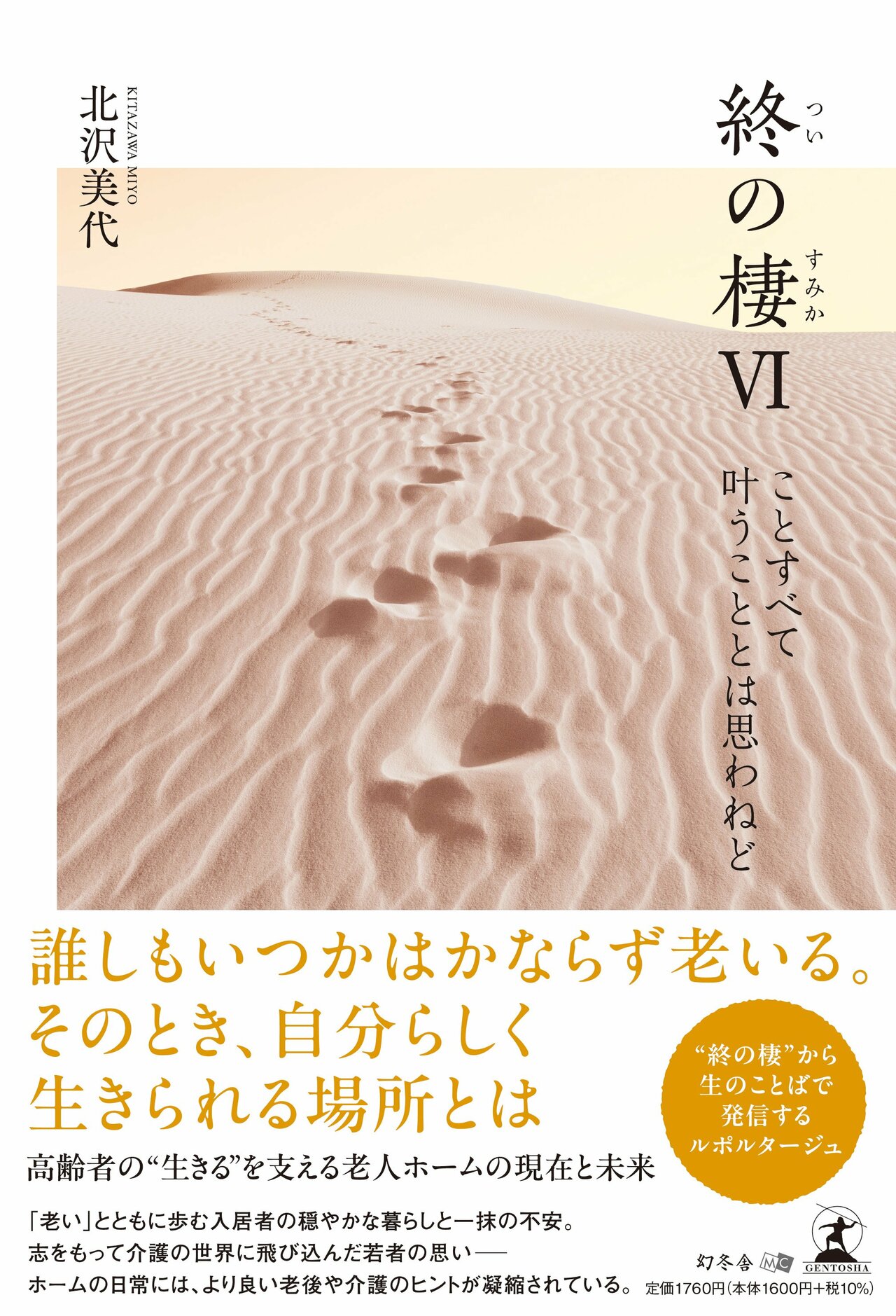まえがき
「ことすべて叶うこととは思わねど おのが歩みをますぐにゆかむ」、この上の句をタイトルに使わせていただいたのには万感の思いがある。このお歌は都立松沢病院の名誉院長齋藤正彦先生のお母さまがアルツハイマー病と診断されてから後の歌である。
超高齢社会、人生百年時代といわれる今の社会で「介護」「認知症」が話題とならないことがない。これは社会的、国民的な問題である。
過日、幻冬舎の担当者からこんな便りをいただいた。
「──喫茶店の隣りの席で、六十代と思しき若々しい感じの紳士が二人、自分が認知症になった時のことを考えて今から子どもたちに何を準備しておいたらいいかと話しているのが聞こえ、認知症が日常的に多くの人々の話題になっていることを改めて思いました」
「呆け(ボケ)老人」「恍惚の人」から「認知症」に用語が変わった頃からだろうか、私自身漠然とした不安が常にあった。松沢病院では公開講座が催されており、私は先生の「認知症」に関する講座には必ず出席していた。
「八十歳を過ぎたら認知症は医療ではなく介護だ」と、またある対談の中で「精神病は治すことはできません。しかしその人々が生きていくのを支えることはできる」というお言葉を知って「認知症」のハードルがグンと下がったのを覚えている。それらが私の老人ホームに入居する大きな動機になったのは間違いない。
しかも先生のこのお言葉はこのホームで働くスタッフ翔君の心にも共通するものだった。『終の棲Ⅱ 老いと共に歩む』は彼自身の言葉である。
「老いも病いも認知症も治すことはできません。しかしこの人たちが生きていくのを支える、それがこのホームで働く僕の姿勢です」
先生のお母さまのこのお歌は漠然とだが確実に不安が心に巣食っている私に一つの指針を与えてくれたのだ。
私の心身の低下から考えて多分『終の棲Ⅵ』は最後の本になると思い先生にこのお歌をタイトルに使わせていただきたいとお願いしたところ、折返しご了承のご返事をいただいた。
しかもその文面には「世の中が求めている本だと思います。母の歌を次回作のタイトルにお使いいただく件、弟、妹も喜んでいます」とあり、このタイトルが決定したのである。このお歌は私のみならず多くの人々の一つの指針となると私は確信している。
改めて、先生とそのご家族にお礼を申し上げます。