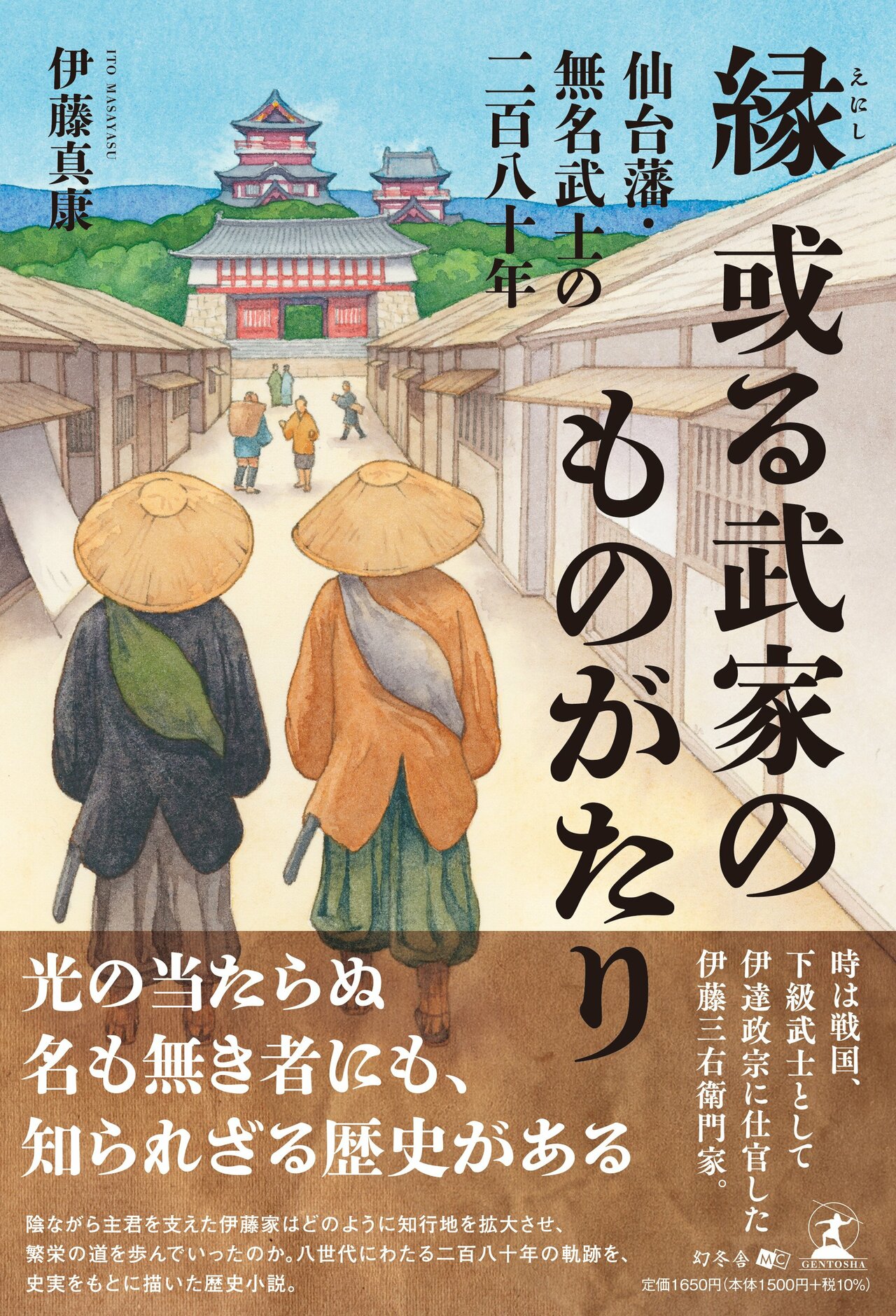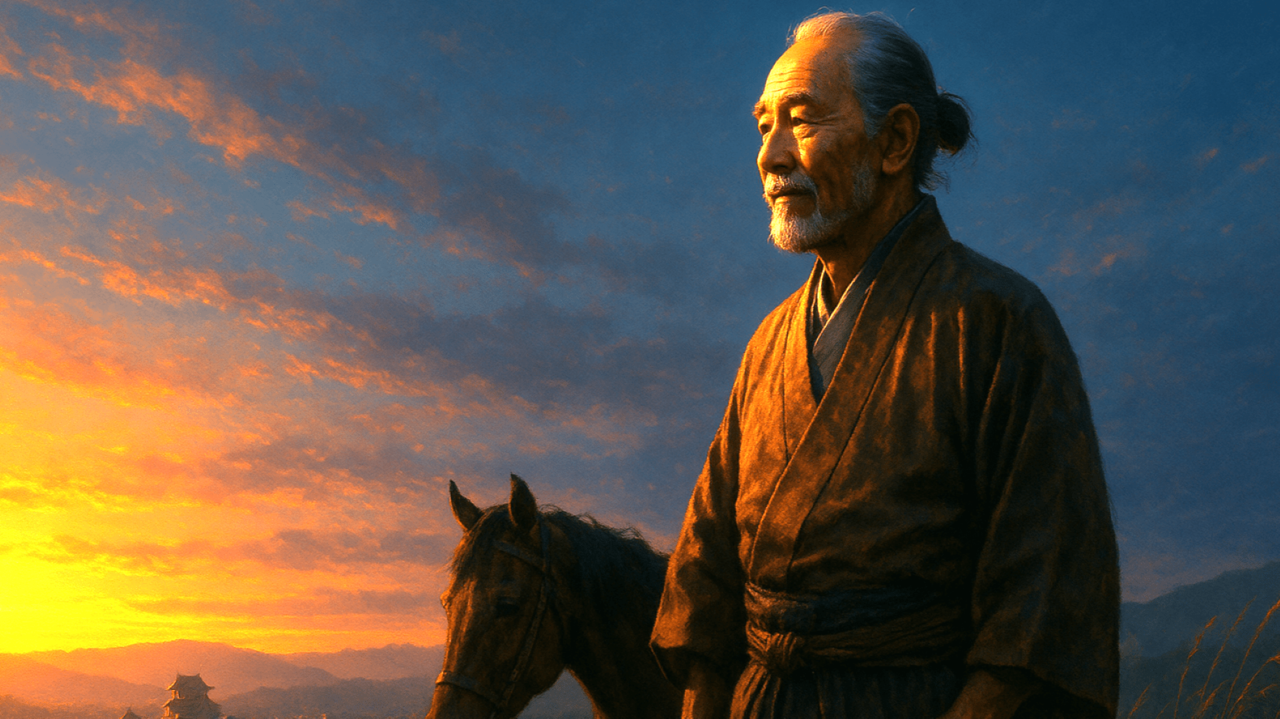二人の息子は、故郷の土佐所縁の地にちなんだ「賀江(かえ)」姓の名乗りを許され、小姓の役目を務めながら、十分な読み書きに四書五経、武芸等の教育を受けている。
時折政宗が「中将! 中将はいずこぞ!」と賑やかに自分を訪ねてきて、古今和歌集に源氏物語の講釈や、自作の和歌の添削を頼んでくる。
婚家から出戻り、絶望で暗く沈んだ表情だった五郎八姫とは、京暮らしの思い出話が尽きることなく、「中将どのと過ごす時が、一番の生きがい」と、すっかり元気を取り戻し、東国一と謳われた五郎八姫の美貌が蘇ってきた。
「殿に一度刃を向けても、いずれ皆残らず味方にする。それが伊達家の流儀……」
戦場で出会った、伊藤肥後なる老将の笑い声が、ふと阿古の脳裏に蘇った。
敵方だった自分たちに、新たに生きる場を与えられた。そればかりか、家中の者誰もがこうして自分を必要とし、いつも声を掛けてくれる。敵方を味方にする……あの老将の言うとおりだった。
考えてもみれば、実家の長宗我部家ばかりではない。嫁ぎ先の佐竹家も、元は常陸国の出で、遠縁の常陸佐竹家は、戦国の世に伊達家とは度々刃を交えてきたのだ。
故郷所縁の、紀貫之『土佐日記』の面白さに触れて以来、物語や和歌の世界に憧れを抱き、勉学に励み多くの教養を身に着けてきた阿古。
しかしこれまで、阿古の熱意と努力を理解し、認める者はほとんどいなかった。武家の女子は所詮、子を産み育てる道具、あるいは人質の道具……しかし今、阿古が積み上げてきた豊かな教養が、初めて人に求められている。これが「生きがい」というものなのだ……阿古は初めて知ることができた。
「父上、長宗我部の血を残せとの仰せ、守ることができました。兄上、『釣鐘の馬印を目指せ』、あのお導きがなかったら、我々親子はどうなっていたか……」
「伊藤肥後殿……命を助けていただいたご恩、この阿古、生涯忘れませぬ。いつかどこかで、恩返しが叶えば……」
思いもかけず仙台に来て、安寧の日々と幸せをつかめたことに、阿古は感謝していた。