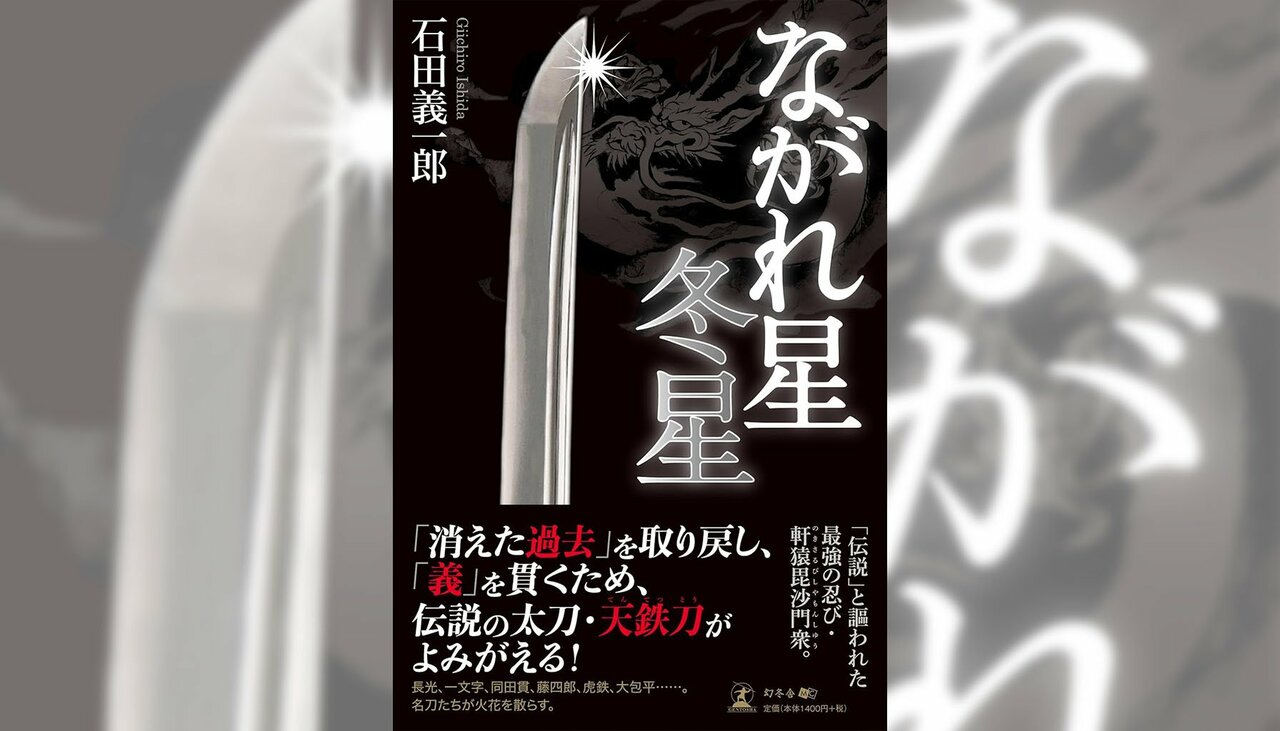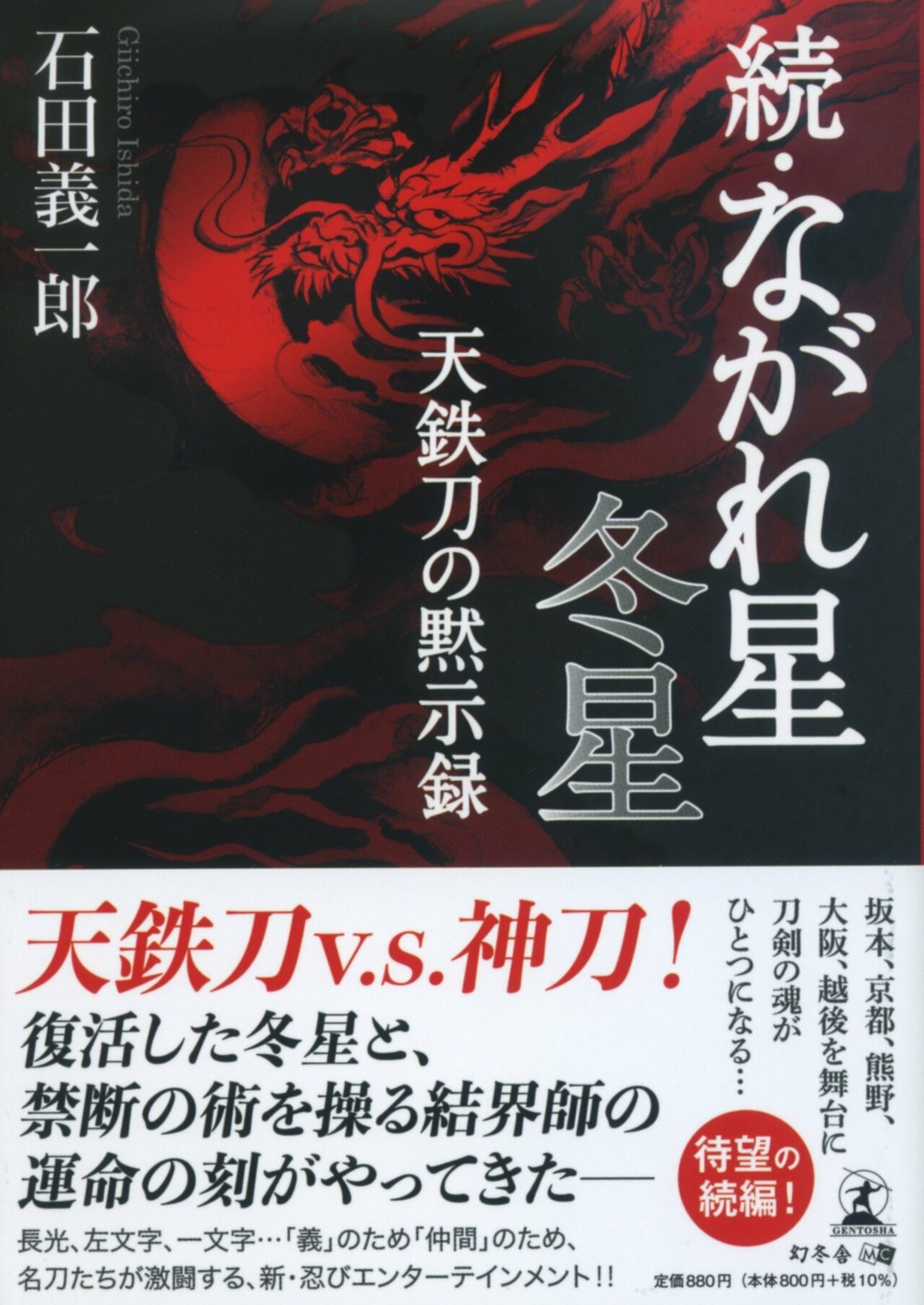【前回の記事を読む】その瞬間、ごろつき連中にやられて倒れていたはずの男の目がバッと見開いた。目をつぶったままの少女を見た瞬間だった。
第一章 帰巣
「これは、まさか七夕(たなばた)か? 七夕は七月の文月でなかったかい。おいらの地元ではそうだけどもなあ……」
勘治は大きな目で不思議そうに七夕のような飾りを見た。
「あ、そうだね、お前さんは信濃の生まれだったね。そう、本当は七月七日が本来の七夕なんだけど、ここ、直江の津・今町では三月三日に七夕をするんだよ」
お遥が苦笑いしながらさくらの短冊を笹に飾った。
「そうよ。三月三日に流れ星をみると、幸せになるっていわれているの。あたい今年は絶対に流れ星をみるの。そう決めてるの」
さくらは自信たっぷりに笑った。
「へぇー、そりゃ珍しい。またなんか由来でもあるんかい?」
「昔々、三月三日にこの今町に流れ星が落ちたそうなんだよ。海辺と山の麓に二つ落ちたそうでね。そしてその年は豊漁で豊作だったことから、きっと天の神様のお恵みだということで、この日に七夕をする慣習になったんだよ。それでこの日に流れ星をみた者には奇跡が起きるといわれているんだよ」
「流れ星ねえ。なかなか、いい話じゃねえか。うん」
「流れ星かどうかはわからないけど、その星といわれている大きな石をお堂に安置していてね。石をお護(まも)りしてくれている毘沙門(びしゃもん)様を三月三日にご開帳するから、その祭りを『びしゃもんさん』と呼んで夏の祇園祭と同じくらいに、たいそう賑やかに祭りをするんだよ」
「祭りか、いいね~。おいらは祭りは大好きだぜ。今年も盛り上がりそうかい」
「それがね……」
お遥は急に顔を曇らせた。
「な、なんか具合の悪いことでもあるんかい? もしや、あの権藤一味が関係しているとか……」