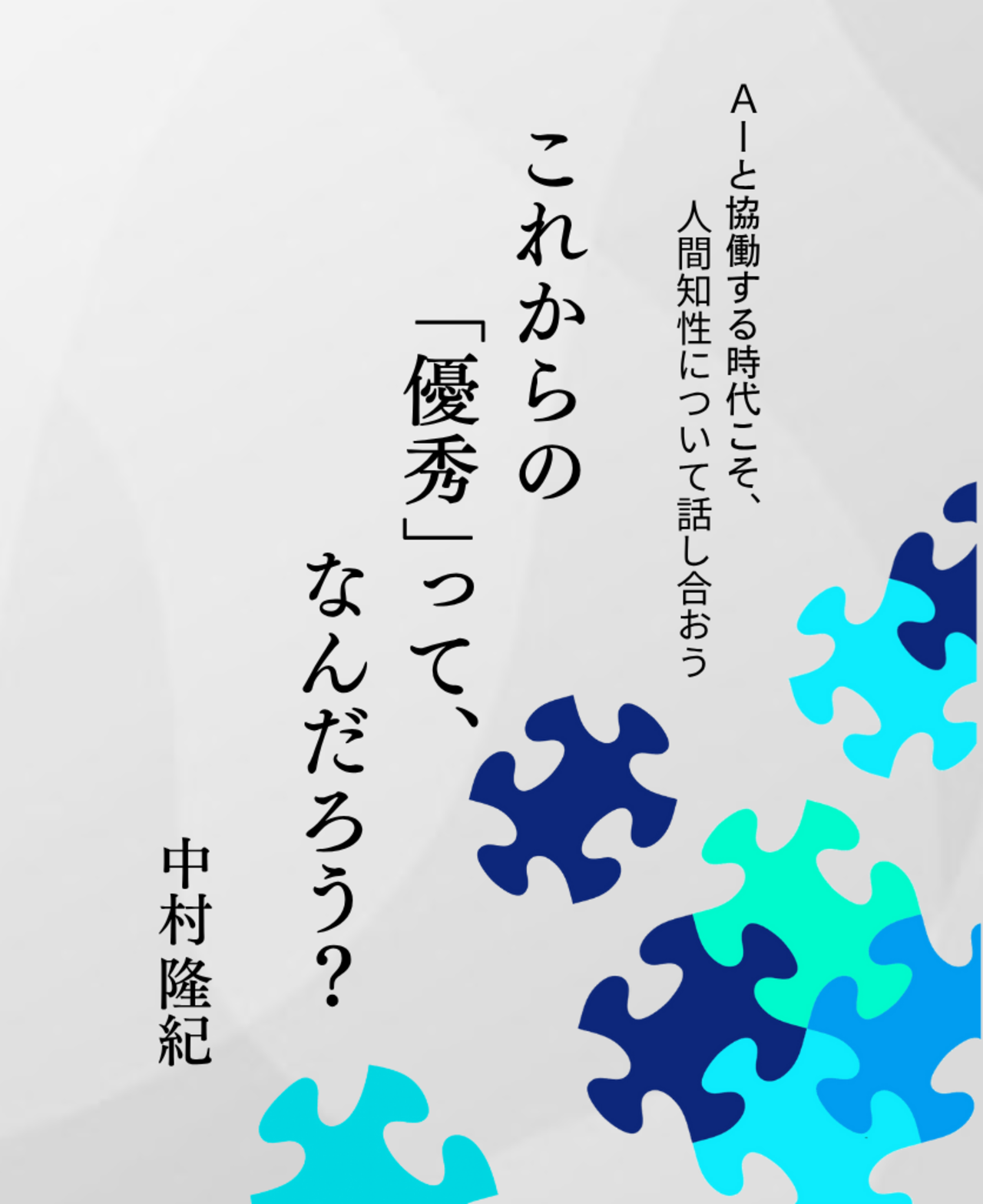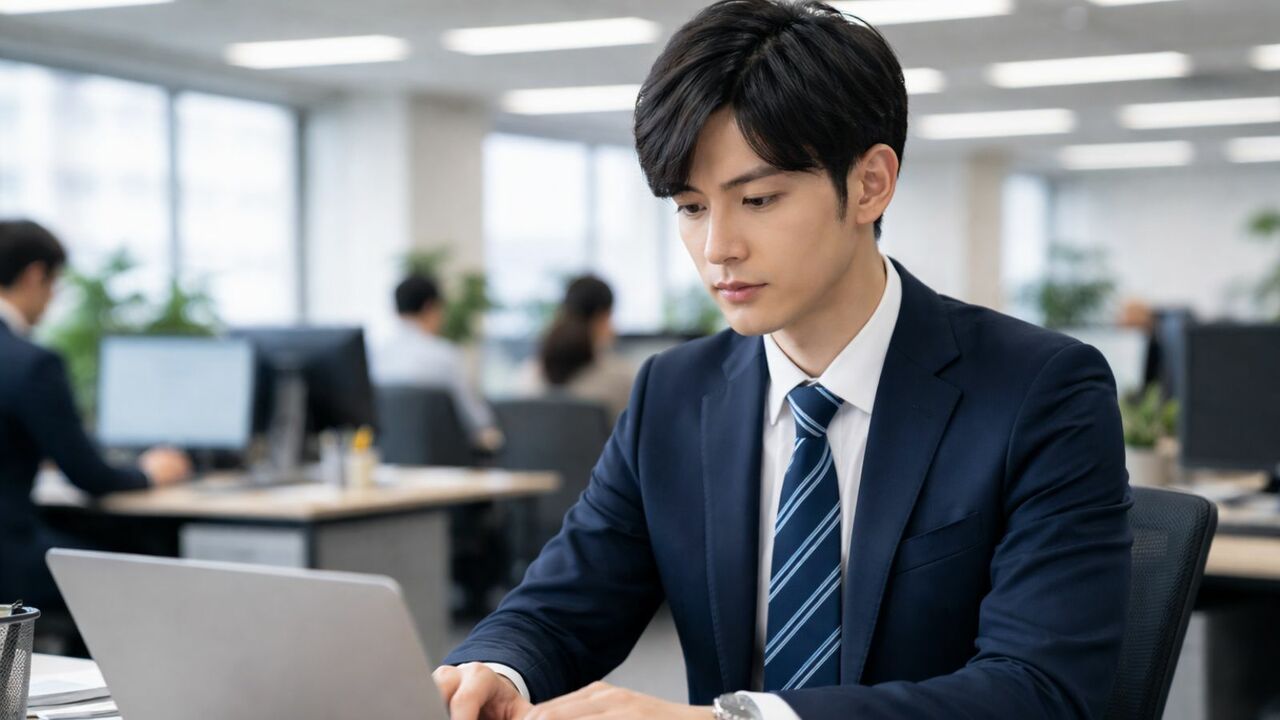「深刻というか、おれたち、慣れていないんだよ。真逆に進んできたから。職人さんたちのように、こつこつと技術や勘を磨いていくようなことは、生産効率が悪いというのが、組織の定説になってしまっていた。
それに、研修に関して言えば、ツカミのいいプログラムとディスカッション、振り返りもしましょう、みたいなパターンで提供して、あとは現場のOJTや個人の掘り込み次第だと、割り切っていたところはある。社員研修で、なんでもかんでも背負えないよ」
「それで現場が若手に、パターンに嵌った仕事ばかりさせたり、個人が自分で先へ学ぼうとしなかったら、本物のプロフェッショナルは、絶滅するんじゃないか?」
「……もう絶滅は、はじまっているかもしれない」
働き方改革にも、功罪があった。後進に、もう少し質を上げよう、粘ってみようと促せば、それって残業の申請になりますけどいいんですか? と返ってくる。甘い仕事を叱った管理職が、パワハラのレッテルを貼られてしまうこともある。
他方では、後進たちに跳び甲斐のあるハードルを提供しているとは、とうてい言えないような、ロボット・マネジメントも横行していた。
組織は、自身が思うより質の低いレベルで効率化してしまったのかもしれない。この状況では、試行錯誤が生命線の〈創造性〉なんて、たまったもんじゃない。
YOさんが、弟に語りかける。
「道具もすさまじく進歩しているけどさ、道具を替えてトリセツを覚えても、腕は上がらないよ。おれたちだって、小さな小さな歯車だ。それでも地道に腕を上げる修行は、大切にしているヤツらがいるよ」
Keiさんがゆっくりうなずく。
――本当は、毎日モヤモヤしている些細なことと、粘り強く取っ組み合うっていうことなのかな、働くということは。イノベーションとかゲームチェンジとか、大っぴらに旗を立てるよりも。
次回更新は8月6日(水)、11時の予定です。
👉『これからの「優秀」って、なんだろう?』連載記事一覧はこちら