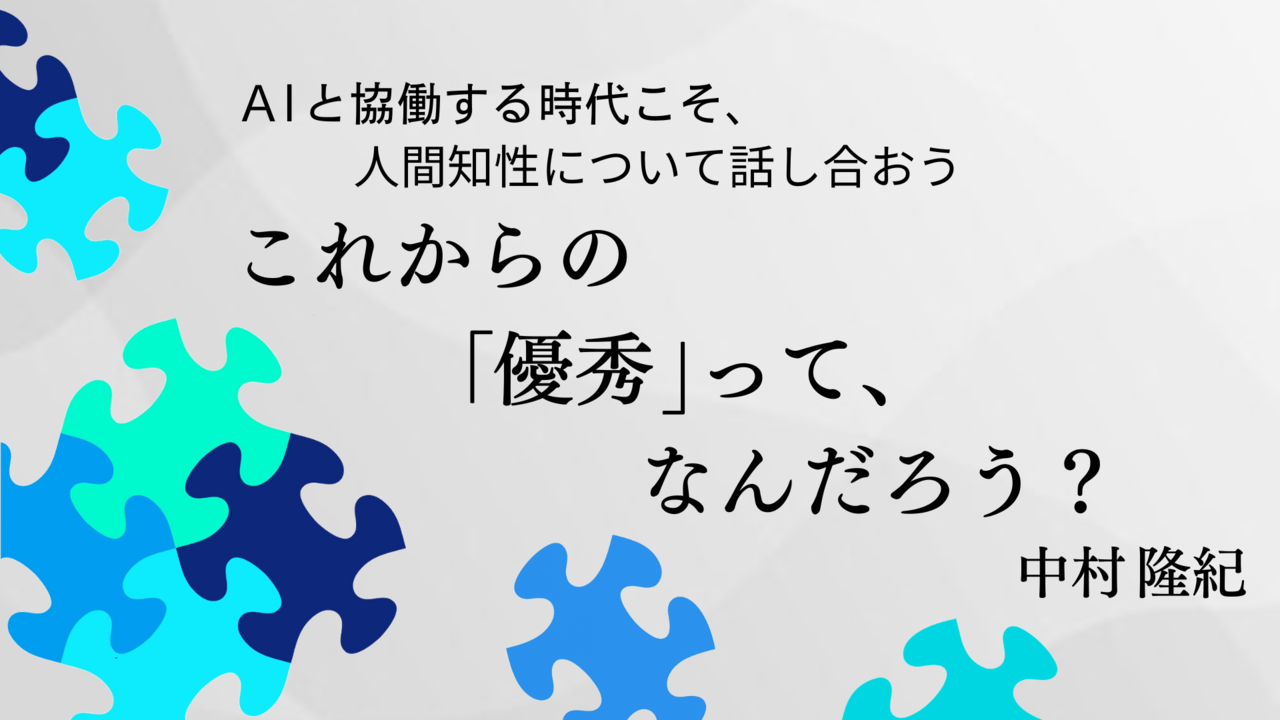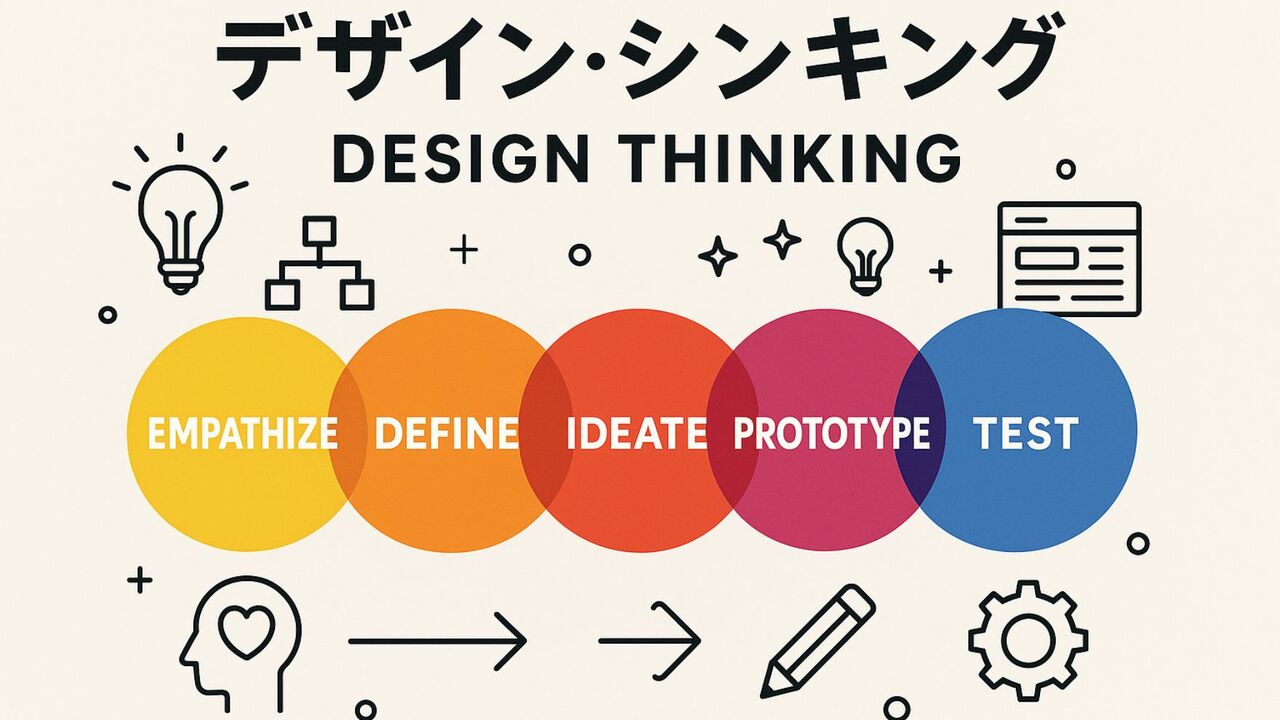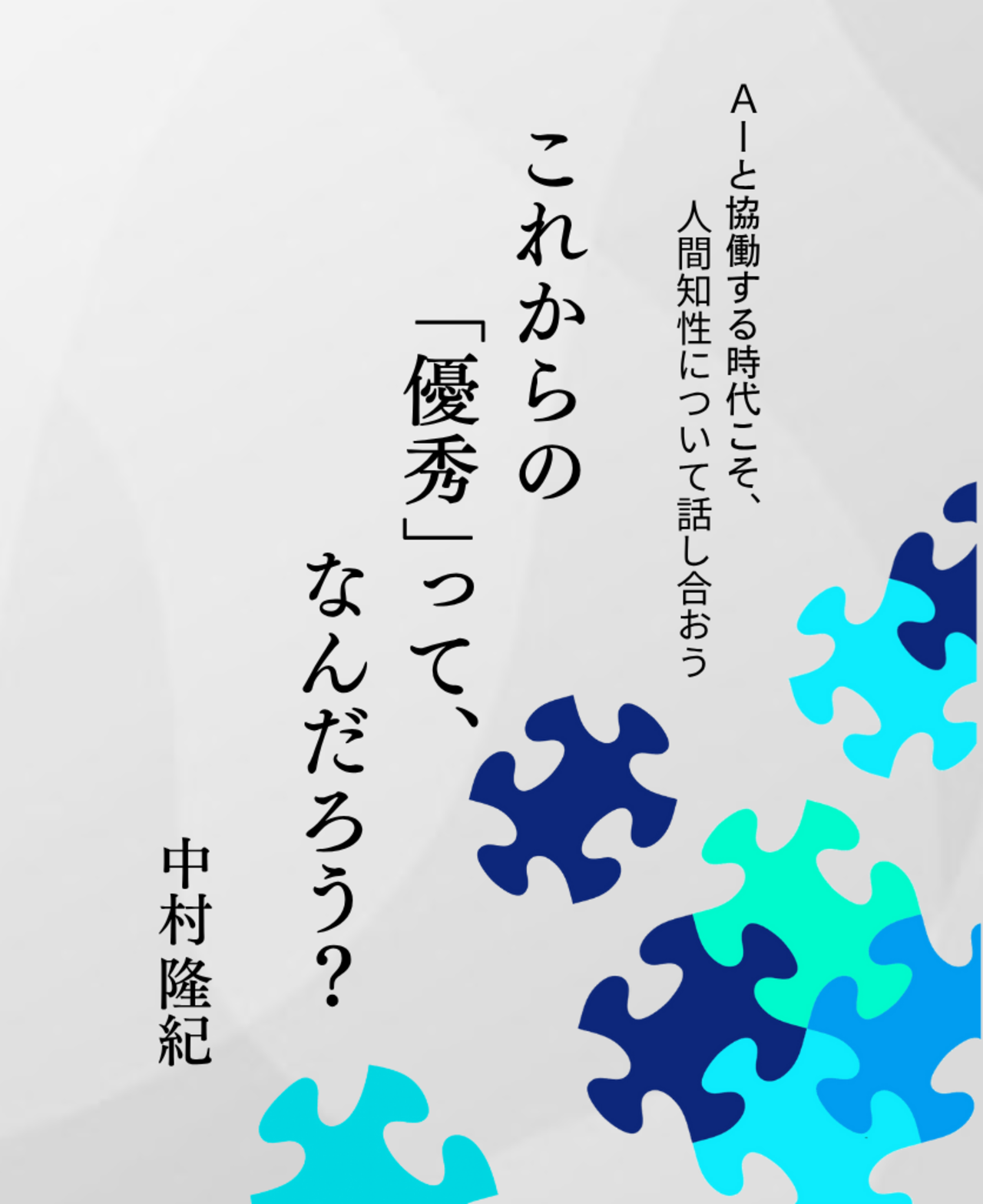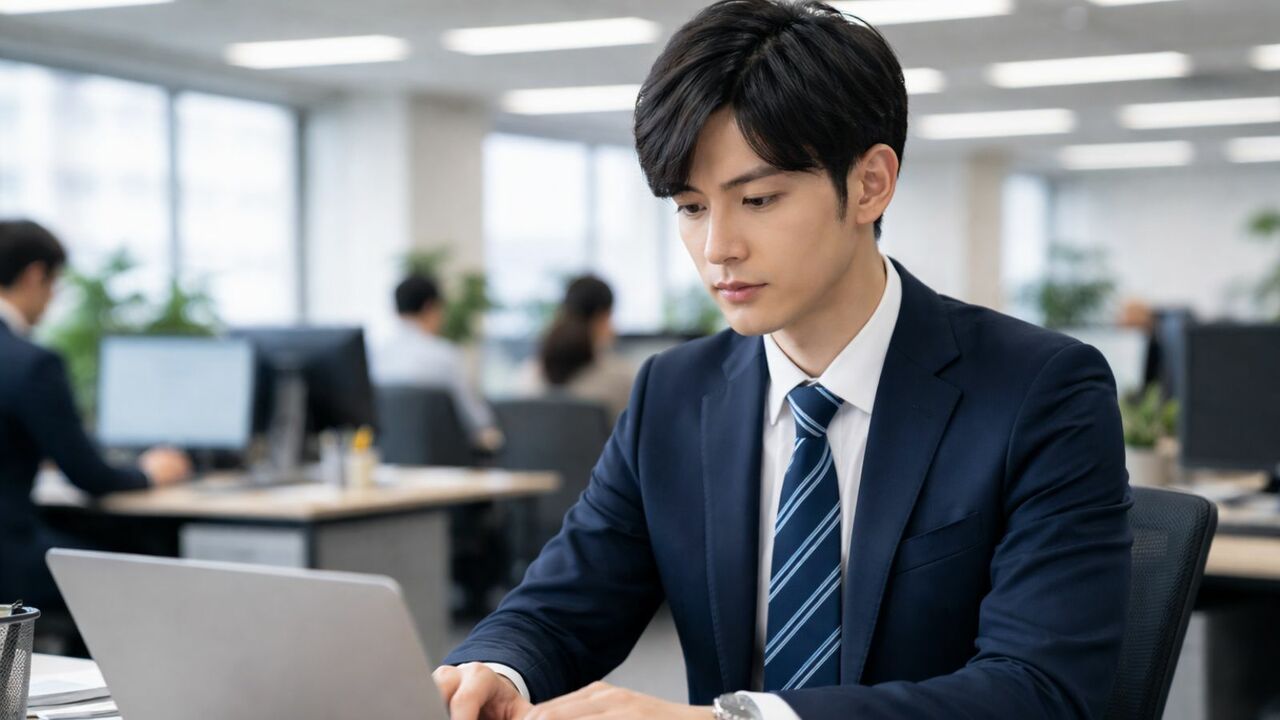【前回記事を読む】「創造性って、教えられたら、方程式を解くように身に付くの?」――育成に必要なのは、受験勉強のような解への導きではなく…
第一章 知覚センサー、機能不全
「すいません。習慣というのは、どんなツールで学ぶのでしょう?」
「すいません。ツールはないんです。あえて言えば、好奇心がツールです。そして、受講者が日々感じ取ったことが教材です。たとえば、帰宅時間に電車が止まると、レンタルスクーターを借りるひとが増えているな。最近、町の居酒屋さんは、おじさんではなく若いご夫婦が、旬の食材を学びに来ているんだな、とか。
それに、毎日観るニュースの中にも、流さずに一度立ち止まって考えると、通常の業務分析とは異なる、時代や人間の欲求が見つかるかもしれません。そうやってずっと、日常を感じ取り続けて、隠れた意味や兆しに気づき、自らチャンスを発想する習慣を育てます」
「ずっと、ですか……6か月間×週1回の全体ブレストに、他にもSNSで、毎日の出来事を対話し続ける」
「あのう、石橋さんは学生の頃、なにかスポーツや音楽など、されていましたか?」
「わたし、ずっとギターをやっていました」
「たとえば、クラプトンと同じギターを買っても、上手く弾けるようにはなりませんよね。毎日絶え間なく音楽を聴いて運指の練習をしてこそ、上達があるはずです。私は創造性の練磨って、勉強より、部活というか修行に近いところがあると思うんですよ。吉岡さんは、なにか、なさっていましたか?」
「私は、野球部でした」
「野球で言えば、バットやスパイクなど道具をいくら揃えたところで、やっぱり素振りを続けないと、身体が球に反応しないでしょう? 毎日素振りを続ければ、野球の感性が変わるはずです。私は本来、創造性の源泉というものは、ツールや方法に発想の糸口があるのではなく、地道に日常と向き合う、アティテュード(態度)の問題だと思うんです」