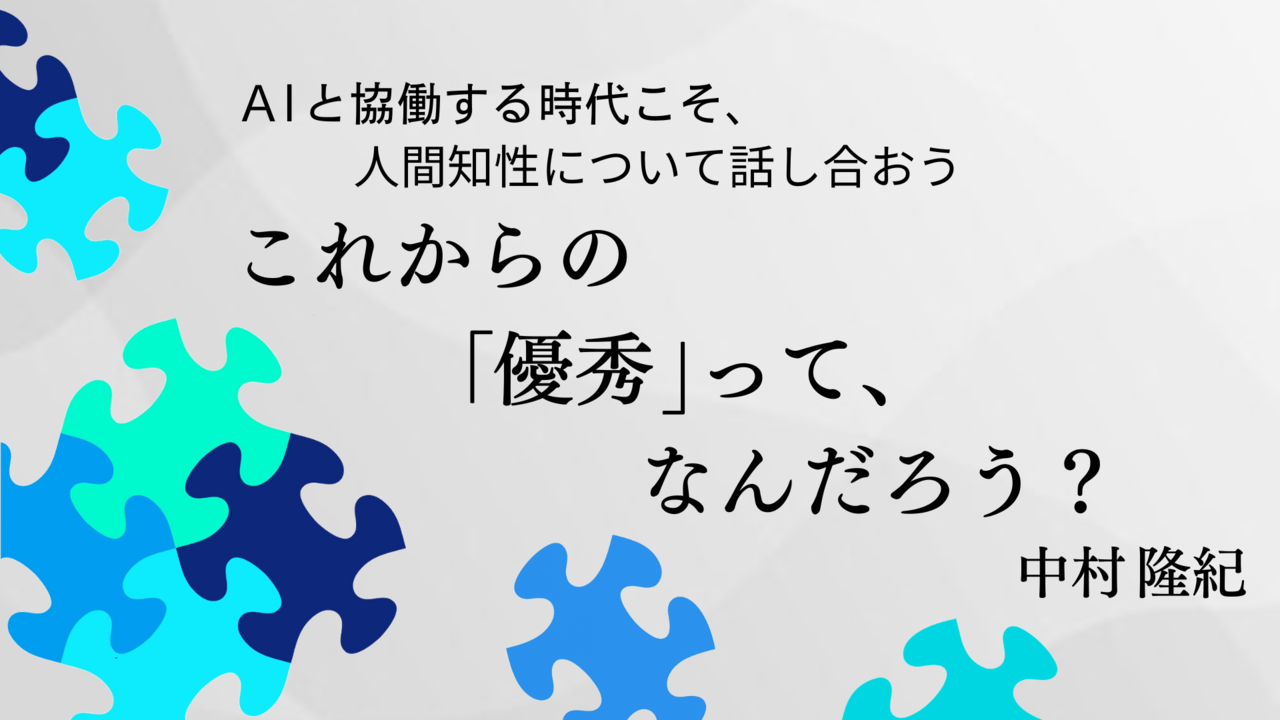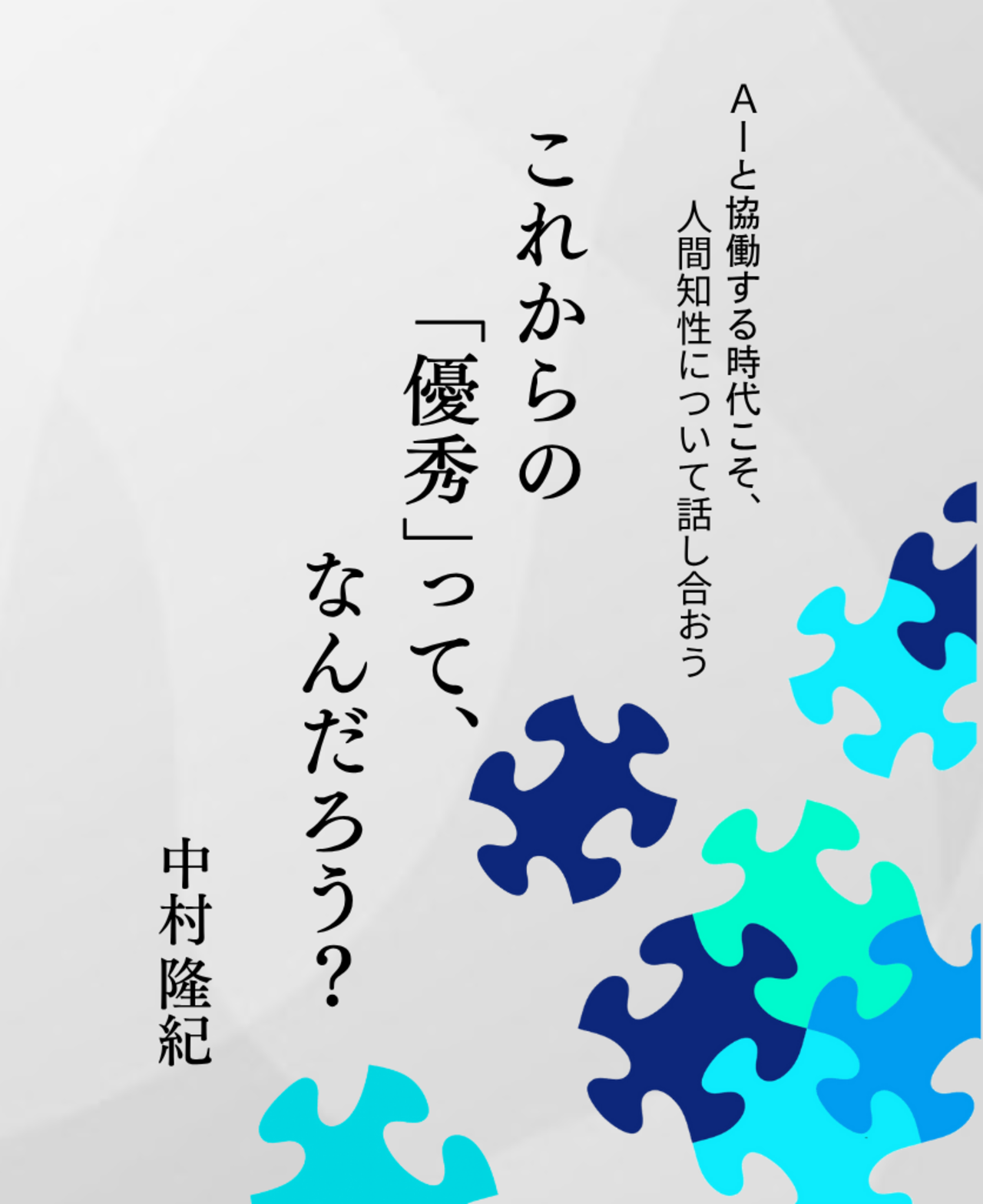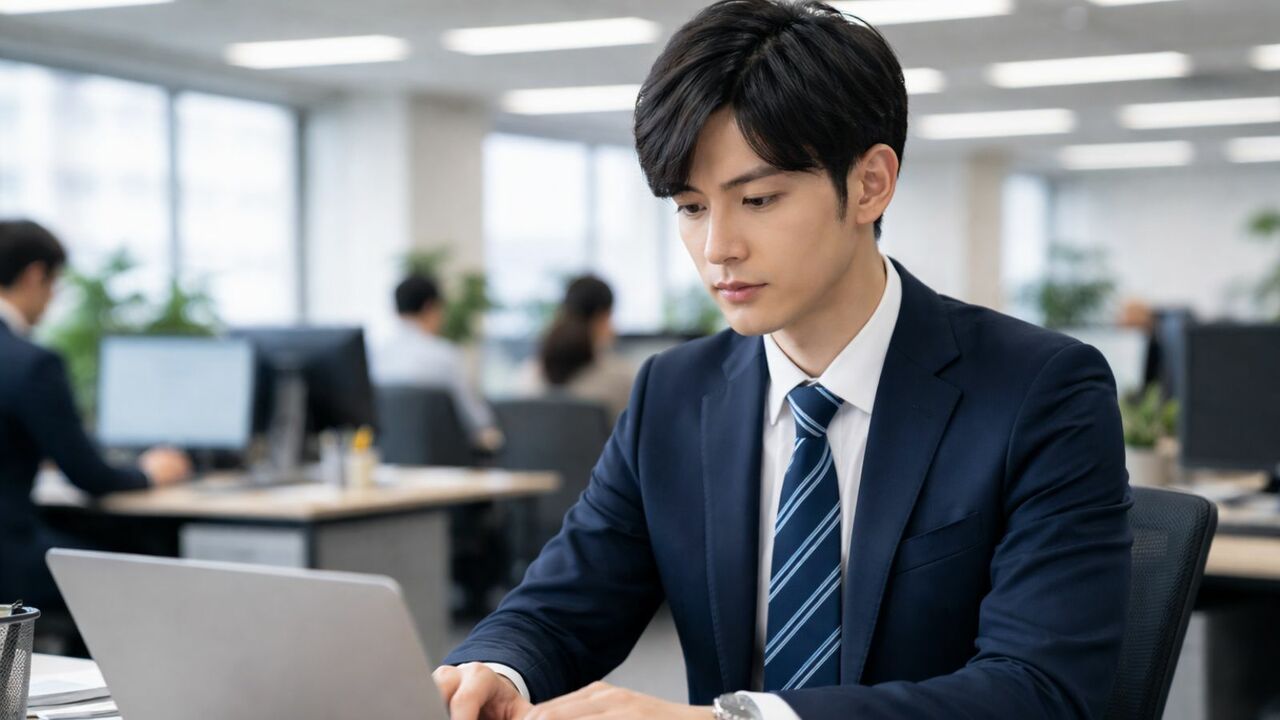【前回記事を読む】陳列を変えただけで客足が伸びた!? 現場の熱意とぶっちゃけトークが職場を変える「心理的安全性」の本質とは何か
第一章 知覚センサー、機能不全
「あたし、この前、デザイン・シンキングのオープン講座を受けました」
「アッちゃん、どうだった?」
「うん、面白かったというか、それがどんなものか輪郭はわかったような気がしますが……1日だけのコースでしたから、身についたかどうかは、また別ですね」
「そうなんだよね。私も研修を受ける側が長かったけど、こりゃあ面白いなと思ったプログラムも、やり続けないと身につかない。たいてい、もらったレジュメがPCや机の中にお蔵入りしてしまう」
Keiさんは焦りを感じている。辞令が下りると同時に、コロナ禍がはじまった。職階研修、職能研修、すべての活動をリモートに転換した。それに加えて、サステナビリティ、ダイバーシティ、コンプライアンス厳格化、社会教養などのプログラムも、新装・拡充しなければならなかった。
部門のひとりひとりが、必死だった。そして、リ・オープンと共に、多くの研修を対面型に戻す……。
そのあたりから、新たな根本課題がふくらんできた。人的資本経営――企業はひとを〈資源〉ではなく、成長する〈資本〉としてとらえ、その力を最大限に活かす。それによって、企業価値の持続的向上を目指す。そんな経営のあり方へ急速なシフトがはじまった。人財育成は、和田さんの言葉通り経営の主要な戦略論点となりはじめた。