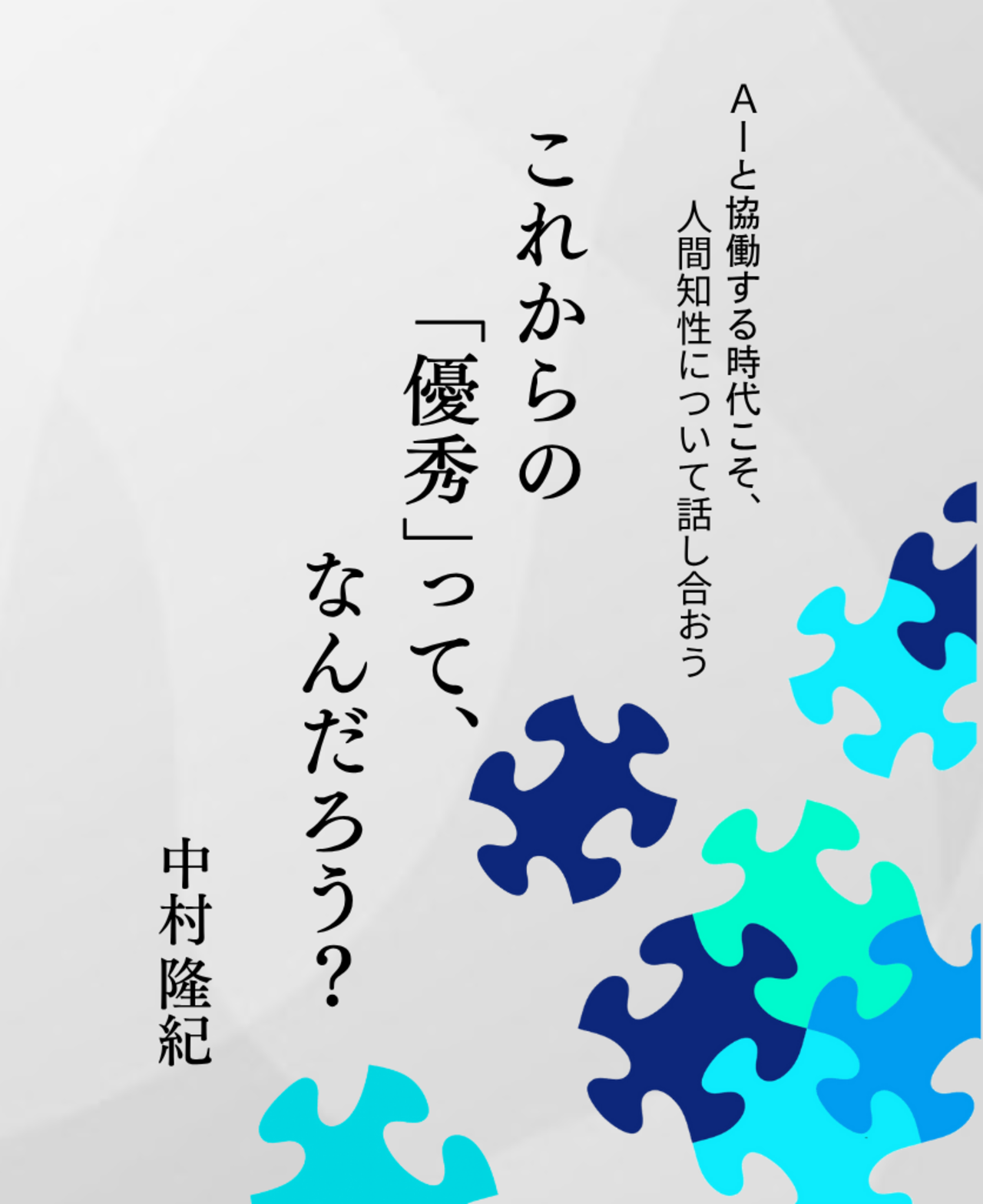いまや、勉強する時間がたっぷり欲しいのは、おれたちのほうだ。そんな繁忙の中で、自分が現在のポジションに呼ばれた理由である〈創造的人財の育成〉が、ぽかんと宙に浮いていた。
奥の席にいた男性は、タエさんのところで会計を済ませ、すでに帰っていた。ネイビーはみんなの話を肴にしながら、カルバドスをオンザロックで飲みはじめている。
――多くの企業は、デジタルなど装備の更新/職能のリスキリング/組織や制度、管理指標の改正で、事業進化を促せると思っていた。ところが、その前提にあるべき、創造的な思考をひろげる個々のモチベーションが、熟練でも若手でも、シワシワに縮んでいたんだ。
経営陣がイノベーションや事業創造の笛を吹けども、たいして誰も踊らず、経営方針のそこかしこに〈創造性〉という言葉が虚しく踊った。
その空虚を見透かすように、〈すぐにできます〉を謳う教育パッケージも乱立した。
問題の根元にある、組織風土をじっくり耕し直そうとする企業は、稀なのかもしれない。
そうこうするうちに、人財育成は、施策の重心をDX領域のリスキリングへ急速に移していく。
創造性は、学びの成果が出にくいジャンルとして、いっそう後回しになっていった。
「そうカンタンに発想が湧きまくる会社には、なれないよなぁ」ネイビーは、同情する。
「そうなんです。そもそも創造性の豊かな人財、という目利きで採用もしてきませんでした。会社が異質な発想を積極的に認める文化も、これからつくることになります。取って付けたようにハウツーだけ提供しても、浮くでしょう。でもなぁ、やらなきゃなぁ」
「創造性って、誰かに教えられて、方程式でも解くようにできるものなの?」
「……ひとり、気になる講師がいるんですけどね」