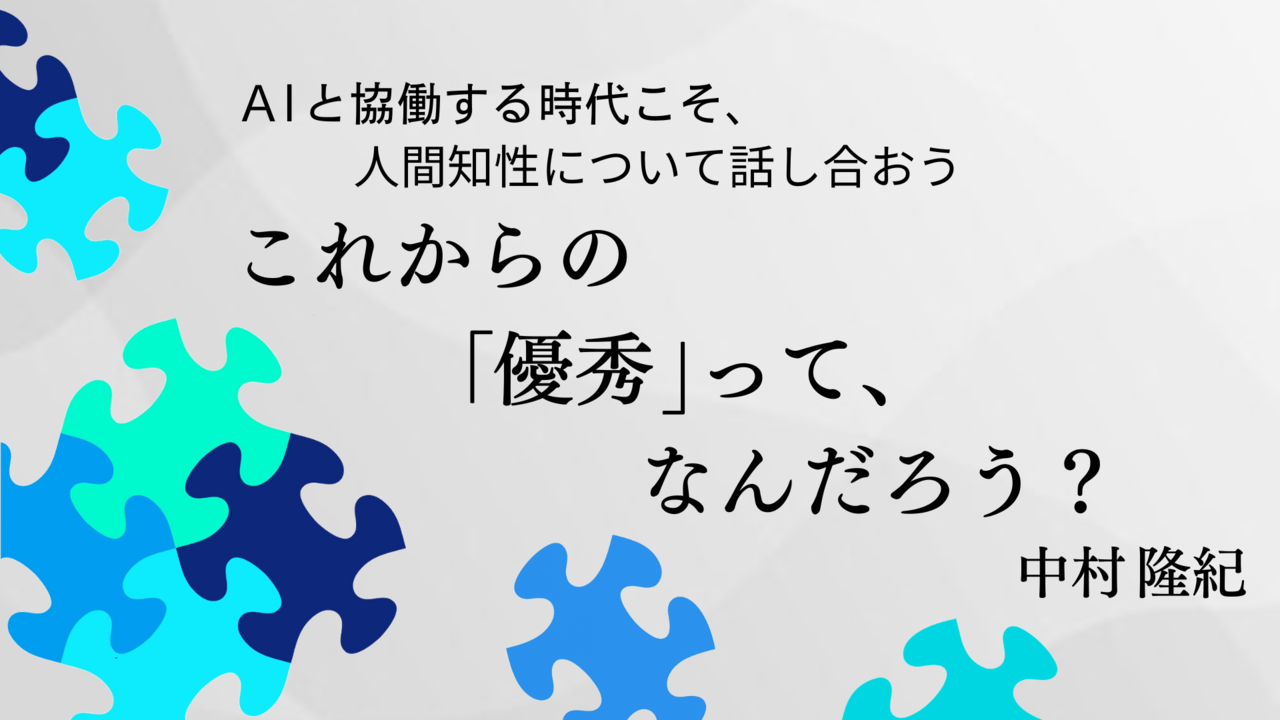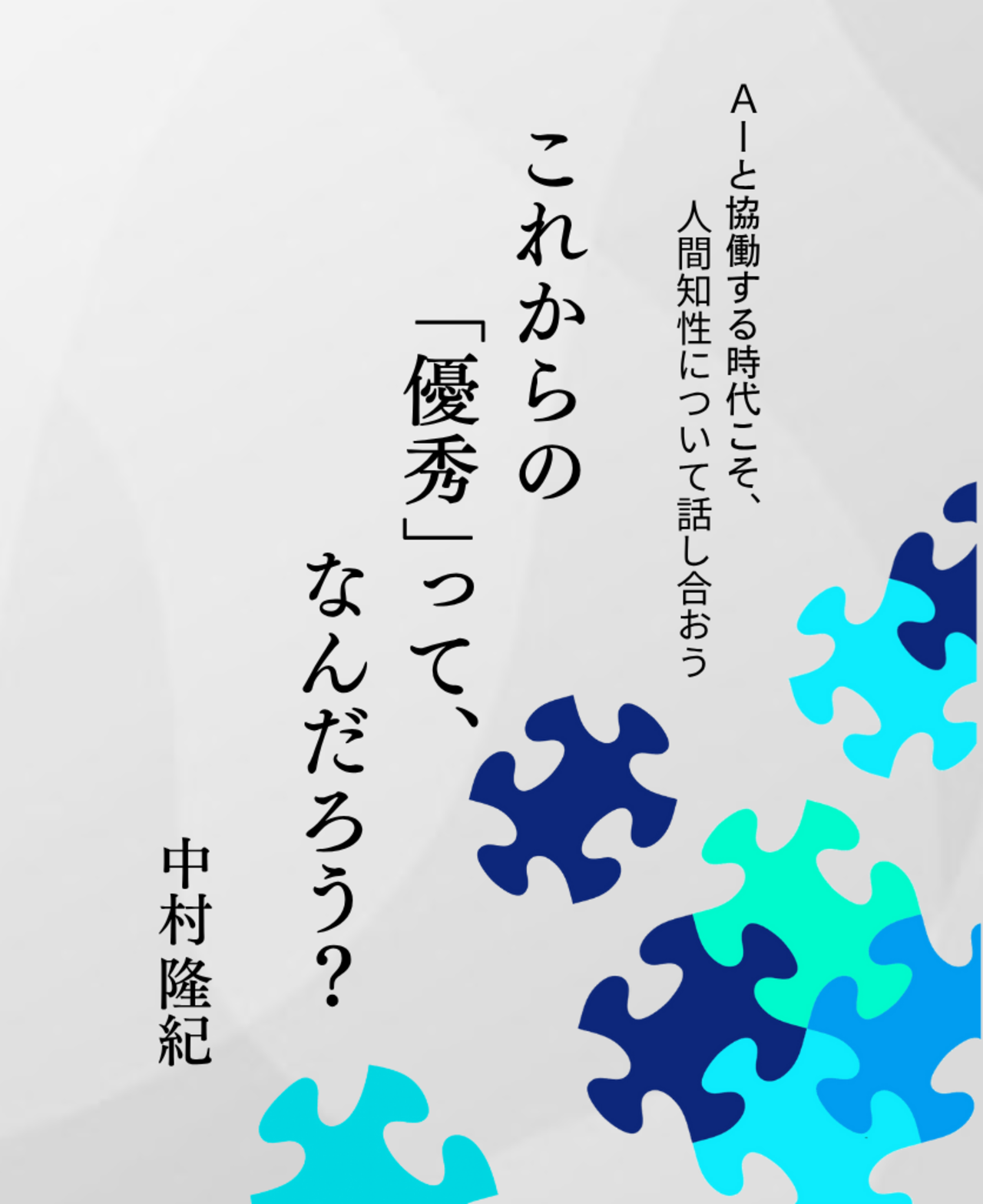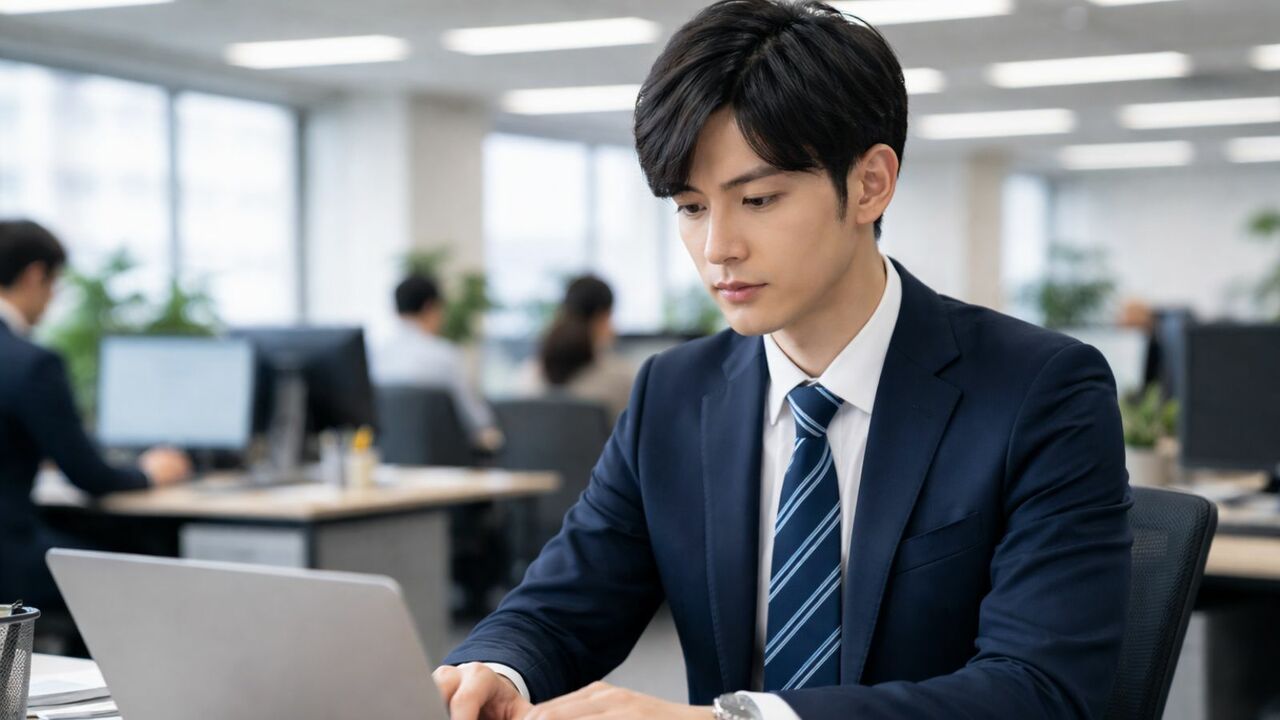【前回記事を読む】五感を使って発想の入り口をひろげる「デザイン・シンキング」―ひとりひとりの知覚習慣を磨いておくことが重要
第一章 知覚センサー、機能不全
ネイビーは、その講師の話に響くものを感じる。
――企業は、人間の創造性ですら、量産可能な工場製品をつくるかのようにとらえる。いままでは、共有された作業プロセスに自分を従わせて、主観を捨てた情報処理や作業分業に秀でていることが、有能の証とされてきた。異端と大胆は、会社という生産ラインの管理規格から外れた風来坊だった。
集団が効率的に動くための、組織教育における暗黙の了解は、人間をスキルという名のひな型に嵌め込み、標準化された物差しで測り、性能を均質化することではなかったか。
人間ひとりひとりは、もともと歪んでいる。違う遺伝子や身体感覚、価値観を持ち、違う家庭環境や地域特性で育つのだから。それぞれの心身が持つ感受性は、世界で唯一無二だ。
ピカソもビリー・アイリッシュもスティーブ・ジョブズも、創造人は、みんな歪んでいる。人生もロックの歌詞も新商品も、毎日の出来事をどう感じ取って、いかに意味づけるか。それが創造性の原点だろう。おれたちは、パッケージ化されたノウハウを学んで働く引き換えに、いびつで大切な感受性の偏りを、丸い氷のように削り取ってきたんじゃないか。
ひょこひょこ講師が話を続けている。
「私にはどうしても、リスキリングという言葉がうまく呑み込めないのです。そりゃ、DXは必要でしょう。でも一方で、『自分の頭で考えよう』とハッパをかけるわりには、他人の頭が考えたフレームの習得ばかりに依存していませんか。
人間の脳に、新たな職能マニュアルをダウンロードして、人間を標準パーツ4.0にバージョンアップするようでは、結局、デジタル・オペレーションに沿って無難に整然と動く、相変わらず異端のない組織になるだけじゃないですかね。しかもそれを、できるだけ効率よく、手っ取り早く、『できた!』と思わせるような学びばかりだったら」
男は、ちょっと目を伏せながら、ため息のような小声で言った。
「企業の教育は、ゆとり教育になっていませんか?」