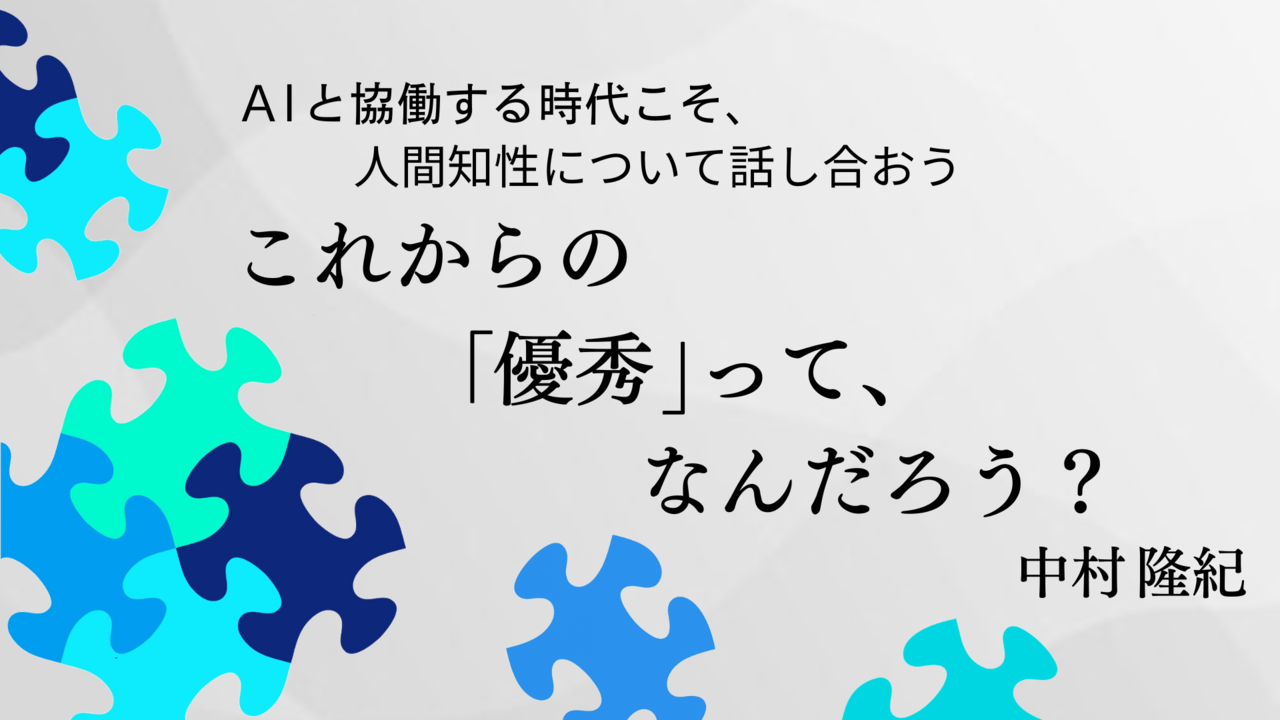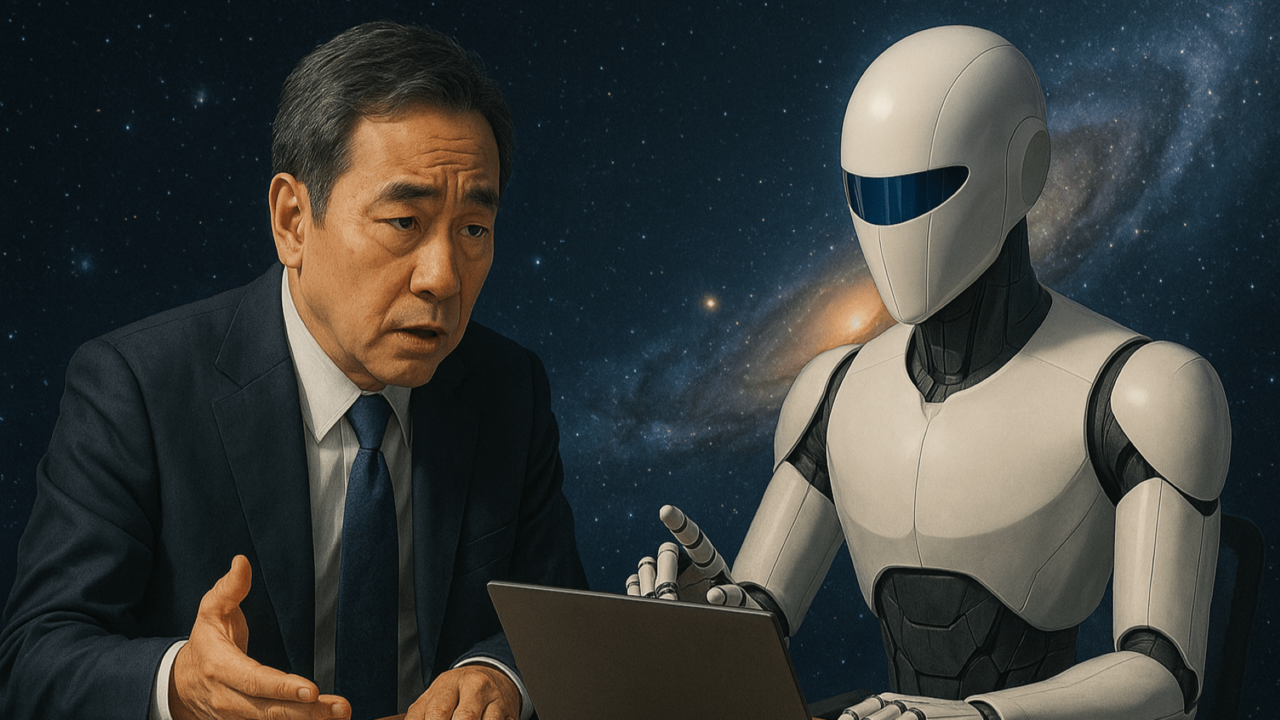【前回記事を読む】現場が若手に、パターンに嵌った仕事ばかりさせたり、個人が自分で先へ学ぼうとしなかったら、本物のプロフェッショナルは――
第一章 知覚センサー、機能不全
アッちゃんはいつも、ケンタッキー・バーボンロックを2杯飲む。そのあとは、濃い目のアイス・アールグレイに切り替える。ネイビーが2杯目のメーカーズ・マークを注いだ。
彼女もジョージとおなじように、グラスの丸い氷をつつきながら、自問するように話す。
「あたし、確かに、カンタンにやろうとしすぎているのかもしれない。なんだか、アッサリわかって、キレイに論理化できて、スマートに仕事を進められるひとが、優秀の鑑!みたいに思ってた」
「やっぱりキミたちは、アンドロイドに憧れているんだ」YOさんが茶々をいれる。
「優秀に働くって、どういう感じなのかな?」
「アッサリわかって」「キレイに論理化できて」「スマートに仕事を進められる」
「知識がいっぱい」「仕事が早い」「計画性がある」「あまり悩まない」
「金儲けがうまい」「偏差値が高い」「説得力かな」「お客さんの信用」
「ほらな、創造性って、誰も言わない」「……あたしの優秀観、けっこう昭和かも」
双子にビールをもう1本。ジョージ、ハイボールでいい? クマくん、ジンライム。ネイビーは、お客さんの酒をひと通り満たす。
彼は飲食業のベテランではないが、テニスのフェデラーやアイススケートのキム・ヨナのように、しぐさにゆらりと余裕があって、無駄がない。ネイビーさんという名前は、海兵隊かどこかで鍛えたからですか?と訊くお客さんもいた。紺色のオープンシャツの店主が、みんなのほうを向く。