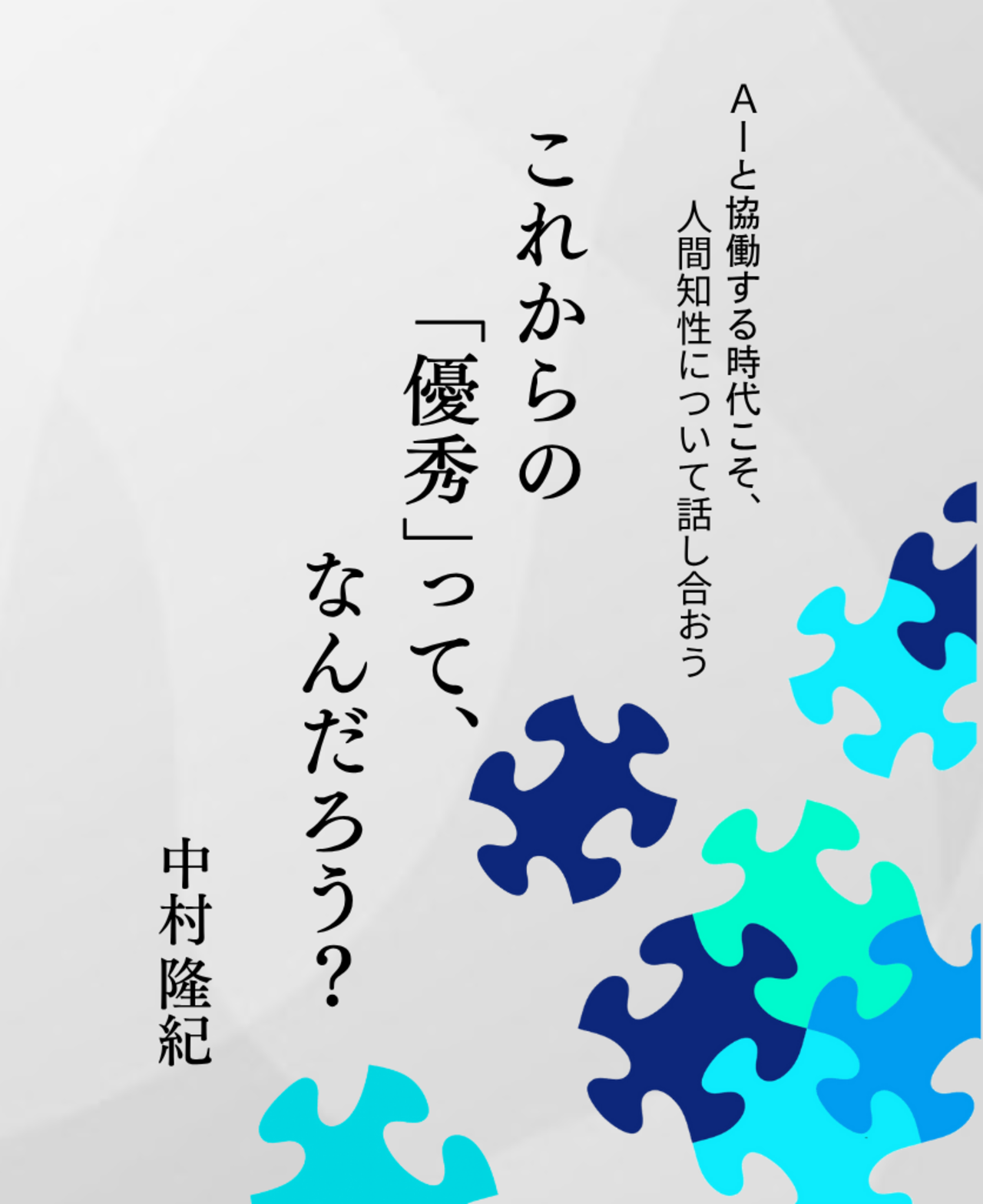「おい、Kei。知覚センサーが治る食べ物、なんかないのか? 売れるぞ」
「もし本当に、コロナ禍がきっかけとなって、まわりと気づき合えない感覚不全が、世界中で増えているとしたらさ。子ども、大人から、それこそ政治家とか」
それまで口をひらかなかったクマくんが、ビワの皮を丁寧にむきながらつぶやいた。
「……絶滅ですね」
会議室では、石橋さんの手が企画書のページを何度もめくり返していた。
「五感を使って発想の入り口をひろげるのは、デザイン・シンキングでもやりますね」
「はい。私はデザイン・シンキングをリスペクトしています。適当に共感するなという意味では、ラテラルやクリティカルな思考法にも意義を感じます。ただし、こうしたメソッドを使う手前に、考えるべき点が二つあると思うんです」
ひとつは、人間の外部にあるプロセス通りに思考を進めても、そもそも内面の感受性が磨かれていないと、常識的な発想をアウトプットしがちです。
それから、もう一点。組織全員が同じフレームやメソッドに沿って、忠実に考えれば考えるほど、異端の発想は生まれにくくなります。多様な個の独創を促すのなら、思考の手順をあまり細かく規定しないほうが、発想の幅はひろがるのではないでしょうか。
これから時代がどう変わろうとも、AIを活用する新しい発想がひろがるとしても、まずは、ひとりひとりの知覚習慣を磨いておくことが、創造性のしっかりとした土台になるはずです。
石橋さんが訊ねる。
「受講生は1クラス25名程度とあります。わたしたちは、できればなるべく早く、多くの社員に学びを提供したいのですが」
「石橋さん、お気持ちはわかります。ただ、創造的人財は、短期間で大量生産できません。量産すると、結果、同質化します。ゼミナール・サイズでディープにやることを、おすすめします」
次回更新は7月30日(水)、11時の予定です。
👉『これからの「優秀」って、なんだろう?』連載記事一覧はこちら