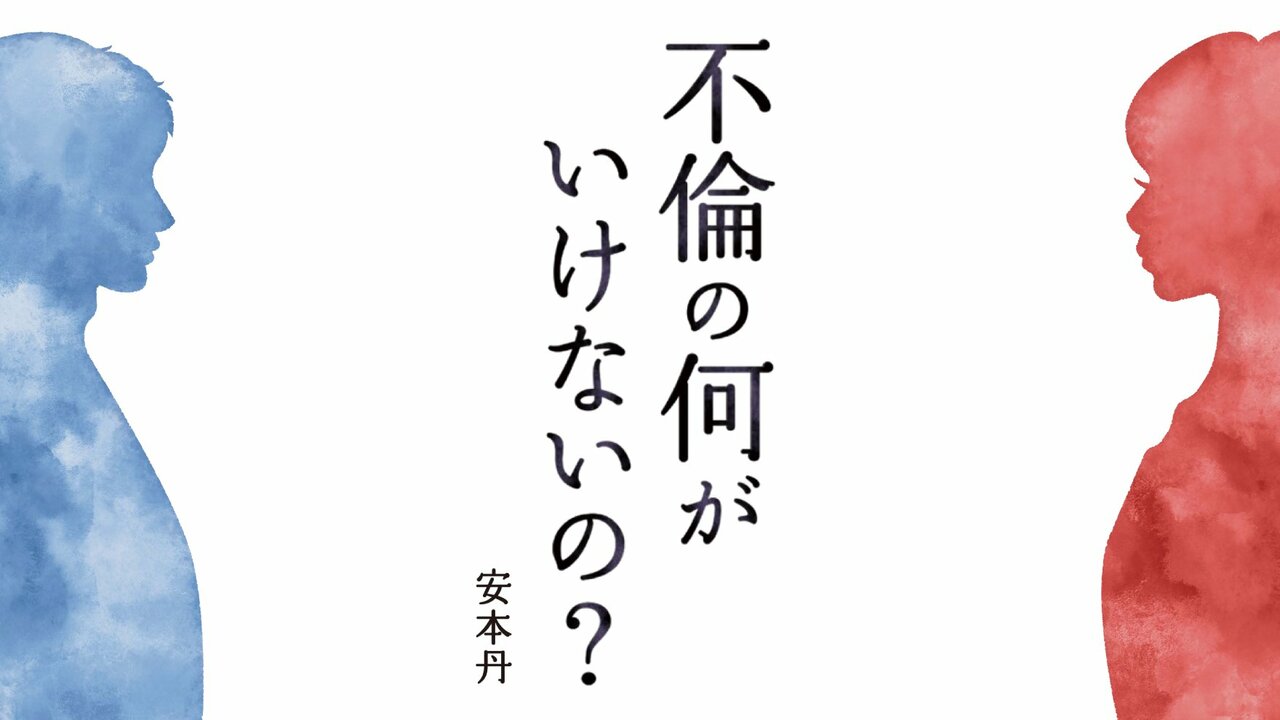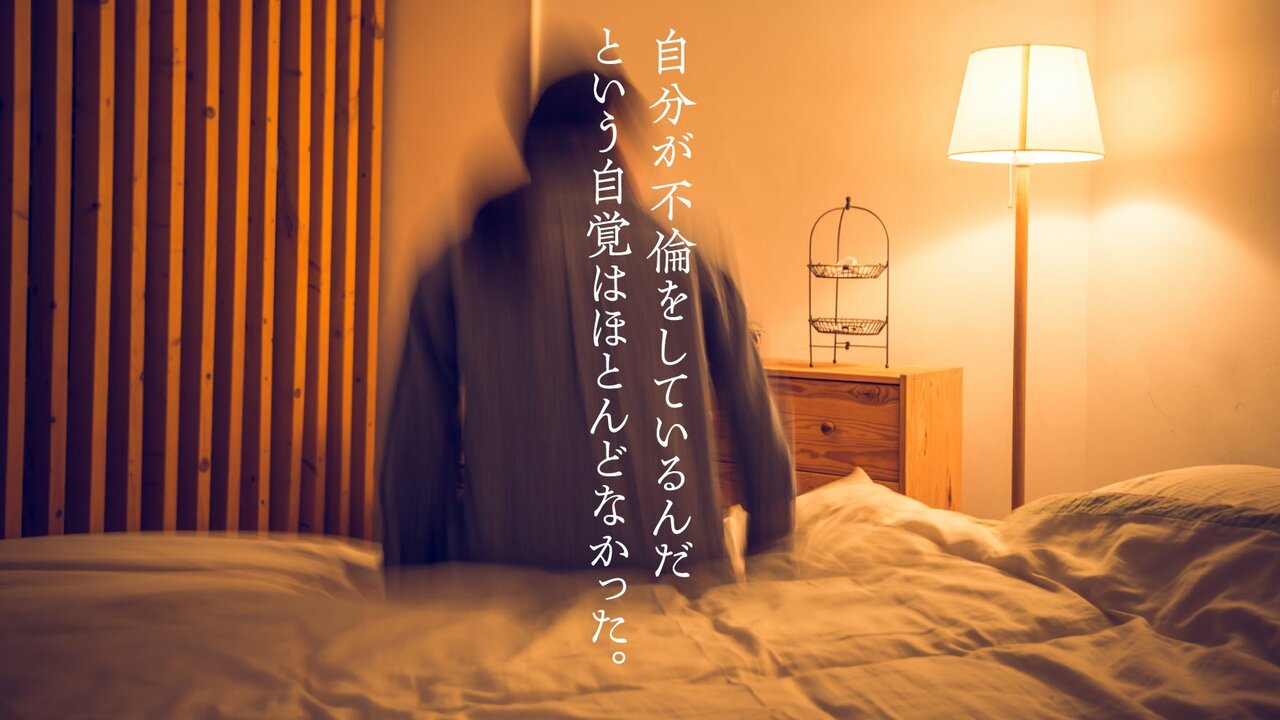第十章 バレンタインデー
気がついたら私はラブホテルにいた。ホテルに入ることを拒めなかった。もう私はショウ君のことが好きになっていたのだ。
「美味しいご飯があるお店、期待したのにな」
皮肉っぽく言う私を彼はキスでなだめた。突然のキスに全身が硬直し、高揚した。もうこのままどうなってもいいとすら思ってしまう。
ショウ君のキスは痛いくらいに強い。こんなキスは初めてかもしれない。そんなに気持ちの良いものではなかった。でも大好きなキスだ。
ショウ君が私の手を取り自分の股間へ持って行く。もう片方の手を私のスカートの中へ伸ばした。
「まだセックスはしたくないな」
それは私の今の正直な気持ちだった。ショウ君は私が下着を着けていないのに気がついて、溜め息を漏らした。
「別に俺にとってはセックスがゴールじゃないから。こうやって触り合ってるだけで感無量だよ」
セックスはしなくてもいい。私はなんだか自分がすごく大切にされているような気がした。それではショウ君にとってのゴールとはなんだろう。
ショウ君がスラックスのファスナーを開けた。旦那のものよりもひと回り小さなペニスが顔を出す。可愛いそれがなんだかとても愛おしかった。手で優しくしごくと、早くも射精しそうになるのだが彼はそれを我慢した。私にキスしては胸やヴァギナを弄(まさぐ)り、射精しそうになっては我慢する。
いつまでやるのかというくらい、ショウ君はしつこかった。彼への気持ちが冷めてしまわない自分が不思議なほどだ。むしろ私は感じていた。細くて身長もそれほど高くない、ショウ君の小柄な身体の一体どこからこんなにも性欲が溢れ出るのか不思議だ。好きな人に激しく身体を求められることに私は幸せを感じた。