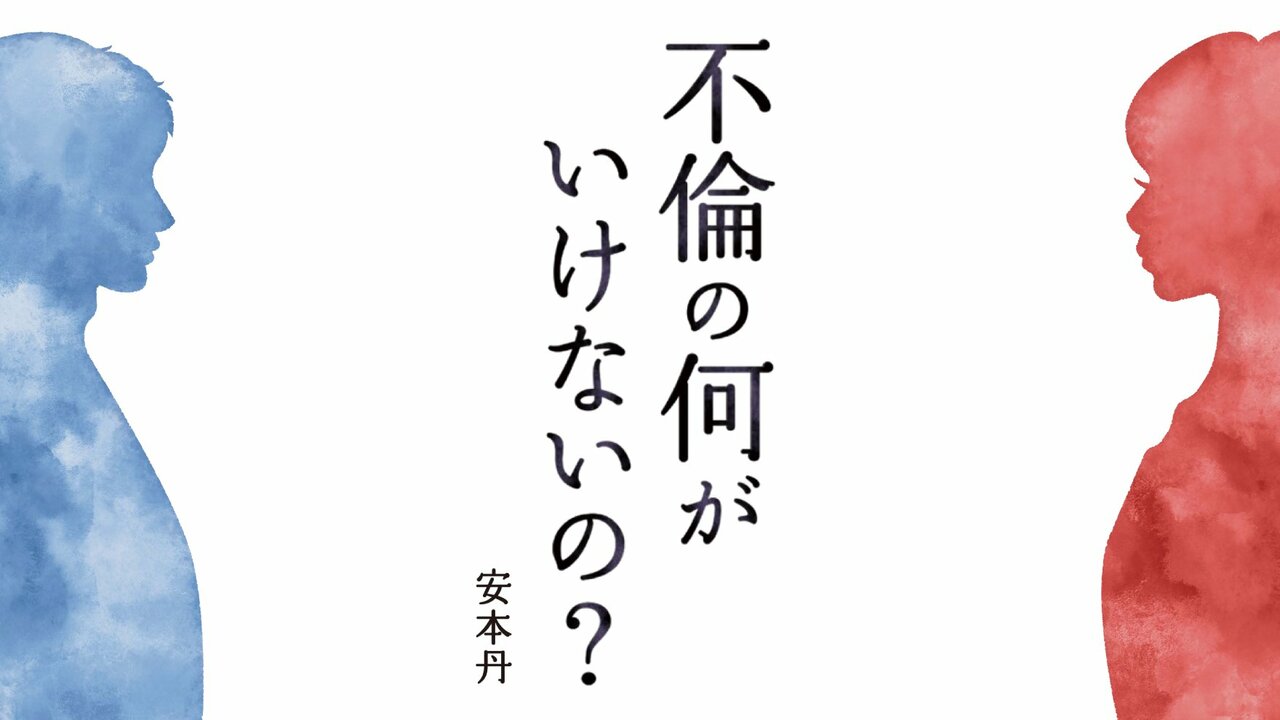第十章 バレンタインデー
ジョイナスから帰ると時刻は二十三時を過ぎていた。
帰宅ラッシュもとうに過ぎ道は空いていたものの、やはり帰るのに一時間半はかかる。
運転の緊張感から解放されて心地よい眠気に襲われた私は、メークを落とすと真っ先に寝室へ向かった。旦那はもう寝ていた。ふと携帯が鳴る。
〈あのさ、すごくみゆちゃんに電話してみたいんだけど、してみていい?〉
ショウ君からのメールだった。私は危うく声が漏れそうになり口を押さえた。そのまま寝室を出る。好きな人からの電話の誘い。私は高鳴る心臓を押さえて、車へと戻った。旦那は寝ていたがやはり家の中で電話をする勇気はなかった。番号を送ると、ショウ君はさっそく電話をかけてきた。
「みゆちゃん、あぁ。嬉しいよ、電話できて」
溜め息交じりのショウ君の声。電話でも同じだった。
うっとりしながら受話器に耳を押し当てた。こんな気持ちは何年振りだろう。
「帰りに牛乳買ってきてくれない? あなた、朝全部飲んだでしょ?」
旦那とは一緒に暮らし始めてから、そんな電話しかしていなかった。こんな風に、会いたい気持ちを胸に秘め、相手の発する一言一句に真剣に耳を傾けて、甘い声で囁き合うなんてことは、もうずっとしていない。
夢のような時間だった。しかし私はあえて早めに電話を切った。
楽しい時間は、短ければ短いほどに愛おしい。私はショウ君を焦らしたかった。もっと話していたいと思ううちに電話を切って、名残惜しい気持ちにさせたかったのだ。しかし本当に名残惜しくて堪らないのは私のほうだった。
電話を切った後も、しばらく車の中でその余韻に浸った。目の前の道を、けたたましくサイレンを鳴らした救急車が通るまで、私はそこから動くことができなかった。