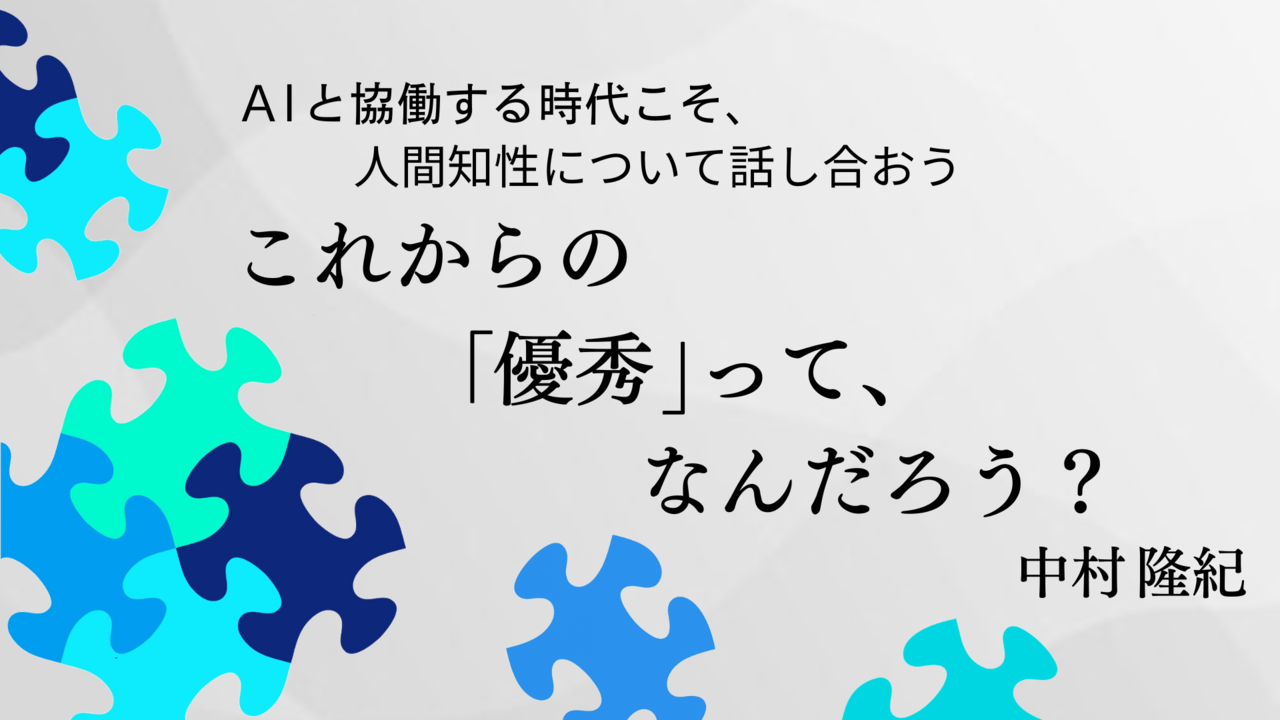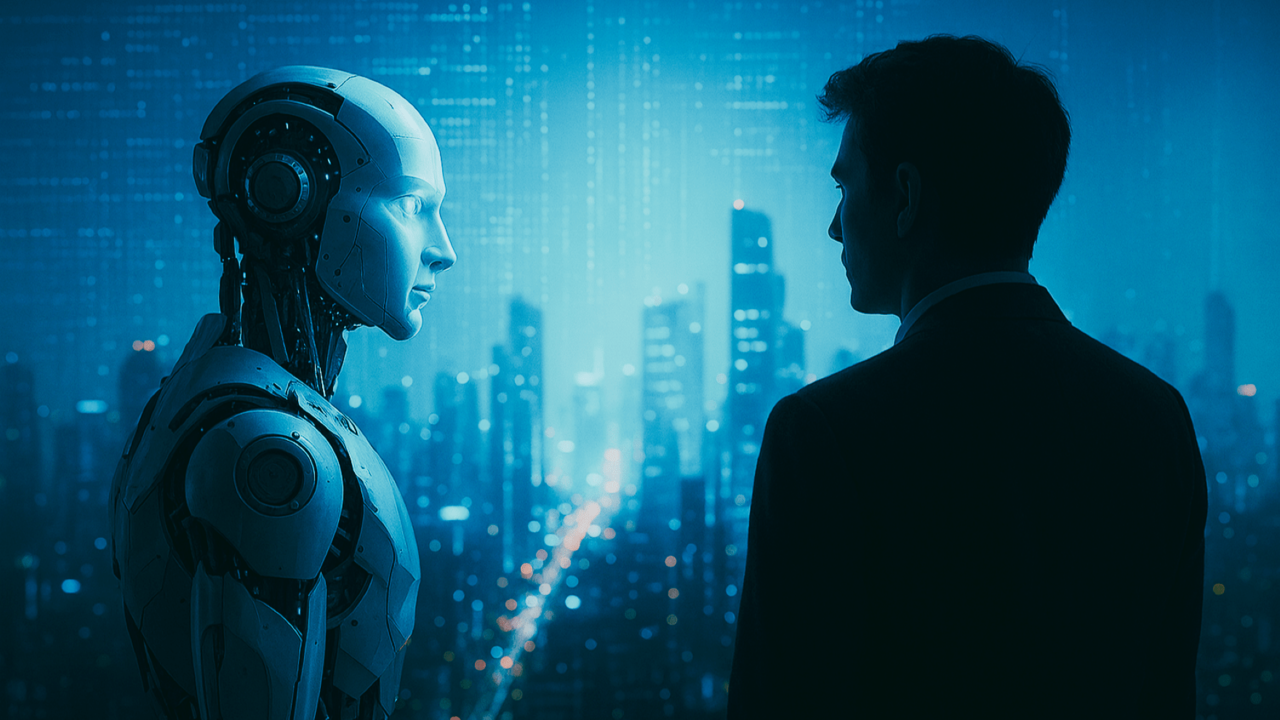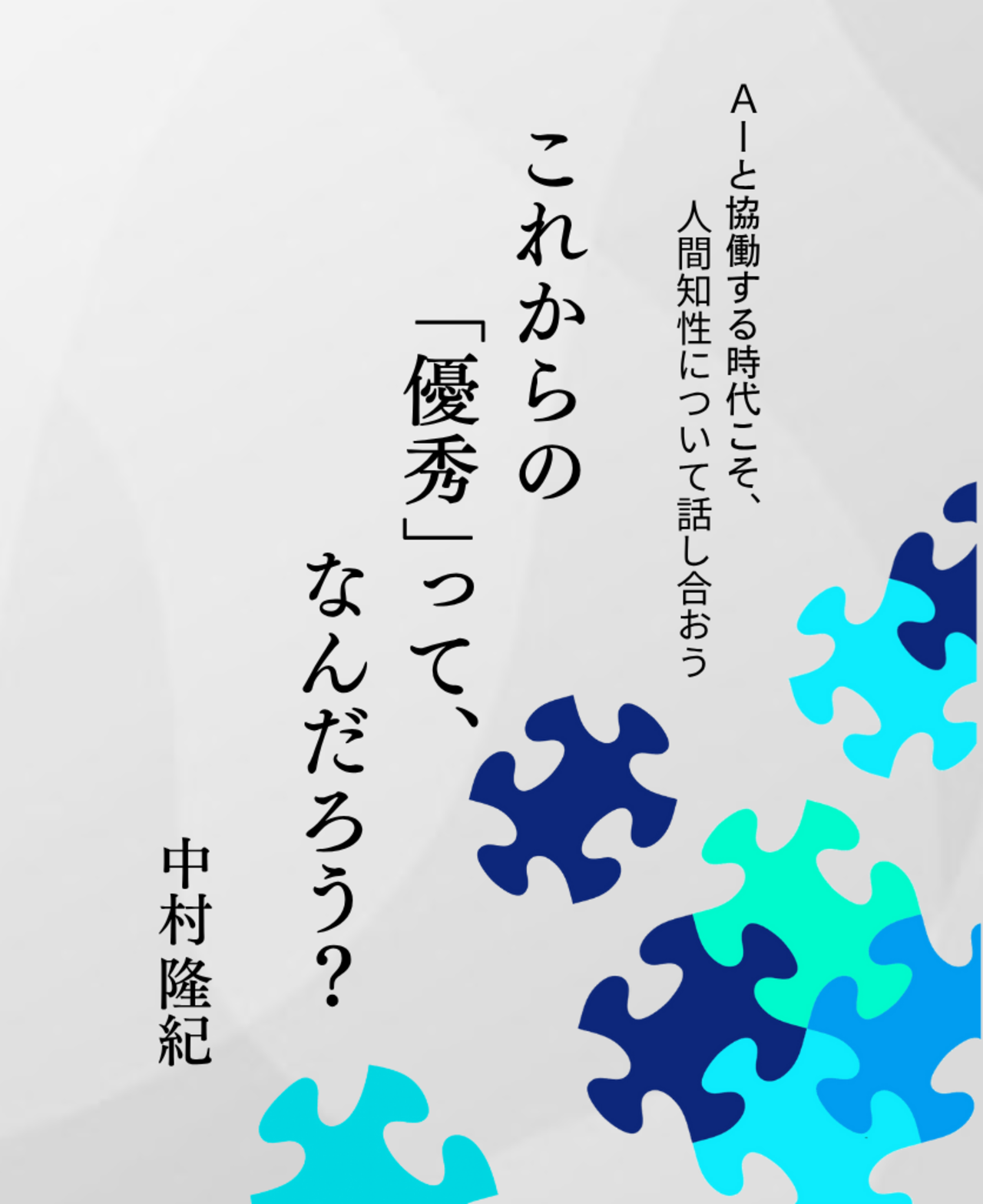【前回記事を読む】リスキリングやスキル更新だけで大丈夫? 社会人が幸せに働くために必要な学びとは
第二章 すぐそばにある、知の分断
シュウトくんはいつも、タエさんの自家製レモネードに、ラムとホワイトキュラソーを垂らしてもらう。カクテルでいえばXYZの亜流だろう。それを背の高いコリンズグラスで飲む。
「いまの子どもたちが社会に出る、10年後の世界がどうなっているのか……僕たちだって、どうなっているかわかりませんけど……マジで、働く前提が違うはずです」
いままで通り、提供された学習をうまくこなして、立派な組織をめざして。それで競争の勝ち組感があって、しあわせな暮らしができるはずだって思えるのかな。10年どころか、5年後に……。
「Keiさんのところでは、AIエージェントの研修はあるんですか?」
「うん。ほんとうはマニュアル本みたいな研修は、やりたくないけど。経理と開発では、入り方が違っていいからさ。みんなが同じように使うと、またちょっと、創造性に幅がでないだろ」
「そうですね。本当は遊びながらトライ&エラーで、自分の使い方を編み出していくのが面白いんだけど……会社はなぁ。でもそのうち、仕事そのものが、変わっちゃいますよね」
「そうなんだ。職務どころか、そもそも働くって、なにをすることなのか、まったく変わるだろうね」
「さっきの英語の話じゃないですけど、プログラミング言語を知らなくても、AIと対話してゲームぐらいつくれてしまう時代になっています。しかもAIは、3か月でバージョンアップするし……」
「シュウトの仕事は、大工より生き残るんじゃないのか?」YOさんが訊ねる。
「わかんないです。AIそのものというか、技術のコンセプトを創造するひとたちは、生き残るかな……AIが自分で進化しはじめるかもしれませんけど。
一般のシステムやソフトウェア開発は、ソースコードを記述できなくても『○○をしてほしい』って指示を出せば、プロセスは、かなりできるようになります。まさかと思っていることが、すごいスピードで進みはじめているんですよ。ね、クマさん?」
「……僕ら、絶滅です……」