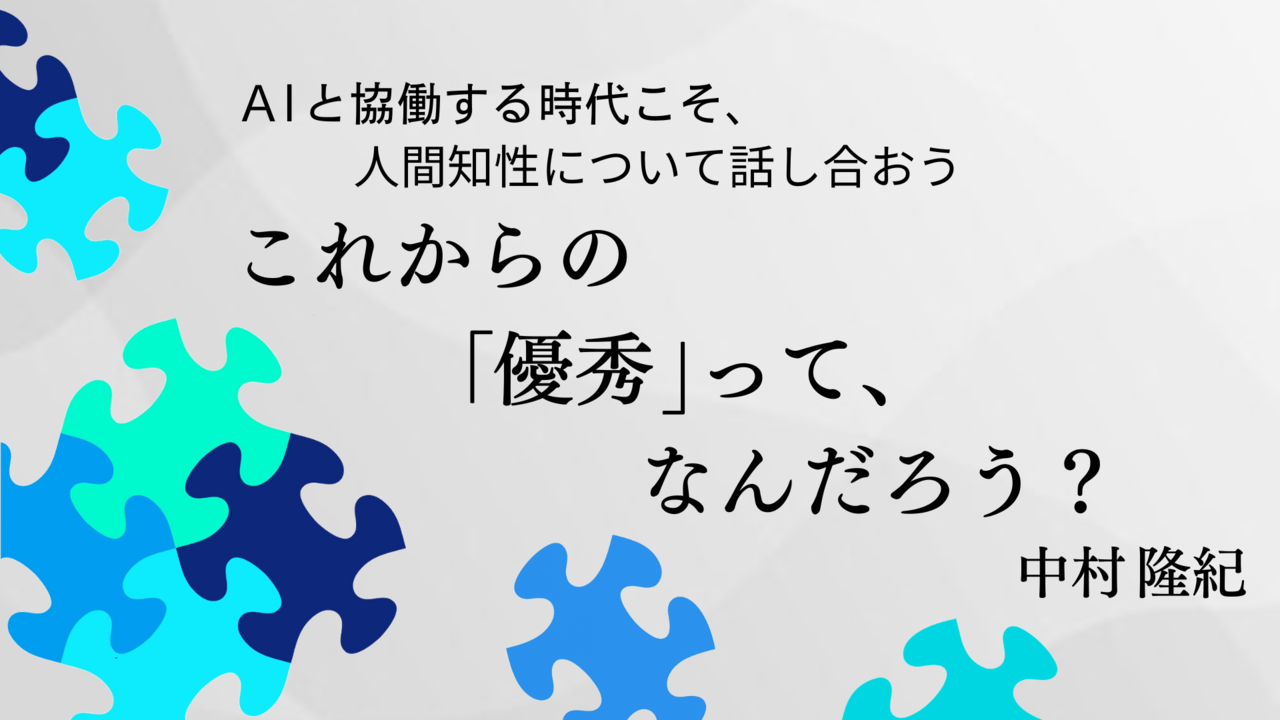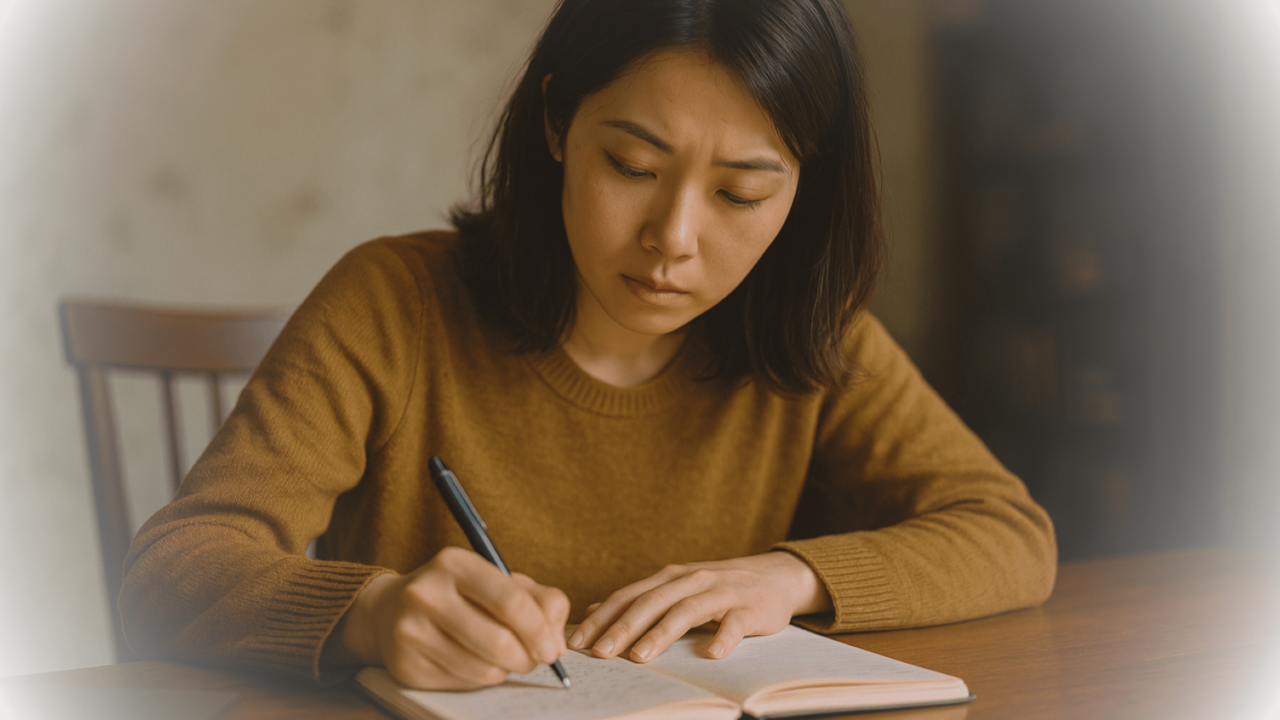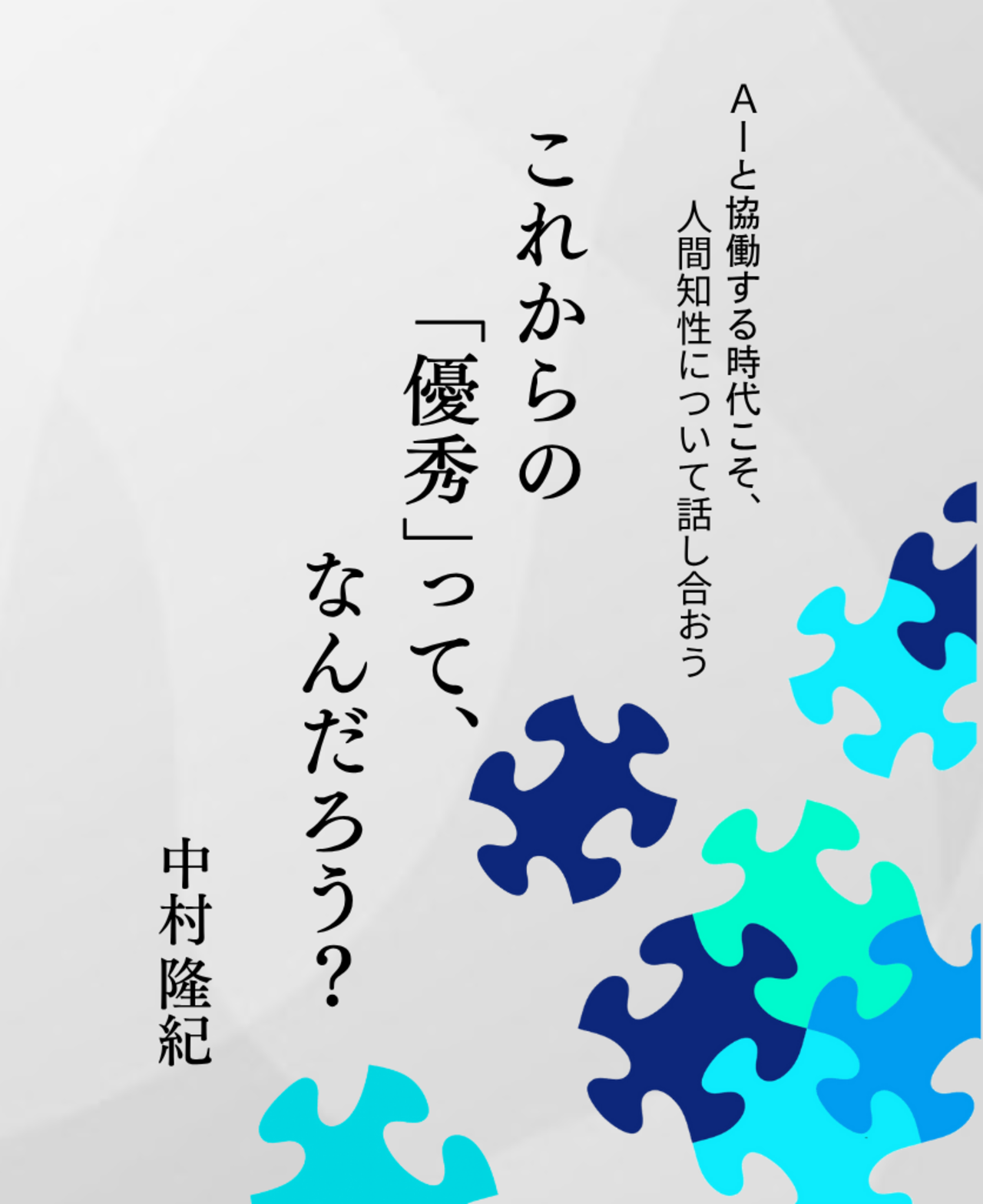【前回記事を読む】【ノートを取らないと覚えられないヤツは、バカ】ノートを取らないことが、知性の証に?
第二章 すぐそばにある、知の分断
ノートは暗記のための記録じゃないわ。わたしたちは、自分の手がつくった書き込みの上で、自分と対面している。ひとの話から、なにを拾ったのか。相手の言うことを、どう解釈したのか。その言葉の脇に、どんな連想が寄ってくるのか。理解と思考は、表裏一体でしょう?
日本語を読んでなんぼ、書いてなんぼが、失われている……そのひとの高校、県立なのよ。いま企業では、実務のリーダーが彼らの世代になりはじめている。わたしはちょっと、気になる。最近の学校は、もう少し言葉を大事にしてくれているのかしら。現場で起きていることは、世の中で言われているより、些細なところで、もっと深刻よ。
Keiさんが、ため息をつく。ウチの若手も、いやおれも、ノートを取らなくなっている。というか、手取り足取り、レジュメやマニュアルが準備され過ぎているのかもしれない。
「そういえば高校の教育では、論理国語と文学国語が分けられましたね」
「なんだそれ? 受験用の国語と、人間用の国語みたいじゃないか」
YOさんのわかり方は、常にスッパリしている。
「学校では、子どもが自分で問いを立てるような探究学習が増えているけれど、まだ教科書を覚えて答えを出して、点数にするような勉強が主流ではあるのよね」
リョウコさんは、ワインを自分でグラスに注ぎ足す。手酌のほうが、気が楽なのだ。
「わたしのプログラムを手伝ってくれるひとたちの中に、美術の先生がいるの。その先生が嘆いていたわ。子どもが美術に興味を持っても、受験の役に立たないからって、親があきらめさせてしまう」
「藤井聡太さんが活躍して、将棋はいいけど、絵はちょっと、とか、偏向もありそうだな」
ネイビーが、ワインクーラーにクラッシュアイスを流し込む。
「いろんな大学のホームページを見ると、あちこちに〈問題解決能力の高い、グローバル人材をつくります〉って書いてある。おれには、〈グローバル経済のパーツ、大量生産します〉って読めるんだ。読解力、ありすぎかな」
「学びの目的が、経済ファーストで画一的なのね」
子どもが英語に興味を持つことは、悪いことじゃないのよ。英語を学ぶのも、その子が海外の何かに興味があるのだったら、それは素敵な挑戦だわ……大切なのは、子どもがどんなことに好奇心を持つのか、親が自分の時代の価値観で、入口を制限しないことじゃない?