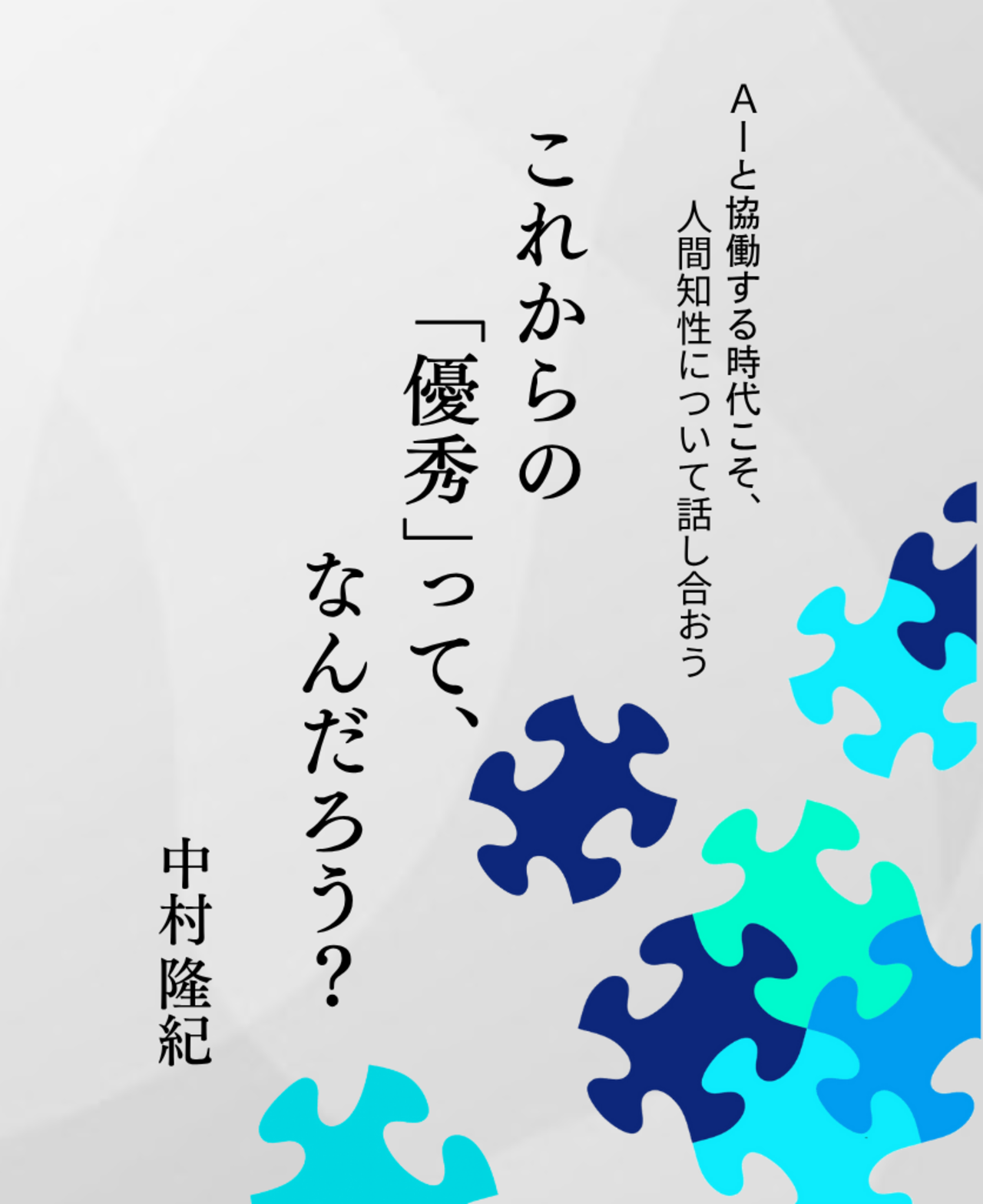いまは、子どもたちのまわりに多彩なプログラムがある。SDGsもあり、書道や武道もあり、ロボット工作もやっている。わたしは、知性の土台みたいなものは、さんざん学び散らかして、体験のすそのを広げておいたほうがいいと思う。だって、人生100年時代なんだから。
Keiさんは思った。そうだな。これからどんな知識が役に立つかなんて、わかったもんじゃない。企業は事業計画に合わせて、必要な職能を設定する。でも、働くことそのものが、ガラッと変わる時代に、職能に合わせて学び続けていくだけでは、そのうち人間自体が摩耗してしまいそうだ。
社会に出てからだって、自らの好奇心に任せて学ぶほうが健全かもしれないな。うーん。でもそれは、自律的な成長形成、自己責任だよ。そこまで、われわれ育成系が提供すべき仕事になるのか?
かつてリョウコさんは、生命保険会社の調査部門で順調にキャリアを積んでいた。彼女の会社では、人口動態から労働環境、医療技術、就学動向、ライフスタイルなど、マクロからミクロまで広範囲の調査を行い、戦略や商品開発の道しるべとしていた。
彼女が40歳を越えてすぐ、お母さんが認知症を発症した。そうした高齢者の状況を調査分析したこともあるが、それと自分の家族に起こったリアルとは、別物だった。
――知ってはいたけれど、わかっていなかった。ましてや感じていなかった。
発症した側の恐れや悲しみ、あきらめ。リョウコさんのお母さんは、記憶から抜け落ちる出来事や予定を、大きな日記帳にびっしりと書き込んでいた。自分の脳に抗いながら、懸命に生きるお母さんが愛おしかった。
ひとびとの、本当の現場と向き合おう。彼女は介護教室を通じて知り合ったNPOに、思い切って転職した。
リョウコさんがワイングラスに視線を落としながら、独りごとのように話す。