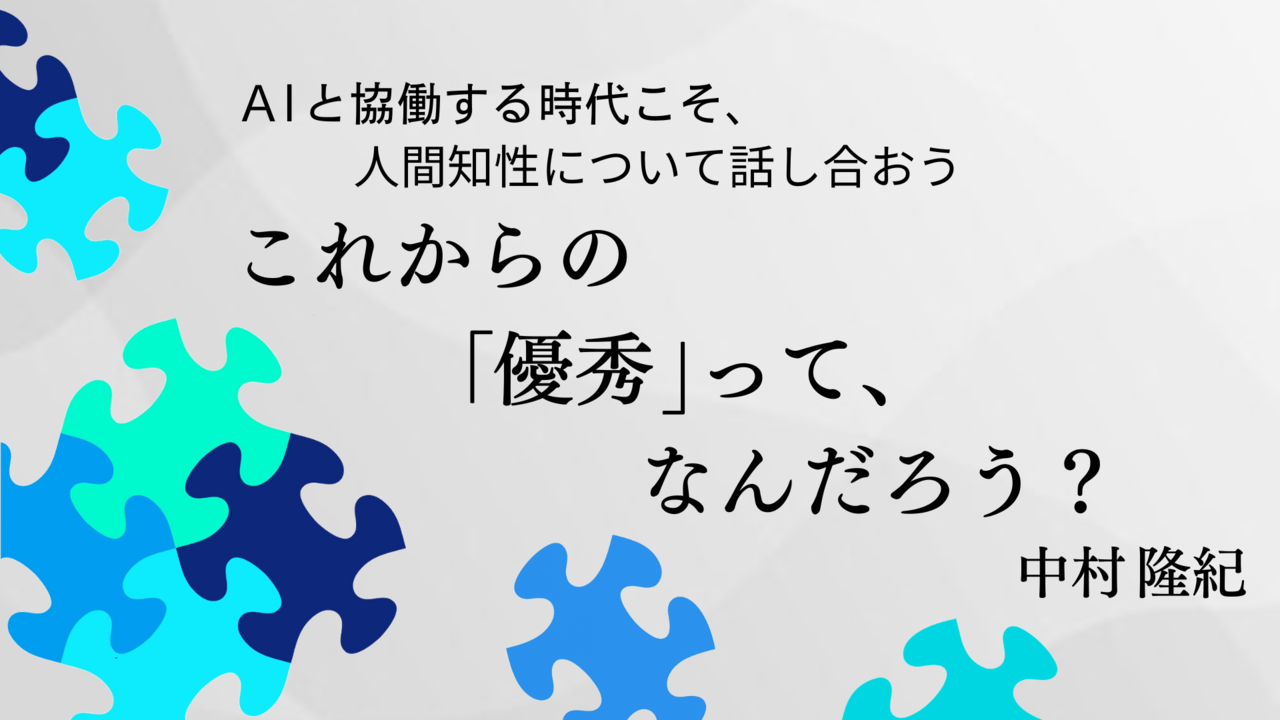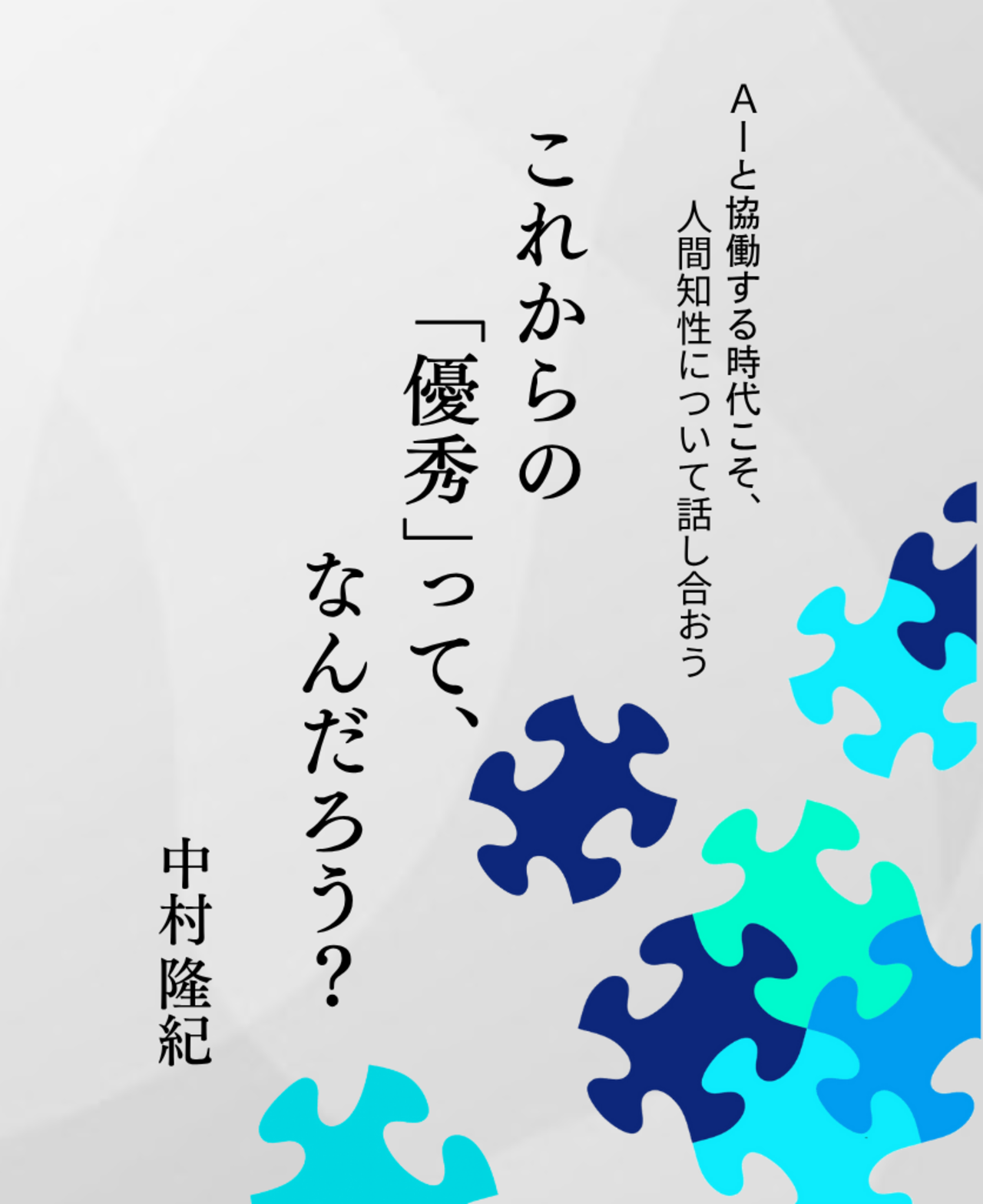【前回記事を読む】AIに仕事を任せる時代、人間に残る役割とは?――迫る仕事の未来
第二章 すぐそばにある、知の分断
「あ、そうです。たぶん。ゲームをつくるんだったら、ゲーム関係だけじゃない本もたくさん読んで、アートも観て、旅行に行ったりヨガの道場に通ったり、神社巡りしたほうが、アイデアが豊かになるとしたら……
プログラミングやタスクの設計がうまいことより、そっちのほうが大切になっていくんじゃないかな。商品やサービスの開発は、中間手続きがかなり激変するような気がします。バックオフィスも、すごく小さくて済みます。でもそうしたら、人間は、なにを学べばいいんだろう?」
クマくんがつぶやく。
「……言葉は大事だ」
シュウトくんが即応する。
「それ、言えてます。AIの性能を引き出すには、すぐれたコミュニケーション力がいるんです。言葉の選び方、ワーディングや、対話の組み立てとか。
ただ、ネットからマニュアルみたいな定型プロンプト(指示文章)を集めてきて、それをコピペして貼り付けても、似たような答えになりがちです。
AI自身も学習していますから、AIに問いの立て方を作ってもらうようなやり方もあるんだけど、う~ん、結局、アウトプットはふつうになる。
いずれ、みんながAIをぶっ飛んで活用するには、気づきをうまく言葉にする能力が〈違い〉になっていくと思う……あれ? ネイビーさん! やっぱり、言語は素養なんだ」
学びのスーパー・ジェネラリストである女性が、Keiさんにひとさし指を小さく振る。
「社会人教育は、新人さんもベテランさんも、〈読む・書く・話す〉を、土台からじっくりやったほうがいいかもしれないわね」
「Keiの仕事は、底なしにひろがるな。可哀想なやつ」YOさんが弟を流し目で見る。
「いや、せめてそこは、学校教育で根っこを太くして欲しいけどなぁ。職業訓練や就活準備みたいなことは、もういいから。まったく、人財開発は、どこの底までやればいいんだよ」
ネイビーは、それぞれプロフェッショナルである常連たちの時代知覚を、心に留める。
――「勉強とは、こういうものだ」先入観を固定されたひとは、仮説に耳をふさぐ。
――「エリートは、こう学んできた」前例から離れないひとは、予兆から目をそらす。
おれたちはいま、学びの常識定説だと思ってきたことから、本当に離脱しようとしているのかもしれない。そう感じるか否かでも、未来への認識が分断しはじめている。
「あと、Keiさんの言う、出口のほうなんですけど」ジョージがスモールトークをつなぐ。
「AIが提案してきたことが、人間にとって適切かどうか、アウトプットを判断する能力が、問題になりませんか」