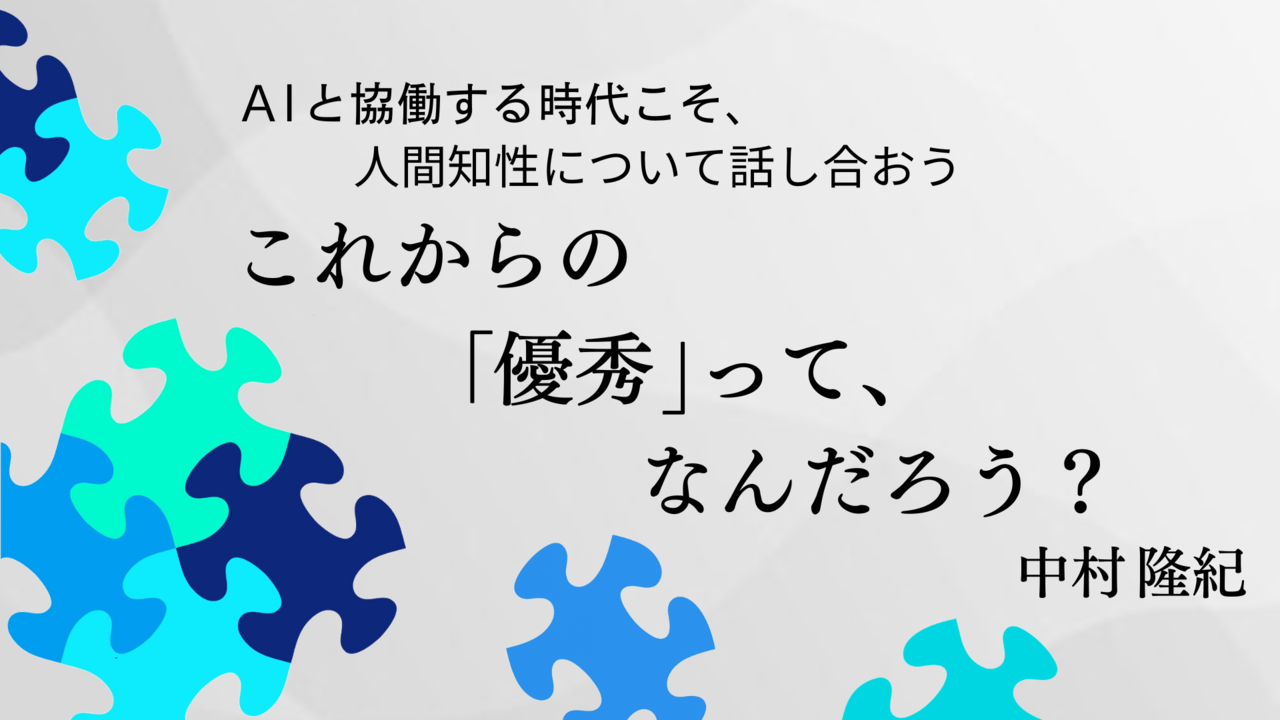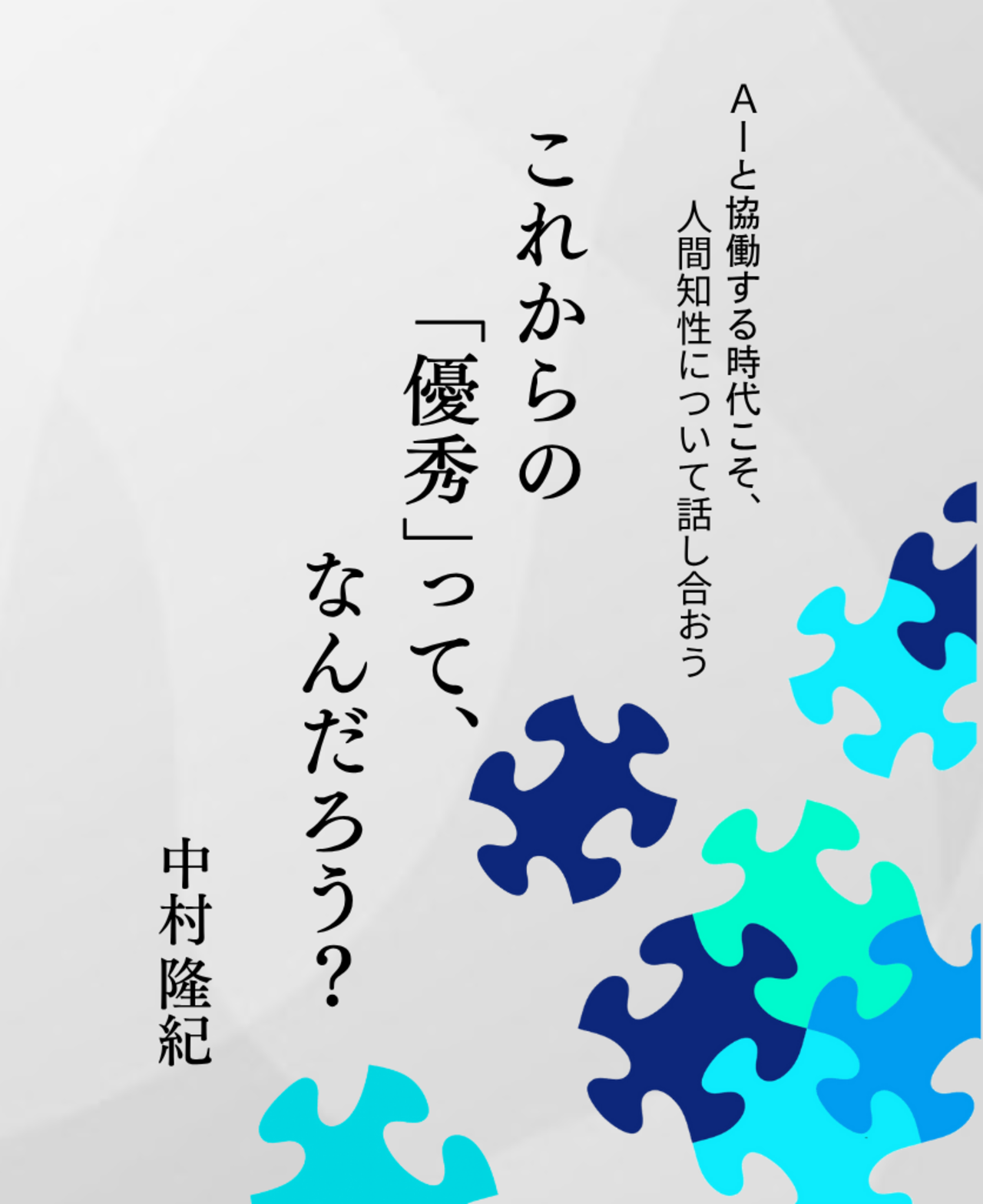【前回記事を読む】「AIに優れた対話力があるんだったら、階層意識も世代分断も、うまいこと、こなすだろ?」AIを挟んだ三者面談は……
第二章 すぐそばにある、知の分断
【クマくんの、もうちょい検索メモ】
[どちらか、なのか? ~二元論の限界~]
『中空構造日本の深層』河合隼雄著
『私たちはどこまで資本主義に従うのか』ヘンリー・ミンツバーグ著
『第三の支柱』ラグラム・ラジャン著
より引用と編集
*精神と物質、主観と客観、マクロとミクロ、我々と彼ら……。ものごとを「どちらか」で考えれば、そこに対立が生じる。二元論の限界は、常に議論されてきた。
*たとえば、資本主義が相当おかしくなってきて、マルクスの指摘を改めて読むことも、すばらしい学びにちがいない。
ただ、資本主義がだめならマルクスしかないでしょうと、ステレオタイプに考えてしまうのも、対立思考が好きなひとたちによる「お約束の議論」のようにも思える。
*世の中は、「どちらか」の選択を延々と論じ合うか、ヘーゲル的に、二項対立を前提とした止揚(「A」vs「B」の矛盾が→「C」を生む)を期待するしかないのか?
■臨床心理学者の河合隼雄さんは、日本人の心の深層を考える際、『古事記』に着目した。
『古事記』の中で、神さまは三子セットで生まれる。
・タカミムスヒ/アメノミナカヌシ/カミムスヒ
・アマテラス/ツクヨミ/スサノヲ
・ホデリ/ホスセリ/ホヲリ
しかし、そのなかで必ずひとり、『古事記』にほとんど活動が記されない「無為の存在」があるという(アメノミナカヌシ、ツクヨミ、ホスセリ)。河合さんはそれを「中空構造」と呼ぶ。
たとえば、アマテラスとスサノヲは時に対立するものの、どちらかが決定的な中心や勝者になることもなく共存している。
日本の神話構造には、3人目の神がふわりといることによって、深刻な決裂を生まない、また一時の敗者に対する愛惜(判官びいき)の醸成といった均衡をはかっているのではないか、という考察だ。