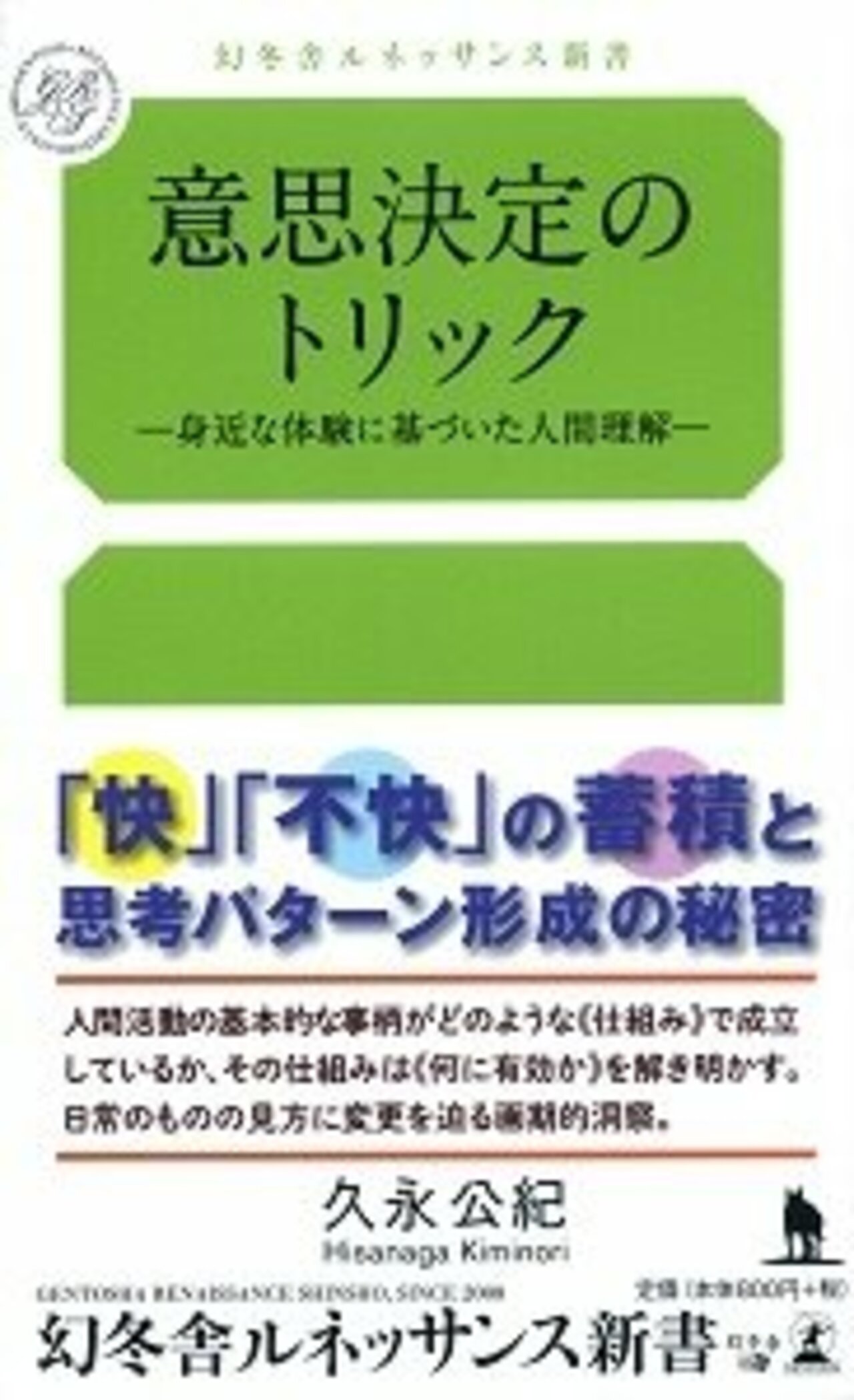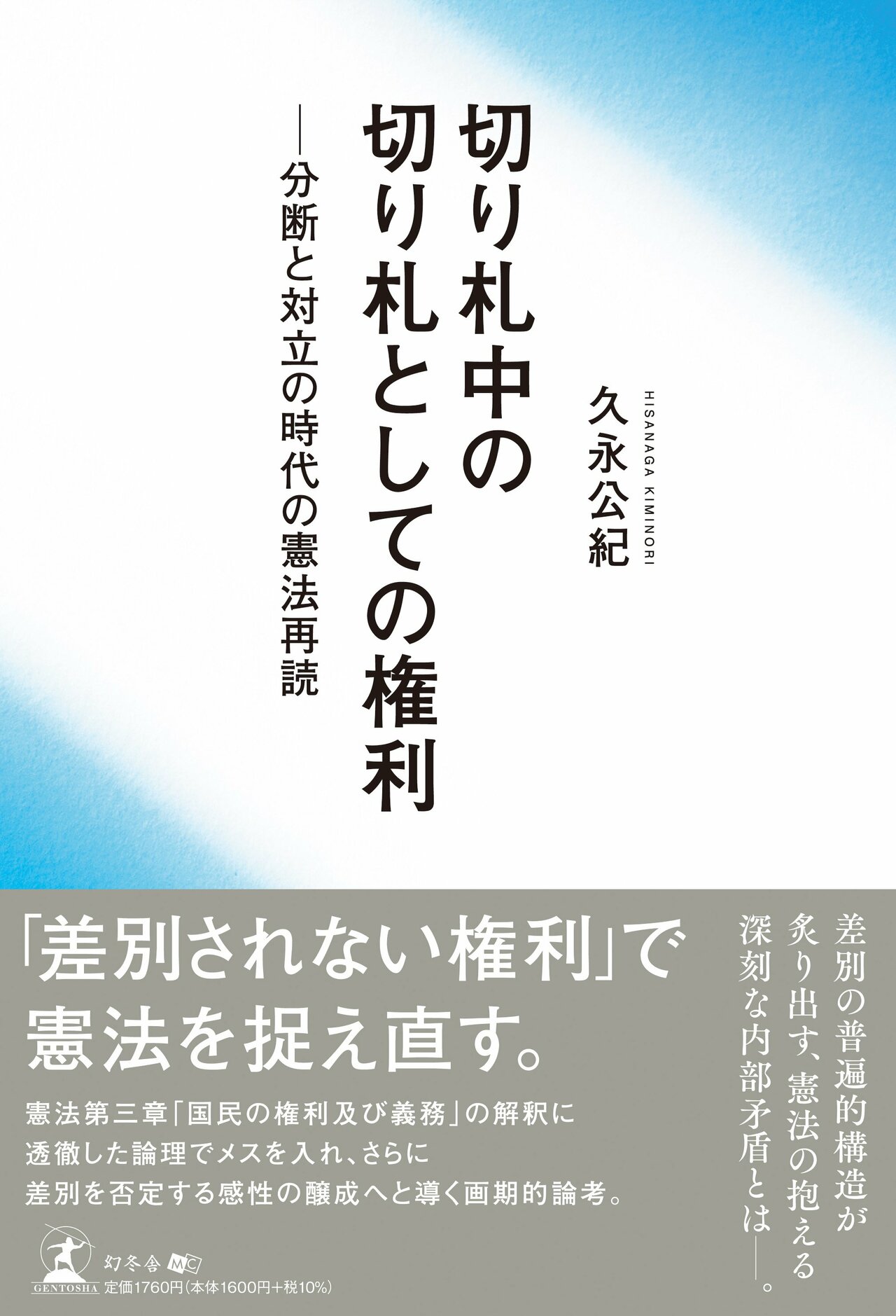第1章と第2章で参照するのは次の五つの文献(以下「参照文献」)。なお、引用にあたっては、本書の流れに合うよう、原文の主旨に影響のない範囲で筆者が適宜改変している場合があることを断っておく。違和感のある読者は是非参照文献にあたっていただきたい。
芦部信喜(高橋和之補訂)『憲法[第八版]』岩波書店2023年 以下「芦部・憲法」
樋口陽一『憲法 第四版』勁草書房2021年 以下「樋口・憲法」
長谷部恭男『憲法「第8版」』 新世社2022年 以下「長谷部・憲法」
木村草太『憲法』東京大学出版会2024年 以下「木村・憲法」
青井未帆・山本龍彦『憲法Ⅰ人権』[第2版]有斐閣2024年 以下「青井・山本・憲法」
第3章では、差別・虐待を否定する感性の確立・涵養を試みる。そのやり方には、感性の変化に必要な時間の長短の観点で次の二つがある。一つは、知識の獲得により一気に感性を変化させる方法。もう一つは、感性そのものを経験により徐々に変化させる方法。
前者の例として、人間には自由意思があり、行動の選択には責任を伴うという、日常的なものの見方(実は誤解)の背景にある仕組みを認識することで、世界への構えが変容し、責任を問い罰することの自明性が消失することを述べる。後者の例として、感情移入能力という、ベースは生得的だが、その後の経験次第で強化されうる能力があることを確認する。
序章 差別の定義
憲法第十四条一項は「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」と規定しているが、この〈差別〉という言葉が何を意味するかは自明ではない。
例えば、樋口・憲法(211頁)に「事実上の差異をも考慮に入れて異なった取扱いをすることが、一四条で禁止された差別となるか、合理的な不均等取扱いと見てよいかが、具体的に争われることとなる。」という記述がある。ここでは、対象とする状況が差別か差別でないかは、本質的に分けられるものではなく、あくまで程度問題、という認識があると思われる。
また、木村・憲法(192~194頁)は「差別とは、人間の類型に向けられた蔑視感情や嫌悪・侮蔑などの否定的評価、ないしそれに基づく行為」と定義した上で、差別的行為には、差別的意図に基づくものとそうでないものがあり次のように分類できるとする。
【イチオシ記事】一通のショートメール…45年前の初恋の人からだった。彼は私にとって初めての「男」で、そして、37年前に私を捨てた人だ
【注目記事】あの臭いは人間の腐った臭いで、自分は何日も死体の隣に寝ていた。隣家の換気口から異臭がし、管理会社に連絡すると...