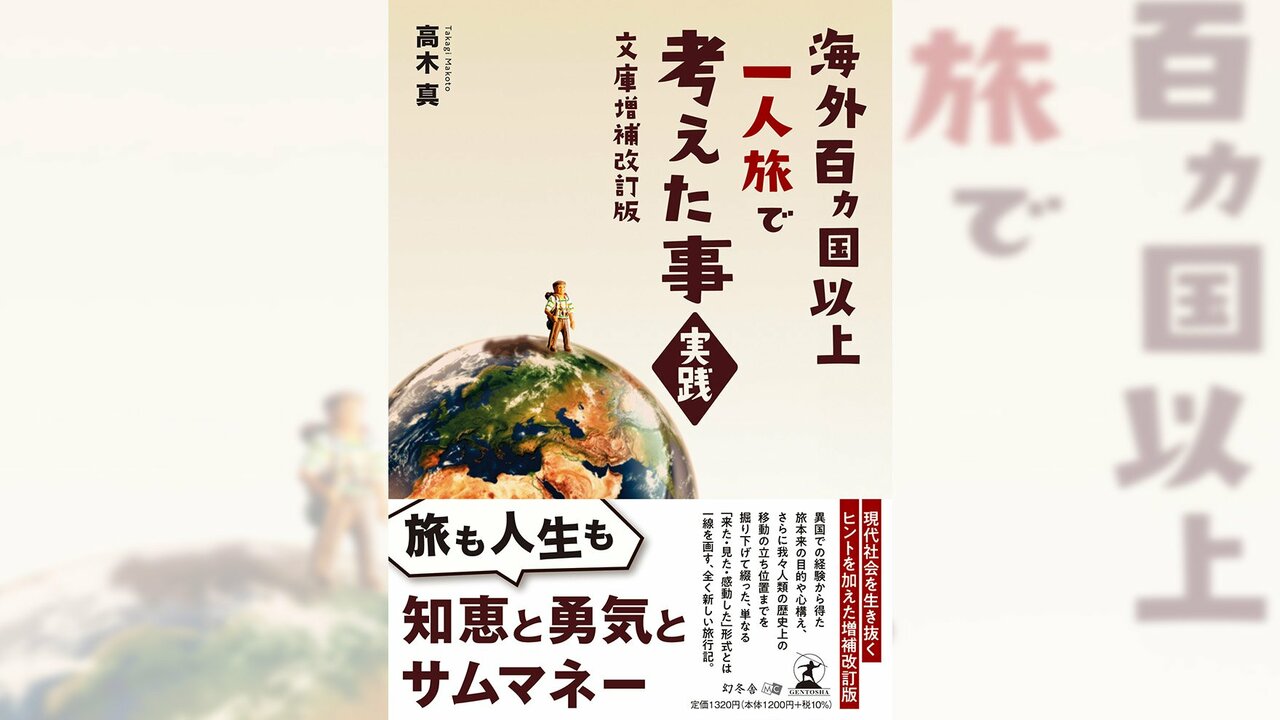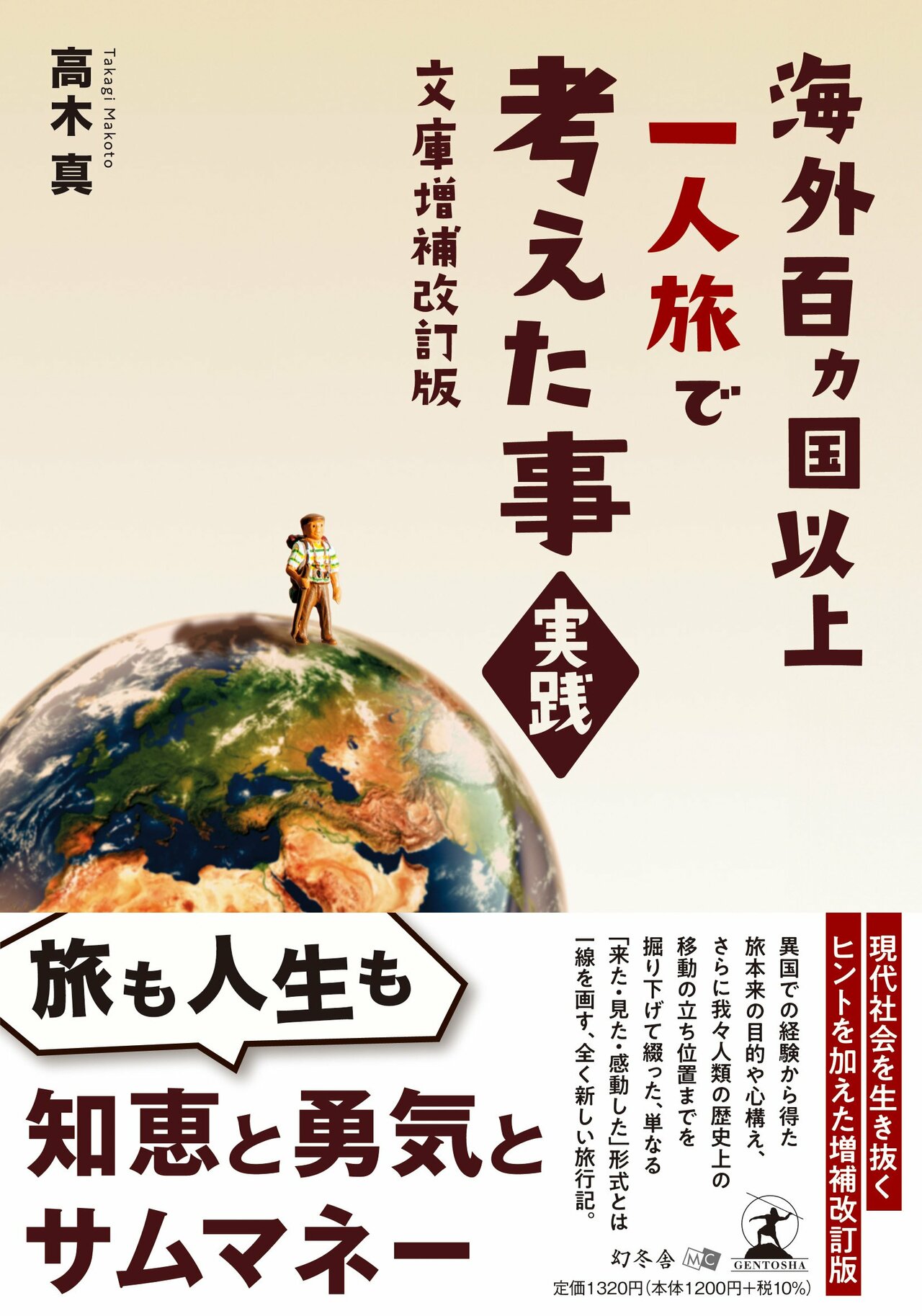【前回記事を読む】海外旅行を禁止された江戸時代の農民。農地に縛られた人々にとっての娯楽とは、現代人にも馴染み深い○○だった。
私の国内外の旅と旅とは何かについて
旅移動に関する我々の現在の立ち位置
戦国時代後期から江戸時代初期、石見銀山から多くの銀が海外輸出されたが、それにかかわった日本人も海外に渡ったと思われる。
また1543年または1542年、ポルトガル人が種子島にもたらした火縄銃も、刀鍛冶が鉄砲鍛冶となり、銃自体は作れても、火薬・銃弾には、硝石・鉛が必要で、当時国内で産出出来ず輸入に頼るしかなく、単に堺等の港で南蛮船を待ち受けていただけではなく、倭寇もいたのだから、積極的に中国大陸・朝鮮半島・東南アジア等に行って輸入貿易をしていた日本人も多くいたと思う。
ヨーロッパ北西のプロテスタントと東のイスラム教徒に対抗・ローマカトリックの危機を打開するため、東方にカトリックの信仰を広めようとインドのゴアにきたイエズス会(スペイン・バスクの貴族ザビエルは、パリ大学でイグナティウス・ロヨラらと出会い、イエズス会を結成した)のザビエルが、マレー半島南西部の交易都市マラッカでヤジロウという日本人の日本布教の要請で、1549年ヤジロウの案内で鹿児島に上陸したので、当時日本人はマレー半島のインド洋側南部の交易中継都市マラッカ辺りまで行っていた事になる(ザビエルは、最初から日本布教を目指していたわけではなかったようである)。
余談だが、マラッカは、インド洋と南シナ海東シナ海とを結ぶ重要交易都市であったというと、紙だけの資料で現地を見ていない人は誤解すると思うが、そんなに大きな街ではないのである。