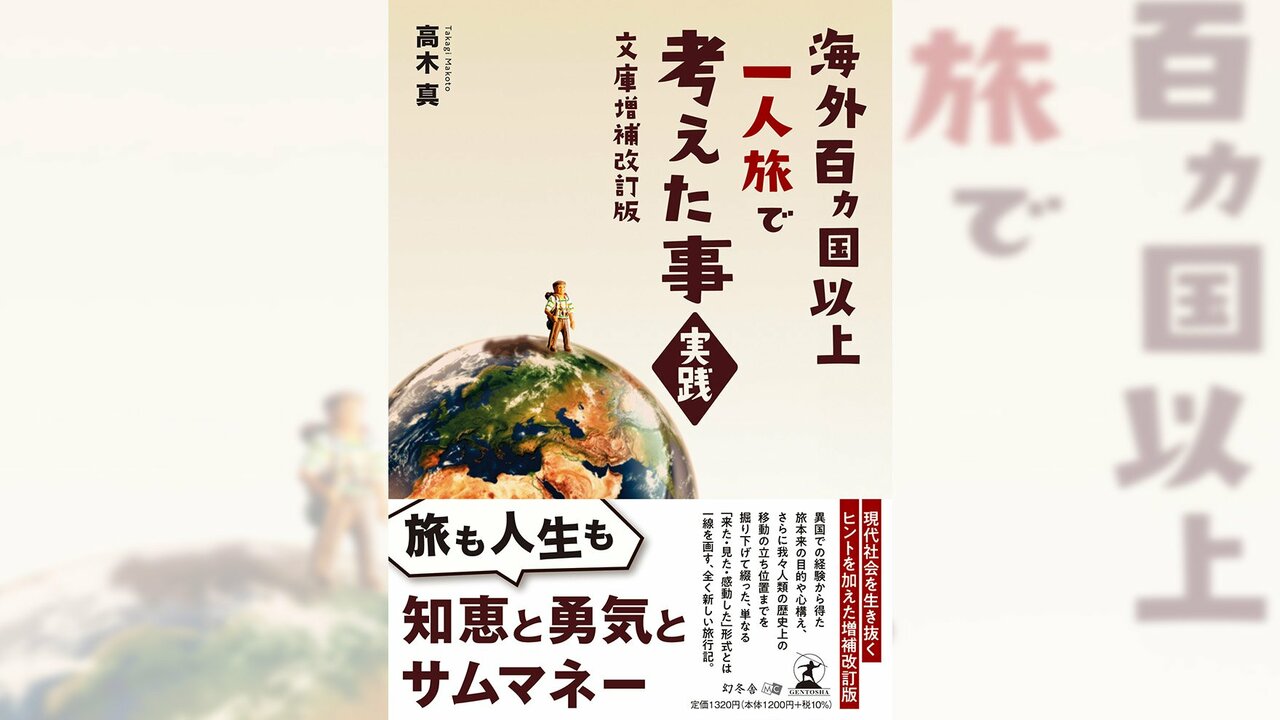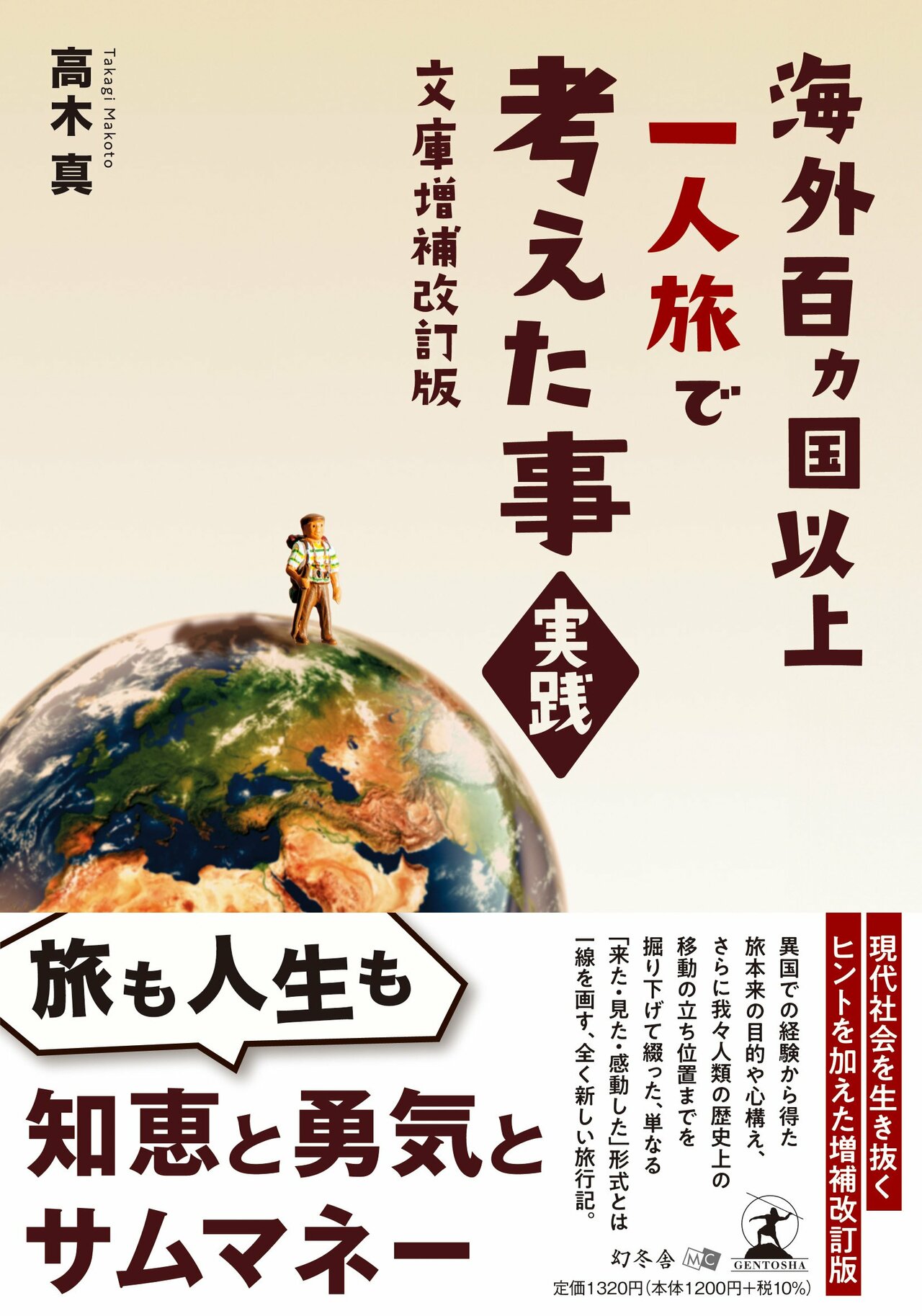【前回記事を読む】明治政府の知られざる海外移民政策──西洋化と矛盾する人口対策としての移民の実態とは?
私の国内外の旅と旅とは何かについて
新領土拡張による移住・旅行
1914年には、第一次世界大戦がヨーロッパで始まった。バルカン半島を巡って、ドイツ・ゲルマンとロシア・スラブの対立・植民地獲得・領土拡大・支配権確立の対立、これに民族主義が絡んでの、サラエボ事件(オーストリア・ハンガリー帝国の皇太子夫妻が、サラエボのラテン橋でボスニア系セルビア人の民族主義者の青年に暗殺された事件。
サラエボのラテン橋の近くに博物館があり、当時の状況を知る事が出来る)に端を発する、これがトリガー(引き金)となった戦争であった。西欧の主な大国は、2派に分かれ同盟を結んでおり、これにより紛争に直接関係のない国々もこの戦争に巻き込まれた。
バルカン半島からは地球の裏側の日本も、日英同盟により、連合国側で参戦し、ドイツの中国租借地山東半島・青島の攻撃占領(日本各地にドイツ軍捕虜収容所がつくられ、日本文化に影響を与えた)、南洋諸島のドイツ植民地(マーシャル・カロリン・マリアナ(グアムを除く。グアムは米西戦争でフィリピンと共にアメリカ支配となっていた)・パラオ・ビスマルク(ドイツ領パプアニューギニアの諸島)等の島々の占領、インド洋・地中海(マルタの戦争博物館には日本の駆逐艦の来航写真がある)での駆逐艦隊によるドイツ・オーストリアのUボートからの艦船保護警護等をした。
ベルサイユ条約(1919年)によりドイツが海外植民地を放棄したため、日本が占領した上記南洋諸島(島嶼部・トウショブ)は、国際連盟により、日本の委任統治領となった。
ただし、アメリカの支配地域と接するためアメリカ側の要望・要請により、委任統治に際し軍事基地化は認められなかったが、日本の国際連盟脱退後、これら南洋諸島をその後も占領し続け、軍事基地を設けている。
これが太平洋戦争で、日本占領の太平洋島嶼(トウショ)部での、島々の攻防戦(米軍・連合軍のアイランド・ホッピング作戦)となった。
ちなみに、10年ごとの戦争というと、明治期10年戦争といわれる別の戦争があった。これは日本の内戦であるが、西南の役・西南戦争と呼ばれる西郷隆盛率いる薩摩青年士族の反乱・内乱である。これが、明治10年に起こったため、10年戦争と呼ばれる。
そしてこれらとは別に、1910年に日韓併合があった。