【前回記事を読む】【海外旅行を加速させた円高】1980年頃、急に日本人観光客がニューヨークにどっと押し寄せ、アメリカ人は驚いた東欧バルカン半島のパルチザンの指導者だったチトー大統領が束ねていたユーゴスラビア(南スラブ人の土地の意味)が崩壊して、「マケドニア」という国が出来た。この国名にギリシャが反発した。アレキサンダーのマケドニアの本質はギリシャにあり、スラブ系の「マケドニア」はその一部でしかな…
[連載]海外百ヵ国以上一人旅で考えた事・実践 文庫増補改訂版
-
実用『海外百ヵ国以上一人旅で考えた事・実践 文庫増補改訂版』【第11回】高木 真

人に何かをさせる時、日本人には「皆がそうしているから」、ドイツ人には「規則だから」。イタリア人には「向こうにいい女が…」
-
実用『海外百ヵ国以上一人旅で考えた事・実践 文庫増補改訂版』【第10回】高木 真

【海外旅行を加速させた円高】1980年頃、急に日本人観光客がニューヨークにどっと押し寄せ、アメリカ人は驚いた
-
実用『海外百ヵ国以上一人旅で考えた事・実践 文庫増補改訂版』【第9回】高木 真

「梅栗植えてハワイに行こう」と掲げられた町のスローガン。当時の日本人にとってハワイとは、まるで別世界の、憧れの旅行地だった?
-
実用『海外百ヵ国以上一人旅で考えた事・実践 文庫増補改訂版』【第8回】高木 真

第一次世界大戦が始まった。バルカン半島を巡って様々な対立、そしてサラエボ事件を引き金に、無関係の国が次々と巻き込まれ…
-
実用『海外百ヵ国以上一人旅で考えた事・実践 文庫増補改訂版』【第7回】高木 真

明治政府の知られざる海外移民政策──西洋化と矛盾する人口対策としての移民の実態とは?
-
実用『海外百ヵ国以上一人旅で考えた事・実践 文庫増補改訂版』【第6回】高木 真

マラッカ・ホイアン・アユタヤ──世界遺産に残る日本人町の記憶と、鎖国以前に海外で活躍した戦国商人たちの真実
-
実用『海外百ヵ国以上一人旅で考えた事・実践 文庫増補改訂版』【第5回】高木 真

海外旅行を禁止された江戸時代の農民。農地に縛られた人々にとっての娯楽とは、現代人にも馴染み深い○○だった。
-
実用『海外百ヵ国以上一人旅で考えた事・実践 文庫増補改訂版』【第4回】高木 真

江戸時代、旅行は原則禁止。なのに大きな「参りブーム(=神社・仏閣参りを口実にした、物見遊山の観光旅行)」は何回かあった
-
実用『海外百ヵ国以上一人旅で考えた事・実践 文庫増補改訂版』【第3回】高木 真

自由に旅することはできなかった江戸時代。そんな状況で、松尾芭蕉が当時国々を自由に旅出来ていたというのが不思議である
-
実用『海外百ヵ国以上一人旅で考えた事・実践 文庫増補改訂版』【第2回】高木 真
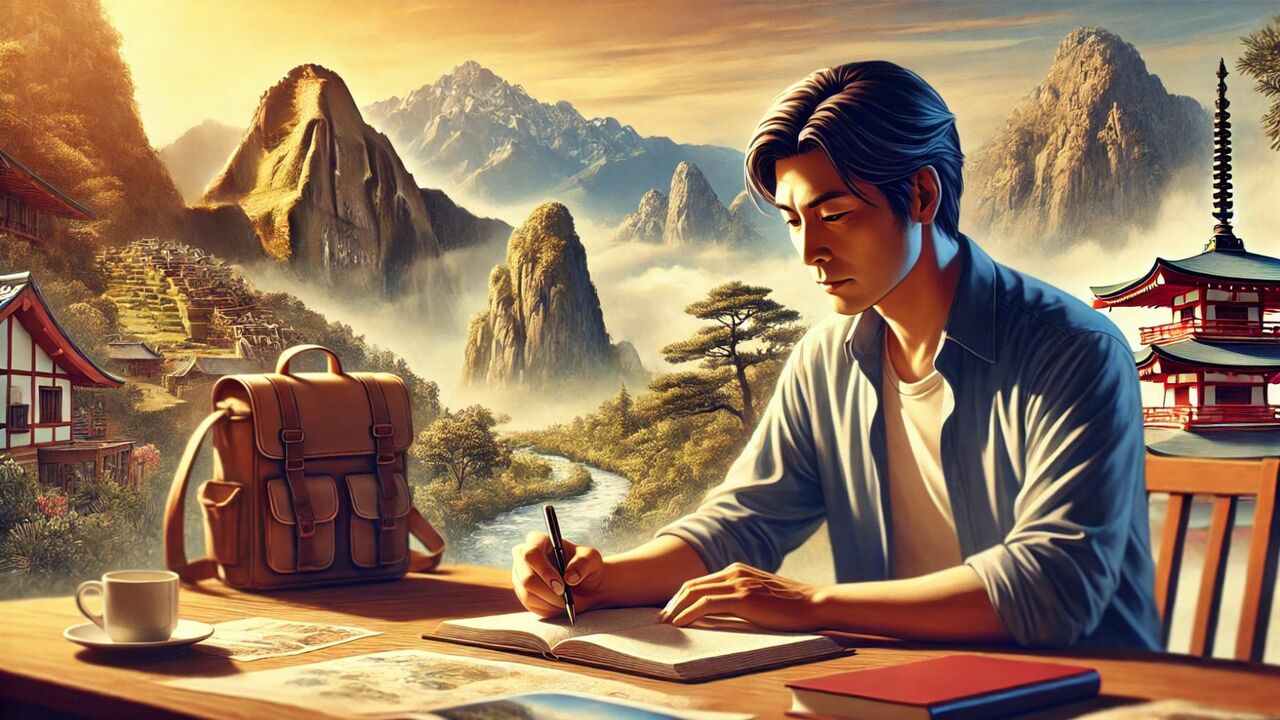
100カ国以上、旅をしてきた。それは、単なる入国スタンプラリーではない。娯楽のための旅行記ではなく、「旅」そのものを考える。
-
実用『海外百ヵ国以上一人旅で考えた事・実践 文庫増補改訂版』【新連載】高木 真

全く知らない異空間で未知の問題に遭遇し、たった一人でいかに取り組んでいくか解決していくかに意義を見出すようになった旅







