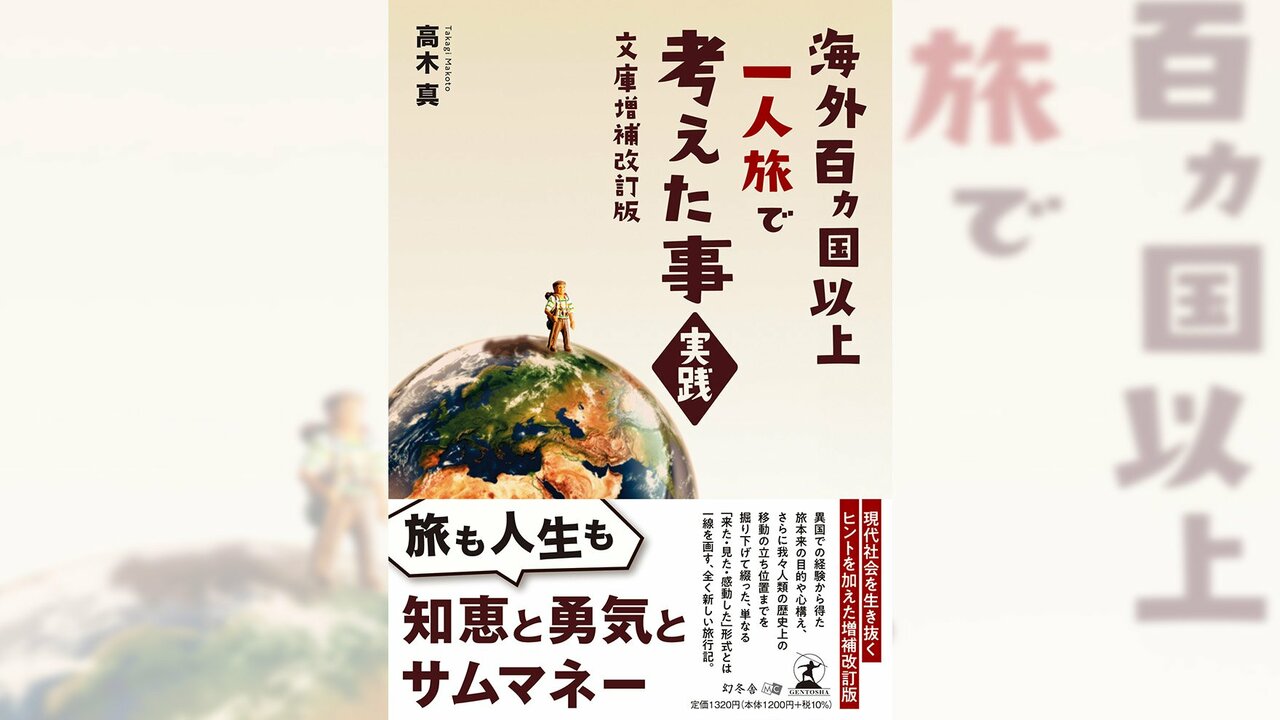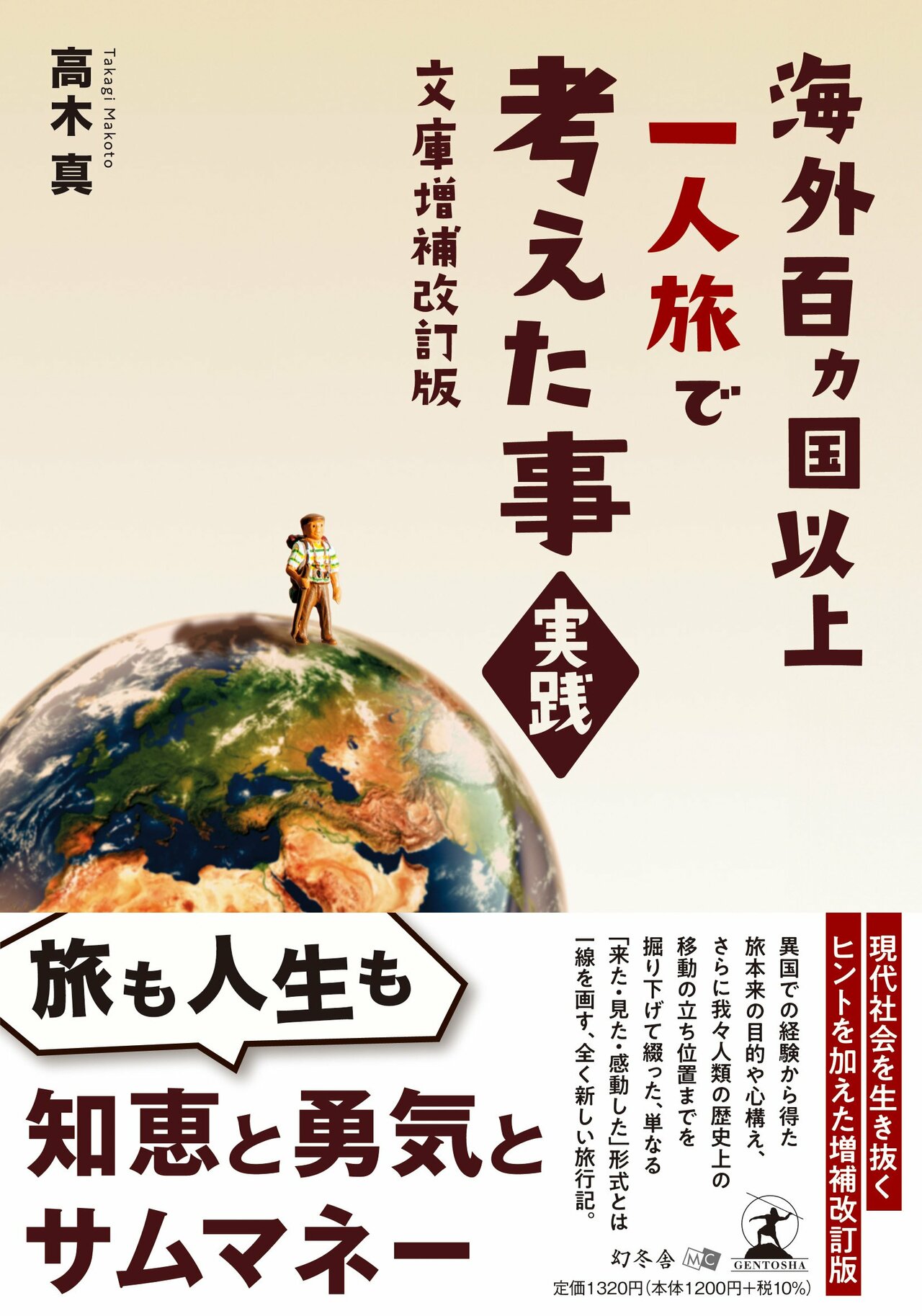私の国内外の旅と旅とは何かについて
旅移動に関する我々の現在の立ち位置
水戸光圀が、中国の司馬遷の「史記」を読んで感銘を受け、日本でも「日本史」を編纂しようと、資料収集のため、実際に家臣を諸国に派遣した(これで、「日本史」・水戸学が水戸藩で生まれた)。
それに尾ひれを付け・盛られて、「水戸黄門(中納言)諸国漫遊記」なる講談・映画・テレビの時代劇・旅の話が生まれた(徳川御三家の水戸光圀は、朝廷から中納言の官位をもらっており、黄門は中納言の唐名で、黄門・中納言はダブりである)との話を聞いた事がある(日常生活と違った、旅の話・異空間・異なる世界の話は、楽しく・好奇心を満たし、いつの時代も人気がある。特に庶民が自由に旅行出来なかった時代には、旅の話は楽しみとなっていた)。
しかし、原則禁止、例外的に認められても、幕府防衛のため原則徒歩・駕籠・小舟でしか旅が出来ないにもかかわらず、江戸時代には何回か大きな「参りブーム」があったようで(実際は神社・仏閣参りを口実にした、物見遊山の観光旅行)、こうなると原則禁止の意味が失われ、何が原則で何が例外か分からなくなるくらいである。
江戸時代、国内旅行も自由にならなかったのに、ましてや海外渡航・旅行は、幕府体制支配に不都合な宗教・思想に感染するのを恐れて(江戸時代交易のためのオランダ人が長崎出島に閉じ込められたのは、一般人への宗教・思想感染を恐れた以外、天然痘・ペスト・コレラ・麻疹・梅毒等の疫病感染を防ぐ防疫の意味もあったかもしれない。出島では、遊女以外の一般人の出入りは禁止されていた)、体制を揺るがすのを恐れて、鎖国で入国・出国が禁止されていた。
特にキリスト教、中でもカトリックが警戒された。江戸時代のキリスト教は、日本史上一般にはカトリックとプロテスタントはあまり意識して区別されていない。
日本のいわゆる熊本・長崎辺りの「隠れキリシタン」は、ザビエル布教由来の、カトリック・イエズス会の信者であった。これは、ザビエルが、日本での布教の許可を幕府・天皇にもらいに鹿児島から九州西海岸沿いの山口を通って京都まで行ったが、その途中の布教により信者となり、幕府禁教後も隠れて信仰したカトリック・イエズス会の信者であった。