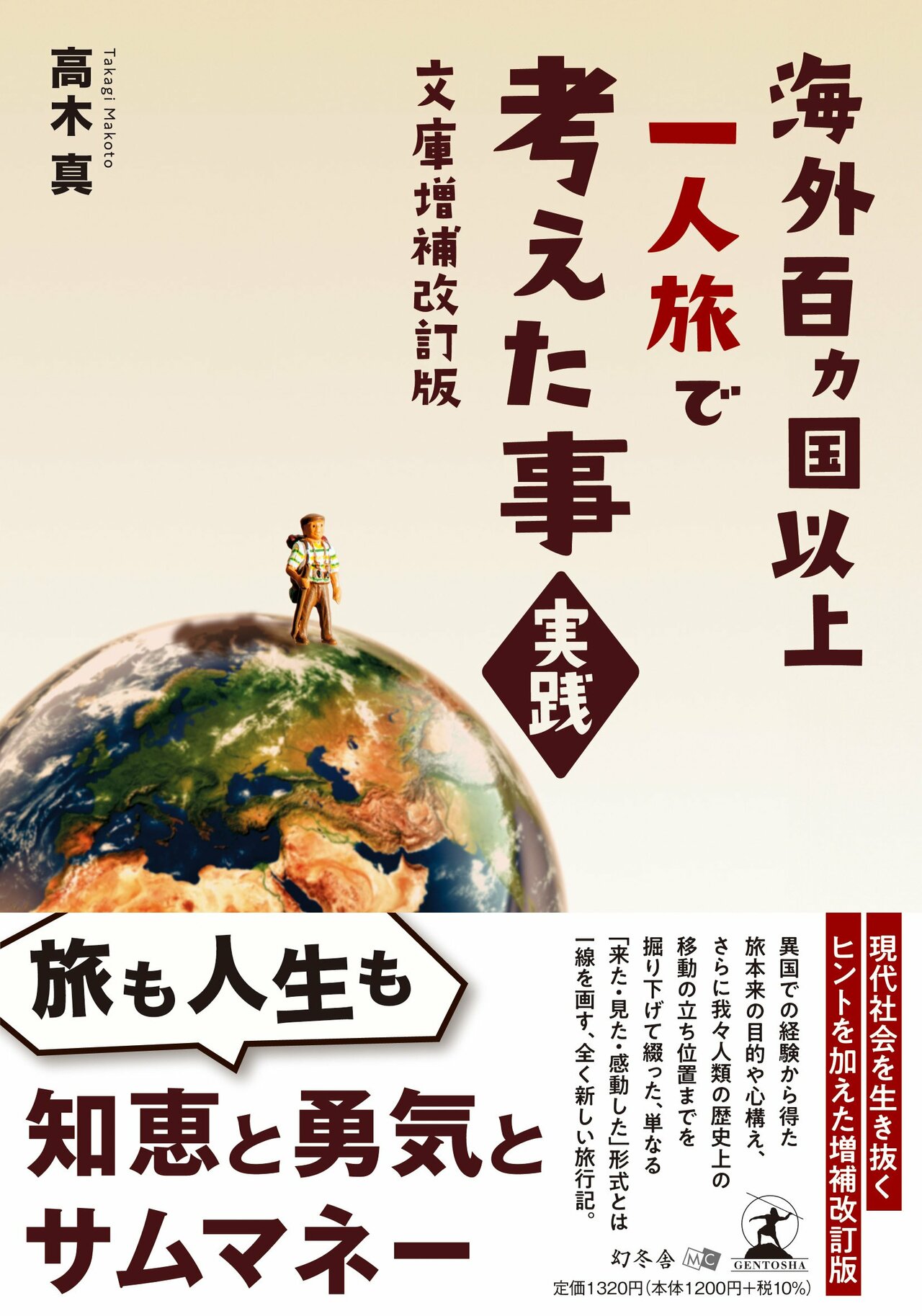ザビエルはその後京都から引き返したが、山口(滞在していた大内氏はその後滅亡した)を経て一時ザビエルが逗留した大友宗麟の豊後の府内は、一時期カトリックの日本布教の中心地となった。この事は、フロイスの書簡(日本史)で分かる。その後豊後は、キリスト教禁止で「豊後崩れ」(1660〜1682年)となり、豊後のカトリック信者は仏教に改宗させられた。
徳川家康は、1600年豊後・臼杵・佐志生・黒島に漂着したオランダ船リーフデ号(この船には、オランダプロテスタントの象徴エラスムス像が飾られていた。実物を国立博物館で見た事がある)に乗っていた、ヤン・ヨーステンとウイリアム・アダムスを、カトリックのバテレン宣教師よりも、領土的野心なしとして厚遇し、幕府の顧問に迎えた(ウイリアム・アダムスは、イギリス人であったが、相模・神奈川・三浦に領地を持つ水先案内の意味の、三浦按針と呼ばれ、西洋人の武士となった)。
徳川幕府は領土的野心がないとして、プロテスタントのオランダとの交易を認めた。イギリスも、ウイリアム・アダムスのよしみであろう交易を認められていた(家康から朱印状をもらっていた)が、イギリスは東アジアの交易覇権でオランダに敗れ(アンボン事件)、東アジアから撤退した。この時イギリスは、日本の平戸島からも同年に同時に撤退した。
50年後、再びイギリスは、幕府に朱印状はいまだ有効だとして、交易再開を要求したが、オランダからの情報であろう、イギリスのカトリック傾向が強まったとして、幕府は交易を断っている(リターン号事件)。
結果的に、幕府は幕末まで、西洋とはオランダとのみ交易をした事になった。プロテスタントのオランダは、島原の乱の時、海上船から反乱軍・カトリック信者を砲撃し、幕府の信任を深めていた。
イギリスとは、前述のように、最初は交易していたが、イギリスのクロムウェルの共和制後の王政復古時カトリック傾向が強まったとして、幕府は中断後の再開を断っている。その後イギリスでは、国王のカトリック傾向に反発が強まり名誉革命が起こりイギリス国教会のプロテスタント化が決定したが、日本との交易の面では既に遅かった事になる。
以上見たように、日本史上でも、カトリックかプロテスタントかを分けて考える意味はあると思う。
【前回記事を読む】自由に旅することはできなかった江戸時代。そんな状況で、松尾芭蕉が当時国々を自由に旅出来ていたというのが不思議である
【イチオシ記事】あの人は私を磔にして喜んでいた。私もそれをされて喜んでいた。初めて体を滅茶苦茶にされたときのように、体の奥底がさっきよりも熱くなった。
【注目記事】急激に進行する病状。1時間前まで自力でベッドに移れていたのに、両腕はゴムのように手応えがなくなってしまった。