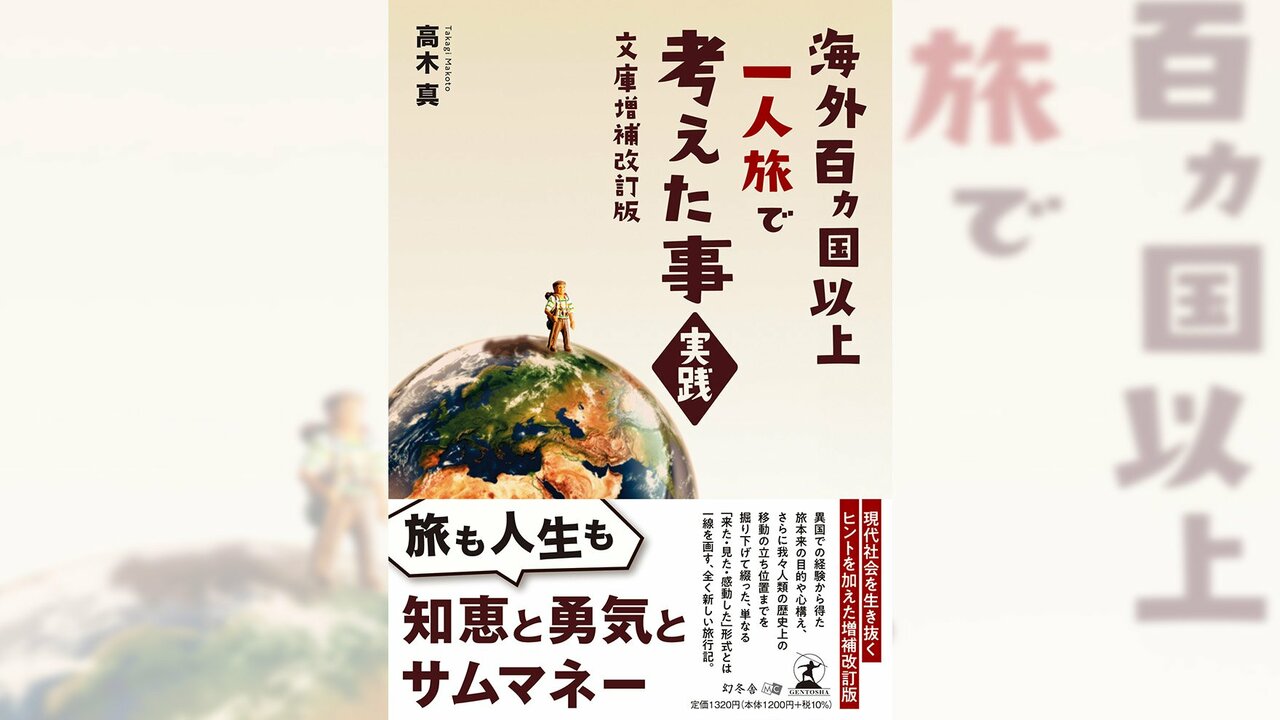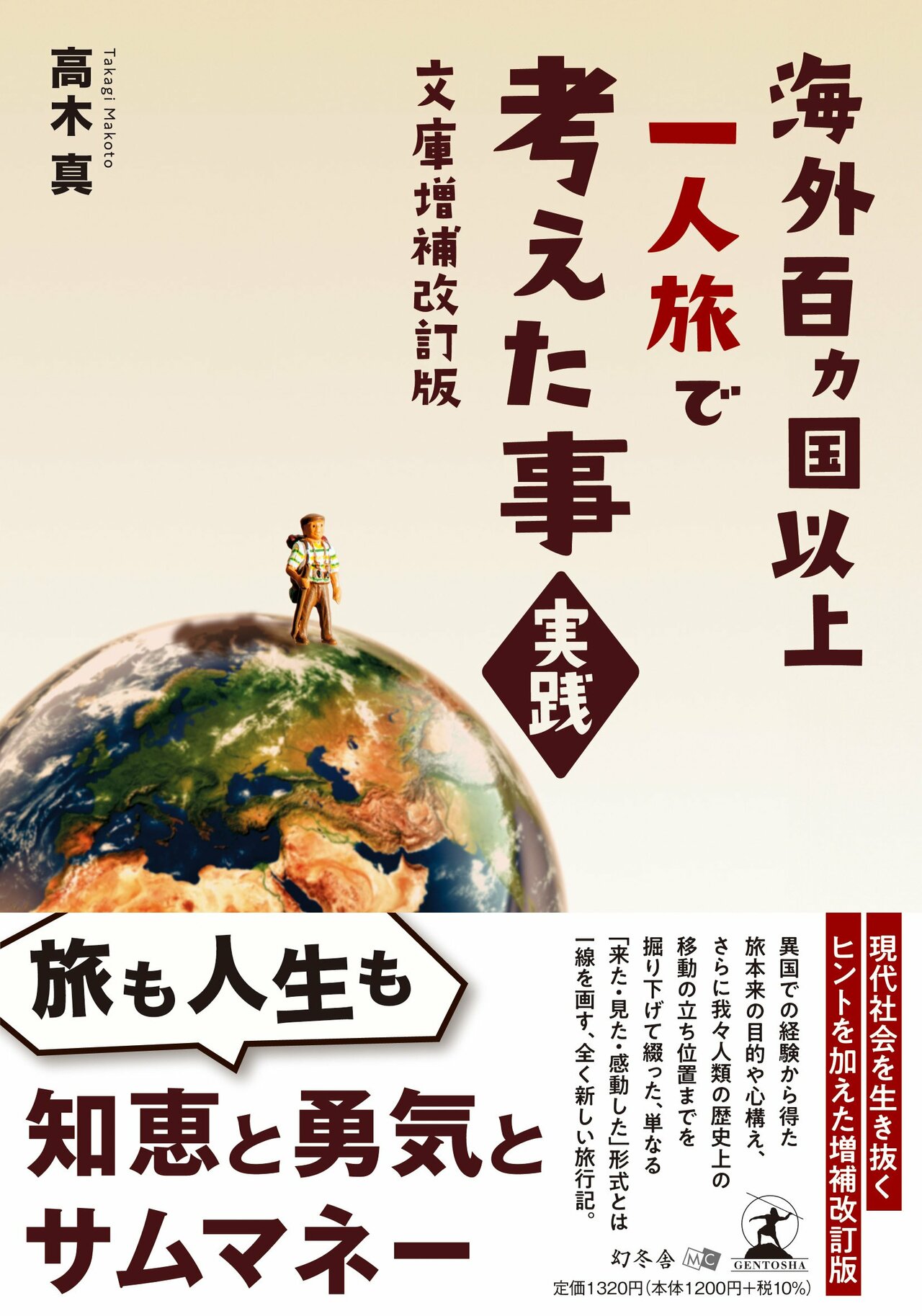【前回記事を読む】江戸時代、旅行は原則禁止。なのに大きな「参りブーム(=神社・仏閣参りを口実にした、物見遊山の観光旅行)」は何回かあった
私の国内外の旅と旅とは何かについて
旅移動に関する我々の現在の立ち位置
西洋のドイツ30年戦争(1618年〜1648年)では、プロテスタントかカトリックかは大問題となり単なる宗教論争ではなく、プロテスタントとカトリックに分かれて、大規模な戦争となった。
最初は、神聖ローマ帝国内のプロテスタント(主に北部ドイツ)とカトリックの戦争であったが、次第にヨーロッパ各国を巻き込む大戦争となった。
鎖国は、中国の明・清朝時代の倭寇を恐れての「海禁」の制度がヒントになったのであろう。
もし江戸時代に生まれていたら、個人で気安く海外旅行等出来なかった。旅が出来ない・禁じられた、農地に縛られた農民の非日常の娯楽・楽しみ・日頃の憂さ晴らし・士農工商の身分を忘れさす無礼講・ストレス解消の社会システム・日本的娯楽レジャーとして、多くは酒を伴った、盆・正月、地域・地方の春祭り・夏祭り・秋祭り等の各種祭り、農閑期に近くの温泉地・湯治場での温泉・湯治、歌舞伎・芝居等があった(当然、生きるのが精いっぱいで、生活に余裕のない人は、それどころではなかった、と思われるが)。
日本人の海外渡航
日本人は、国外に出る事を「海外に行く・海外渡航」と何の気なしにいうが、当然ながら、これは日本が島国で、外国に行くには、原則船で(現在は原則飛行機で)海を渡っていくしかなかった事による。
世界には、他の国を通らなければ海に出られない国(内陸国)もある。これらの国々では、人々は船を利用し他国へ移動する必要がある時は、一度陸の他国を通過しなければならない。今は人の移動は、遠くでは飛行機が主流なので、あまり問題はないが。
ただ、ヨーロッパの内陸国の小さな国では、鉄道も飛行場・空港もない所があり、車・バスで国外に出るしかない国もある(実際にバスで訪れた、ヨーロッパの小国ピレネー山脈の山間のスペイン・フランスに挟まれたアンドラ、イタリアに囲まれたアドリア海に近い山の上のサンマリノ等は、バスか車で国外に出るしかない)。