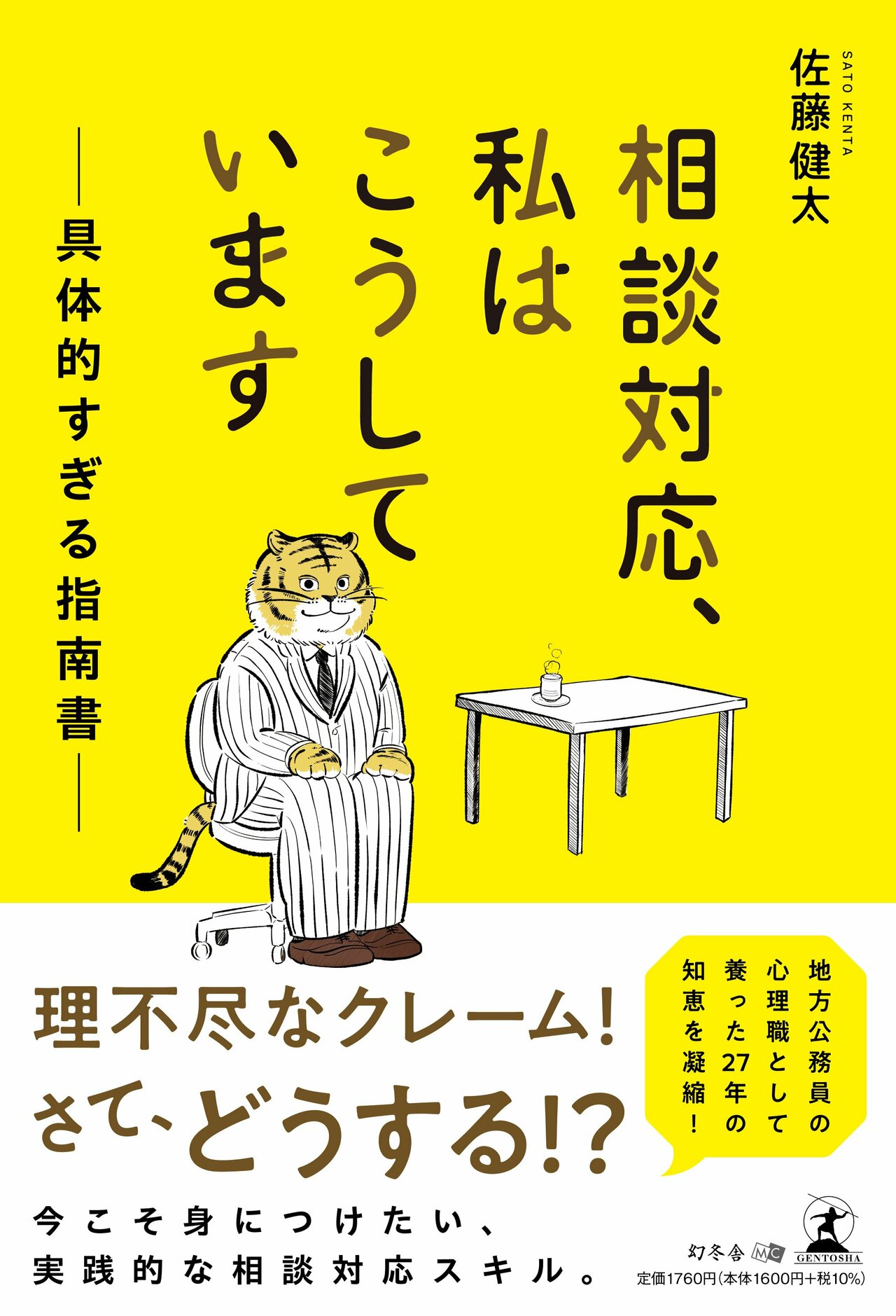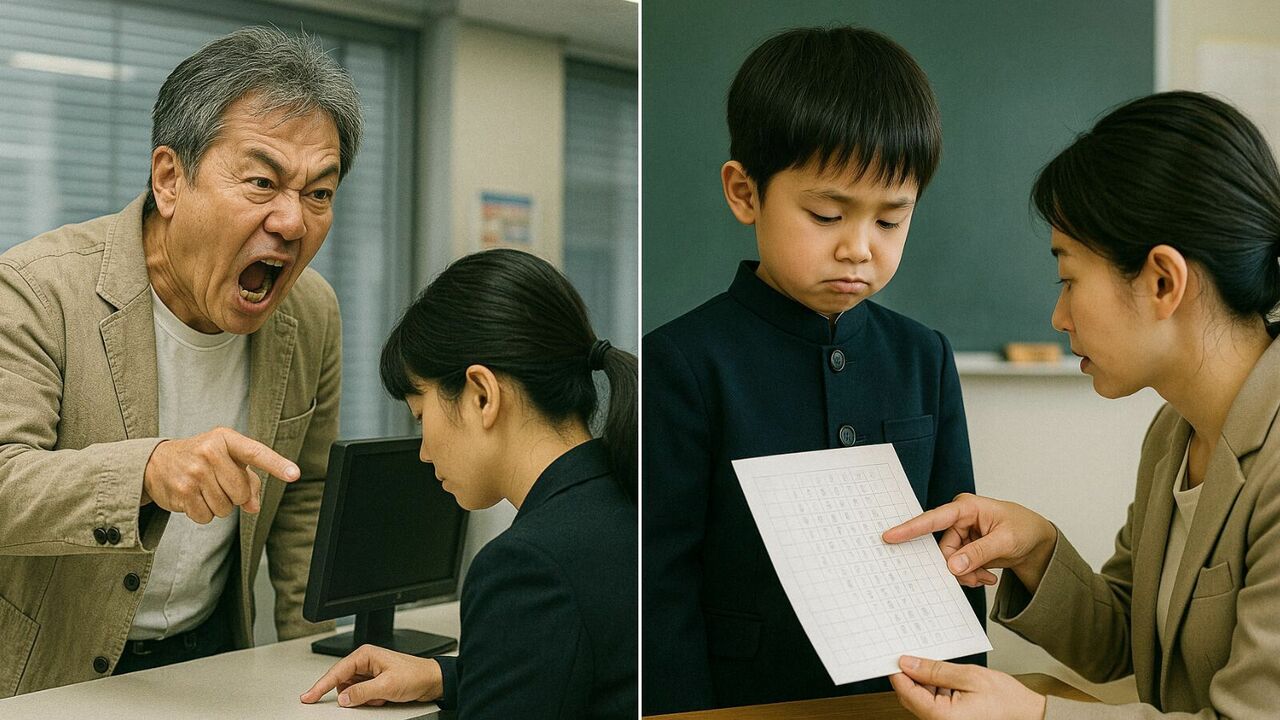事例4の対応方法 さて、どうする?
何度か面談を重ねていると相談者から、「実は話を聴いて一緒に考えてくれる人が身近にいる」という話がありました。
「最近は少しずつ気持ちが整理されて、受診に向き合う気持ちになっている」という話も聞けました。そのため、私はその気持ちに沿いながら、「受診をいつにするか」「誰と行くか」など、具体的な行動のイメージを持ってもらえるような話をして、面談を終えました。
・ゲートキーパーの視点で
事例3のように、「死ぬ」と言われても冷静に対応できないので、すぐに専門家に任せた方がよいと考える人もたくさんいることでしょう。しかし、すぐに専門家につながるとは限らないため、そこにつなげるための支援が必要になります。社会全体で支えていく包括的支援(第6章参照)という視点が必要で、特定の人の力のみで支えられることはなかなかありません。
「自分にとって身近な人がそのような状況に追い込まれる」といったことも全くの絵空事ではありません。そんな時には、自分も微力ながら支え手としてできることがある、という自分事としての視点を持ってもらいたいと願っています。
ゲートキーパー(コラム④参照)という言葉をご存じでしょうか。隙間をつなぐ支援がまさにそれにあたります。
事例4のまとめ
[結果]
・30代男性は、精神科を受診した。
・精神科受診までをつないでくれた人が身近にいたので、何度か話を聞いてもらい一緒に考えてもらう、ということを繰り返した。
[ポイント]
・ 「AだからBをすればいい」だけで本当に解決に向かえるのかを考える。
・必要に応じて、その隙間でできる支援を考える。
次回更新は5月2日(金)、8時の予定です。