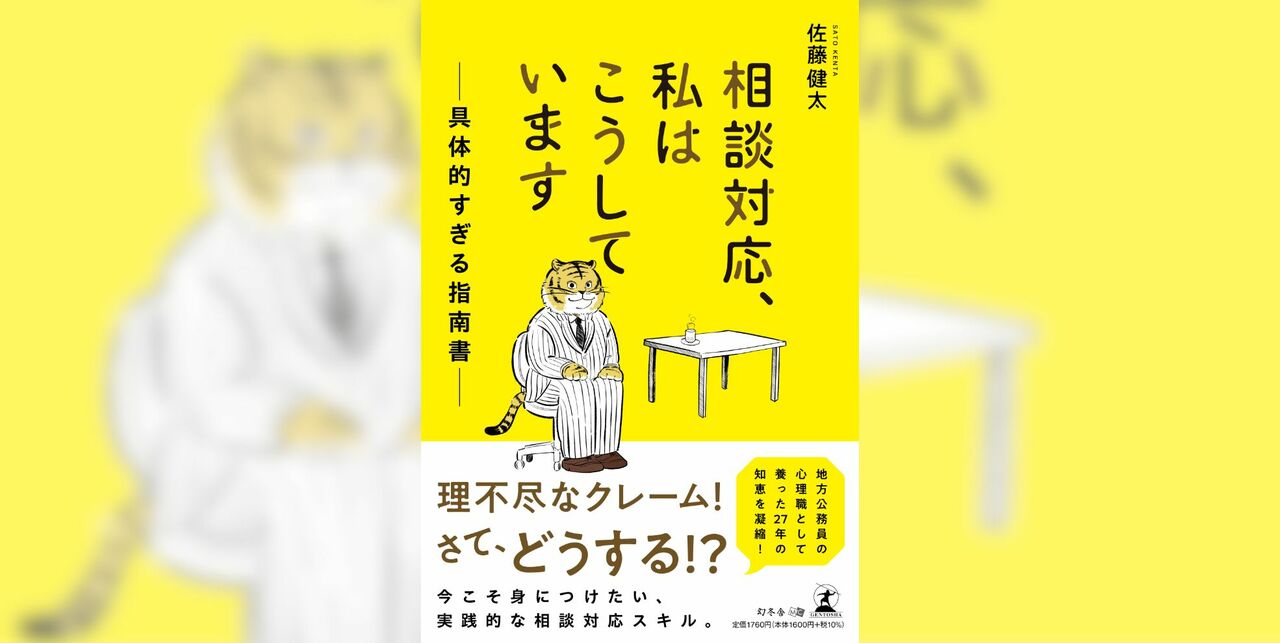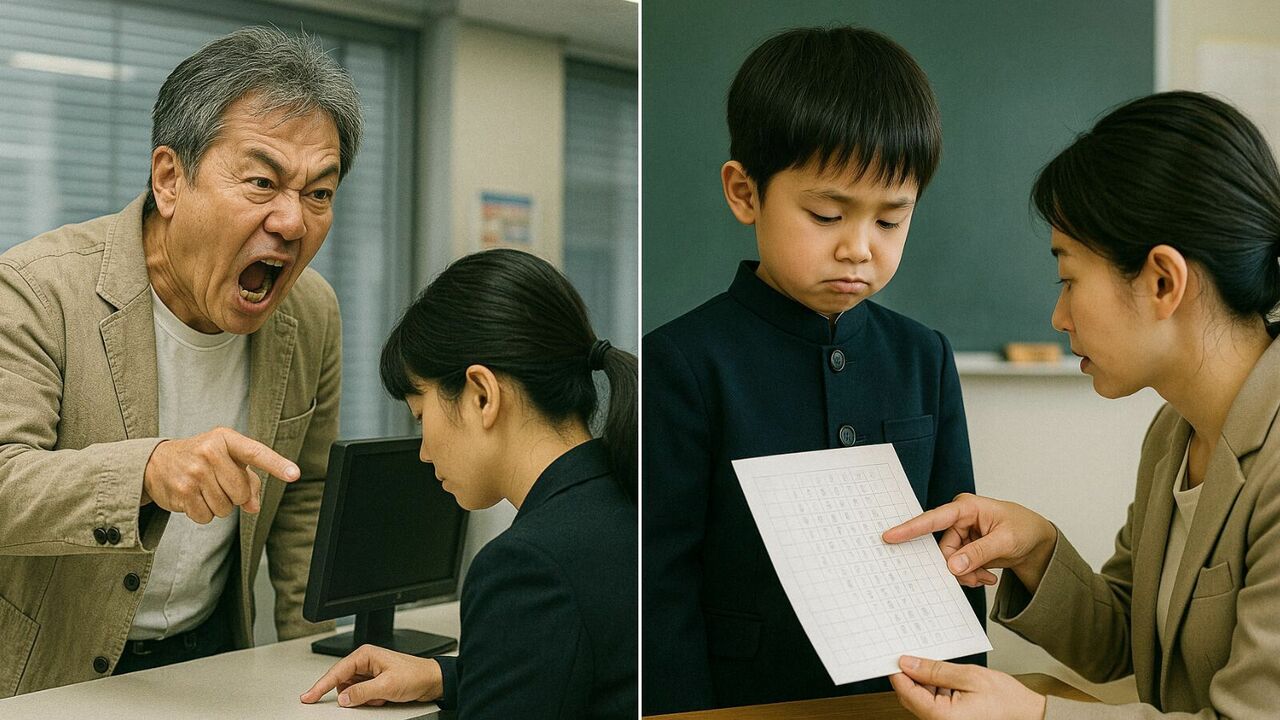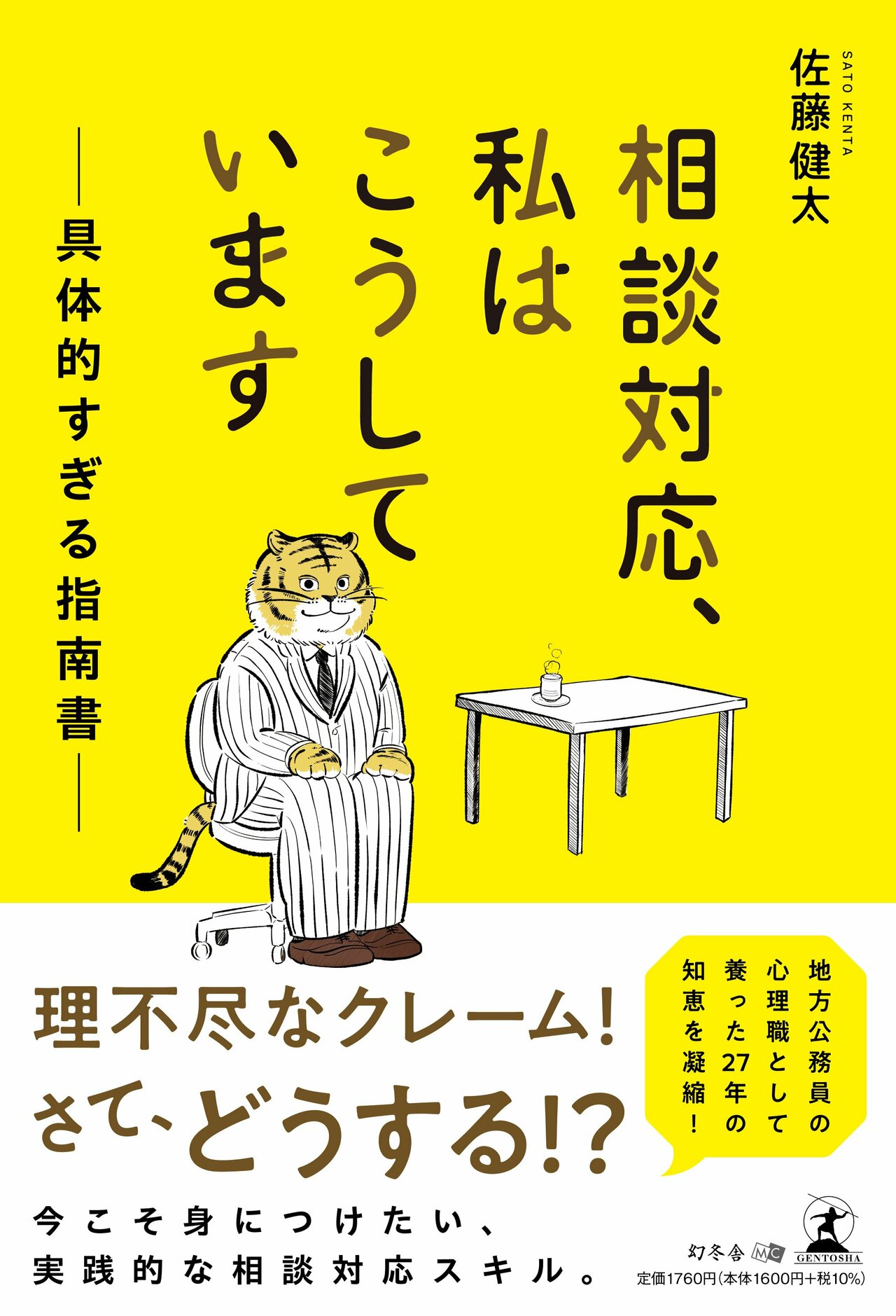【前回記事を読む】40代女性からの相談:不登校引きこもり息子のことを別機関に相談したら「本人を連れて来ないと相談にならない」と言われた。
事例と解決篇
第3章 価値観の押し売りはNG
【事例7】
事例7のまとめ
[結果]
・最初に相談してくれた家族の信頼を得て、定期的に面談することができた。
・ 一緒に話し合いながら解決を探る中で、本人も面談に来てくれるようになった。
[ポイント]
・まずは困っている人に寄り添う。
・そこから本人に結びつくように丁寧に話をつなげる。
コラム⑤
苦い思い出
「ぼくはおとうさんがくるまでまっていました」
これは私が小学1年生の時に書いた作文の一部です。漢字で書くと「僕はお父さんが来るまで待っていました」となります。しかし、小学1年生なので、漢字は使っていません。
この作文の概要はこうです。私の父が、仕事で出かけた際に私もその車に同乗し、父の仕事が終わるまで車内で待っていたという話です。
そういった文脈を考えると、既述の漢字に変換されるはずなのですが、先生はなぜか「お父さんが車で待っていました」と変換したようで、「なんでお父さんが車で待っているの」「あなたが仕事に行ったの」と言われ、反論するスキルのなかった小学1年生の私は、ただただモヤモヤした気持ちを抱え、いまだに忘れられない苦い思い出となってしまいました。
あまりに悔しかったので、時々思い出してはその作文を見つめる自分がいました。最後に見たのは小学校高学年頃と記憶していますが、やはりどう見ても、文章全体を見渡せばどんな話かわかりますし、「お父さんが車で待っていました」だとしても、その直前にある「ぼくは」とつながらないでしょう、と作文に怒りをぶつけていました。
なぜこんなエピソードを紹介したかというと、この怒りの気持ちを持った自分と、怒鳴っている相談者が重なったからです。
相談の多くは、相談者に何か要件や聴いてもらいたいことがあってのことですが、要件が伝わらなかったり、聴いてもらえずに他に回されたりすると、怒りの感情が湧いて当然です。また、対応者の価値観で話を捉えてしまうと、相談者には寄り添ってもらえなかった感が募ります。