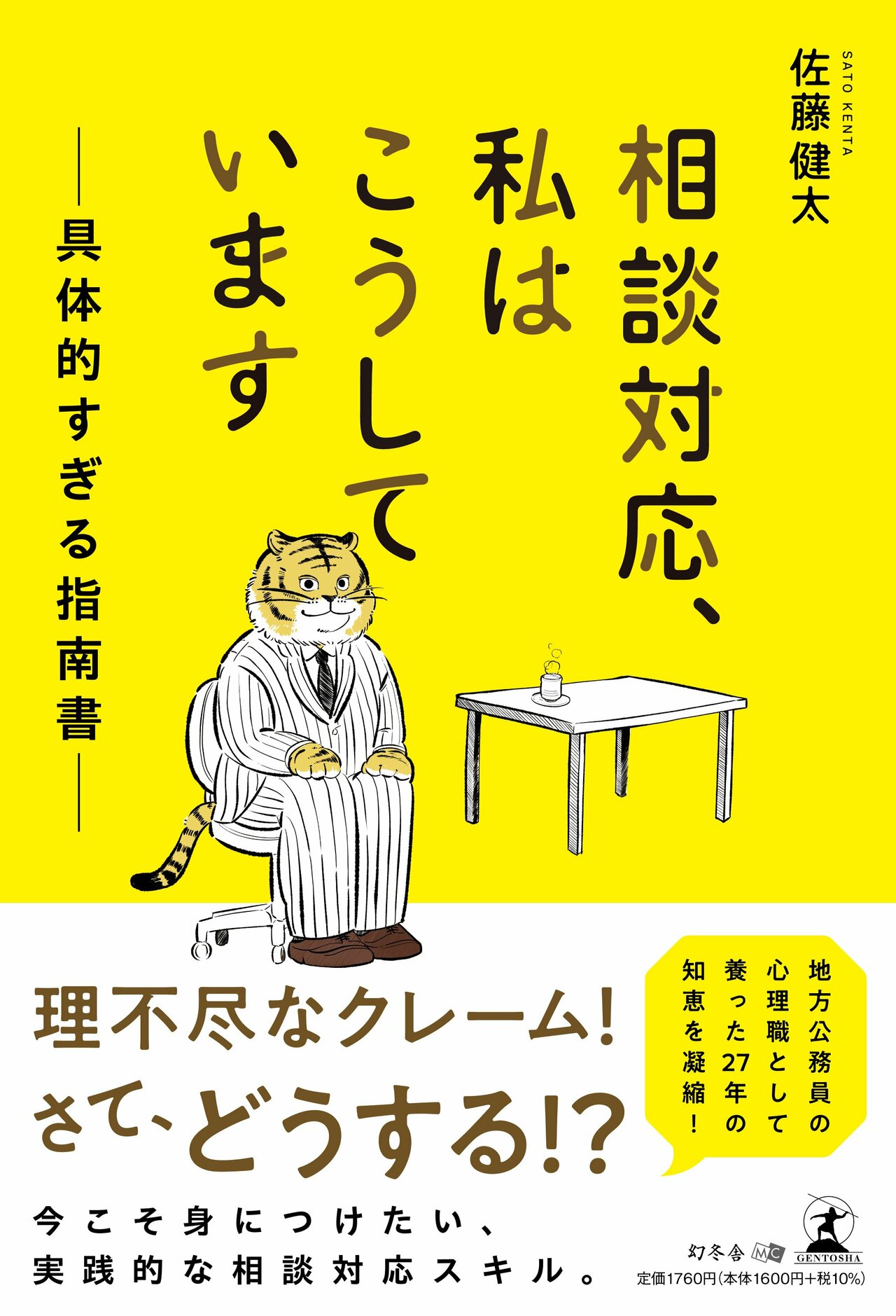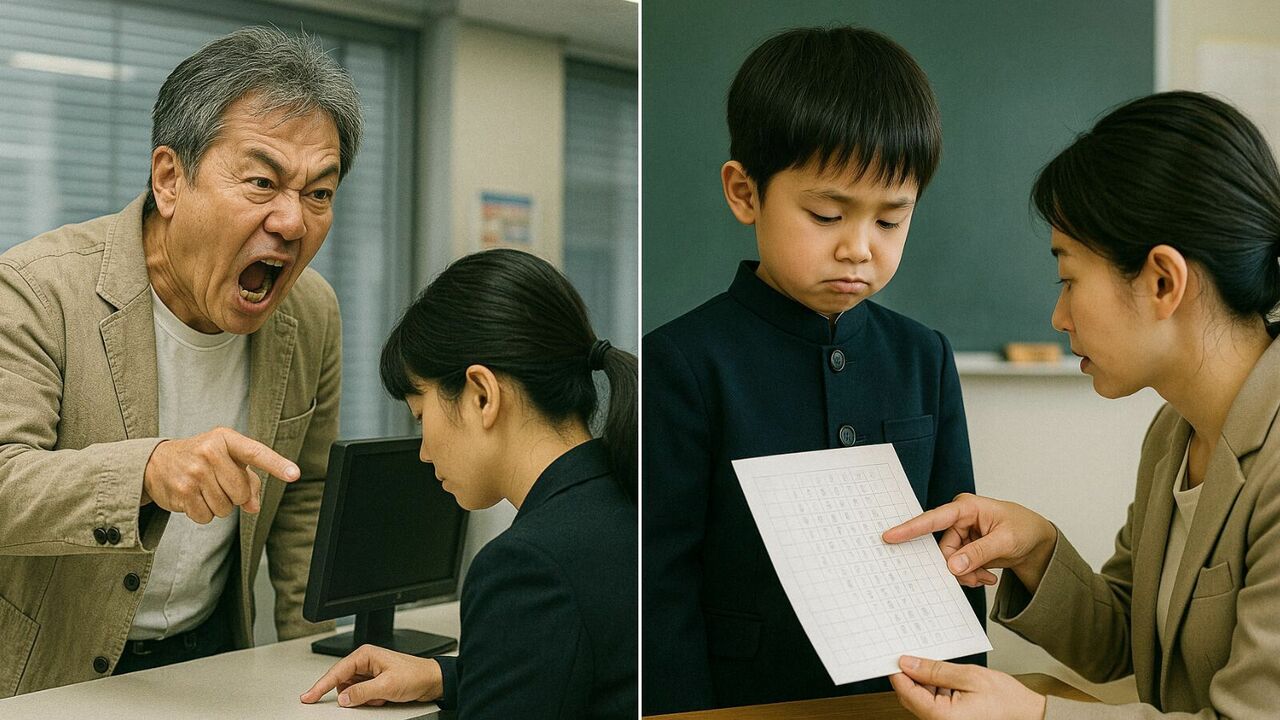考え方篇
第4章 どのような姿勢で臨むか?
1. 場合によっては、ある程度の自己開示もあり
これまで、自己開示の研究に関する講演を聞いたり、論文を読んだりする機会がありました。そこから得た私なりの理解として、自己開示とは「対応者が、自身の個人的な経験や体験を明かすこと」や「相談者との話の中で、対応者に生じた感情などを明かすこと」なのだと認識しています。
対応者が自己開示をするかについては、肯定する人もいれば否定する人もいて、その人が寄って立つ考え方で様々です。私は表題の通り「場合によっては、ある程度の自己開示もあり」という考えです。
前者の「対応者が、自身の個人的な経験や体験を明かすこと」については、話の入り口で相手を惹(ひ)きつける程度に用いるのはありだと思っています。「つかみはOK!」のイメージです。それ以上のことをしてしまうと、せっかく相談してくれた方に不信感が生じます。
これまでも、相談していただいた方から、別の相談機関に対する不満を聞く機会が何度もありました。それは、「話を聴いてほしくて電話したのに、相談員の体験談を聞かされて、私がその聞き役をする時間が長かった」「相談員の成功体験から、その価値観を押し付けられた」などといった内容です。
また、そういった体験をした人から、「もうそこには相談しない」「別の相談機関に相談する時に、またそうなるのではないかと強い不安を感じた」といった話を聞くこともありました。これは明らかに「ある程度」をはるかに超えてしまった結果だと思います。
一方、話の入り口で相手を惹きつける程度に用いるというのは、「必要以上に自分の個人的な経験や体験は言わない」という姿勢は持ちつつ、場合によっては自分のことを少し明かした方が、信頼して話してもらえることがあるということです。
例えば、子育ての悩みで相談を受けた時、私自身の経験を聞かれることがあり、「私にも子育ての経験がある」という程度の情報を提供することがあります。
なぜ相手がそれを聞いてくるのか、何を意図した質問なのか、といったことに対応者が関心を向けることが大事です。
この程度の情報提供をすることによって、相手には「子育ての経験があるのであれば、わかってもらえるのでは」という対応者に対する期待が生じ、もっと話してくれるきっかけになるだろう、という考えに基づいて行った記憶があります。
また、後者の「相談者との話の中で、対応者に生じた感情などを明かすこと」については、相談者に対して肯定的な内容であれば、積極的に伝えています。それにより、「この人には話しても大丈夫だ」という信頼感が増し、「もっと話したい」という気持ちを高め、相談を促進させる効果があると感じています。
一方、相談者に対して否定的な内容であれば、なぜそのような感情が湧いたのかを自分なりに考えますし、伝えるかどうかは吟味します。
話をつないでいく中で、このような自己開示がその話の流れをつなぐ役割を担うこともありますが、気を付けなければならないこともあります。
本連載は今回で最終回です。ご愛読ありがとうございました。