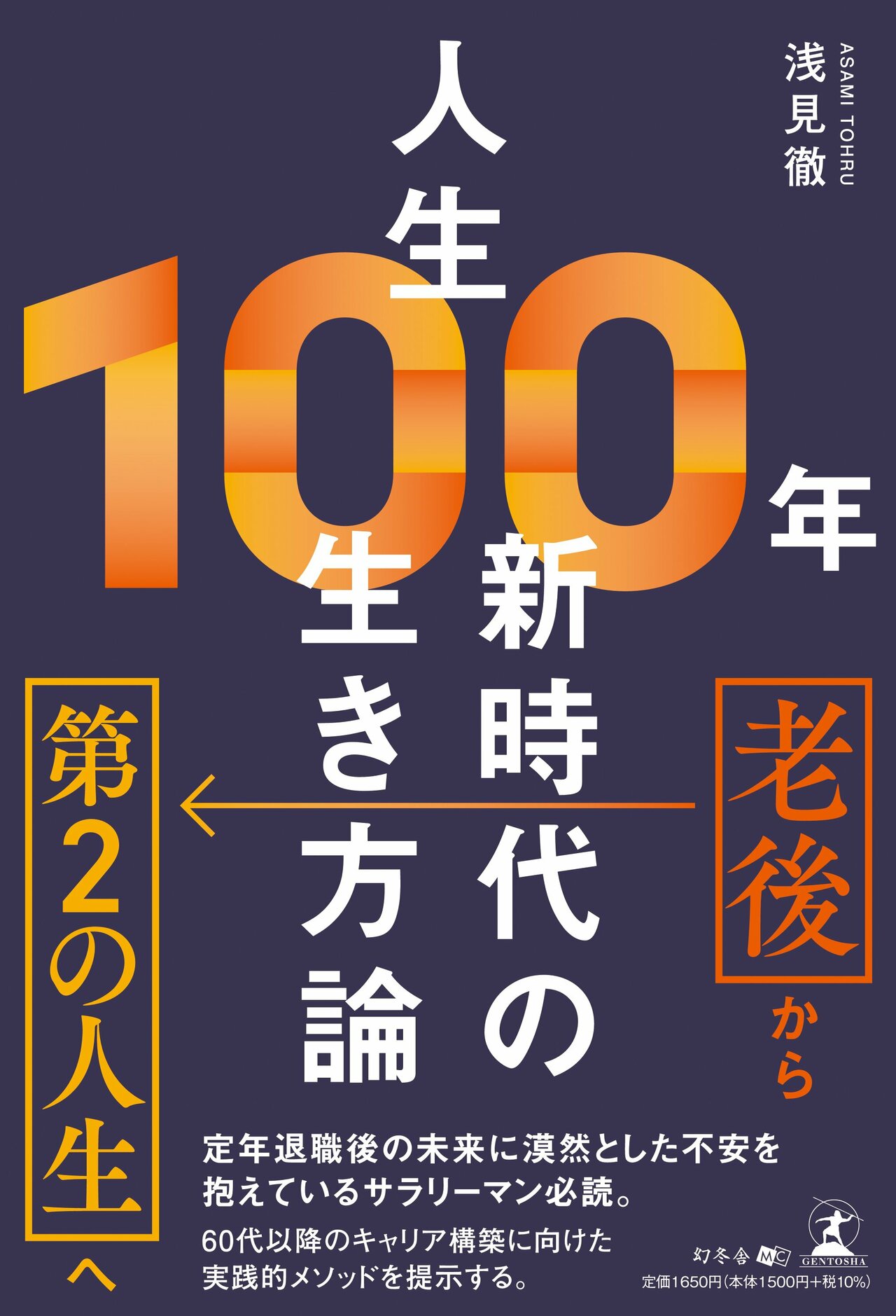我々が住んでいる心地よい暖かさの惑星は、摂氏6000度という太陽熱を吸収しながら、絶対温度わずか3度という極寒の宇宙空間に廃熱を放射している。
第2にマサチューセッツ工科大学(MIT)生物物理学者のジェレミー・イングランドによると、熱力学は熱的死よりも目を引くような目標を自然界に提供するというのだ。その目標は『散逸駆動適応』という専門的な名前で呼ばれている。
簡潔に言うと、粒子のランダムな集団がおのずから組織的な構造を作って、周囲からできる限り効率的にエネルギーを引き出すという意味である(散逸とはエントロピーを増大させること。
ふつうは有用なエネルギーを熱に変え、その過程で有用な仕事を行う)。例えばある種の分子の集合体を太陽光にさらしておくと、徐々に整列して太陽光の吸収能が上がっていく。
つまり自然は、より生命に似た複雑な自己組織系を次々に作っていくという目標をもとから持っているらしく、その目標は物理法則そのものに組み込まれているのだ。生命を目指すというこの宇宙的原動力と、熱的死へ向かうという原動力とは、どうしたら両立できるか。
その答えは、量子力学を確立した一人であるエルヴィン・シュレディンガーが1944年に書いた『生命とは何か』から得ることができる。生命系の証しは周囲のエントロピーを増大させることで自身のエントロピーを一定に保つ、または減少させることであると、シュレディンガーは指摘した。
つまり熱力学の第2法則には生命という抜け穴があって、全体のエントロピーは必ず増大させる決まりだが、ある場所のエントロピーが減少するとともに、それ以外の場所のエントロピーがそれよりも多く増大することはあり得る。生命は周囲をもっと散らかすことで、自身の複雑さを維持または増大させているのだ。」
【イチオシ記事】3ヶ月前に失踪した女性は死後数日経っていた――いつ殺害され、いつこの場所に遺棄されたのか?