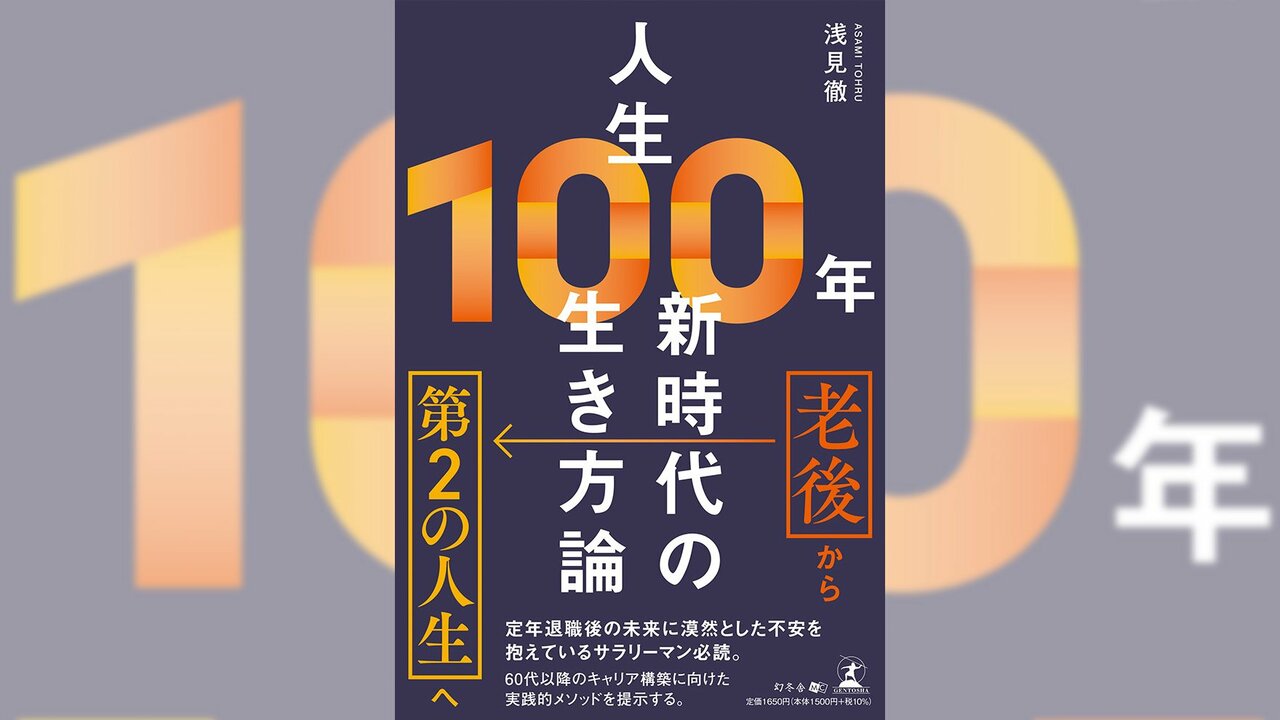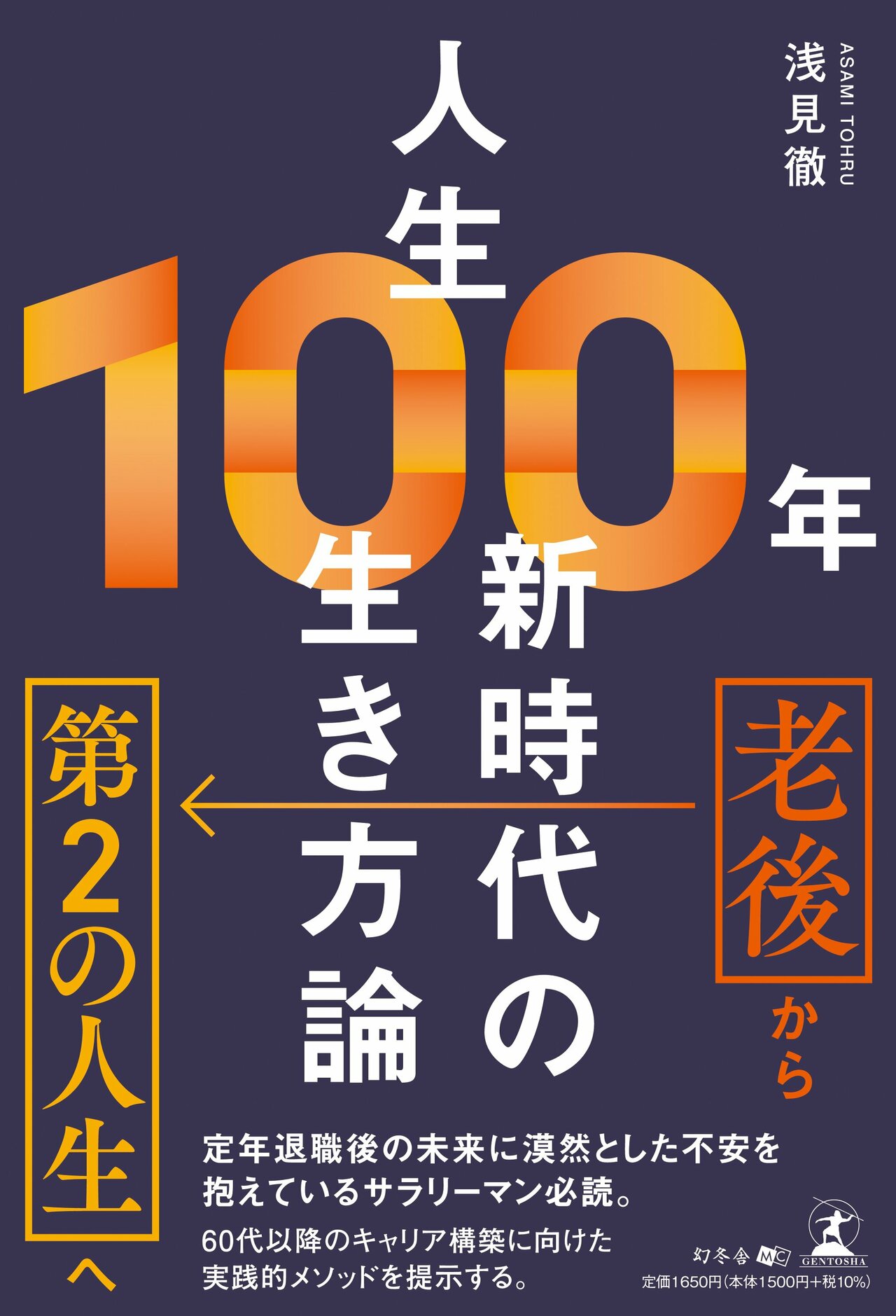【前回の記事を読む】活動=人間×換算係数とすると、活動がゼロの状態は、人間自体もゼロの状態である。つまり我々人間の存在とは、〇〇のことである。
第2章 考え得る多様な対応へのアプローチ
1.人間は粒子の集まり
この宇宙物理学、熱力学第2法則エントロピーの言及からは2つの重要なキーワードが見て取れる。一つは「目標指向的」であり、二つ目は「散逸駆動適応」である。
考えられる最大のマクロ観は138億年の宇宙法則である。ここから人生100年時代の、とりわけ60歳からの第2の人生で何をどのようにやるべきかが浮き出てくるのではないだろうか。
エントロピー理論によれば形あるものは必ず崩れる。秩序あるものは必ず無秩序になる。ただこの崩壊・無秩序があるおかげで、重力により宇宙に星ができ銀河が形成され、そして我が地球が46億年前に誕生したのだ。
また我々生命体・人間も多くの子孫を増やし、英国生物地質学者のチャールズ・ダーウィン氏が著作『種の起源』で言及したように進化発展してきた。見方を変えればこの形あるものが必ず崩れる状態は、無数の星の如く、また多くの生命体の誕生の如く、「分化していく現象」ともいえるのではないか。
さて2番目の「生命とは何か? 人間とは何か?」の案件である。
生命を持っているものを生命体・生物と呼んでいる。人間もその中に含まれる。生物とは生きて活動し複製・繁殖するものである。人間も複製・繁殖を繰り返し、チャールズ・ダーウィン氏の提唱した進化論の如く脳を発達させ発展してきた。
この状況は複製・繁殖・進化という表現よりも分化をしてきたという表現の方が的を射ていると私は感じる。人間とは散逸という散らかし行為により複製・繁殖・増殖を繰り返し周囲のエントロピー増大に多大の寄与をしてきた。
一方人間自身はさらに変容し、より進化発展すべく統合へ向かう。この状況自体はエントロピー減少である。
しかし人間は自己の統合によるエントロピー減少よりも周囲への散逸・ちらかしによるエントロピー増大の方が多いので、結果としてはエントロピー増大法則になっている。
このことを宇宙物理学では「散逸駆動適応」といわれている。「生命・生命体・人間とは何か?」とは「周囲の散逸を増やしながら自らの複雑さを維持し高めて増殖することで、全体の散逸をより速く進行させる現象である」ということになる。