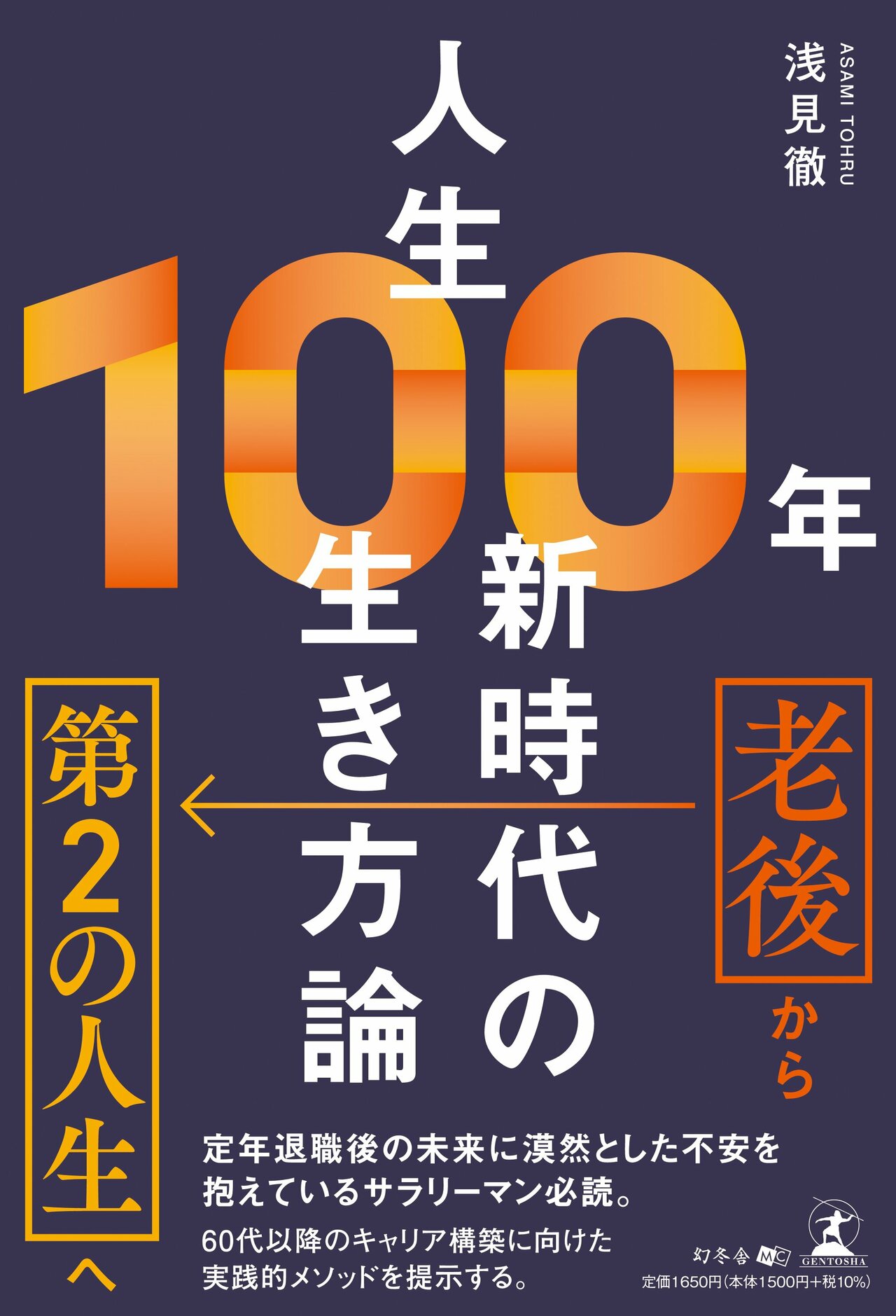自然は何かを行うために選ぶことのできるあらゆる方法の中から一般的には何らかの量が最小化または最大化されるような最適な方法を選ぶ。
全ての物理法則は、過去が未来を決定するという形で表現できると同時に、自然が何かを最適化するという形で表現することもでき、この二通りの方法は数学的に同等である。
二つ目の方法は数学的内容が難しくなるので物理学の入門過程で教えられることは普通ないが、前者よりも簡潔だし奥深い。人間が何らかのもの(資産・幸福等)を最適化しようとしていたらそれを追求する営みは目標指向的であるととらえるのが自然であろう。
したがって自然そのものが何かを最適化しようとしているのであれば、目標指向的な振る舞いが出現することには何の不思議もない。物理法則そのものに最初から組み込まれているのだ。
自然が最大化しようとする量としてよく知られたものの一つがエントロピー、つまり大雑把に言うと物事の散らかり具合である。熱力学の第2法則によると、エントロピーは増大していって最終的には取り得る最大値に達する。
さしあたりの重力の効果を無視すると、その最も散らかった最終状態、いわゆる『熱的死』はあらゆるものが完全に均等に散らばって複雑な構造も生命も存在せず変化も起こらない状態に対応する。
熱的死(最後には必然的に宇宙全体が静止して死んだ状態になる。自然の長期的な目標が死と破壊を最大限まで増やすこと)これはかなり落ち込む結果だ。
だが最近のいくつかの発見によってそこまで悪いことではないと分かってきた。第1に重力は他のどんな力とも違う振る舞いをして、この宇宙を一様で退屈ではなくもっとあちこちに塊のある興味深いものにしようとする。
その証拠にほぼ完全に一様だった退屈な初期宇宙は、重力によって、銀河や恒星や惑星に満ちあふれた今日の美しいほどに複雑な宇宙へと変わった。そして今では重力のおかげで高温と低温が組み合わさって幅広い範囲の温度が実現し生命が繁栄することができる。