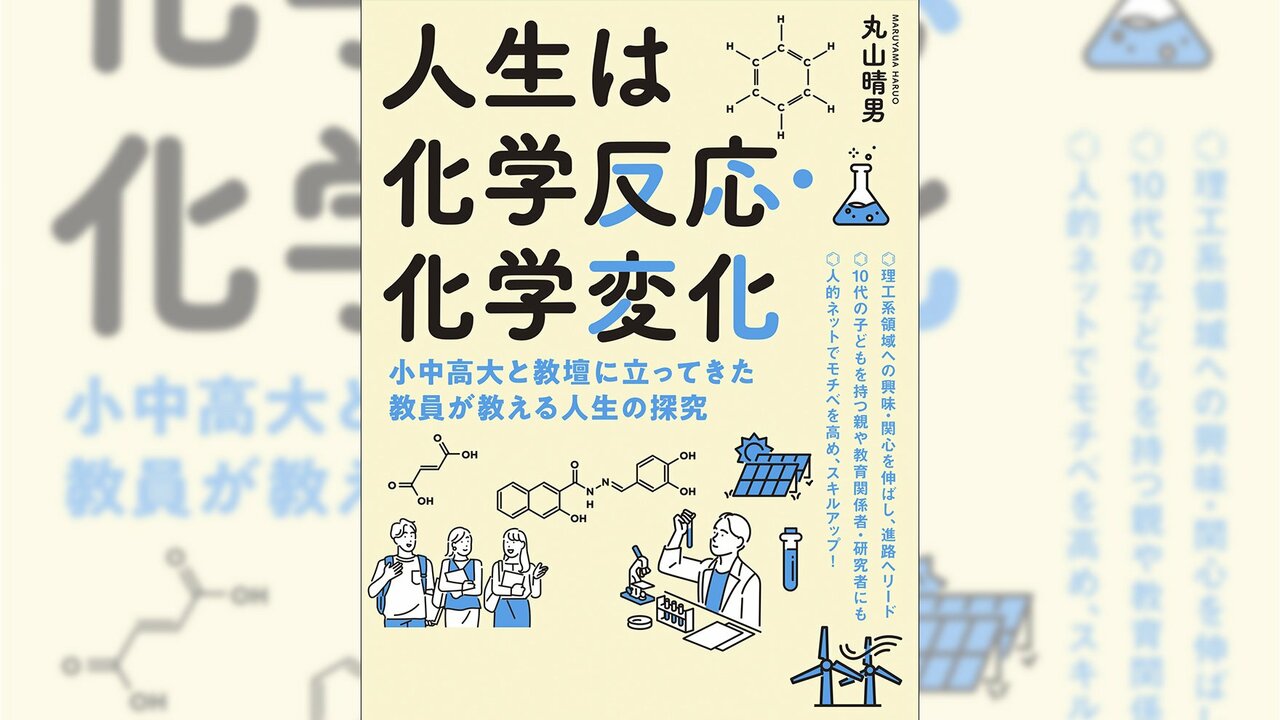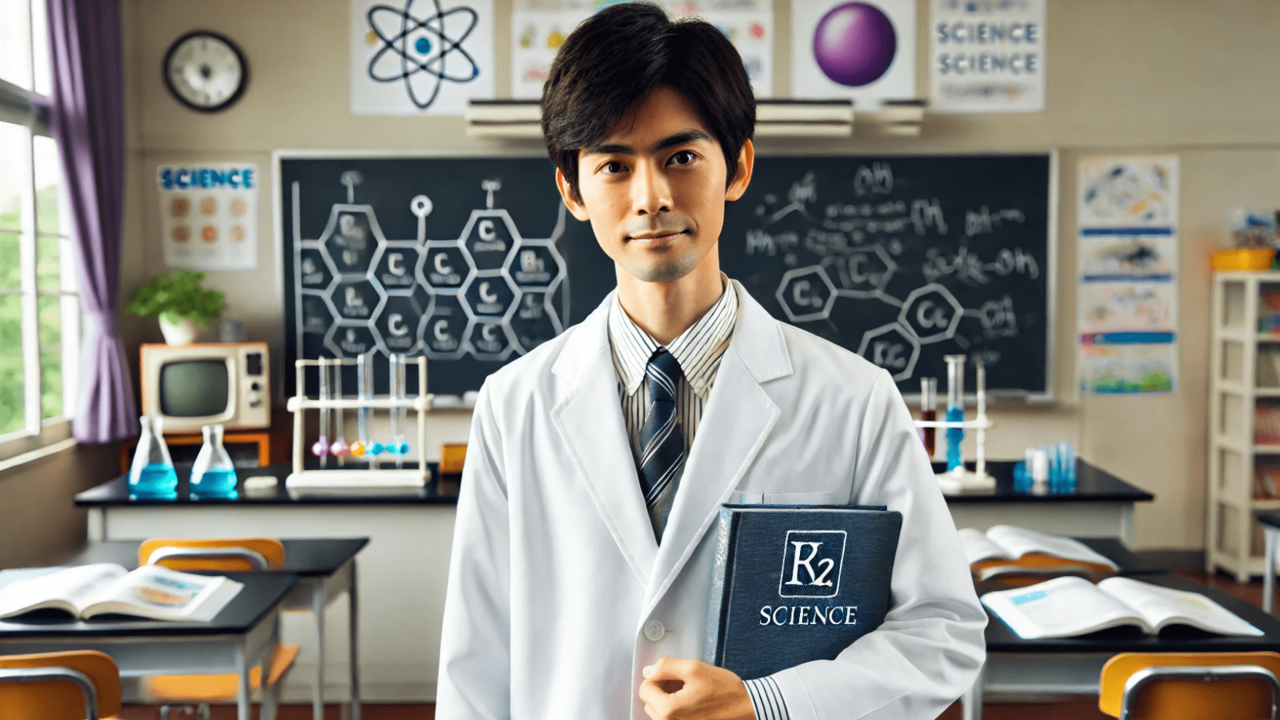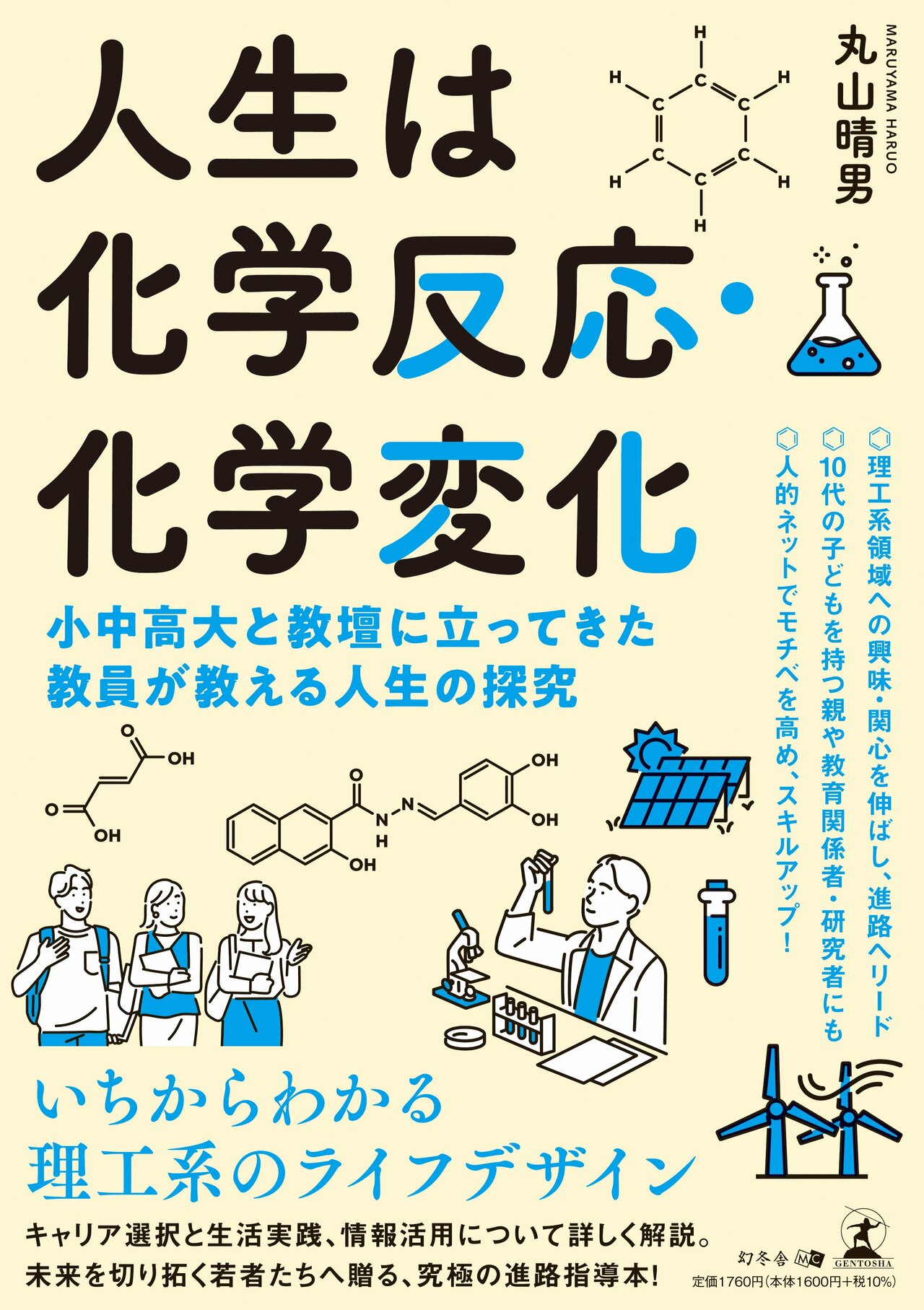【前回の記事を読む】【理系・理工系】理科、技術、工業科の授業実践! 理科好きな子供から、理工系列の学生・社会人になる道筋がここに…
B 授業
理科,理学,工学の授業や理工系に合わせた楽しい学び方
理科(小学校,中学校,高等学校),技術(中学校),工業科(高等学校)の授業実践はこれだ!
B-01 学習は教科書を基盤に,教科書の有効活用で深め広げる
おおむね,普通科の教科はカラーページスタイルが多く,専門教科の教科書は今までは白黒が多く,令和4年度の新カリキュラム対応教科書から,実教出版の「工業科」の教科書において,大きく改訂され2色刷りやカラー編集も増えてきました。
専門的な教科で,履修する生徒が限定的(工業科の生徒)のため出版数を多くできない側面もあります。さらに,専門的に対応できる出版社からの発行となっているので対応出版社も限られているのです。現場で教科書を活用していて,よく努力されていると実感しています。
2 各教科書を共有化して活用する
専門教科の「工業科」の教科書は,現在使用している実教出版の教科書は専門性が高く,現在,大学の1,2年生レベルに対応できる内容も多く,実際同等レベルの教科書を大学でも活用しているところもあるようです。これらの教科書をうまく活用することにより,大きな教育効果を高めることができるのです。
「機械工作」の教科書においては,機械材料の部分を「化学基礎」「化学」「工業化学」の教科書との共有化ができます。「電気回路」の教科書においては,「物理基礎」「物理」「数学」などの教科書との共有化ができます。
詳細の事例についてはB-04、B-05、B06で提示することにします。この考え方や実践は,小学校でも活用できます。私の実践では,「小学校理科」の生物分野の学習では,「生活科」や「図画工作科」との学習の共有化もできますし,「生物の成長とその環境」を視点に置けば,小学校3年生から6年生までの生物分野の共有化も可能です。
この考え方により,「短時間で深く,興味深く」学習することが可能になるのです。中学校においては,「理科」と「技術科」の共有が可能ですし,実際にこの2教科を担当していましたので実践可能です。この実践とその成果については,学会発表と学術論文にもまとめましたので,ご興味がある方はぜひご覧いただければ幸いです。後述F-01の論文リストに関係文献を一覧として掲載しました。
このような実践は,すべて教科書の活用が中核になっています。教科書を読めばその内容から流れ,重点や共有点が分かるのです。もっともっといろいろな立場から教科書を活用してみませんか。次ページから同じよう授業な内容が続きますが,事例を入れて説明をしていきます。