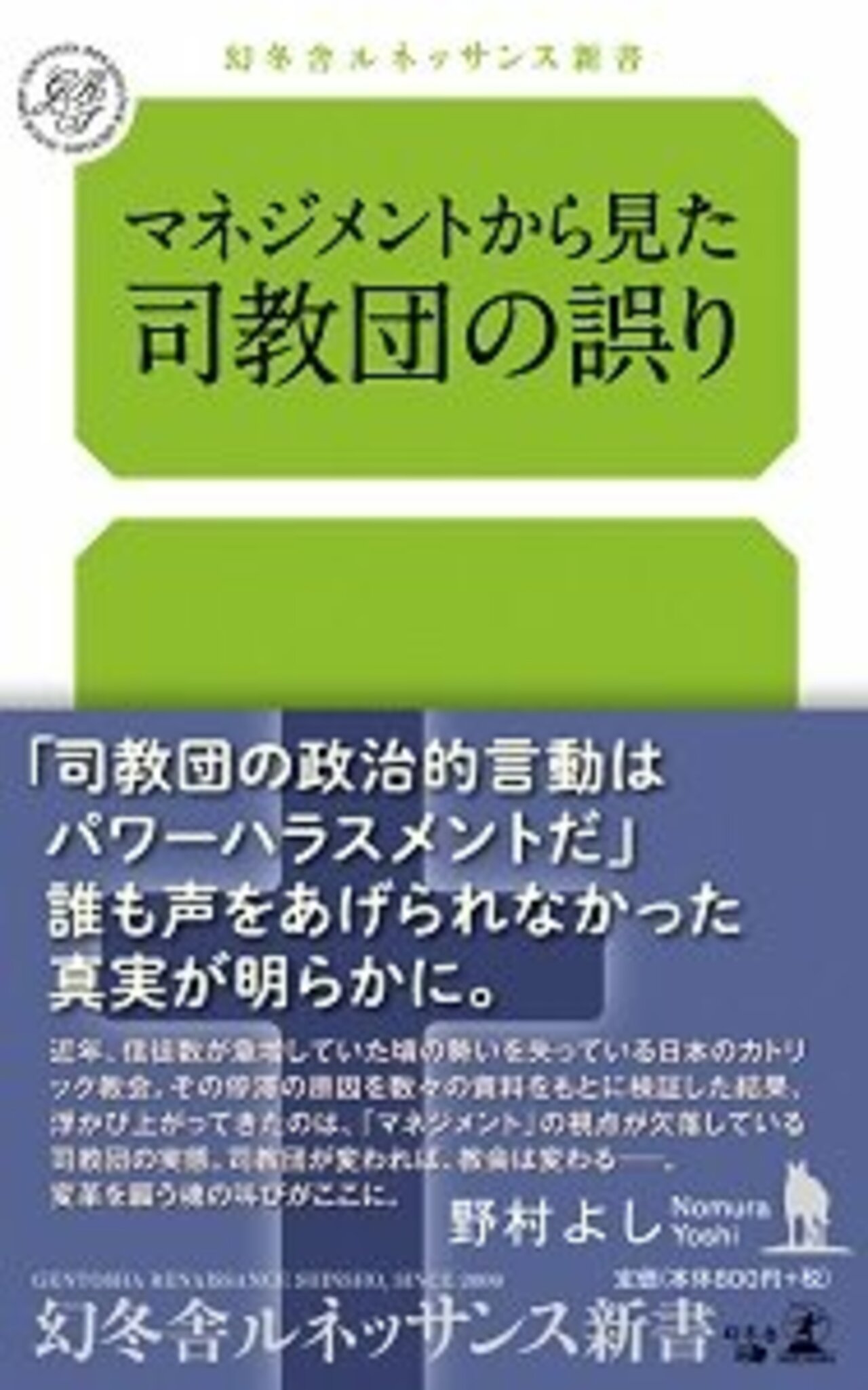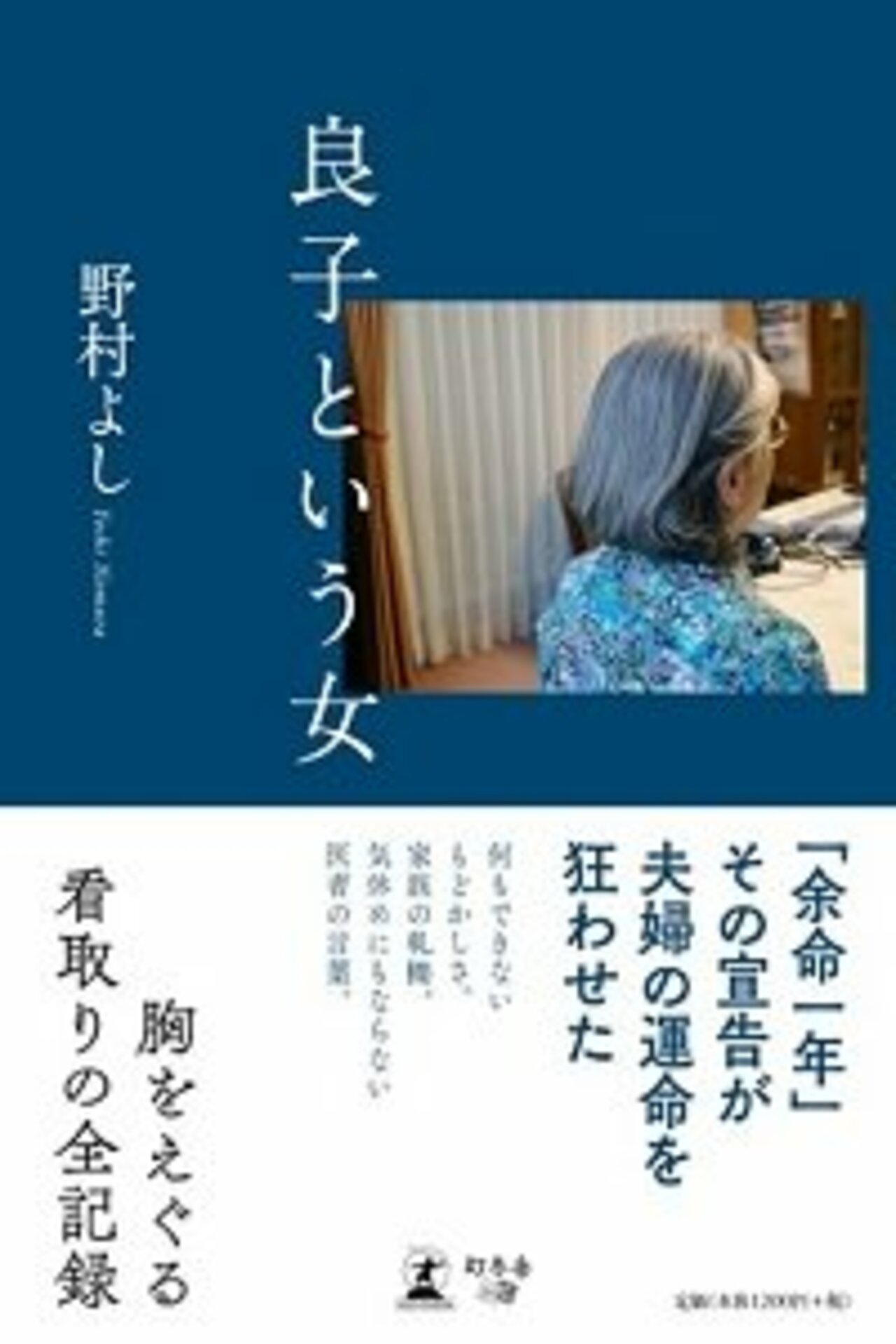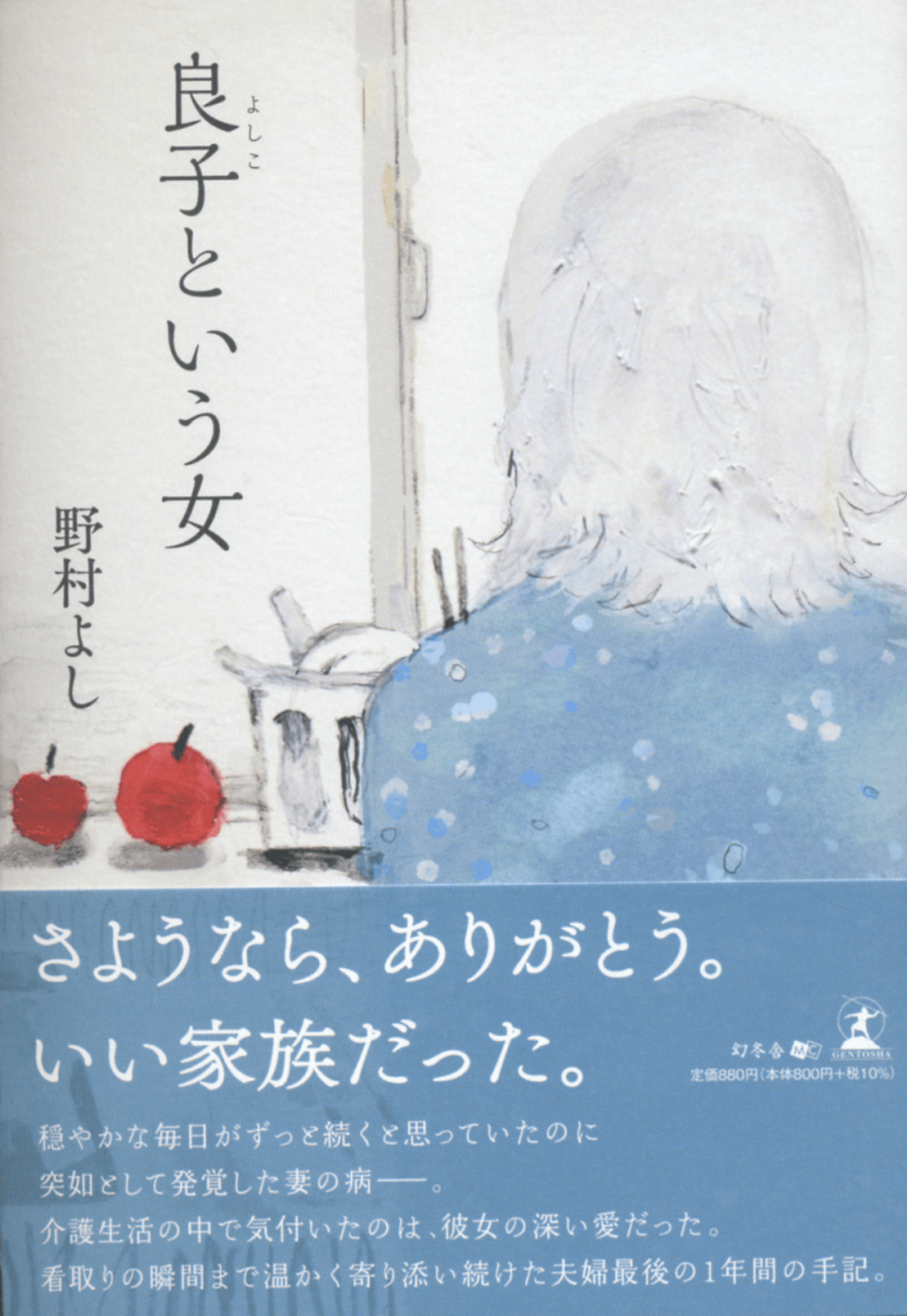「だんまり(第2場)が始まれば見ようと思っていた。それまではつまらないから見なかった」
と彼は言った。ということは一場中、彼はその動作を続けるつもりでいたことになる。
「見たくなければ目をつむっていればいいじゃないか」
「私の勝手だ。自分の価値観を人に押しつけるな」
「価値観の問題でなく、エチケットの問題だろう」
小さな声での会話だったので、幕間のざわめきの中、周囲の誰も気付かなかったであろう。あい子は、「あとで父に言い聞かせますから」というような言葉で私に非があるとし、おさめようとした。
あい子に反論すれば数倍する反撃が予測できるので、大塚家具を劇場で演じたくなく、私は黙った。しかしあい子の位置は男の真うしろで、私が問題とする動作は見えていないのである。
歌舞伎座は勿論、どこの劇場・コンサートホールでも、ビニール袋が立てる音にまで注意する。プログラムをめくる動作には、音に加えて視覚的迷惑影響がある。私の場合は芝居でもコンサートでも、開演中はすべてを足下に置き、膝上には何も乗せない。
一昨年(2013年)の2月に東京文化会館で、三枝成彰作曲のオペラ「KAMIKAZE──神風──」があった。
私の左にいた中年女性は開始直前まで携帯メール操作をし、慌てて切ろうとしたが開始の弦の最弱音は鳴り始めた。携帯のライトが目の前で動いた。私は息を詰めて、出だしを聴きたいのである。作曲者も命を込めて、その音を発見したと思う。残念であった。
作者も演者もスタッフも、一瞬一瞬、精魂込めてやっていると思う。私たちもそのように仕事をしている。
観客は楽しみで行くのであるが、周囲に対する配慮は勿論、提供者に対しても感謝と敬意を持ちたいと思う。
次回更新は4月7日(月)、20時の予定です。
【イチオシ記事】3ヶ月前に失踪した女性は死後数日経っていた――いつ殺害され、いつこの場所に遺棄されたのか?