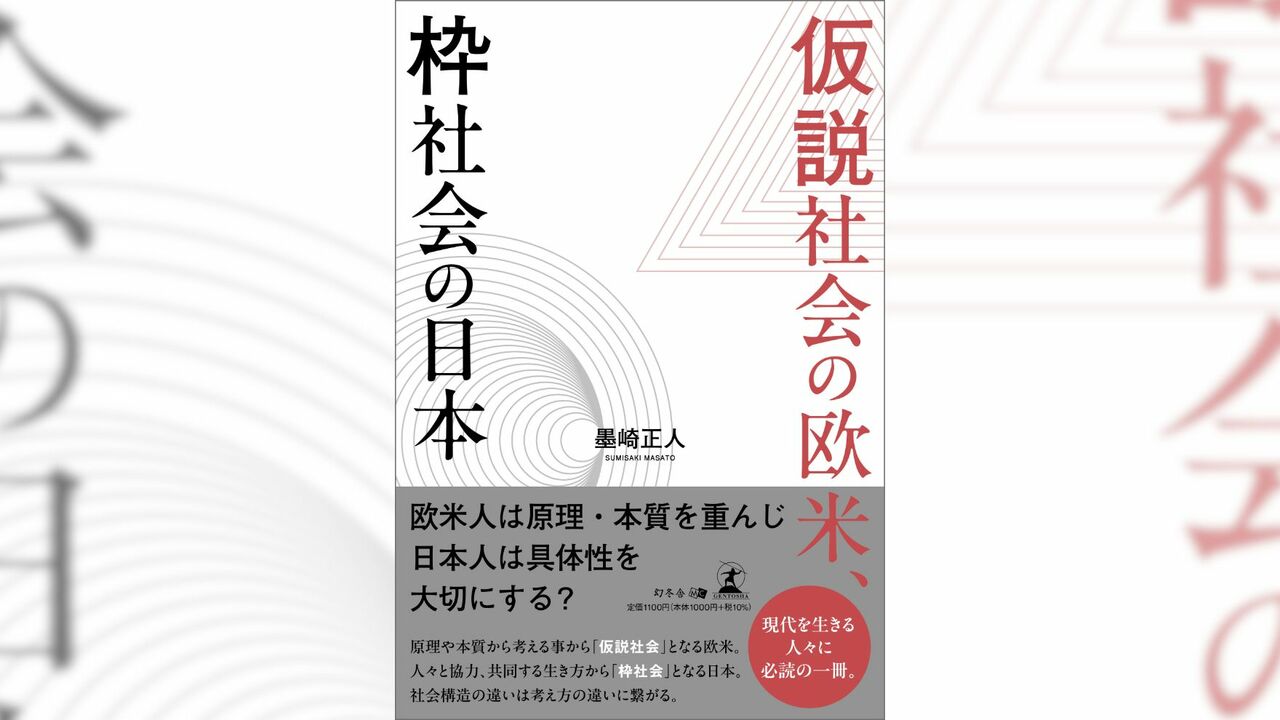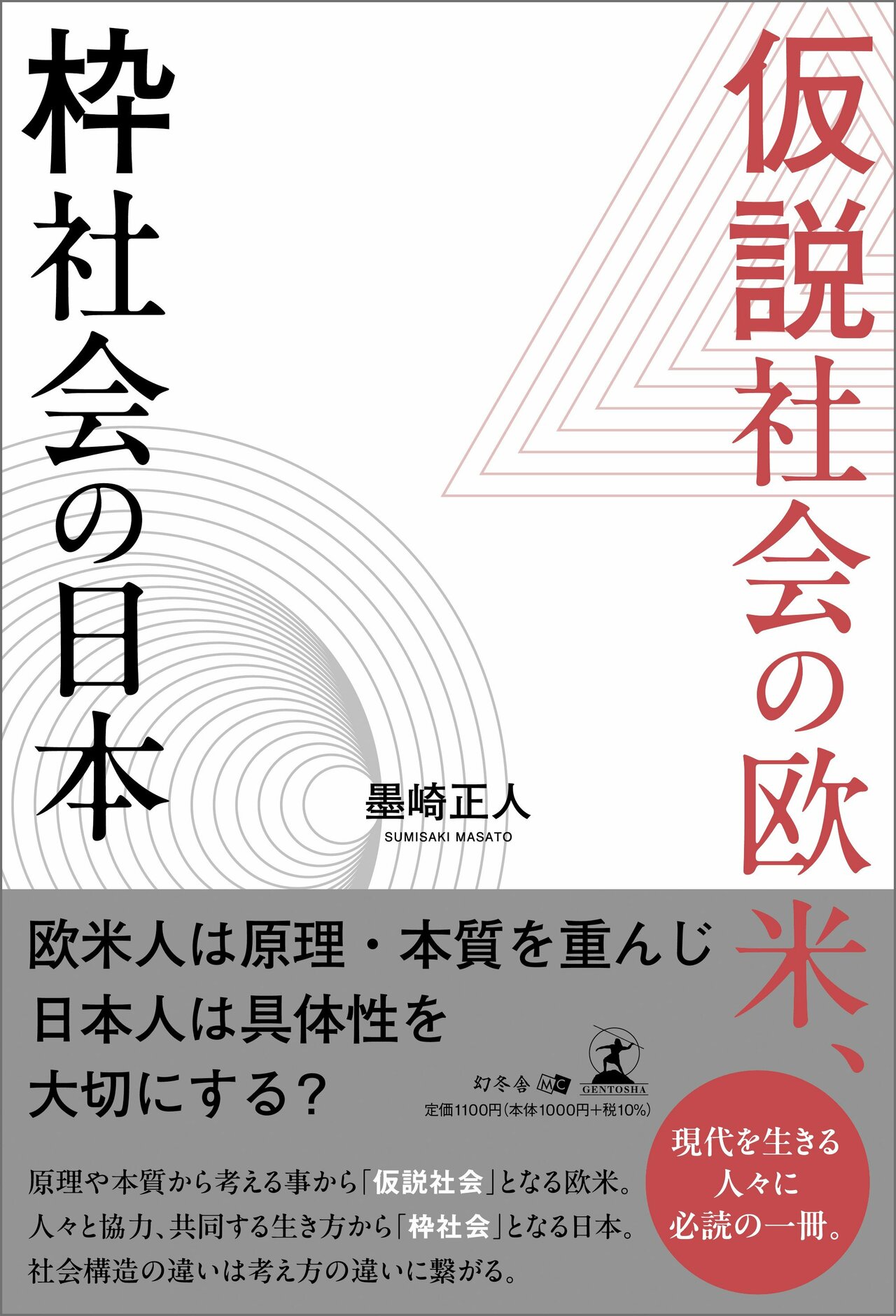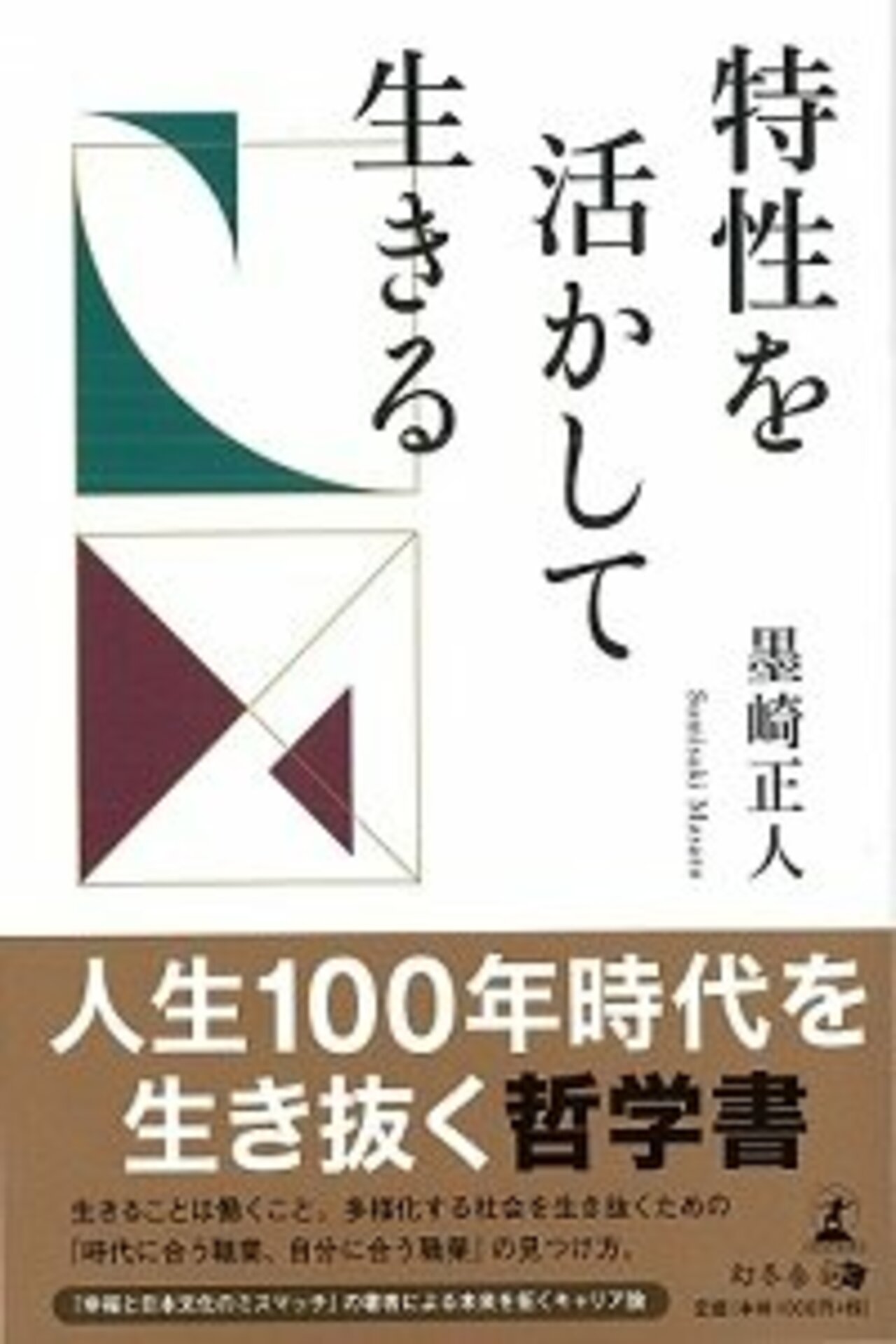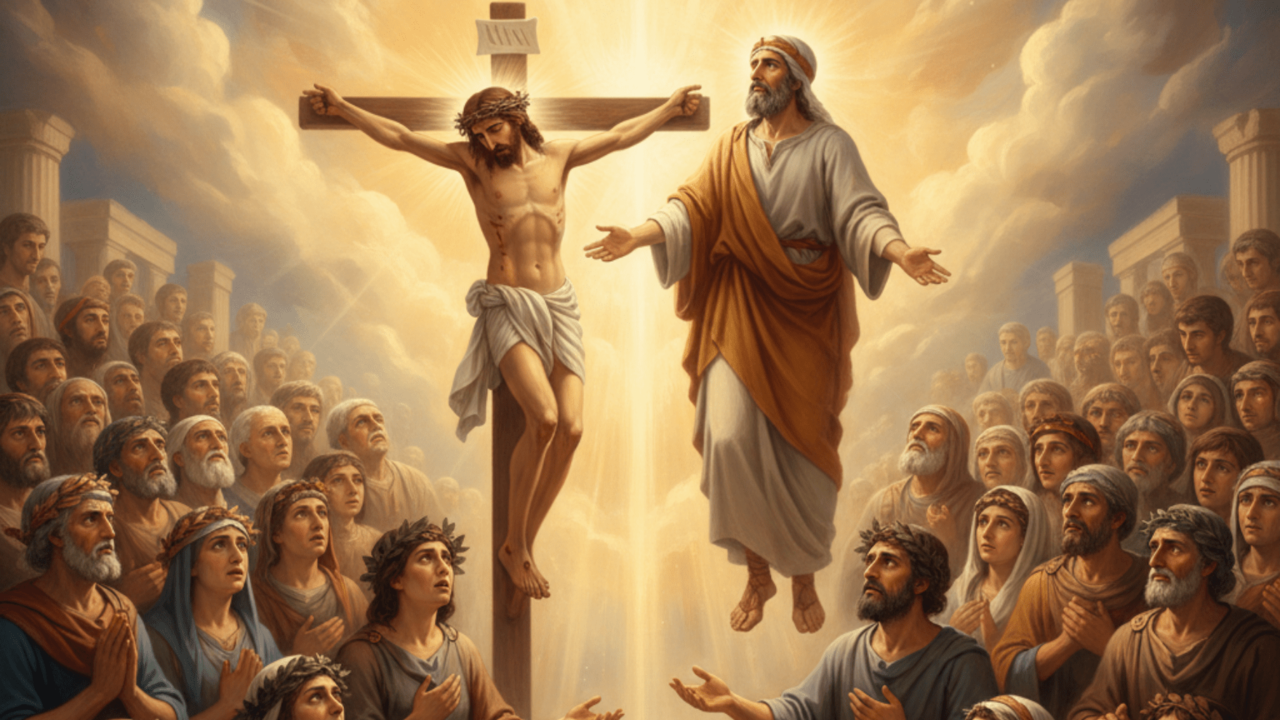【前回の記事を読む】宗教・多様性・グローバル化、各国で訪れる急激な社会の変化。意外性と妥当性を兼ね備えた視点から混迷する社会をとらえる!
第1章 テレビに映る日本の風景と周辺国の文化と特徴
日本社会はコロナの影響が薄れてきましたが、私たちはコロナ禍の最中諸々の面で影響を受けた生活をしていました。
コロナが起こる前迄は、会社で仕事をするのが普通でしたが、コロナ禍で事態が一変し、自宅でのテレワーク等への仕事となった人が多くいたと思います。
私は仕事の合間、気晴らしにテレビを見たり、携帯を見たりの生活をしていましたが、その時自宅で見るテレビが従来放映されていた内容と大分様変りしている事に、気付いていました。
テレビを管轄する当局の自粛要請があったのか、否かは分かりませんが、旅行番組が少なくなり、中でも外国への旅行番組がさっぱり見られなくなっていました。
旅行番組の異変だけではありません。新規ドラマも少なく、代わりに再放映されたドラマが多くなっていました。
再放映されている中でも「家族ドラマ」がよく放映されていました。だが、家族ドラマはいつも同じ場所で同じ事を繰り返す内容になります。
家族ドラマをよく放映するテレビ局、それをいつも飽きもせずにチャンネルを合わせて見入る視聴者。このマンネリ化した変化のない光景に、私は不思議な感覚を覚えていました。
日本のテレビ局が何故コロナの最中に家族ドラマをよく放映するかを考えてみると、家族ドラマには日本の文化が映っています。
文化はその国、地域の人たちの心の拠り処となり、人の心を安心させる処があり、私たちは家族ドラマを見て安心し「幸福感」を味わっていた事にもなります。
本章の前半は、コロナ禍の時よく放映されていた動物の生態ドキュメントから人間の特性について論じ、同じ事を繰り返す家族ドラマから日本人の幸福観を話してみたいと思います。
そして後半は、日本の近隣に存在する中国、韓国そしてロシアの3国に焦点を当て、これらの国々の人たちの生き方と文化、特徴について話してみたいと思います。
テレビに映る動物から人間の特性を見る
私はコロナ禍の最中テレワークで仕事をしていた合間、テレビに映っている動物のドキュメンタリー番組をよく見ていました。その中で成長したオスとメスが独自の行動を取る様を面白く見ていました。
動物は基本的に群れを組み集団化して生きています。だが、オスとメスは、一定の時期に達すると集団から脱し、独自の行動を取るようになります。
その時に映るオスは、メスの前で急に肩を怒らせ、身振り手振りを大きくしたりし、中には奇声を発するオスもいました。