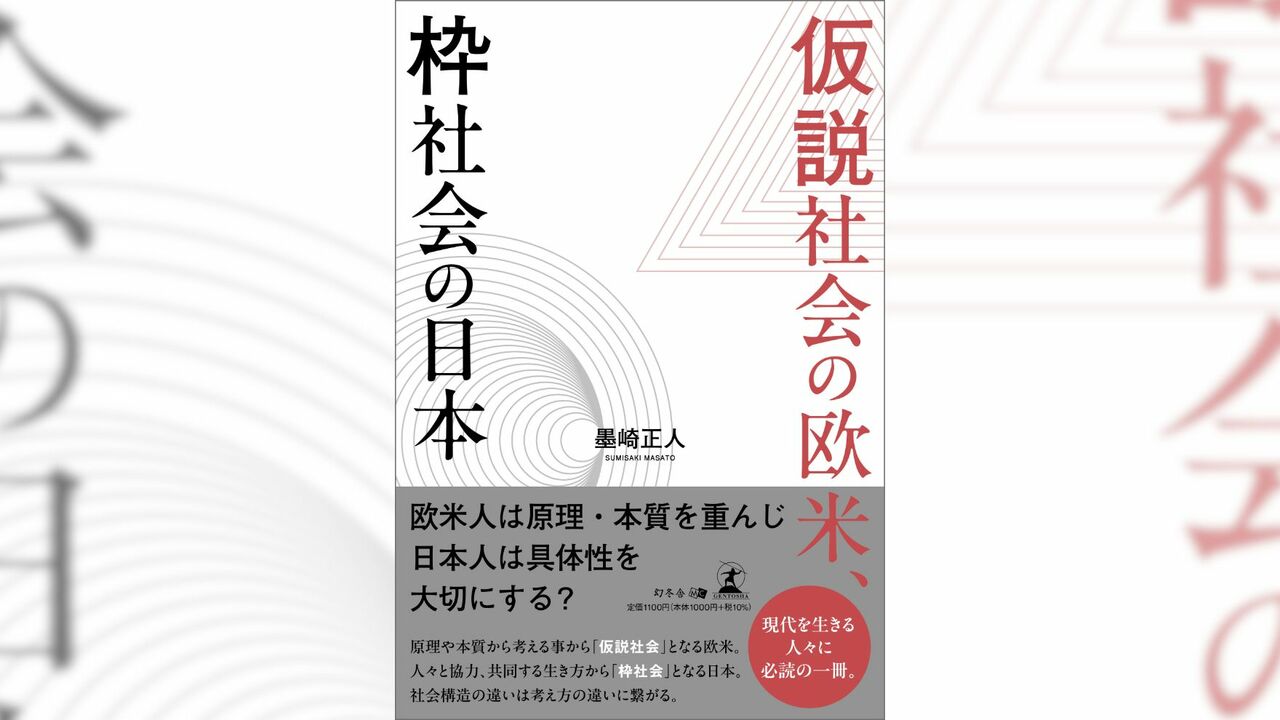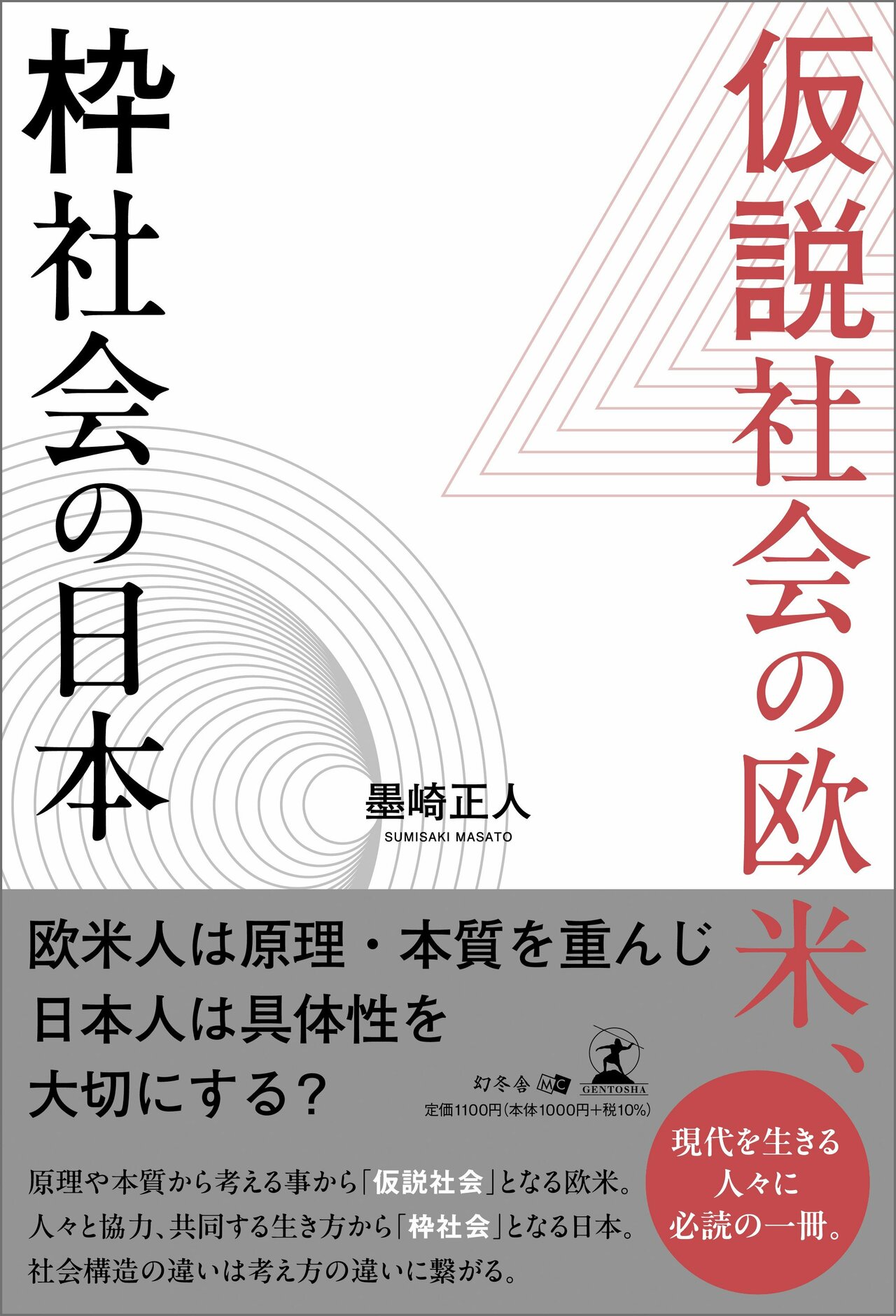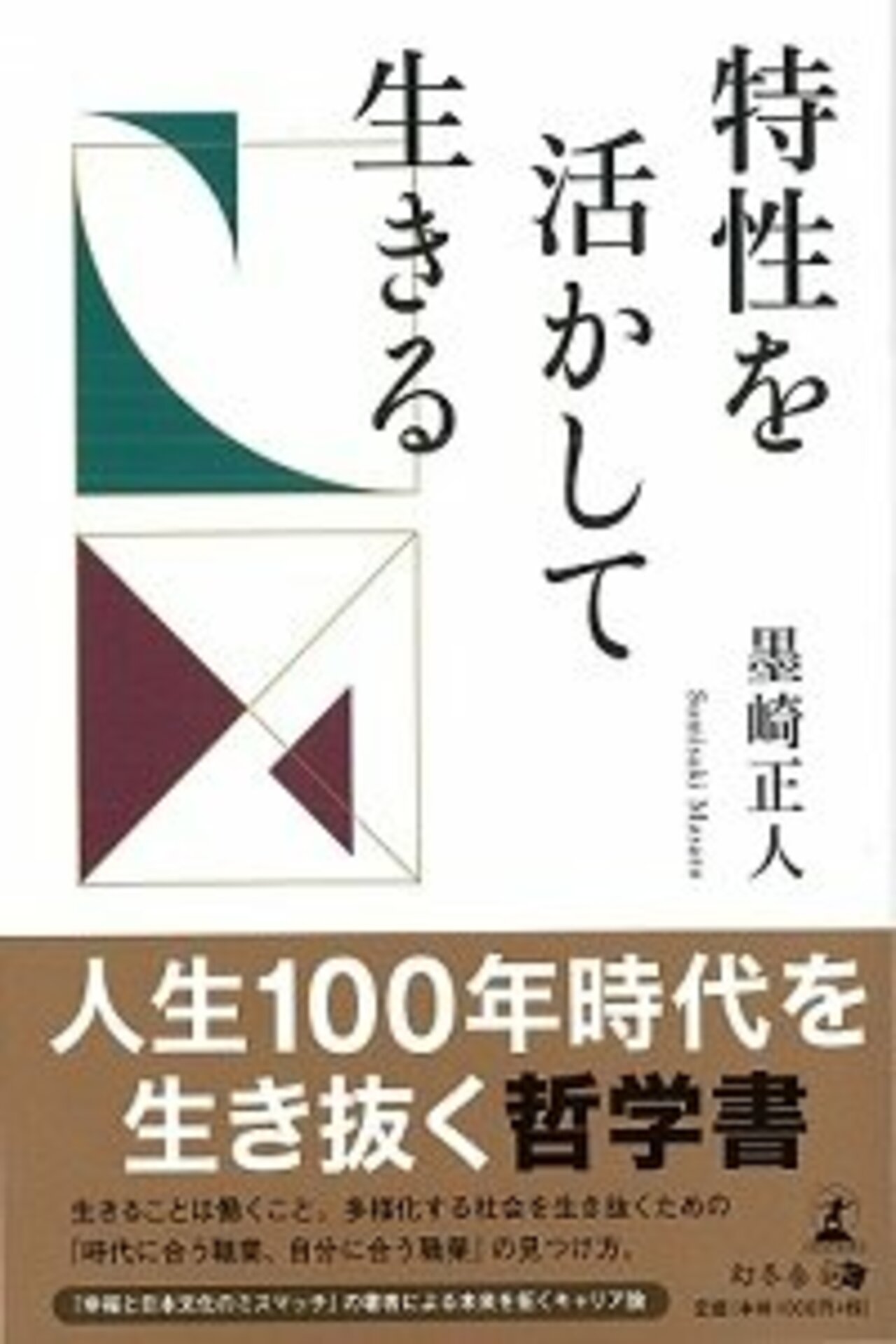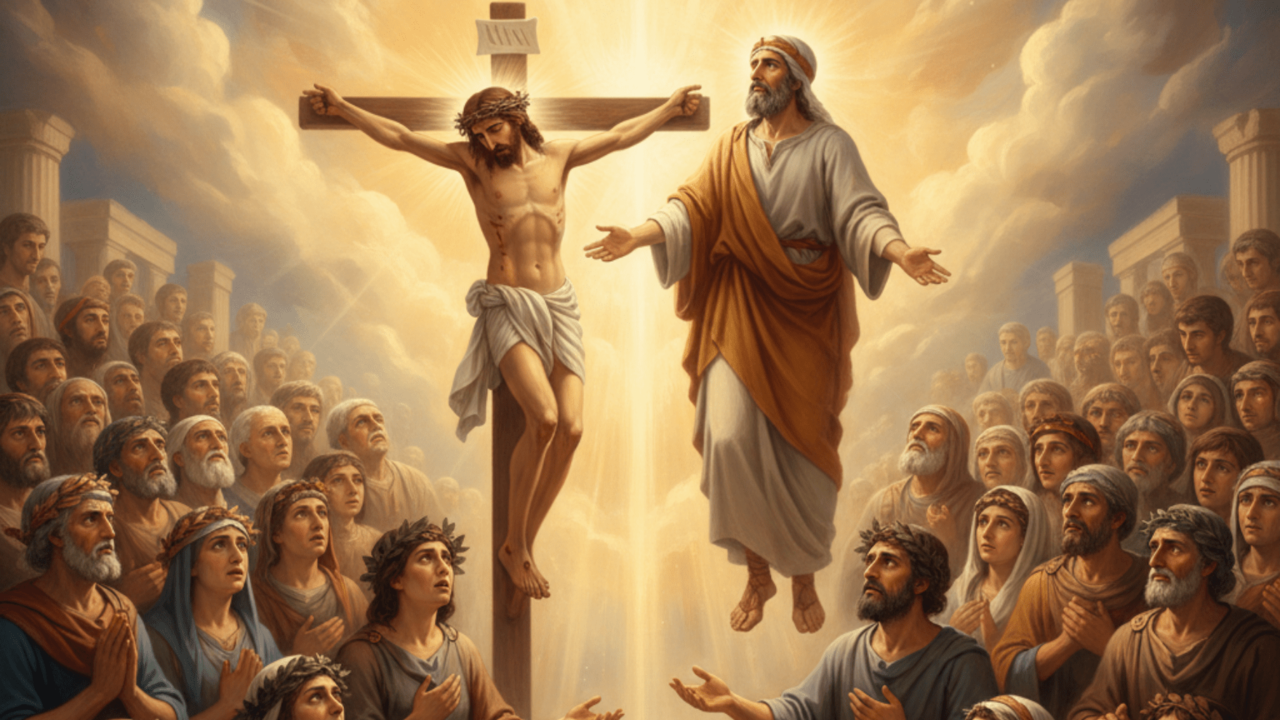【前回の記事を読む】プーチン・ロシアの強気な外交。周辺国への気配りと領土拡張の「二面作戦」で生き抜ぬく外交スタイルとは?
第1章 テレビに映る日本の風景と周辺国の文化と特徴
固有の地政学から発想するロシア その③
社会主義を打ち立てたドイツの経済学者マルクスは、著書の資本論の中で「労働価値説」を打ち立てています。労働価値説は、経済原理の下で作動する市場法則の考えをマルクス独自の考えで説いたものです。
経済は人間が持つ欲望から成り立っている側面が強くあります。それを受け経済に人間の欲望が絡み、経済は人間の欲望が「原理」となって諸々の法則が成立している側面があります。
人が生活している場所に昔から市場(いちば)が存在するのは川の流れのようなもので当たり前の光景です。だが、マルクスが説く労働価値説は、魚や果物等の日用品を取り扱う市場(いちば)でなく、資本主義下の需要と供給が交差する広い市場(しじょう)を前提にしての労働価値説となっています。
マルクスが説く労働価値説の骨子を説明しますと、労働者が働いて得た賃金は正当なものとしています。だが、賃金は資本家に吸い取られ、その結果労働者は市場から「疎外」されるようになるとする理論です。
マルクスの労働価値説は、ロシアに受け継がれ、1917年にロシアは労働者による共産主義国家としてソ連邦を誕生させています。
しかし、ソ連は、経済原理が作用する市場法則を正しく理解する事が適わず、労働価値説に固守し、労働者の優遇政策を過度に実施した事から、生産が上がらず、市場が機能不全に陥り、社会主義国家のソ連邦は崩壊し、いまはロシア共和国となっています。
ロシア経済の実体は、形ばかりの自由経済で、国が管理や統制を行う、歪な経済体制となっていました。
経済を大まかに説明しますと、基本は生産と消費、そして分配の三つから成り立つ構図になります。資本主義社会は、この三つを軸に経済が相乗、循環し、社会が成長する仕組みになっています。
だが、いまのロシアの経済は、生産と消費が程よく循環して拡大する資本主義経済でなく、諸々の面で国が市場に介入する歪な経済体質の国となっています。
ロシアは穀物の生産が世界一で、石油や天然ガスも豊富な国です。だが、GDPは世界で10位と韓国よりも下にランクされています。この数字は、ロシアが自由な競争に基づく資本主義体制の経済でなく、歪な統制経済国である事と関連しています。
世界一広い国土を保有し、世界一の穀物を量産、且つ豊富な石油や天然ガスを保有しているロシアです。普通に考えるとロシアは世界一の経済大国になれる筈です。だが、ウクライナに侵攻しても武器の供給さえ儘ならない経済の実体。ここに相も変わらず経済原理を理解していないロシアの実態があります。
ウクライナへ侵攻し、それが上手くゆかない戦局。いまのロシアの実体は「ロシアとは如何なる国か?」と問われた場合の格好の答えとなる「ヒント」があります。
日本の近隣に存在する国々はそれぞれの生き方、スタイルで国家を運営しています。独善の中華思想の中国、その中国の隣にあっていつも揺れ続ける朝鮮半島。そして歪な地政学条件と統制経済に固守し、周辺国を監視、威嚇するロシア。
日本は、海洋国としてこれらの国々と海を隔てて存在しています。私たちは日本が危うく、厄介な地政学条件にある事をシカと認識し、対応して生き抜く事が必要であると思います。