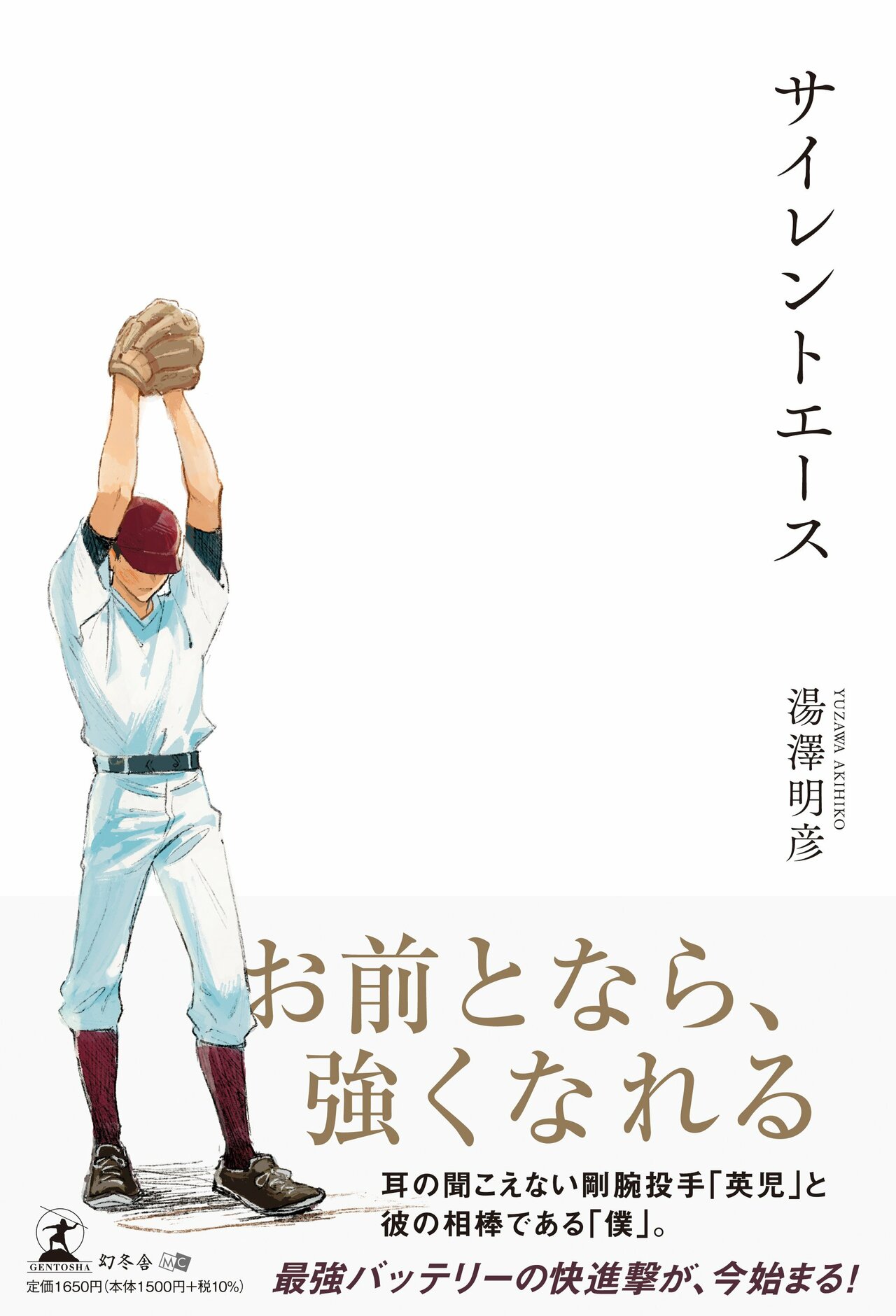第二章 中学野球編
あまりに重い話に僕は言葉もなかった。ただ、ひとこと、「そんな大切なものをいただくわけにはいきません」とだけ小声で答えた。
「いいんだよ。僕は池永のためにも記者として一生懸命頑張ってきたし、そのノートも十分参考になった。あとは、同じキャッチャーの君が、このノートを競技に活かしてくれないか、頼む」
僕はおそるおそるノートを開いた。几帳面でまじめな池永さんの性格が伝わってくるようなメモだった。
ピッチャーの特徴や相手打者のくせなどに応じた配球の仕方などがイラスト付きで見事に描かれていた。まだ読めない漢字もあったが、これはすごい。直観的に分かった。このノートを僕は池永メモと呼んで、生涯大事にしていくことになる。
その日はスポーツ談義に花が咲き、いつの間にか夕暮れどきになってしまっていた。僕は、このとき漠然とある憧れを抱いた。
坂本や英児はプロ野球の世界へ行ってしまうだろう。僕にはとてもそれは出来まい。でも、出来ることなら大学野球、それも東都六大学野球でプレーをしてみたい。
「福田さん、僕、M大学で野球がしたいです。こんな小さい体で勉強もまだまだ全然だめなんですが、出来るでしょうか?」
福田記者はにこりと笑って言った。
「かつて日本で無敵だったラグビーチームでウイングとして活躍したある選手はひときわ小柄な体で世界に名高いオーストラリア代表のメンバーにもなっている。その彼が言った言葉がある。『体格差なんて、言い訳だ』だよ。大丈夫、出来るさ。