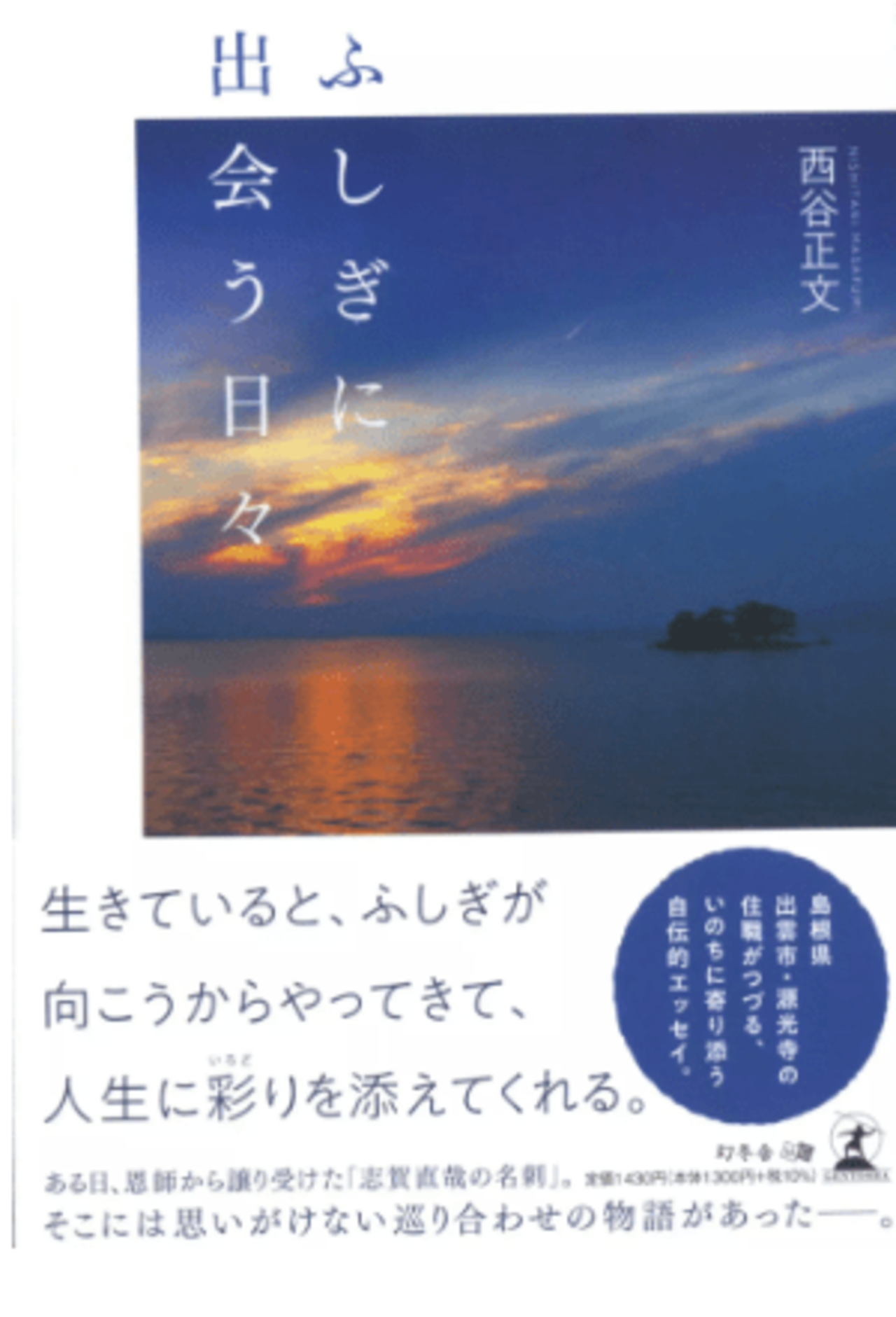明治という時代は、西洋の文化や事物が一気に日本に入ってきたときであり、同時に西洋的思考方法も入ってきている。江戸時代までのものの考え方とは異なる、西洋人の考え方。それを受け入れるということは、現代に生きる私たちが考えるよりも、はるかにむずかしいことだったのではないだろうか。
私たちが目にする翻訳語はことばの表面の形であるが、そのことばを編み出す過程では、東洋と西洋の思考の葛藤があったのではないか、と思っている。
翻訳語の一つに「交響曲(こうきょうきょく)」がある。よく知られたことばだ。このことばを編み出したのは、西より三十歳ばかり年下の森鷗外(おうがい)(本名林太郎 以下、鷗外)である。
鷗外もまた津和野に生まれて養老館に通い、幼いときから論語や蘭学を学んで、早くから人並みはずれた才能を示していたようだ。鷗外については、すでに多くの方がご存じだと思うので、ここでは彼が残した遺書を取り上げることにする。
鷗外は、その生涯を終える三日前に遺書を残している。彼自身が書いたのではなく、口述したことばを筆記してもらっている。記したのは、「一切秘密無ク交際シタル友ハ賀古鶴所(かこつるど)君ナリ」と遺書のなかで述べている親友であり、まず「死ニ臨ンデ賀古君ノ一筆ヲ煩(わずら)ハス」と記している。
遺書の筆記を託すことができるほどの親友をもつということは、そうたやすいことではないと思う。まして鷗外は、軍医であり、小説家であり、翻訳家であり、官僚でもあった。そんな多くの顔をもつ人物が、自分の最後の決断を記述してもらうのである。真の友と認めなければできなかったことだろう。そしてその友を前にして、鷗外は裸になる。
余ハ石見人森林太郎トシテ死セント欲ス
鷗外は十歳のときに津和野を、石見をあとにして、東京に出ている。その後、一度も郷里には帰っていないそうだ。さらに石見について触れた文章も残していないらしい。それなのに、最期は「石見人(いわみのひと)」として死にたい、と遺書に記している。
いろいろな解釈があるようだが、私は裸で生まれてきたときと同じように、裸のままで死を迎えたいと思ったのではないか、と受けとめている。それが「鷗外」としてではなく、「林太郎」として死にたい、という表現になったのではないだろうか。
今年(二〇二二年)は鷗外が亡くなって百年。たくさんの小説や翻訳作品を残し、また軍医としての功績も残しながら、六十歳でいのちを終えている。同じ時代を生きた夏目漱石は、四十九歳で亡くなっている。ともに生きることを急ぎすぎた、と思うしかない。
【前回の記事を読む】製鉄から生まれた農業地、奥出雲地方は「日本農業遺産」注目のスポットに